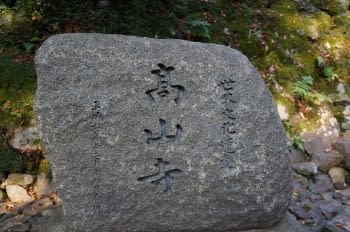山行き記録は、ヤマレコをご覧ください
164金剛山(石ブテ尾根・中尾の背コース) [金剛山・岩湧山] 
今シーズン2度目の金剛山紅葉狩りに出かけた。石ブテ尾根コースで登り、中尾の背コースで下った。
下山時、六道の辻から中尾の背コースは、激下りながら紅葉を左手(西側)に見ながらが標高差400mもの超ロングコース、
見ごろを過ぎていたが、まだまだ自然林の紅葉を楽しめた。急斜面、紅葉に気を取られ何度か滑ってしまいました。
国見城址広場、平日だがベンチは満席、 曇り空、遠くは霞んでいて視界悪し、幻想的かな

残り少ない紅葉を探してきました。 紅葉は、まだまだ残っていました。落葉してすごく明るい
たいていの紅葉は登山道から距離があり足下の悪い急斜面。近寄れない。





散りばめたような紅い葉

大日岳1094m付近の広葉樹、すっかり冬支度

中尾の背を下りきった所の滝、丸滝谷と石ブテ東谷の分岐点。シャッター速度を遅くして撮ったがほとんどぶれていた。