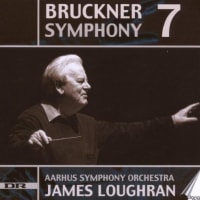下野竜也が読響に帰ってきた。いかにもこの人らしいプログラムを携えて。定期会員の一人として「お帰り下野さん」と、今公開中の映画「お帰り寅さん」に倣っていってみたくなる。
1曲目はショスタコーヴィチの「エレジー」。原曲はオペラ「ムツェンスク郡のマクベス夫人」の第1幕第3場のカテリーナのアリアを作曲者自身が弦楽四重奏用に編曲したもので、それをシコルスキが弦楽合奏用に編曲したそうだ(柴辻純子氏のプログラム・ノーツより)。読響の弦がほの暗く、しっとりした音を鳴らした。前座のノリをこえた演奏だった。
2曲目はジョン・アダムズ(1947‐)の「サクソフォン協奏曲」(2013年)。サクソフォン独奏は上野耕平。全2楽章、演奏時間約29分(プログラム表記)の曲だが、全編にわたって気の狂いそうな変拍子が続く。下野竜也の指揮から目が離せず、よくこんな曲を振れるものだと思った。
上野耕平の、その変拍子の曲に同化したような演奏には、脱帽以上の、何か異次元のものを感じた。もうそれ以上の言葉が出てこないので、話を先に進めるが、アンコールにテュドールの「クォーター・トーン・ワルツ」という曲が演奏された。これもおもしろかったが、それよりも、ジョン・アダムズの、あの神経がすり減るような曲の後で、よくアンコールができるものだと感心するほうが先だった。
3曲目はモートン・フェルドマン(1926‐87)の「On Time and the Instrumental Factor」(1969年)。演奏時間約8分(同)の短い曲。弦は16型、管は基本的に3管編成の大オーケストラだが、それが静謐な音に終始するのはこの作曲家だから当然として、むしろおもしろかったのは、弦と管のバランスが、管のほうが前面に立ち、弦はほとんど聴こえるか聴こえないかの音に終始することだ。ともかくモートン・フェルドマンのオーケストラ曲を聴く機会は稀なので、何かと興味深かった。
4曲目はグバイドゥーリナ(1931‐)の「ペスト流行時の酒宴」(2005年)。物々しい題名だが、それはプーシキンの戯曲からとられている。プーシキン全集(河出書房新社)に収録されているので、事前に読んだ。疫病が蔓延する中、酒宴に明け暮れる人々を描いた風刺的な戯曲だ。グバイドゥーリナのこの曲は、プーシキンの戯曲を逐一追った作品ではなさそうだが、疫病を連想させる電子音のリズムがオーケストラに忍び込む点が、プーシキンの戯曲との関連を印象付ける。作曲者はこの曲について「そこに何かあるとしたらそれは希望」と記しているそうだが(プログラム・ノーツ)、それはたぶん反語だろうと思った。
(2020.1.15.サントリーホール)
1曲目はショスタコーヴィチの「エレジー」。原曲はオペラ「ムツェンスク郡のマクベス夫人」の第1幕第3場のカテリーナのアリアを作曲者自身が弦楽四重奏用に編曲したもので、それをシコルスキが弦楽合奏用に編曲したそうだ(柴辻純子氏のプログラム・ノーツより)。読響の弦がほの暗く、しっとりした音を鳴らした。前座のノリをこえた演奏だった。
2曲目はジョン・アダムズ(1947‐)の「サクソフォン協奏曲」(2013年)。サクソフォン独奏は上野耕平。全2楽章、演奏時間約29分(プログラム表記)の曲だが、全編にわたって気の狂いそうな変拍子が続く。下野竜也の指揮から目が離せず、よくこんな曲を振れるものだと思った。
上野耕平の、その変拍子の曲に同化したような演奏には、脱帽以上の、何か異次元のものを感じた。もうそれ以上の言葉が出てこないので、話を先に進めるが、アンコールにテュドールの「クォーター・トーン・ワルツ」という曲が演奏された。これもおもしろかったが、それよりも、ジョン・アダムズの、あの神経がすり減るような曲の後で、よくアンコールができるものだと感心するほうが先だった。
3曲目はモートン・フェルドマン(1926‐87)の「On Time and the Instrumental Factor」(1969年)。演奏時間約8分(同)の短い曲。弦は16型、管は基本的に3管編成の大オーケストラだが、それが静謐な音に終始するのはこの作曲家だから当然として、むしろおもしろかったのは、弦と管のバランスが、管のほうが前面に立ち、弦はほとんど聴こえるか聴こえないかの音に終始することだ。ともかくモートン・フェルドマンのオーケストラ曲を聴く機会は稀なので、何かと興味深かった。
4曲目はグバイドゥーリナ(1931‐)の「ペスト流行時の酒宴」(2005年)。物々しい題名だが、それはプーシキンの戯曲からとられている。プーシキン全集(河出書房新社)に収録されているので、事前に読んだ。疫病が蔓延する中、酒宴に明け暮れる人々を描いた風刺的な戯曲だ。グバイドゥーリナのこの曲は、プーシキンの戯曲を逐一追った作品ではなさそうだが、疫病を連想させる電子音のリズムがオーケストラに忍び込む点が、プーシキンの戯曲との関連を印象付ける。作曲者はこの曲について「そこに何かあるとしたらそれは希望」と記しているそうだが(プログラム・ノーツ)、それはたぶん反語だろうと思った。
(2020.1.15.サントリーホール)