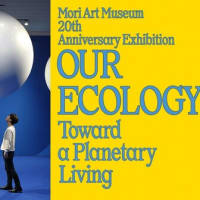高関健体制になって、東京シティ・フィルの定期は毎回注目すべきプログラムを組んでいる。今回もその一つ。1曲目はモーツァルトの「魔笛」序曲。ノンヴィブラートというほどではないが、最小限のヴィブラートで、ピリオド奏法の影響を感じさせる演奏。生気のあるその演奏に、「今回も好調だ」と思った。
だが、次のR.シュトラウスの「4つの最後の歌」では問題を感じた。高関健はプレトークで「カラヤンの演奏でこの曲を何度か聴いた」と語っていたが、その余韻が残っているのか、重い音でたっぷりとオーケストラを鳴らしていた。その音がソプラノ独唱の森麻季の声と合っていたのかどうか。
森麻季の声は、元々細くて軽い声だと思うが、今回はオーケストラの音に合わせたのだろうか、太い声でしっかり歌おうとしているようだった。だが、それでも声がオーケストラに埋もれがちで、結果が出なかった。
持ち前の細くて軽い声で旋律線をくっきり出し、オーケストラの編成をもっと絞って(当日は14型)、透明で室内楽的な世界を目指したら、ユニークな演奏が生まれたのではなかろうかと、後で想像した。
上記の「魔笛」序曲と「4つの最後の歌」は、それぞれ作曲者最晩年の作品だが、最後のブルックナーの交響曲第1番は、作曲者の若書きというか、すでにオルガン奏者として名を成していたが、そのブルックナーが交響曲という意外な分野に転戦した、その初期の頃の意欲と苦心が刻まれた曲だ。
その曲を、おそらく初演のときはこのような曲であったろうと、初演時の姿を復元しようとした「1868年リンツ稿、新全集版」(2016年出版)で演奏した。おそらく日本初披露ではなかろうか、とのこと。2018年5月にパーヴォ・ヤルヴィ指揮N響が同曲を演奏したが、そのときは「1866年リンツ稿、ノヴァーク版」と謳っていた。1866年は作曲年、1868年は初演年なので、実質的には同じだろうが、違いは「新全集版」と「ノヴァーク版」だ。
耳で聴いて、その違いがわかるわけではなかったが、時々音が薄くなって、次の展開が読めなくなるところとか、音楽の運びが率直で速いところとか、全体的にいえば、初々しいところがおもしろかった。絵画でいえば(完成作の前の)デッサンを見るような感じがした。
演奏は慎重だった。最後はよく鳴っていたが、そこに至るまでの過程では、慎重に音を吟味しているようなところがあり、感興が湧かなかった。
(2019.4.13.東京オペラシティ)
だが、次のR.シュトラウスの「4つの最後の歌」では問題を感じた。高関健はプレトークで「カラヤンの演奏でこの曲を何度か聴いた」と語っていたが、その余韻が残っているのか、重い音でたっぷりとオーケストラを鳴らしていた。その音がソプラノ独唱の森麻季の声と合っていたのかどうか。
森麻季の声は、元々細くて軽い声だと思うが、今回はオーケストラの音に合わせたのだろうか、太い声でしっかり歌おうとしているようだった。だが、それでも声がオーケストラに埋もれがちで、結果が出なかった。
持ち前の細くて軽い声で旋律線をくっきり出し、オーケストラの編成をもっと絞って(当日は14型)、透明で室内楽的な世界を目指したら、ユニークな演奏が生まれたのではなかろうかと、後で想像した。
上記の「魔笛」序曲と「4つの最後の歌」は、それぞれ作曲者最晩年の作品だが、最後のブルックナーの交響曲第1番は、作曲者の若書きというか、すでにオルガン奏者として名を成していたが、そのブルックナーが交響曲という意外な分野に転戦した、その初期の頃の意欲と苦心が刻まれた曲だ。
その曲を、おそらく初演のときはこのような曲であったろうと、初演時の姿を復元しようとした「1868年リンツ稿、新全集版」(2016年出版)で演奏した。おそらく日本初披露ではなかろうか、とのこと。2018年5月にパーヴォ・ヤルヴィ指揮N響が同曲を演奏したが、そのときは「1866年リンツ稿、ノヴァーク版」と謳っていた。1866年は作曲年、1868年は初演年なので、実質的には同じだろうが、違いは「新全集版」と「ノヴァーク版」だ。
耳で聴いて、その違いがわかるわけではなかったが、時々音が薄くなって、次の展開が読めなくなるところとか、音楽の運びが率直で速いところとか、全体的にいえば、初々しいところがおもしろかった。絵画でいえば(完成作の前の)デッサンを見るような感じがした。
演奏は慎重だった。最後はよく鳴っていたが、そこに至るまでの過程では、慎重に音を吟味しているようなところがあり、感興が湧かなかった。
(2019.4.13.東京オペラシティ)