オールFETミニアンプのイルミネーションにLEDホタルを使いたいという読者がいるので、専用の電源をアセンブルしてみました。
LEDホタルは3V~4.5VのDC(直流)電源で動作します→こんなのとかこんなの。ミニアンプのACアダプタは24VDCですが、アンプ回路には中央にアースを配置した±12VとしてDC供給します。そこで、3V~4.5Vの可変出力電源が必要になるわけで、可変式3端子レギュレータのLM317Tを用います。
LM317Tは、ヤフオクの誤発送のトラブルがあった時に、別に欲しくもなかったけど大量に入手したもので、可変式3端子レギュレータとして最も定評のあるものです。可変式でなかったら、東芝などからも様々な電圧の3端子レギュレータが出ています。ただし、3Vとか4.5Vピッタリは無し→千石電商の例。
LM317Tの使い方は色いろあるのですが、今回は、抵抗220Ω、1KΩ可変抵抗器、1μF電解コンデンサ、0.1μFマイラーコンデンサ、で組んでみました。0.1μFのコンデンサは発振防止用だと思うので、ホタルを光らせる超低周波で発振するとは思えませんが、とりあえず入れてあります。おそらく、オーディオアンプの電源に使うときは発振防止に有効なのだと思います。
電圧調整範囲は半固定抵抗の大きさで決まり、最初に取り付けた10kΩトリマーでは大きすぎて、ちょっと回しただけで2Vも動くので1KΩトリマーにしました。おそらく、1KΩトリマーだと低い電圧しか取り出せないのだと思いますが、それでも6V以下の電圧が必要なときは使い勝手が良い。逆に、20V程度の電圧が欲しい時はトリマーの抵抗値も大きくしたほうが良いのだと思います→ちゃんと検証しているサイト。
実際の基板は次の画像の通りですが、0.1μFマイラーコンデンサのお陰で、電源部に並列接続するはずの小容量フィルムコンデンサーのスペースが無くなりました。0.1μFマイラーコンデンサは無くても良さそうだし、使うとしても移動させて構わないので、ジャンパー線などで空いているスペースに押し込もうと考えています。

手前の赤(+)と黒のケーブル(-)が3VDC
中央 緑(中点アース)、橙(+12V)と白のケーブル(-12V)




ただ、今回は24Vのマイナス側をLM317Tのアースにしたのですが、もしかしたら±12Vの中点アースをアースにしたほうが良いのかもしれず、こればかりは動作させてみないと分かりません。普通のLEDを使った時は24Vのマイナス側をアースとして問題はありませんでした。
ということで、LM317Tは大量に余っているので、遠慮なく使ってもらいます (;・∀・)
エフライム工房 平御幸
LEDホタルは3V~4.5VのDC(直流)電源で動作します→こんなのとかこんなの。ミニアンプのACアダプタは24VDCですが、アンプ回路には中央にアースを配置した±12VとしてDC供給します。そこで、3V~4.5Vの可変出力電源が必要になるわけで、可変式3端子レギュレータのLM317Tを用います。
LM317Tは、ヤフオクの誤発送のトラブルがあった時に、別に欲しくもなかったけど大量に入手したもので、可変式3端子レギュレータとして最も定評のあるものです。可変式でなかったら、東芝などからも様々な電圧の3端子レギュレータが出ています。ただし、3Vとか4.5Vピッタリは無し→千石電商の例。
LM317Tの使い方は色いろあるのですが、今回は、抵抗220Ω、1KΩ可変抵抗器、1μF電解コンデンサ、0.1μFマイラーコンデンサ、で組んでみました。0.1μFのコンデンサは発振防止用だと思うので、ホタルを光らせる超低周波で発振するとは思えませんが、とりあえず入れてあります。おそらく、オーディオアンプの電源に使うときは発振防止に有効なのだと思います。
電圧調整範囲は半固定抵抗の大きさで決まり、最初に取り付けた10kΩトリマーでは大きすぎて、ちょっと回しただけで2Vも動くので1KΩトリマーにしました。おそらく、1KΩトリマーだと低い電圧しか取り出せないのだと思いますが、それでも6V以下の電圧が必要なときは使い勝手が良い。逆に、20V程度の電圧が欲しい時はトリマーの抵抗値も大きくしたほうが良いのだと思います→ちゃんと検証しているサイト。
実際の基板は次の画像の通りですが、0.1μFマイラーコンデンサのお陰で、電源部に並列接続するはずの小容量フィルムコンデンサーのスペースが無くなりました。0.1μFマイラーコンデンサは無くても良さそうだし、使うとしても移動させて構わないので、ジャンパー線などで空いているスペースに押し込もうと考えています。

手前の赤(+)と黒のケーブル(-)が3VDC
中央 緑(中点アース)、橙(+12V)と白のケーブル(-12V)




ただ、今回は24Vのマイナス側をLM317Tのアースにしたのですが、もしかしたら±12Vの中点アースをアースにしたほうが良いのかもしれず、こればかりは動作させてみないと分かりません。普通のLEDを使った時は24Vのマイナス側をアースとして問題はありませんでした。
ということで、LM317Tは大量に余っているので、遠慮なく使ってもらいます (;・∀・)
エフライム工房 平御幸















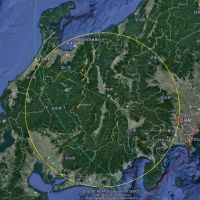
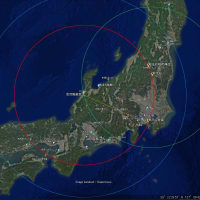

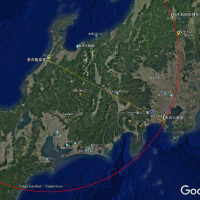






LEDの電源取り付けお疲れさまですm(__)m
レギュレータを知りませんでした。トランジスタに似てるようですが、違うものですね、、、
マイラーコンデンサというものもあり、理解できてなくて、ついて行けませんが、申し訳ありませんorz
3端子レギュレーターはトランジスタ、抵抗、ダイオードを組み合わせた集積回路です。簡単な電源を作るときに便利 (;^ω^)
機械は、一つの電源で全て事足りるものと勝手に思っていました。
変化に富んだLEDを付けるだけでも、色々なパーツを組まなくてはならないのですね。
興味を持つことによって、少しずつでも理科に明るくなりたいと思いました。小学生レベルですが、、^^;
ミニアンプ基板は元々、3V電源が組み込めるパターンを想定しています。ただ、いい加減に作ったので実用的でなかっただけ (;´Д`)
ダムや貯水池は巨大なコンデンサー。溜められたエネルギー(リソース)を使う仕組みが大切で、ウリナラのように役に立たない溜池を作っても国民の借金になるだけす。日本は古代から治水灌漑で仕組みを作ってきた。その考えを電機産業に応用できたのも当然ですね。
ヤフオクの誤発送で手元に部品があったとは、どこで何が使う事になるか分かりませんね:(; ・`д・´)
基盤が複数の電源が組み込めるパターンを想定していたとは知りませんでした。
普通に考えれば一つのパターンしか使えなければ基盤ごと換えないといけないですよね。。。
何事も色々な道を想定して考えなければと思いました。
最近仕事で頭が固いと言われたばかりですorz
交流を直流にする整流ダイオード。アンプでは4本組み込まれたブリッジダイオードが多いですが、1本ずつハンダ付けするためのパターンが併設されているものもあります。日立のHMA-9500Ⅱもそうですが、これだと自分で高性能のダイオードに交換できます (=^・^=)
頭で考えているうちは頭は固く、手で考えるようになれば頭は柔らかくなります (;・∀・)
設計お疲れさまですm(__)m 先生がちょうど良いパーツを沢山持っていらっしゃるとは(^^)
写真を拝見し、どんな風に配置するのかわかりましたm(__)m
海神神社の仏像がやっと返ってきましたが、指が更に欠けているとか。。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150718-OYT1T50047.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150719-OYT1T50014.html
17・18日というのも偶然でしょうか・・・
日本も甘いですね。損害賠償を韓国に要求すべきだし、返って来たら良いという姿勢を取るべきではありません。
指は神との契約に必要で、指が欠損しているということは神と契約ができないということ。要するに、韓国は永遠に神と和解できないということなのです。たかが指だと思っていると、まだまだ恐ろしいことが続きますね (;´Д`)