洸人さんの個展を観たあと元町まで行き「こうべ版画シティ『梓の会』展」を観に行った。
由良佐知子さんからの案内によって。

由良さんは元「火曜日」同人の詩人でもあります。
彼女の作品。

「はじめまして」

「まどろみ」ユーモラスでやさしい絵ですね。
こんなのも。「寿齢」

リアルです。
カレンダーの絵も。

そして、わたしが最も彼女らしいと思った作品。

「樹齢」です。「じゅれい」と読むのが2点出てました。なんか思いがあるのでしょうか?
他の作家の作品ではこんなのが。

なんかユーモラスでした。腕前もなかなかのようですね。
そして、この版画の会ではわたしが以前から好きな作家、稲継次郎さんの作品。





純和風です。しかしこの人、以前はイタリアなどヨーロッパの風景を描いておられた。
わたしと家内が見ているのを解説して下さったのが山崎忠厚さんという人。
その人のお話しによれば、稲継さんは年を重ねられて、海外への取材旅行が出来なくなり今は日本の風景を描いておられるとのこと。
わたしはもっとお若い人だと思っていたのでびっくりしました。
しかしやはりいい絵ですねえ。質感があります。
外国人に好まれるとか。さもありなん。
その解説をして下さった、山崎忠厚さんの作品。

「山荘の秋 三つの窓」です。
聞けば、六甲にある山荘だそうで、あの有名建築家ヴォーリズの手になる建築物だと。今も会員は利用できるのだという。
そして「元気なたまねぎ」

タイトルがいいですねえ。
由良さんには会えませんでしたが、山崎さん、親切に色々教えて下さいました。
ありがとうございました。
あ、ほかにも気になる作品がありました。


橋本定男さんという人の版画です。神戸や美山など、わたしの好きな絵です。

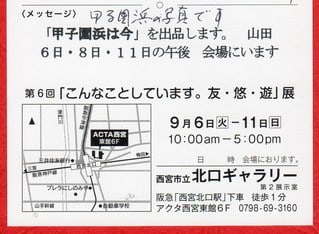

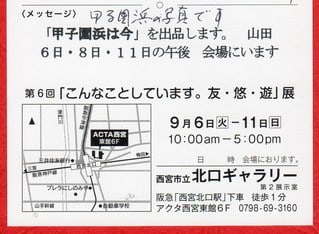












 ちょっと理由があって。
ちょっと理由があって。



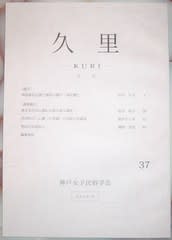








 6月4日の「朝日新聞・be」
6月4日の「朝日新聞・be」


 これ以外にもあるのだが、今見つからない。
これ以外にもあるのだが、今見つからない。

 「はじめまして」
「はじめまして」 「まどろみ」ユーモラスでやさしい絵ですね。
「まどろみ」ユーモラスでやさしい絵ですね。 リアルです。
リアルです。
 「樹齢」です。「じゅれい」と読むのが2点出てました。なんか思いがあるのでしょうか?
「樹齢」です。「じゅれい」と読むのが2点出てました。なんか思いがあるのでしょうか? なんかユーモラスでした。腕前もなかなかのようですね。
なんかユーモラスでした。腕前もなかなかのようですね。




 「山荘の秋 三つの窓」です。
「山荘の秋 三つの窓」です。 タイトルがいいですねえ。
タイトルがいいですねえ。














