ちょっと前に編集工房ノアさんからお贈り頂いていた。
『海鳴り』28号です。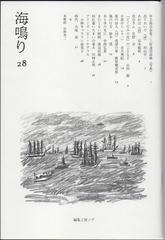
巻頭詩は例によって杉山平一先生。
 ←クリック
←クリック
右のページには三好達治の詩碑。
そしてページを繰ると、我が師匠、安水稔和氏の詩「あれは」
 ←クリック
←クリック
ほかに随筆のいいのがたくさん載っている。
鈴木漠さんの「風の行方」。連句を通じての生前の多田智満子さんとの交流を書いておられる。多田さんの辞世の句「草の背を乗り継ぐ風の行方かな」は、わたしも多田さんのことを『KOBECCO』に書かせて頂いた時に使わせて頂いた。
渡辺信雄さんの「またとない時間」。これは昨年お亡くなりになった伊勢田史郎さんへの追悼文。情愛のこもったいい文章でした。
ほかに庄野至さんの「住吉さん」が懐かしげな文章で好感が持てます。
それから、山田稔さんの「「どくだみの花」のことなど」が、随想を書く上で大変勉強になりました。
他にもいっぱい中身の濃い随想が載っていて勉強になります。
涸沢さん、ありがとうございました。
『海鳴り』28号です。
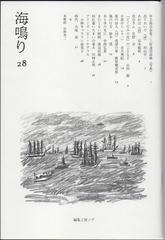
巻頭詩は例によって杉山平一先生。
 ←クリック
←クリック右のページには三好達治の詩碑。
そしてページを繰ると、我が師匠、安水稔和氏の詩「あれは」
 ←クリック
←クリックほかに随筆のいいのがたくさん載っている。
鈴木漠さんの「風の行方」。連句を通じての生前の多田智満子さんとの交流を書いておられる。多田さんの辞世の句「草の背を乗り継ぐ風の行方かな」は、わたしも多田さんのことを『KOBECCO』に書かせて頂いた時に使わせて頂いた。
渡辺信雄さんの「またとない時間」。これは昨年お亡くなりになった伊勢田史郎さんへの追悼文。情愛のこもったいい文章でした。
ほかに庄野至さんの「住吉さん」が懐かしげな文章で好感が持てます。
それから、山田稔さんの「「どくだみの花」のことなど」が、随想を書く上で大変勉強になりました。
他にもいっぱい中身の濃い随想が載っていて勉強になります。
涸沢さん、ありがとうございました。















































