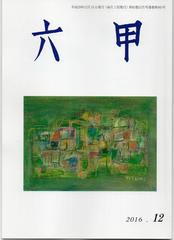「六甲」2月号が届きました。
巻頭に田岡弘子さんの作品が。

「寿をつけるがほどにめでたいか七十七・八十過ぎて来にけり」
ほろ苦ユーモアでしょうか。最近読んだ本『九十歳。何がめでたい』を思い起こしておかしかった。
田岡さんのほかの作品も軽みがあっていいですねえ。
田岡さんのはほかのページにもありました。
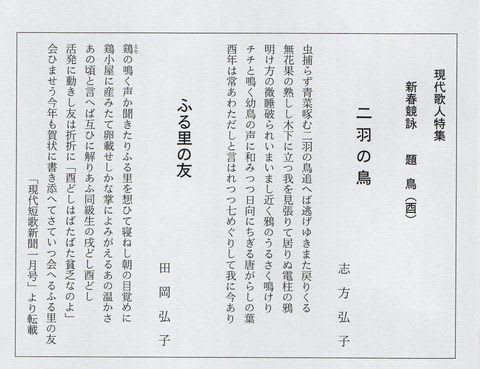
創作意欲が旺盛ですね。
わたしも真似なくては。
今号の「湯気の向こうから」は「百人一首」と題して書かせて頂きました。
お目に触れれば幸い。
巻頭に田岡弘子さんの作品が。

「寿をつけるがほどにめでたいか七十七・八十過ぎて来にけり」
ほろ苦ユーモアでしょうか。最近読んだ本『九十歳。何がめでたい』を思い起こしておかしかった。
田岡さんのほかの作品も軽みがあっていいですねえ。
田岡さんのはほかのページにもありました。
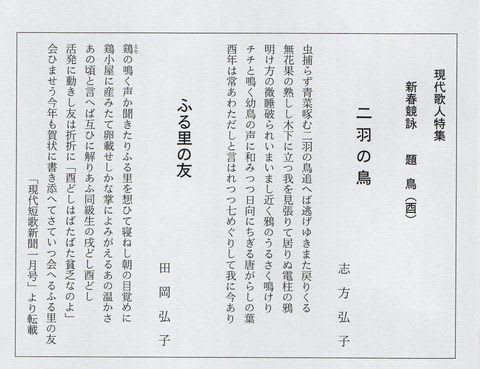
創作意欲が旺盛ですね。
わたしも真似なくては。
今号の「湯気の向こうから」は「百人一首」と題して書かせて頂きました。
お目に触れれば幸い。