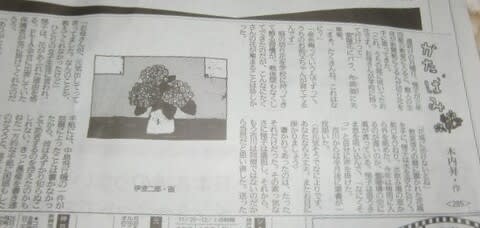今読んでいる本。

『漂砂のうたう』(木内昇著・集英社)。
読み始めたときは馴染まぬ言葉が多く、ストーリーも進まず、ちょっと読みづらかったが、読み進むにつれて興味が増してきた。
さすがに直木賞作です。
その時代(明治初期)のその場所(廓)とそこで蠢く人を描いて秀逸といえるのでしょう。
ぽつぽつと出て来る比喩がまた素晴らしい。
さりげなくいい比喩を使っておられる。
今日読んだところではこんなの。
《楼主の声はなお、手の中で碁石を揉むほどの音でしか伝わってこない。》
人の声を「碁石を揉む音」と比喩した例をわたしは知りません。
上手いものですねえ。独特のその場の雰囲気が伝わります。
『触媒のうた』多くの著名文人のここでしか読めない秘話が満載。

『漂砂のうたう』(木内昇著・集英社)。
読み始めたときは馴染まぬ言葉が多く、ストーリーも進まず、ちょっと読みづらかったが、読み進むにつれて興味が増してきた。
さすがに直木賞作です。
その時代(明治初期)のその場所(廓)とそこで蠢く人を描いて秀逸といえるのでしょう。
ぽつぽつと出て来る比喩がまた素晴らしい。
さりげなくいい比喩を使っておられる。
今日読んだところではこんなの。
《楼主の声はなお、手の中で碁石を揉むほどの音でしか伝わってこない。》
人の声を「碁石を揉む音」と比喩した例をわたしは知りません。
上手いものですねえ。独特のその場の雰囲気が伝わります。
『触媒のうた』多くの著名文人のここでしか読めない秘話が満載。