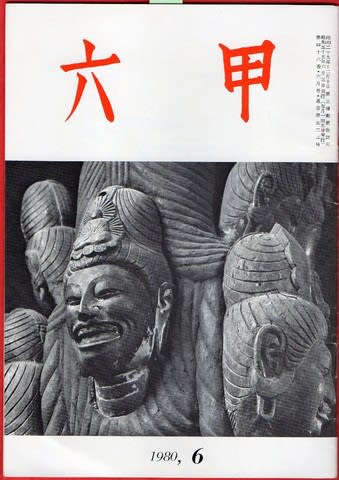昨日「花森書林」さんで入手した「階段」9号をパラパラ見ていて、「ほほう」という文章に出会った。
当時(1992年)の神戸文化会議議長の服部正氏が書いておられる「資料なき所に文化なし」。
 ←二段階クリック。
←二段階クリック。
第一行目にいきなり足立巻一先生の名前が出てくる。
こんな箇所がある。
《大阪社大学長(大阪府副知事待遇であった)在任前後から、癩学の魔力にとりつかれ、社会学博士論文「負の文化としての癩」の後日執筆を期しての全国の癩者とその癩院の血膿が沁み込み、異臭を放たんばかりの資料の提供にあずかった。》
要するに「癩」、いまでいうハンセン病のことを書いておられる。
《わたしはいつか「癩女性史」の執筆を念じている。》ともある。
そして、
《陛下(平成天皇)はアマミの癩院を訪れ、病院内に入って一人一人に声をかけられた。史上最初のでき事である。(略)皇后とともに癩院の坂を登られたのである。》
癩(ハンセン病)のことは、以前から多少知ってはいたが、ドリアン助川さんの『あん』を読み、その映画を観てから、特に気になるようになった。しかし、27年前のこの冊子にその話が出てくるとは思いもしなかった。
そして文章の最後を服部氏はこう結んでおられる。
《故足立巻一等の文学資料館建設をという悲願の訴えを、無視黙殺し去った神戸市の文化行政は、往年の文化不毛の地神戸の蔑称を再び裏書きするつもりであろうか。》
なんか、かなり怒ってはりますね。
恥ずかしながら、わたしはこの服部正氏を知らなかった。
この1992年当時には、わたしの文化への目線もかなり低いものでしたから仕方がありません。
ところで、服部氏は、ここに書いておられる「癩女性史」は執筆されたのだろうか?
当時(1992年)の神戸文化会議議長の服部正氏が書いておられる「資料なき所に文化なし」。
 ←二段階クリック。
←二段階クリック。第一行目にいきなり足立巻一先生の名前が出てくる。
こんな箇所がある。
《大阪社大学長(大阪府副知事待遇であった)在任前後から、癩学の魔力にとりつかれ、社会学博士論文「負の文化としての癩」の後日執筆を期しての全国の癩者とその癩院の血膿が沁み込み、異臭を放たんばかりの資料の提供にあずかった。》
要するに「癩」、いまでいうハンセン病のことを書いておられる。
《わたしはいつか「癩女性史」の執筆を念じている。》ともある。
そして、
《陛下(平成天皇)はアマミの癩院を訪れ、病院内に入って一人一人に声をかけられた。史上最初のでき事である。(略)皇后とともに癩院の坂を登られたのである。》
癩(ハンセン病)のことは、以前から多少知ってはいたが、ドリアン助川さんの『あん』を読み、その映画を観てから、特に気になるようになった。しかし、27年前のこの冊子にその話が出てくるとは思いもしなかった。
そして文章の最後を服部氏はこう結んでおられる。
《故足立巻一等の文学資料館建設をという悲願の訴えを、無視黙殺し去った神戸市の文化行政は、往年の文化不毛の地神戸の蔑称を再び裏書きするつもりであろうか。》
なんか、かなり怒ってはりますね。
恥ずかしながら、わたしはこの服部正氏を知らなかった。
この1992年当時には、わたしの文化への目線もかなり低いものでしたから仕方がありません。
ところで、服部氏は、ここに書いておられる「癩女性史」は執筆されたのだろうか?
























 巨大なクスノキ。
巨大なクスノキ。