





工藤恵美子さんからお贈りいただきました。

詩集『柿色の家』(工藤恵美子著・編集工房ノア・2024年10月1日刊)2000円+税。
工藤さんとは昔「火曜日」という同人誌で長くご一緒しました。いつも控えめの静かなお人柄。何度か「喫茶・輪」にご来店下さいましたが、一度ご主人と来て下さったことがあります。「輪」で「詩書展」をやっていて、丁度杉山平一先生のご来店と一緒でした。
工藤さんは「テニアン島の詩人」といってもいいお人。テニアン島が故郷なのです。今は観光の島になっているようですが、戦時中は激戦の地。お父上はそこでお亡くなりに。彼女もお母さんたちと命からがら脱出。後、テニアン島は米軍の出撃地になり、広島に原爆を落とす「エノラゲイ」が発進した島でした。
そのことを彼女は自分の原点として詩に書き続け、『テニアン島』という詩集にしました。その後も二冊の詩集を出しますが、どちらにもタイトルに「テニアン島」という言葉が含まれています。
しかし、今回は『柿色の家』。やっとテニアン島から離れた詩集を出されたのです。中にはそれに関する詩もありますが、それは仕方のないことで。
読ませていただきましたが、すべて美しく整った詩です。文に破綻がありません。伸び伸びとした詩で安心して読めます。
散水する
ああ
空いっぱいの
虹
と続きます。ご主人がお亡くなりになったのですね。
詩は上げませんが、表題詩「柿色の家」の終連に「木守柿」という言葉があります。これにはエピソードがあります。
わたしが『KOBECCO』に「木守り柿への想い」というエッセイを書いた時に、「こんな詩を書きました」とお便りをいただいたのでした。もう7年前ですね。
それからこの詩集には曾孫さんのことを書かれた作品もいくつかあって、わたしは勇気づけられました。そうだ、わたしにも曾孫が生まれる日がくるだろうと。そうすればまた子どもの詩が書けるなあと。
彼女の最初の詩集『テニアン島』(2001年・編集工房ノア刊)でもこのテーマの詩があって、衝撃を受けたのでした。
詩集の後半には、生前のご主人と世界のあちこちを旅行した詩が並んでいて、それは素晴らしいのですが、わたしはちょっとうらやましかったです。さすがにいいお仕事をなさっていたご主人、生活にゆとりがおありだったのだ。私は妻にこんな思いをさせてはやれなかった。
一巻を閉じるのにふさわしい詩ですね。
お若い時は大変な思いをなさった工藤さんですが、人生後半は優れた子どもさんお孫さん曾孫さんに恵まれて幸せで良かった。その幸せ感がしみじみと感じられる詩集でした。
『コーヒーカップの耳』面白うてやがて哀しき喫茶店。
加古川の詩人高橋夏男さんからお贈りいただきました。
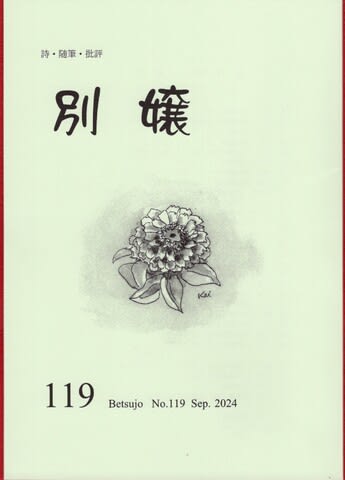
詩・随筆・批評の雑誌、「別嬢」119号です。
編集が若い人になってしばらく経ちましたが、装幀が変わらないのはいいですね。
でも文字が少し小さくなったかな?作品を多く入れるためかもしれませんが、わたしには少し小さいです。
だいたいわたしが馴染める作風の作品が並んでます。
いつもと違う趣の作品を東めぐみさんが書いておられました。ここには上げませんが意欲的というのか、「創作連詩集」とあります。物語性があって面白かったです。
七彩さんのは「別嬢」の中では半歩枠から進んでいるような新鮮さがありますね。
わたしの胸に響いたのは小西誠さんの2作品。
「詩が書けなくなって」の一篇には「がんばってください」と声をかけたくなりました。
なんか味のある「虚しさ」とでもいうのでしょうか。
たしか今は関東方面の老人施設で暮らしておられるのだったか?
小西さん、頑張って書き続けて下さいよ。
高橋夏男さんの「冬は住み憂き」は能登の震災を書いたものですが、なんということでしょうか、先日の大雨被害。
心が痛みます。夏男さんも言葉がないのではないでしょうか。
夏男さんの「おかんのいる風景」(24)はやはり労作。読ませて頂くと、いまだに発見があります。いや、高橋さんがいまだに草野心平の書き残したものを渉猟しておられて、読者にそれを披露して下さっているということ。貴重です。
高橋様、ありがとうございます。どうかお元気で。
『コーヒーカップの耳』面白うてやがて哀しき喫茶店。
今、昔に書いた孫詩をFB(読者限定)上に順次上げているのだが、その関連で金子光晴の詩集『若葉のうた』を再読してみた。

優しく柔らかい詩を書いている。
「問答」後半部分。
つみ木の門のようにあぶなっかしく
ひとりで立上った孫娘に、じじが
ほんとうは誰に似てるのときくと
しわがれた声で、わんわんと言う。
こんな詩を書く詩人です。
金子は筋金入りの反骨詩人というイメージがわたしにはあったので、この詩集は全く別物という感じ。
出版当時はとかくの批判もあったという。
関東大震災の後、西宮の縁者のところに一時住んだことがあり、そこで着想した詩もある。
そのことも詳しく知りたくて、このほど図書館からお借りしてきた。

『金子光晴自伝・詩人』(講談社文芸文庫刊)。
読んでみたが、少年、青春時代は、聞きしに勝る放蕩無頼ぶりだった。
それを赤裸々に書いている。凄い人です。
およそあのような孫詩を書く人とは思えない。
『コーヒーカップの耳』面白うてやがて哀しき喫茶店。無頼の人も多数登場。

詩集『雷がなっている』(朝倉裕子著・編集工房ノア刊・2000円+税)を読ませていただいた。

著者の朝倉さんは元「火曜日」同人。
帯文が以倉紘平さん。今は以倉さんのところで書いておられるんだ。
以倉さんはわたしも尊敬する素晴らしい人格の詩人。いいところへ行かれた。
朝倉さんの詩はともすると平凡に見えてしまうことがあって読み流してしまいそうになるが、実は油断ならない。
ひとつ短い詩を紹介しよう。
「ささやかな」です。
一見何でもないような詩。でも最後の一行に彼女の思いがさりげなく隠されています。味わえる詩といえるでしょう。
こんなのもどうでしょうか。
「ぼくのこと君にはどう見えるのか」
情景描写が上手いですねえ。
しみじみと読ませてくれます。味わい深い詩。
表題詩「雷がなっている」も良かった。特にその出だし。「急いでも急がなくても/歩調が変らないのはとしのせいだろう」なんて、ドキッとさせられます。読めば当たり前のことですが、こうして書かれてみると「そうだった!」と突きつけられるような衝撃。このあとは軽いユーモアが漂っている詩なのですが、最後は「遠くで/雷がなっている」で締められています。上手いものです。
ほかにわたしが衝撃を受けたのが「「抑留のあとさき」」ほか、何篇かの義父のシベリヤ抑留に関する詩。
ここには上げませんが重い詩群です。
実はこの「抑留のあとさき」は、もう十数年前に、この詩の元になる資料をわたしは彼女から戴いています。

A4版大型の冊子。144ページもあるもの。
貴重な写真もふんだんに使われており、日本の戦時資料としても貴重なものと思われます。
彼女の詩「抑留のあとさき」はそのことを取り上げて書かれていますが、難しい取り組みだったと思います。
でもこうして残しておかなくてはならなかったのでしょう。
また改めて散文にすることも考えてもらいたい気がしますが。
『雷がなっている』は編集工房ノア(06-6373-3641 )へご注文下さい。
「火曜日」が終刊して以来なので、9年ぶりの同人誌参加です。

西宮市芸術文化協会の元会員9人で創刊しました。
タイトルの「対角線」はわたしが提案したもの。
同人9人で無記名投票した結果です。
42ページの倹しいものですが、愛しくもあります。
わたしは、詩一篇とエッセイ一篇を載せました。
発行間隔など、詳細はまだ決まっておらず、次号発行は今後協議してのことになります。
『コーヒーカップの耳』 おもしろうて、やがて哀しき喫茶店。喫茶店ファン必読の書。
詩集『いきている』(荻野ゆう子著・編集工房ノア刊)・1980円税共)を読ませていただきました。

まず驚いたのが発行日。
8月16日だというのだ。これはびっくり。
著者の荻野ゆう子さんは、詩人江口節さんが主宰する詩誌『鶺鴒』の同人。
『鶺鴒』はいつもお贈りいただいて楽しませていただいています。
荻野さんは現役の教師らしい。
わたしが若き日になりたかった職業。
全て読ませていただいて感じるのは、難しい詩はないということ。
「現代詩」を書いてやろうという気負いなんかは全くありません。
ごく自然体で書かれています。なので安心して読めます。
詩集は三章に分かれています。
その第一章。身辺のことがどちらかといえば淡々と書かれています。
ものごとを大げさにとらえるのではなく、心に響いたことをさりげなくと言った感じで。
これが好感度を上げているのかな。
巻頭詩「いきている」です。
日ごろ小学生の子どもと接しておられるのが、こんな文体を生むのかもしれません。
この詩だけが平仮名で書かれています。そのせいか、柔らかで平明な感じがします。
第一連の素直さ、伸びやかさ。
が、「じっと とまっているのに/もとのばしょに いない/ちきゅうが まわっているあいだは」
などと、心の襞も少しのぞかせて。
「牛脊雨」には「小学生の頃から/夢を聞かれる度に/学校の先生 と答えていたが」とあります。
いいなあ。夢が実現して。でもこの次の行には「一番の夢は別にあった」なんて思わせぶりなことが書いてあります。
「揺れ」には阪神大震災のことが書かれていて、「少ししか離れていないのに 地震なんか無かったみたいやな」という言葉があります。これはわたしも体験したこと。大阪へ風呂に入りに行った時、武庫川を超えると、まるでなんにもなかったかのようにカラオケの音楽が鳴っていたのでした。
第二章は、お母さんのこと、お父さんのこと、祖母のこと、いずれもすでに亡き人のことが書かれています。
中でも「年越しそば」は、しんみりと、そしてあたたかで好きな詩でした。
お父さんお母さんへの思いの深さが思われます。祖母のことを書かれた「丸い背中」は描写が具体的で思いが良く伝わりました。
そして第三章は、待ってましたの子どもの詩。受け持ちの小学生の生き生きとした姿が見えます。
「女やなあ」は好きでした。なんでもない、普通は聞き逃してしまいそうな子供の言葉をしっかりとアンテナに受信して詩に昇華したのは、やっぱり長年の教師生活の賜物なのでしょう。羨ましいことです。
そして特に好きだったのが「はじめてのけしき」。
発見の喜びを「かわいい」という言葉で伝えるトオル君。これを詩にしてしまう荻野さん。これも普通は見逃してしまいそうな場面ですが。
ほかの多くの詩、いちいち紹介しませんでしたが、興味のある人は入手して読んでください。
編集工房ノア 電話番号06―6373-3642
荻野さん、ありがとうございました。
昔読んだ詩集を出してきて読んでいる。

『若葉のうた』(金子光晴著)。
社会的な詩で有名だったが、こんな詩集も出していた。
孫娘をうたった詩である。
昔に読んだ時とは、受ける気持ちが大きく変わったように思う。
こんなに味わい深い詩だったのかと。
この詩集を味わうにはある程度の年齢が必要なのでしょうね。
金子の代表作にはこんなのがある。