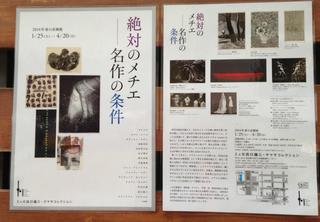紫式部が書いた「源氏物語」五十四帖の中で、
最後の十帖の舞台となった宇治。
宇治には、国内唯一の源氏物語専門の
ミュージアムがあるのです。
エントランスや中庭は藤、桔梗、紅葉、寒椿などの
「源氏ゆかりの花」で彩られています。

復元模型やハイビジョン映像を通じて「源氏物語」や
王朝絵巻の華やかな平安文化を学べます。

光源氏の邸宅「六条院」の模型
光源氏を主人公に華やかで雅やかな平安貴族の暮らし、
数多くの女性との恋愛模様が繰り広げられる前半。
政界でも頭角を現し、異例の出世をする光源氏。
二町四方・計四町という広大な面積を誇る六条院は、
栄耀栄華の象徴なのです。
しかし、地位、名誉、富も関係なく苦悩に満ちた晩年。
光源氏は、過去に犯した己の罪と
宿世の恐ろしさを思い知ることになるのでした。

時は流れ、光源氏の死後、孫の匂宮と子の薫、
二人の貴公子と宇治の八の宮の姫君たちが
織り成す悲恋の物語が始まり、
主な舞台は宇治に移ります。
「源氏物語」には、四百人以上の人物が登場しますが、
官職名や愛称しか記されていないので、実名はわかりません。
光源氏も源の何がしかの名前だったのでしょうが、
「光」は名前ではなく、たぐいまれなる
気高さを形容する言葉なのです。

貴族の遊びや年中行事なども展示されています。
こちらは平安時代の双六ですが、
何やら高尚なもののように見えます。
平安時代の天皇や貴族にとって、
漢詩・和歌・管弦などの知識・才能は必須でした。
音楽の素養は出世に関わる必須条件だったようです。
映像展示室で「浮舟」「橋姫」の
上映時間2本で50分の映画を楽しむと
無料で楽しめる情報ゾーンへ行く時間もなく
午後5時の閉館時間となってしまいました。
京都府宇治市宇治東内45-26
2016.1.8














 )
)