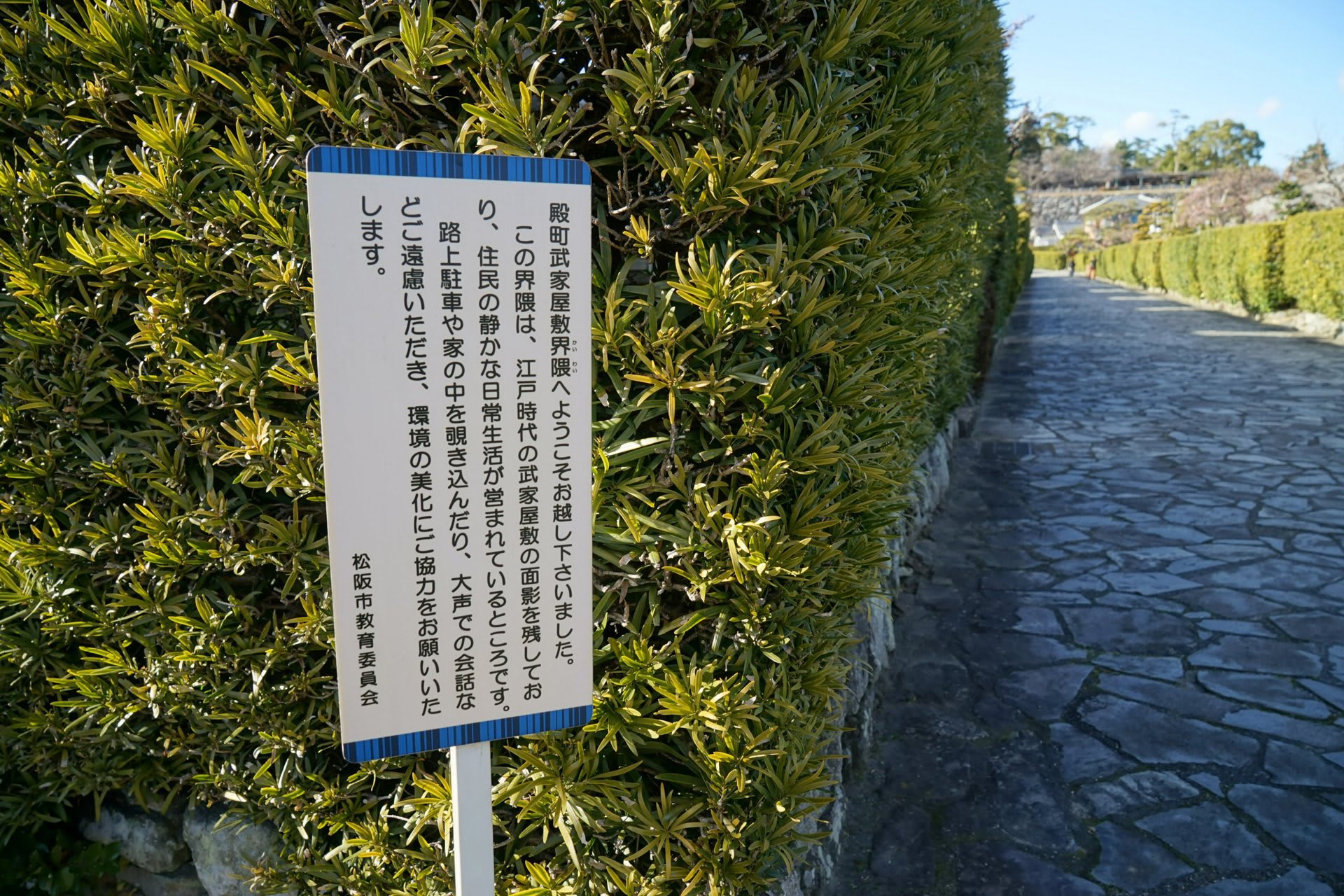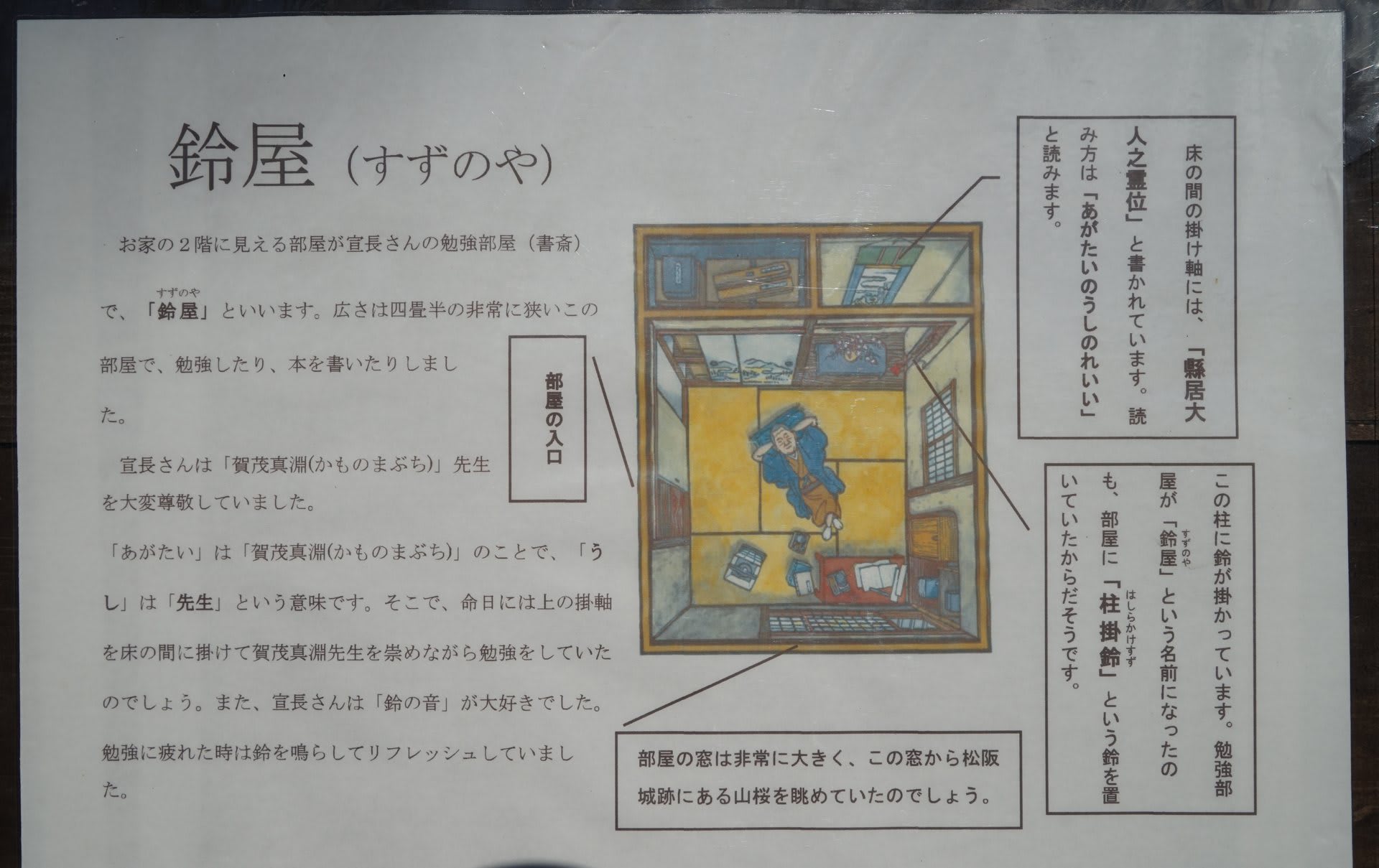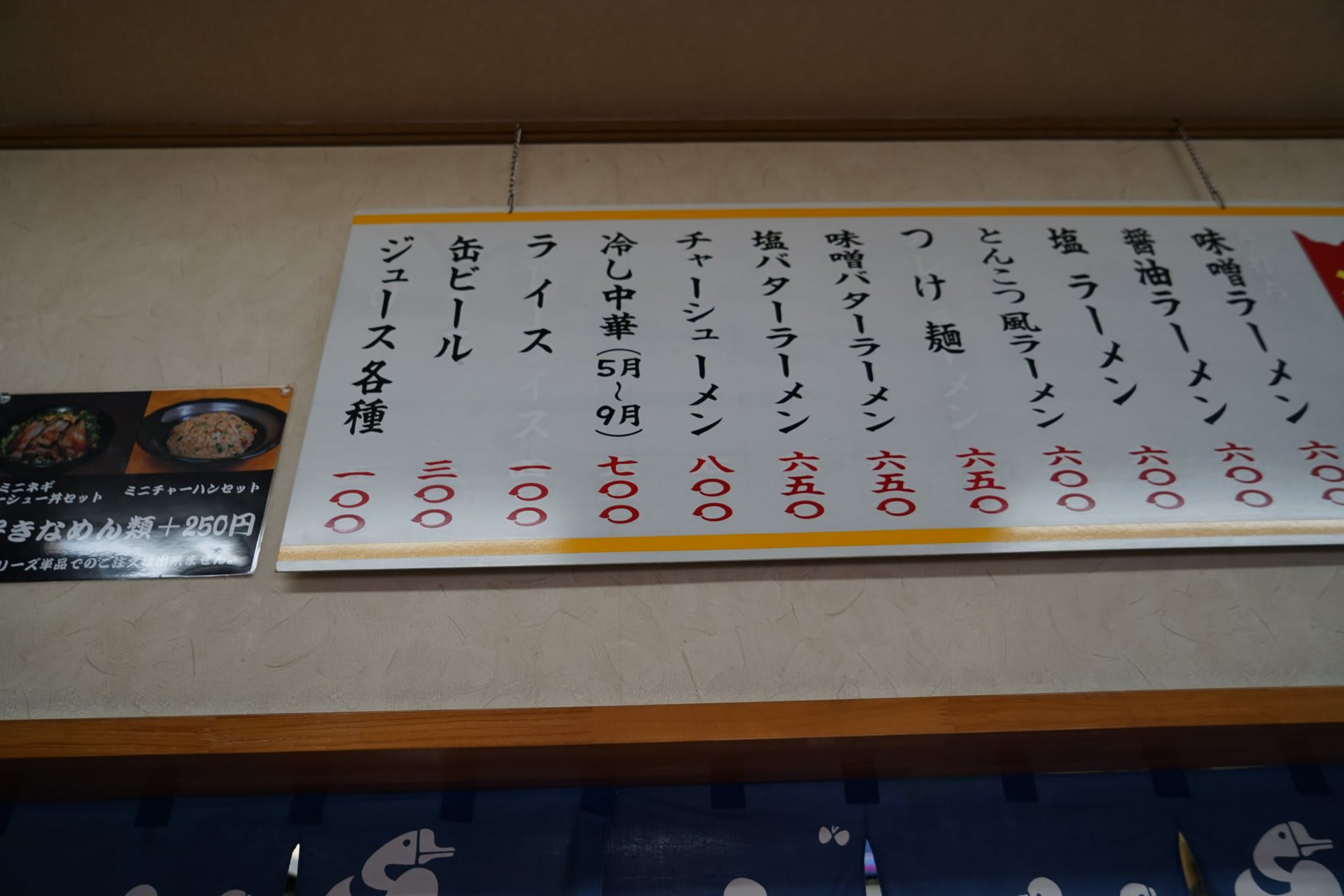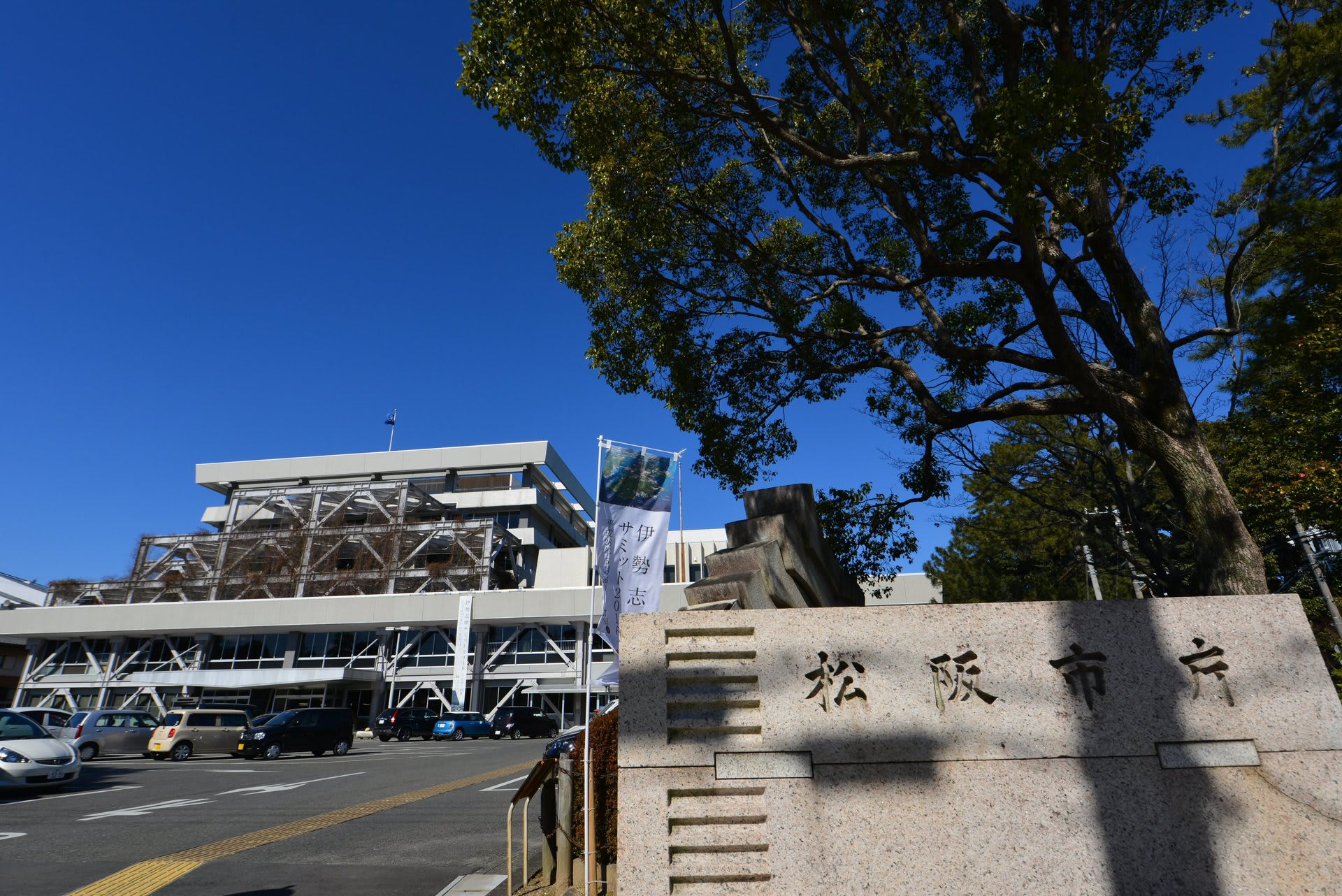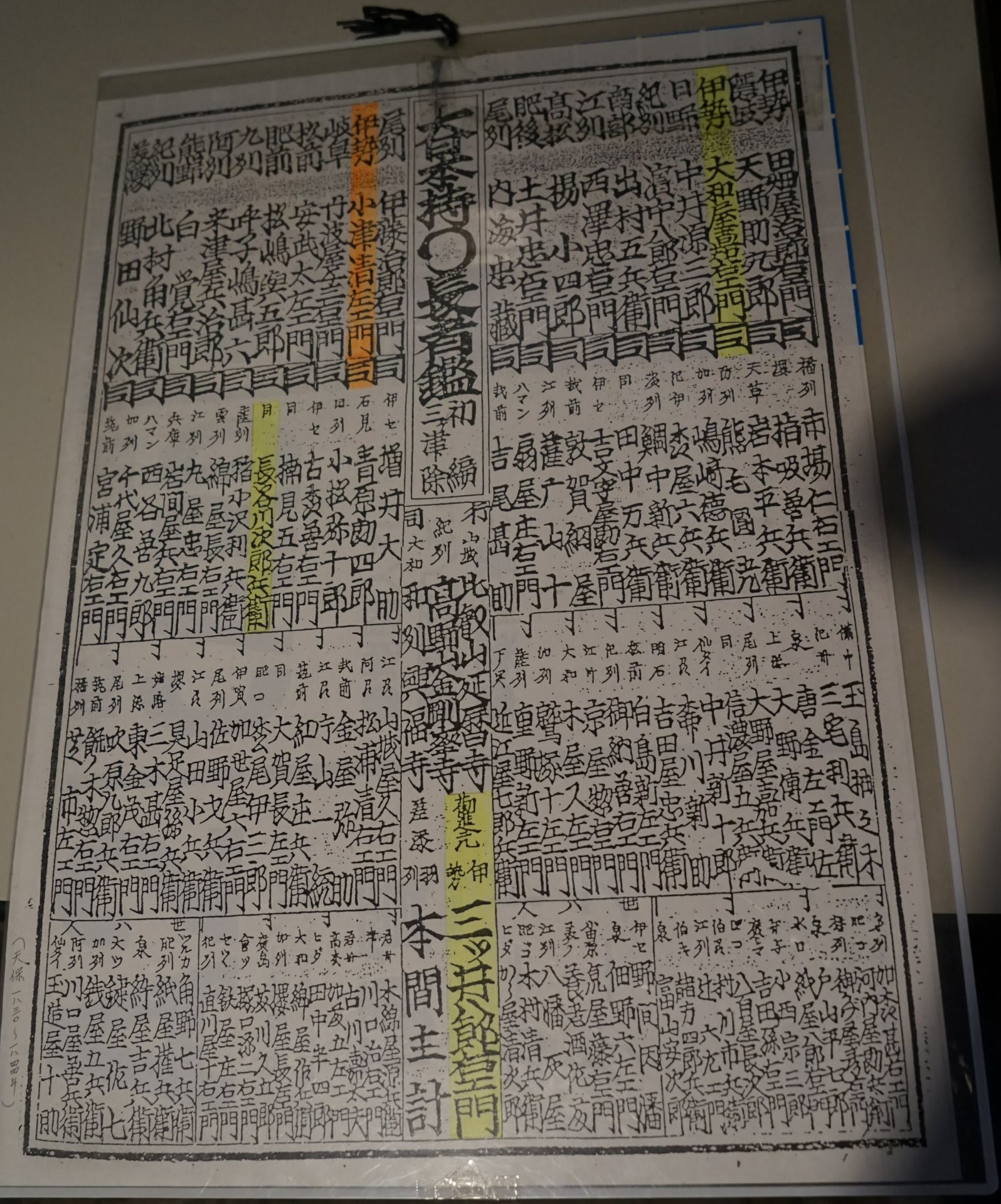高さ300メートル日本一の「あべのハルカス」
先進的な都市機能を集積した立体都市。
B2-14階は、あべのハルカス近鉄本店、
16階があべのハルカス美術館、
19-20階、38-55階・57階がホテル、
58-60階があべのハルカス300です。

あべのハルカス300のチケットカウンターは
16階にありますが、同じフロアに無料で
楽しめる庭園もあり、
眺望もなかなかのものです。

チケットを購入し、専用のエレベーターで
60階天上回廊へ昇ります。
大阪市阿倍野区にある「あべのハルカス」は、
2014年3月7日に全面開業、今年5周年。

日本初のスーパートールのエレベーターにて
16階から一気に60階まで上昇


「横浜ランドマークタワー(高さ296m)」の
高さが日本一であった時期もありました。
オープン間もない頃に展望台に上がり、
横浜ロイヤルパークホテルにも宿泊しました。
客室から下を眺めると雲ばかりで
残念ながら何も見えなかった記憶がありますが、
今回はどうでしょうか?

東側の風景がこちらになります。
奈良方面になり、高安山、信貴山、吉野山、葛城山、
今年世界遺産に指定された百舌鳥・古市古墳群
(応神陵等)も見えるかも


北側は京都方面になります。
手前に見えるのが天王寺公園、
四天王寺、大阪城、道頓堀、通天閣、
大阪国際空港(伊丹)などが見えるはずです。

天王寺公園、慶沢園、
大阪市立美術館が良く見えるでしょう。

西側は神戸・四国方面です。
手前が大阪市立大学医学部、付属病院、天王寺動物園、
京セラドーム大阪、ユニバーサルスタジオジャパン、
明石海峡大橋が見えるのもこちらです。

『アベンジャーズ/エンドゲーム』との連携企画。

いたるところに『アベンジャーズ』のメンバーが・・・。

最後に南側が和歌山方面です。
手前が阪神高速松原線、交差しているのが
あべの筋と阪堺電車、その先に安倍晴明神社、
高速の向こう側は霊園です。
ヤンマースタジアム長居なども見えて、
学生時代に長居YHに宿泊したことを
懐かしく思い出したのでした。
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
2019.5.18













 オリックス3連戦を観戦するつもりでしたが、
オリックス3連戦を観戦するつもりでしたが、