
(2004年/岩波書店)監修/加藤周一、R.ドーア、福岡ユネスコ協会/編
<第1部>加藤周一の仕事(私と戦後五五年)
・私と戦後55年(加藤周一)
・古典的知識人加藤周一(I・日地谷・キルシュライト)
・自伝における創造と虚構―『羊の歌』を中心に(ジャニン・ジャン)
・加藤周一と日本文化雑種性の問題―雑種性から普遍性へ(P・ジュリー・ブロック)
・韓国における「日本文学史序説」(金泰俊)
・「夕陽妄語」に見る加藤周一(ウィリアム・J・タイラー)
<第2部>ロナルド・ドーアの仕事(変動の激しい半世紀を振り返る
・グローバル・スタンダードにどこまで従うべきか(ロナルド・ドーア)
・社会進化・儒教・個人主義―ドーアの日本研究五〇年をふりかえって(稲上毅)
・社会調査史のなかの『都市の日本人』(佐藤健二)
・講舎と書院(劉岸偉)
<対談>日本とは何か
私は高校生の頃、現代国語の教科書に掲載されていた「龍安寺の石庭」に関する随筆に感動を覚えた記憶があります。その作家プロフィールの写真には、黒のタートルネック、鋭い眼光の持ち主が写り、東大医学部を卒業し、詩人で文芸評論家であるという、まさに「COOL」そのものの、加藤周一氏でした。その教科書は今手元にありませんが、ネットで検索すると、「庭にみる境涯」(http://homepage2.nifty.com/tskigawa/column-3.htm)でその一部が掲載されていました。
以来、加藤氏の書籍を手当たり次第読みふけりました。また、地元に加藤氏が講演で訪れたときにも聴講に行きました。確か、一緒に来熊されたのが作家の安岡正太郎さんでした。安岡さんの面白おかしい話とは対極の、国際性豊かで、外国語をそのネイティブの発音で話す、あの独特の語り口による文化論に私は大いに酔いしれました。あれは30年余り前のことだったでしょうか。
その加藤氏について、ベルリン自由大学・日本文学教授、ドイツ-日本研究所所長のI・日地谷・キルシュライトは本書の中で、「20世紀の日本が生んだ、最も優れた文化的外交官の一人」としています。
I・日地谷・キルシュライト氏は、アメリカの社会学者ダニエル・ベルの論文から、“昔風”の文化批評がほとんど沈黙に追い込まれてしまった事実を取り上げ、「そのかわりとして、新しさと刺激、直接性などが求められ、“真実”と“虚偽”の判定などという課題は、全くわすれさられています。歴史が終焉したとさえ言われる今、“成功”と“娯楽”こそが、現代的な存在の意義と体験漁りのための決定的な要素となってしまったのです」と語ります。この時代に対峙するのが加藤周一氏であると。そして、加藤氏の著作である「夕陽妄語」の中から次の一節を引用します。
「明日を思い患うこと少なく、今日を愉しもうとする態度は、遠い世界を考えず仲間内の此処に感心を集中する習慣と共に、長い日本文化の伝統である。故に明日の世界恐慌よりも今日此処での暮らしに係わる。政治家は当面の政争に、役人は予算の分捕りに、週刊誌は毒殺殺人に、女性誌は、今すぐにいかにして痩せるかに、NHKは台風が今どこへ向かっているかに。そういう関心のあり方には、たしかに一種の生活の智慧がないとはいえない。しかしその限界もあるだろう、と私は思う」。(P33)

自分が平均的な日本人であることを自覚したことが執筆するモチベーションとなったという加藤氏の代表的作である自伝「羊の歌」。カリフォルニア大学。日本文学教授のジャニン・ジャンは、その「平均的」という加藤氏の資質について、次のような意義を唱えます。
「東京の洗練された山の手の恵まれた上流中産階級での育ち、第一高等学校、さらには東京帝国大学でのエリート教育、作家・詩人・評論家・医師としても経歴、留学がいまだほとんどの日本人学生にとって稀な特権であった1950年代におけるヨーロッパでの経験、戦後の日本文学界における彼の活躍など、すべてが、経験の異例さを物語っている」。(P52)
この加藤氏については、現在、朝日新聞への執筆やNHKへの出演などから左派・進歩的文化人というレッテルを貼られていますが、私は決してそのようなレッテルには惑わされません。評論家として、日本語の構造が、「部分から全体への方向をとり、その反対ではなく、これが日本の建築の構造であり日本文化の語順である」((P90)という概念を見事に提示したり、文化を次のように定義する文化人であります。
「文化の領域には、軍事力や経済力とはちょっと違う面があります。国内では軍事力を増大させる一番の主要な役者は政府です。日本型の巨大な経済力を発展させる主要な推進力は大企業でしょう。文化は政府からも大企業からも出てこない、政府や大企業は文化を援助することはできるけれども、主導的な役割を演じるのは民間の個人です。個人のすぐれた芸術家がいなければ芸術的創造はできません」
「文化の基礎は、言葉や価値です。倫理的な価値を求めての価値の再建が必要でしょう。法律だけで社会秩序は保てない。法律と価値体系との両方からでないと、安全な良い社会はできないと思います。そういうわけで政府・大企業主導から、民間個人に移るという点が、軍事力や経済力と文化の違いだと思います」(P18)

加藤周一(かとう しゅういち 1919年9月19日-)は、「左派・進歩的文化人系の学者・評論家である。医学博士。専門は血液学。東京都出身。旧制府立一中(現都立日比谷高校)、旧制第一高等学校を経て、1943年東京大学医学部卒業。学生時代から文学に関心を寄せ、在学中に、中村真一郎・福永武彦らと『マチネ・ポエティク』を結成し、その一員として韻律を持った日本語詩を発表、他に文学に関する評論、小説を執筆。新定型詩運動を進める」。
「終戦直後、日米『原子爆弾影響合同調査団』の一員として被爆の実態調査のために広島に赴き、原爆の被害を実際に見聞している。1947年、中村真一郎・福永武彦らとの共著『1946 文学的考察』を発表し、注目される。また、同年、『近代文学』の同人となる。1951年からは、医学留学生としてフランスに渡り医学研究に従事する一方で、日本の雑誌や新聞に文明批評や文芸評論を発表。帰国後に、マルクス主義的唯物史観の立場から『日本文化の雑種性』などの評論を発表し、1956年には、それらの成果を『雑種文化』にまとめて刊行した」。
「1960年、カナダのコロンビア大学に招聘され、日本の古典の講義をおこなった。これは1975年に、『日本文学史序説』としてまとめられている。以後、国内外の大学で教鞭をとりながら執筆活動を続けている。『雑種文化』・『読書術』・『羊の歌』等の著書がある。また、林達夫のあとをつぎ、平凡社の『世界大百科事典』編集長をつとめ、その『林達夫』『日本』『日本文学』の項目を執筆した。上智大学教授、エール大学講師、ベルリン自由大学、ブリティッシュ・コロンビア大学教授、立命館大学国際関係学部客員教授、立命館大学国際平和ミュージアム館長を歴任。1984年より現在でも、朝日新聞にて『夕陽妄語』を連載している」。(ウィキペディア)
そして、もう一人のインテレクチュアル、ロナルド・ドーア氏。本書で中心的に扱われる「都市の日本人」(1958年、邦訳1962)を読んだことがあるか、あるいは本書を取り上げた別の本を読んだのか定かではありませんが、本書に示される調査方法については記憶がありました。ここではドーア氏が問い続けた日本のコーポレート・ガバナンスの誤謬について取り上げておきます。

「日本では株の持ち合い制度がありますので、結局、実質的には敵対的買収が不可能となる。敵対的買収が不可能となるのは株主の力が非常に弱く、企業の社長が株主の福祉よりもむしろ従業員の福祉をより優先的に考えることができるからだとう思います。これをおおざっぱに要約しますと、日本は従業員重視、アメリカは株主重視企業。あるいは一橋大学の伊丹敬之先生の言葉を借りれば、日本は『従業員民主主義の制度』であって、アメリカは『株主主権の制度』です。それを引っ繰り返して社外重役を入れたり、ROE(株主資本利益率)を目標としたり、インサイダー・システムを止めたり、終身雇用をなくしたりしなければならないとコーポレート・ガバナンス改革者はいう。そういう動きはどこから出てきたのでしょうか」(P149)
「このコーポレート・ガバナンス論の中には、二つの大きな流れがあると思います。一つは透明性を強調すること。もう一つは株主重視企業への移行です。しかし、それは切りはなすべきだと思います。透明性は大事ですが、株主に対する透明性ばかりではなく、従業員に対して透明であるような会社の経営が非常に重要であると思います」。
「もう一つの大きな流れはやはり株主重視です。つまり、今までにあまりにも従業員を大事にしてきたために、人間尊重がいき過ぎて株主の価値の創造が無視されてきたという論法です。そして株主を尊重しなければ過激化しつつある世界のメガ・コンペティションに勝ち抜けないというように-いわば国益のために-論じられているような主張です。しかし、それは同時に、国益のために論じられて株主主権の論法で、その株を持っている人たちの利益になることです。株主尊重の主張がアメリカやイギリスと同じように強くなれば、国民の中の貧富の差が開く結果にもなりますし、社会的連帯感が薄くなることはどうしても避けられないと思います」。(P153~154)
最後に、東京大学・社会学教授の稲上毅氏が本書「社会進化・儒教・個人主義―ドーアの日本研究五〇年をふりかえって」で最後に引用した、ドーア氏の著書「都市の日本人」の結びを私も引用しておきます。
「日本人が他国の価値を利用し、他国の尺度で自己の業績を測ることに甘んじていられる時代がいつまでもつづくわけがない。・・・やがて鋭敏な自尊心(amour prpre)が強固な利害関心と結びついて、ちがった種類の新しい-「真に日本的な」-目標を発展させ、古い依存形式と新しいものとを巧みに結合した、新しい社会と新しい政治体制をつくりあげてゆくものと思われる」(P181)

ロナルド・ドーア(Ronald P Dore)は、「1925年英国ポーツマス生れ。ロンドン大学東洋アフリカ研究学院卒。現在、ロンドン大学経済パフォーマンス研究所長。ドーア自身が書くところによれば「『連合』を信念もなく根無し草だと非難、『規制緩和』の決まり文句を唱える連中の浅薄さを罵り、護憲派にも小沢流の改憲派に対しても、絶えず悪口を書いて、自主的平和宣言としての憲法改正を主張……」、それがいまのドーア氏だという(「日本を面白がりつづけて」『中央公論』95年7月号)。五○年に初来日以来、来日を繰り返し日本社会を研究。自ら足を運び、読み・書き・喋る達者な日本語を駆使して調査を行う。その日本の社会、歴史、産業、教育と多岐にわたる考察は鋭い。 著書に『イギリスの工場・日本の工場』(ちくま学芸文庫、93年)、『「こうしよう」と言える日本』(朝日新聞社、93年)がある」。(THE 21 なんでもランキング/人名事典)
<第1部>加藤周一の仕事(私と戦後五五年)
・私と戦後55年(加藤周一)
・古典的知識人加藤周一(I・日地谷・キルシュライト)
・自伝における創造と虚構―『羊の歌』を中心に(ジャニン・ジャン)
・加藤周一と日本文化雑種性の問題―雑種性から普遍性へ(P・ジュリー・ブロック)
・韓国における「日本文学史序説」(金泰俊)
・「夕陽妄語」に見る加藤周一(ウィリアム・J・タイラー)
<第2部>ロナルド・ドーアの仕事(変動の激しい半世紀を振り返る
・グローバル・スタンダードにどこまで従うべきか(ロナルド・ドーア)
・社会進化・儒教・個人主義―ドーアの日本研究五〇年をふりかえって(稲上毅)
・社会調査史のなかの『都市の日本人』(佐藤健二)
・講舎と書院(劉岸偉)
<対談>日本とは何か
私は高校生の頃、現代国語の教科書に掲載されていた「龍安寺の石庭」に関する随筆に感動を覚えた記憶があります。その作家プロフィールの写真には、黒のタートルネック、鋭い眼光の持ち主が写り、東大医学部を卒業し、詩人で文芸評論家であるという、まさに「COOL」そのものの、加藤周一氏でした。その教科書は今手元にありませんが、ネットで検索すると、「庭にみる境涯」(http://homepage2.nifty.com/tskigawa/column-3.htm)でその一部が掲載されていました。
以来、加藤氏の書籍を手当たり次第読みふけりました。また、地元に加藤氏が講演で訪れたときにも聴講に行きました。確か、一緒に来熊されたのが作家の安岡正太郎さんでした。安岡さんの面白おかしい話とは対極の、国際性豊かで、外国語をそのネイティブの発音で話す、あの独特の語り口による文化論に私は大いに酔いしれました。あれは30年余り前のことだったでしょうか。
その加藤氏について、ベルリン自由大学・日本文学教授、ドイツ-日本研究所所長のI・日地谷・キルシュライトは本書の中で、「20世紀の日本が生んだ、最も優れた文化的外交官の一人」としています。
I・日地谷・キルシュライト氏は、アメリカの社会学者ダニエル・ベルの論文から、“昔風”の文化批評がほとんど沈黙に追い込まれてしまった事実を取り上げ、「そのかわりとして、新しさと刺激、直接性などが求められ、“真実”と“虚偽”の判定などという課題は、全くわすれさられています。歴史が終焉したとさえ言われる今、“成功”と“娯楽”こそが、現代的な存在の意義と体験漁りのための決定的な要素となってしまったのです」と語ります。この時代に対峙するのが加藤周一氏であると。そして、加藤氏の著作である「夕陽妄語」の中から次の一節を引用します。
「明日を思い患うこと少なく、今日を愉しもうとする態度は、遠い世界を考えず仲間内の此処に感心を集中する習慣と共に、長い日本文化の伝統である。故に明日の世界恐慌よりも今日此処での暮らしに係わる。政治家は当面の政争に、役人は予算の分捕りに、週刊誌は毒殺殺人に、女性誌は、今すぐにいかにして痩せるかに、NHKは台風が今どこへ向かっているかに。そういう関心のあり方には、たしかに一種の生活の智慧がないとはいえない。しかしその限界もあるだろう、と私は思う」。(P33)

自分が平均的な日本人であることを自覚したことが執筆するモチベーションとなったという加藤氏の代表的作である自伝「羊の歌」。カリフォルニア大学。日本文学教授のジャニン・ジャンは、その「平均的」という加藤氏の資質について、次のような意義を唱えます。
「東京の洗練された山の手の恵まれた上流中産階級での育ち、第一高等学校、さらには東京帝国大学でのエリート教育、作家・詩人・評論家・医師としても経歴、留学がいまだほとんどの日本人学生にとって稀な特権であった1950年代におけるヨーロッパでの経験、戦後の日本文学界における彼の活躍など、すべてが、経験の異例さを物語っている」。(P52)
この加藤氏については、現在、朝日新聞への執筆やNHKへの出演などから左派・進歩的文化人というレッテルを貼られていますが、私は決してそのようなレッテルには惑わされません。評論家として、日本語の構造が、「部分から全体への方向をとり、その反対ではなく、これが日本の建築の構造であり日本文化の語順である」((P90)という概念を見事に提示したり、文化を次のように定義する文化人であります。
「文化の領域には、軍事力や経済力とはちょっと違う面があります。国内では軍事力を増大させる一番の主要な役者は政府です。日本型の巨大な経済力を発展させる主要な推進力は大企業でしょう。文化は政府からも大企業からも出てこない、政府や大企業は文化を援助することはできるけれども、主導的な役割を演じるのは民間の個人です。個人のすぐれた芸術家がいなければ芸術的創造はできません」
「文化の基礎は、言葉や価値です。倫理的な価値を求めての価値の再建が必要でしょう。法律だけで社会秩序は保てない。法律と価値体系との両方からでないと、安全な良い社会はできないと思います。そういうわけで政府・大企業主導から、民間個人に移るという点が、軍事力や経済力と文化の違いだと思います」(P18)

加藤周一(かとう しゅういち 1919年9月19日-)は、「左派・進歩的文化人系の学者・評論家である。医学博士。専門は血液学。東京都出身。旧制府立一中(現都立日比谷高校)、旧制第一高等学校を経て、1943年東京大学医学部卒業。学生時代から文学に関心を寄せ、在学中に、中村真一郎・福永武彦らと『マチネ・ポエティク』を結成し、その一員として韻律を持った日本語詩を発表、他に文学に関する評論、小説を執筆。新定型詩運動を進める」。
「終戦直後、日米『原子爆弾影響合同調査団』の一員として被爆の実態調査のために広島に赴き、原爆の被害を実際に見聞している。1947年、中村真一郎・福永武彦らとの共著『1946 文学的考察』を発表し、注目される。また、同年、『近代文学』の同人となる。1951年からは、医学留学生としてフランスに渡り医学研究に従事する一方で、日本の雑誌や新聞に文明批評や文芸評論を発表。帰国後に、マルクス主義的唯物史観の立場から『日本文化の雑種性』などの評論を発表し、1956年には、それらの成果を『雑種文化』にまとめて刊行した」。
「1960年、カナダのコロンビア大学に招聘され、日本の古典の講義をおこなった。これは1975年に、『日本文学史序説』としてまとめられている。以後、国内外の大学で教鞭をとりながら執筆活動を続けている。『雑種文化』・『読書術』・『羊の歌』等の著書がある。また、林達夫のあとをつぎ、平凡社の『世界大百科事典』編集長をつとめ、その『林達夫』『日本』『日本文学』の項目を執筆した。上智大学教授、エール大学講師、ベルリン自由大学、ブリティッシュ・コロンビア大学教授、立命館大学国際関係学部客員教授、立命館大学国際平和ミュージアム館長を歴任。1984年より現在でも、朝日新聞にて『夕陽妄語』を連載している」。(ウィキペディア)
そして、もう一人のインテレクチュアル、ロナルド・ドーア氏。本書で中心的に扱われる「都市の日本人」(1958年、邦訳1962)を読んだことがあるか、あるいは本書を取り上げた別の本を読んだのか定かではありませんが、本書に示される調査方法については記憶がありました。ここではドーア氏が問い続けた日本のコーポレート・ガバナンスの誤謬について取り上げておきます。

「日本では株の持ち合い制度がありますので、結局、実質的には敵対的買収が不可能となる。敵対的買収が不可能となるのは株主の力が非常に弱く、企業の社長が株主の福祉よりもむしろ従業員の福祉をより優先的に考えることができるからだとう思います。これをおおざっぱに要約しますと、日本は従業員重視、アメリカは株主重視企業。あるいは一橋大学の伊丹敬之先生の言葉を借りれば、日本は『従業員民主主義の制度』であって、アメリカは『株主主権の制度』です。それを引っ繰り返して社外重役を入れたり、ROE(株主資本利益率)を目標としたり、インサイダー・システムを止めたり、終身雇用をなくしたりしなければならないとコーポレート・ガバナンス改革者はいう。そういう動きはどこから出てきたのでしょうか」(P149)
「このコーポレート・ガバナンス論の中には、二つの大きな流れがあると思います。一つは透明性を強調すること。もう一つは株主重視企業への移行です。しかし、それは切りはなすべきだと思います。透明性は大事ですが、株主に対する透明性ばかりではなく、従業員に対して透明であるような会社の経営が非常に重要であると思います」。
「もう一つの大きな流れはやはり株主重視です。つまり、今までにあまりにも従業員を大事にしてきたために、人間尊重がいき過ぎて株主の価値の創造が無視されてきたという論法です。そして株主を尊重しなければ過激化しつつある世界のメガ・コンペティションに勝ち抜けないというように-いわば国益のために-論じられているような主張です。しかし、それは同時に、国益のために論じられて株主主権の論法で、その株を持っている人たちの利益になることです。株主尊重の主張がアメリカやイギリスと同じように強くなれば、国民の中の貧富の差が開く結果にもなりますし、社会的連帯感が薄くなることはどうしても避けられないと思います」。(P153~154)
最後に、東京大学・社会学教授の稲上毅氏が本書「社会進化・儒教・個人主義―ドーアの日本研究五〇年をふりかえって」で最後に引用した、ドーア氏の著書「都市の日本人」の結びを私も引用しておきます。
「日本人が他国の価値を利用し、他国の尺度で自己の業績を測ることに甘んじていられる時代がいつまでもつづくわけがない。・・・やがて鋭敏な自尊心(amour prpre)が強固な利害関心と結びついて、ちがった種類の新しい-「真に日本的な」-目標を発展させ、古い依存形式と新しいものとを巧みに結合した、新しい社会と新しい政治体制をつくりあげてゆくものと思われる」(P181)

ロナルド・ドーア(Ronald P Dore)は、「1925年英国ポーツマス生れ。ロンドン大学東洋アフリカ研究学院卒。現在、ロンドン大学経済パフォーマンス研究所長。ドーア自身が書くところによれば「『連合』を信念もなく根無し草だと非難、『規制緩和』の決まり文句を唱える連中の浅薄さを罵り、護憲派にも小沢流の改憲派に対しても、絶えず悪口を書いて、自主的平和宣言としての憲法改正を主張……」、それがいまのドーア氏だという(「日本を面白がりつづけて」『中央公論』95年7月号)。五○年に初来日以来、来日を繰り返し日本社会を研究。自ら足を運び、読み・書き・喋る達者な日本語を駆使して調査を行う。その日本の社会、歴史、産業、教育と多岐にわたる考察は鋭い。 著書に『イギリスの工場・日本の工場』(ちくま学芸文庫、93年)、『「こうしよう」と言える日本』(朝日新聞社、93年)がある」。(THE 21 なんでもランキング/人名事典)












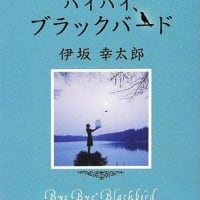







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます