

⑨ピエール・ボナール(Pierre Bonnard, 1867年10月3日 - 1947年1月23日)は、「ナビ派に分類される19世紀~20世紀のフランスの画家。ポスト印象派とモダンアートの中間点に位置する画家である。版画やポスターにも優れた作品を残している。ボナールは一派の画家(ナビ派)のなかでももっとも日本美術の影響を強く受け、『日本的なナビ』と呼ばれた。また、室内情景などの身近な題材を好んで描いたことから、ヴュイヤールとともにアンティミスト(親密派)と呼ばれている」。(ウィキペディア)
ナビ派(Les Nabis)は、「19世紀末のパリで活動した、前衛的な美術家の集団。『ナビ』はヘブライ語で預言者を意味する。ナビ派は当初、パリのアカデミー・ジュリアンに通う若い画家たちのグループであった。彼らは既存のアカデミズムの絵画に飽き足らず、ポール・ゴーギャンに強い影響を受けて新しい絵画技法を探究した」。
「ポール・セリュジエは1888年、ゴーギャンに直接の手ほどきを受けて『タリスマン』を描き、この作品はナビ派に取って象徴的な意味を持つことになった。ナビ派のアーティストたちは絵画だけでなくポスター・デザイン、印刷、テキスタイル、装丁、家具制作、舞台美術なども手がけた」(ウィキペディア)。
ピエール・ボナールが1925年に南フランスの静かな町ル・カンネの町で買って、夏になると、暇がある限りやって来たという家は、村の人々からは「小さなバラ色の家」と呼ばれていたといいます。著者は、フロラン・フェルスの著書「生きている芸術」の中の次の文章を引用しています。
「・・・そこを訪れる者は、この画家が好んで作品の中に描き出した愛犬ダッケル(ダックスフンド)の吠声に迎えられて門を通り、世間を離れ、世界の悩みや不安を離れた別世界にはいりこむ。そこには、絵画というただひとつのかぎえられた目的のためだけに生きている完全にフランス的な芸術家がいるのである」
「魔法の世界は、この色彩の隠者のアトリエに一歩足を踏み入れたところからはじまった。・・・床の上には大きな装飾画の習作が拡げられてあり、テラスから望み見た人や、これまでに百回近くも繰り返されたあの浴女の姿が見えた。・・・透明な水の輝きのなかに若い娘の横たわった身体があり、そのどこかもの憂げな様子は、生きることの喜びを全身で表現していた・・・」(P198)
「対象やモティーフの存在は、実際に制作している時には、画家にとって大変邪魔になるものだ。絵画の出発点というのはひとつの理念であるので、もし制作中に対象が眼の前にあると、そのものの持つ直接の映像に惹かれて最初の理念を忘れてしまう危険性があるからだ。そのようにしてしばらく描き続けていると、もはや最初の理念を取り戻すことはできなくなり、眼に見える影を映し出したり、その他でも偶然の効果を頼るようになってしまう・・・」(P206)

⑩ラウル・デュフィ(Raoul Dufy, 1877年6月3日 - 1953年3月23日)は、「野獣派に分類される19世紀~20世紀期のフランスの画家。『色彩の魔術師』。20世紀のフランスのパリを代表するフランス近代絵画家」。(ウィキペディア)
「デュフィは多くの不安や不幸に満ちた二十世紀において、芸術の持っている本質的な機能のひとつである『楽しさ』を決して見失うことがなかった」と著者はデュフィを評し、貧乏学生であった当時の彼を語る友人の次の文章を引用しています。
「いかにあの時代とは言え、そしていかにもモンマルトルにおいてとは言え、毎月百フランでそれほど立派な生活ができるわけはなかった。ところが、ラウル・デュフェは、この奇蹟をなしとげたのである・・・彼が他の多くの仲間たちのようにカラーもつけず、仕事着のままだらしない恰好をしているのなど、いちども見たことがなかった。ボヘミアン生活は彼にとっては嫌悪の的だった。身につけるものはつねにさっぱりしており、靴はいつもちゃんと磨いてあり、貧しいながらも彼はつねに堂々としてた・・・」(P216)
更に、著者は、「ゴーガンとその時代」(1977年)の著者シャルル・シャッセの次の言葉を引用しています。
「彼は他の誰よりも明るい楽天主義、夢の世界への憧れを持っており、自己の芸術のすべてにその痕跡を残している、彼は、自分が絵を描く時に感ずる喜びを見る人たちにも感じて貰いたいと望んだ。<私は自分の探求の喜びを後から来る者にも分ちたいのだ>と彼はつねづね言っていた。また、友人たちの作品を比較しながら、自分は作品のなかに<楽しさと優しさ>を盛りこみたいとも語っていた・・・」(P215)

⑪パブロ・ピカソ(Pablo Picasso, 1881年10月25日 - 1973年4月8日)は、「スペインのマラガに生まれ、フランスで制作活動をした画家・彫刻家・芸術家。ジョルジュ・ブラック同様、キュビスムの創始者のひとり。生涯におよそ13,500点の油絵と素描、100,000点の版画、34,000点の挿絵、300点の彫刻と陶器を制作し、最も多作な画家であるとギネスブックに記されている」。(ウィキペディア)
言わずもがなの巨匠です。本書では、「アヴィニョンの娘たち」以前のピカソのエピソードが記述されています。ピカソの作品で有名なキュビスム以降のあの独特なタッチを初めて観たときは、ほんとうにこの人は絵が上手いのかと思ってしまいましたが、その才能を本書では次のように記しています。
「もともとピカソは、父親に絵の手ほどきを受けただけで、1895年、バルセロナの美術学校にはいるまでは、正規の絵画教育は受けていない。しかし、父親が熱心だったということと、何よりの天賦の才能によって、早くから完璧に近いデッサンの才能を示していた。ふつう一ヶ月間の制作期間を与えられる課題をたった一日で仕上げて、しかも先輩の誰よりも優れた出来栄えで人々を驚かせたというエピソードは、この美術学校入学試験のときのことである」
「事実彼のデッサン力は、父親が絵の道を断念したという、あのエピソードにも現われているとおり、抜群のものであった。今でこそわれわれは、ピカソというと妙にデフォルメされた人間像を思い浮かべるが、ピカソ自身は、誰よりも巧にアカデミックなデッサンを仕上げる腕の持ち主である。1946年、ブリティッシュ・カウンシルの主催で世界の児童画の展覧会が行われたとき、すすめられてそれを見に行ったピカソは、
『私が子供だったら、きっとこの展覧会には出品できなかったに違いない。なにしろ十二歳のとき私のデッサンは、ラファエルのようだったからね』
と語った」(P148~149)

この巨匠に関しては、アンソニー・ホプキンスがピカソを演じた1996年の「サバイビング ピカソ」(ジェームズ・アイヴォリー監督)がありますね。

⑫モーリス・ユトリロ(Maurice Utrillo, 1883年12月25日 - 1955年11月5日)は、「近代のフランスの画家。母は「モンマルトルの女王」で画家シュザンヌ・ヴァラドン。ユトリロは、エコール・ド・パリの画家のなかでは珍しくフランス人である。ユトリロは母親が18歳の時の子供で、父親がいなかったため祖母に育てられた」。
「ユトリロは、10代でアルコール中毒になり、治療のため、医師に勧められて絵を描き始めたことはよく知られている。作品のほとんどは風景画、それも、小路、教会、運河などの身近なパリの風景を描いたものである。ありふれた街の風景を描きながら、その画面は不思議な詩情と静謐さに満ちている。特に、壁などの色に用いられた独特の白が印象的である」。
「第二次世界大戦後まで余命を保つが、作品は、後に「白の時代」といわれる、アルコールに溺れていた初期のものの方が一般に評価が高い。パリ郊外のサノワ(サンノワ)にはモーリス・ユトリロ美術館がある。またモンマルトルにある墓には献花が絶えない」。(ウィキペディア)
「ユトリロの父については、7歳のときに、スペイン人ジャーナリストのミゲル・ユトリロが彼を認知したが、ユトリロは生涯この法律上の父に会うことはなかった。ユトリロの実父については諸説あり、わかっていない。諸説とは、酒飲みの放浪者・ボワッシー、画家ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ、ミゲル・ユトリロその人など」。(P92-94)
ユトリロについては、1954年の「ユトリロの世界(原題:L'Univers D'Utrillo)」(ジョルジュ・レニエ監督)という映画があるようです。また、後述するモディリアーニの映画ではフランスの俳優イポリット・ジラルドがユトリロを演じているようです。

⑬アメデオ・クレメンテ・モディリアーニ(Amedeo Clemente Modigliani, 1884年7月12日 - 1920年1月24日)は、「20世紀初頭に活動した画家・彫刻家で、イタリア出身だが、渡仏し、おもにパリで制作活動を行った。1884年、イタリア・トスカーナ地方のリヴォルノに生まれた、セファルディ・ユダヤ系のイタリア人である。芸術家の集うモンパルナスで活躍し、エコール・ド・パリ(パリ派)の画家の一人に数えられる」。(ウィキペディア)
「ルノワールやロートレックを中心とする印象派、ポスト印象派の歴史がもっぱらモンマルトルを舞台として展開されたのにたいし、第一次大戦をはさむエコール・ド・パリの歴史は、モンパルナスの灯の下で織り出されていった。モディリアーニがコーランクール街(モンマルトル)からシテ・ファルギエール(モンパルナス)に移ったということは、その点はなはだ暗示的である。つまりそれは、ひとりモディリアーニだけの問題ではなく、当時の芸術界全体の動きを象徴的に示しているとも言えるからである」(P114)

彼については、アンディ・ガルシアがモディリアーニに扮した2004年の映画「モディリアーニ ~真実の愛~」(ミック・デイヴィス監督)があります。この映画のキャプションには「愛する女性との関係を軸にピカソとの対決、当時のモンマルトルの雰囲気などを描き出した、画家モディリアーニの最晩年のドラマ」とあります。また解説には次のように記されています。
「この作品『モディリアーニ~真実の愛~』が描くのは画家モディリアーニが死に至るまでの最後の1年間の姿である。作品を商売の道具と考えず、アルコールに薬とやりたいようにやり続けるモディリアーニ、その対照として描かれる作品を売り、名声を高めてきたピカソ。物語はこのふたりのその才能を認めながらも反発し続けるライバル関係、ユトリロ、マックス・ジャコブらとの固い友情、当時のモンパルナス、サロンに集う芸術家たちの姿をモディリアーニとジャンヌの愛の関係を軸に捉えていく」。(ムービーネット)

高階秀爾(たかしな しゅうじ);1932年東京生まれ.東京大学教養学部卒業.専門は西洋美術史.東京大学名誉教授,大原美術館館長,京都造形芸術大学大学院長,同比較芸術学研究センター所長.主な著書に,『名画を見る眼』『続 名画を見る眼』『芸術のパトロンたち』(以上,岩波新書)『フィレンツェ』(中公新書)『フランス絵画史』(講談社学術文庫)『美の思索家たち』『西洋の眼,日本の眼』(青土社)ほか多数.












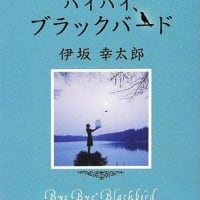







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます