 平成25年9月25日(水)
平成25年9月25日(水)
「アッくんさん アッくんさん こちらは現地リポーターのイチョウです。
私は今 開田城土塁公園に来ています。
開田城は1辺が70mの四角形で
平地に土塁と堀を設け
石垣や城のない館城(かんじょう)と呼ばれるものでした。
戦国時代の前半
国衆のひとり 中小路氏の居館だったそうです。
土塁は堀を掘った土で造られています。
土塁の高さは約2mで幅6m
堀は深さ1.2~2.3mで幅8mなので
堀底と土塁の高低差は3~4mあったようです。
脚立では届かないかも・・・
写真の壁は土塁の盛り方をタイルでデザイン化したもので
盛り方の様子が伺えます。

以上 開田城土塁公園から
イチョウくんの現地レポートでした!」
パチン!(電源OFF)
「あのぉ・・・
実際にみると大きいね
 」
」「掘って盛ったというけれど・・・
3~4mの高低差
土木仕事としてはシンドかっただろうね」
「だよね。ボクたちには無理だね
 」
」「あたりまえでしょ
スコップどころか・・・
鉛筆で 次の日にミが入るくらいだから
 」
」(写真の場所はココです!)











 》
》



 」
」 」
」 。。。」
。。。」 」
」
 」
」






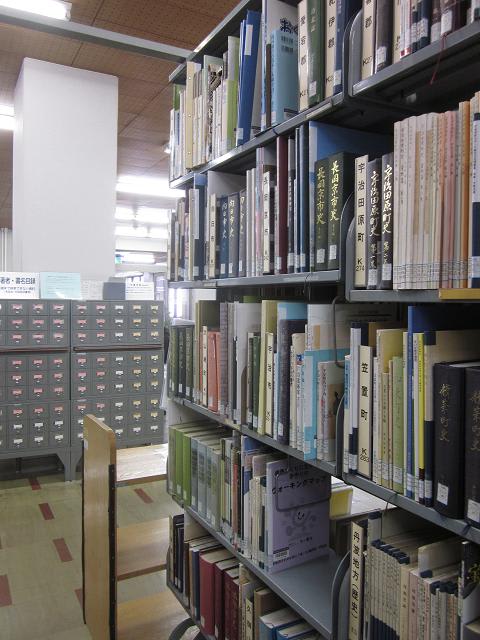
 」
」




 」
」
 」
」