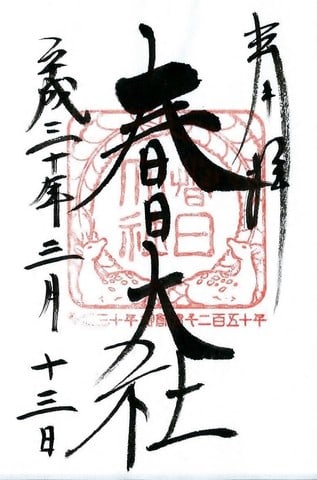地蔵禅院に隣接して耳慣れない御祭神の神社「玉津岡神社」がありました。
創建は、6世紀中頃で、元は「椋本天神」とも呼ばれていました。
天平3年(731)に、橘諸兄により、現在地に再建されたと伝わっています。
明治11年、井手郷の各村合併により神社も当社にまとめられました。
本殿は、貞享4年(1687)再建の春日造りで、京都府登録文化財。
境内末社に井手の里を橘氏の本拠地とした、橘諸兄とその一族である
楠木正成を合祀した「橘神社」があります。
主祭神 下照比賣命 欽明天皇元年(540)兎手玉津岡の南に降臨
大 神 六柱
•下照比賣命 大国主命の娘で味耜高彦根神(アジスキタカヒコネノカミ)の妹
•天兒屋根命
•少彦名命 大国主命と共に日本の国造りに力を尽
•素戔嗚命
•味耜高彦根命 大国主神と宗像三女神のタキリビメの間の子
•菅原道真公
玉津岡鎮座・八王子社・下照比賣命、
西垣内鎮座・春日社・祭神 天兒屋根命、
宮の前鎮座・田中社・祭神 少彦名命
西前田鎮座・八坂社・祭神 素戔嗚命、
玉の井鎮座・天神社・祭神 味耜高彦根命 下照比賣命
五社が八王子社殿(玉岡の社)に合祭している.
玉津岡神社と改称された後、有王天満宮 祭神 菅原道真が合祀された。
時代の変遷の中で、社の名前が変わったり、合祀されたりしてとても分かり難い…


神社の石標と略記


坂道の参道と一の鳥居


二の鳥居と扁額


急な石段を上がり三の鳥居を潜ると拝殿(舞殿)


蛙(カワズ)の水の注ぎ口の手水舎 (手を浄めるだけでなく、「心洗水」です)


向拝の付いた幣殿、本殿


狛犬

向拝の屋根瓦に神紋「山吹水(ながれ山吹)」紋
(「菊水」紋に似ていますが異なります。)
向拝の欄間彫刻等には珍しいものが…

中央面は鶴と松


左面は蝙蝠?と梅 右面は親子亀と竹
松竹梅や鶴亀は吉祥のスタンダードですが蝙蝠は初めてみました…?
中国では、蝙蝠は福の韻をふむため幸福、長寿の縁起物らしいですが…


手水舎に蛙の注ぎ口に続き、「木鼻」の左右にも阿吽の蛙さんが…
古来より井手は山吹と共に、歌枕になるほど、美しい声で鳴く
「蛙(カジカカワズ)」の名所だそうで、それに由来するのか…
瓦にも…


波兎と?
境内には、天照大神を祀る太神宮社、橘諸兄を祀る橘神社など13の末社があります。



太神宮社 橘神社 八幡宮社


八百神社、多賀神社、竈神社、大黒神社、恵比須神社、厳島神社、住吉神社、水分神社、山上神社、稲荷神社の末社
(雑記帳の記載にあたっては、略記、井手町HPなどを参考にさせていただきました。)
創建は、6世紀中頃で、元は「椋本天神」とも呼ばれていました。
天平3年(731)に、橘諸兄により、現在地に再建されたと伝わっています。
明治11年、井手郷の各村合併により神社も当社にまとめられました。
本殿は、貞享4年(1687)再建の春日造りで、京都府登録文化財。
境内末社に井手の里を橘氏の本拠地とした、橘諸兄とその一族である
楠木正成を合祀した「橘神社」があります。
主祭神 下照比賣命 欽明天皇元年(540)兎手玉津岡の南に降臨
大 神 六柱
•下照比賣命 大国主命の娘で味耜高彦根神(アジスキタカヒコネノカミ)の妹
•天兒屋根命
•少彦名命 大国主命と共に日本の国造りに力を尽
•素戔嗚命
•味耜高彦根命 大国主神と宗像三女神のタキリビメの間の子
•菅原道真公
玉津岡鎮座・八王子社・下照比賣命、
西垣内鎮座・春日社・祭神 天兒屋根命、
宮の前鎮座・田中社・祭神 少彦名命
西前田鎮座・八坂社・祭神 素戔嗚命、
玉の井鎮座・天神社・祭神 味耜高彦根命 下照比賣命
五社が八王子社殿(玉岡の社)に合祭している.
玉津岡神社と改称された後、有王天満宮 祭神 菅原道真が合祀された。
時代の変遷の中で、社の名前が変わったり、合祀されたりしてとても分かり難い…


神社の石標と略記


坂道の参道と一の鳥居


二の鳥居と扁額


急な石段を上がり三の鳥居を潜ると拝殿(舞殿)


蛙(カワズ)の水の注ぎ口の手水舎 (手を浄めるだけでなく、「心洗水」です)


向拝の付いた幣殿、本殿


狛犬

向拝の屋根瓦に神紋「山吹水(ながれ山吹)」紋
(「菊水」紋に似ていますが異なります。)
向拝の欄間彫刻等には珍しいものが…

中央面は鶴と松


左面は蝙蝠?と梅 右面は親子亀と竹
松竹梅や鶴亀は吉祥のスタンダードですが蝙蝠は初めてみました…?
中国では、蝙蝠は福の韻をふむため幸福、長寿の縁起物らしいですが…


手水舎に蛙の注ぎ口に続き、「木鼻」の左右にも阿吽の蛙さんが…
古来より井手は山吹と共に、歌枕になるほど、美しい声で鳴く
「蛙(カジカカワズ)」の名所だそうで、それに由来するのか…
*木鼻とは
「木の先端」という意味の「木端(きばな)」が転じて「木鼻」に書き換えられたものです。
頭貫などの水平材(横木)が柱から突き出した部分に施された彫刻などの装飾をいいます。
よく見かけるのは「象鼻・獅子鼻・獏鼻…」
「木の先端」という意味の「木端(きばな)」が転じて「木鼻」に書き換えられたものです。
頭貫などの水平材(横木)が柱から突き出した部分に施された彫刻などの装飾をいいます。
よく見かけるのは「象鼻・獅子鼻・獏鼻…」
瓦にも…


波兎と?
境内には、天照大神を祀る太神宮社、橘諸兄を祀る橘神社など13の末社があります。



太神宮社 橘神社 八幡宮社


八百神社、多賀神社、竈神社、大黒神社、恵比須神社、厳島神社、住吉神社、水分神社、山上神社、稲荷神社の末社
(雑記帳の記載にあたっては、略記、井手町HPなどを参考にさせていただきました。)