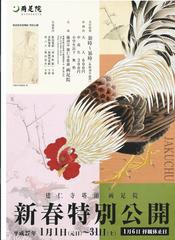妙法院第479回仏教文化講座を聴講してきました。
講師は、菅原信海門主で、「江戸初期の天台僧慈性」
開講の前に、蓮華王院「三十三間堂」で読経があります。
お経の本を、お借りして、千手観音の内陣に入れて頂き
執事長を導師に、皆で観音経、般若心経を読経。
妙法院本坊へ移動して、いよいよ開講です。
浅学の者には、余り耳慣れない「慈性」という僧。
先ず、その生い立ち、経歴の紹介がありました。
名門、日野家の家系図でその位置付けがなされ、
名門の出であるが故か、
かの有名な、「天海僧正」に従って「家康」に会い、
以後、天海と共に朝廷と幕府を結ぶキーマンになります。
若くして「青蓮院院家尊勝院」住持、
15歳で家康の命で「多賀大社別当不動院」を兼務。
そのキーマンが「慈性日記」を記していたのだから貴重な資料です。
慶長19年(1614)〜寛永20年(1643)ですから、秀吉の没後
大阪冬の陣、夏の陣を経て、徳川政権が発足した当時の時代背景や
多くの事柄、それに伴う天台僧侶の活動が詳細に記されているとのこと。
大阪冬の陣、夏の陣の頃、天海に従って、家康の御前での天台論議、伝授等に
20回近く行っていたりしている。伝授だけなら数日で終わるはずだから、
それは口実で、もっとキナ臭い遣り取りがあったのでは…と。
家康の神号について
神君家康公
唯一神道・明神号 (吉田神道)神龍院梵舜(豊国廟社僧) ← 金地院崇伝
山王一実神道・権現号 天海 ↓
権現=諾尊いざなぎの尊・冊尊いざなみの尊
明神=相国官位相当
御前論議 喜多院・天海
山王一実神道=本命元神=一切諸神は山王権現の分身なり
山王三聖=大宮
二宮
聖真子 薬師 釈迦 阿弥陀
山王権現 東照大権現 摩多羅神
(薬師如来)
東照 「東に照る」
「天に照る」皇室の祖先神=天照大神=太陽的存在
東から昇る ⇒ 天空に輝き ⇒ 天に照る
徳川幕府の天下支配を込めた「神号」
空 = 真 諦 = 仏の立場 仏 = 薬師如来(本地仏)
仮 = 俗 諦 = 世俗の立場 人間= 家康(現世の英雄)
中 = 中道第一義諦 = 真俗一如の立場 神 = 東照大権現(垂迹神)
神君 ⇒ 「神」・東照大権現 = 「君」・君主(家康)
阿弥陀如来・西方極楽浄土 東方薬師瑠璃光浄土・薬師如来
↓
観世音菩薩 東
南方補陀落浄土
講師は、菅原信海門主で、「江戸初期の天台僧慈性」
開講の前に、蓮華王院「三十三間堂」で読経があります。
お経の本を、お借りして、千手観音の内陣に入れて頂き
執事長を導師に、皆で観音経、般若心経を読経。
妙法院本坊へ移動して、いよいよ開講です。
浅学の者には、余り耳慣れない「慈性」という僧。
先ず、その生い立ち、経歴の紹介がありました。
名門、日野家の家系図でその位置付けがなされ、
名門の出であるが故か、
かの有名な、「天海僧正」に従って「家康」に会い、
以後、天海と共に朝廷と幕府を結ぶキーマンになります。
若くして「青蓮院院家尊勝院」住持、
15歳で家康の命で「多賀大社別当不動院」を兼務。
そのキーマンが「慈性日記」を記していたのだから貴重な資料です。
慶長19年(1614)〜寛永20年(1643)ですから、秀吉の没後
大阪冬の陣、夏の陣を経て、徳川政権が発足した当時の時代背景や
多くの事柄、それに伴う天台僧侶の活動が詳細に記されているとのこと。
大阪冬の陣、夏の陣の頃、天海に従って、家康の御前での天台論議、伝授等に
20回近く行っていたりしている。伝授だけなら数日で終わるはずだから、
それは口実で、もっとキナ臭い遣り取りがあったのでは…と。
家康の神号について
神君家康公
唯一神道・明神号 (吉田神道)神龍院梵舜(豊国廟社僧) ← 金地院崇伝
山王一実神道・権現号 天海 ↓
権現=諾尊いざなぎの尊・冊尊いざなみの尊
明神=相国官位相当
御前論議 喜多院・天海
山王一実神道=本命元神=一切諸神は山王権現の分身なり
山王三聖=大宮
二宮
聖真子 薬師 釈迦 阿弥陀
山王権現 東照大権現 摩多羅神
(薬師如来)
東照 「東に照る」
「天に照る」皇室の祖先神=天照大神=太陽的存在
東から昇る ⇒ 天空に輝き ⇒ 天に照る
徳川幕府の天下支配を込めた「神号」
空 = 真 諦 = 仏の立場 仏 = 薬師如来(本地仏)
仮 = 俗 諦 = 世俗の立場 人間= 家康(現世の英雄)
中 = 中道第一義諦 = 真俗一如の立場 神 = 東照大権現(垂迹神)
神君 ⇒ 「神」・東照大権現 = 「君」・君主(家康)
阿弥陀如来・西方極楽浄土 東方薬師瑠璃光浄土・薬師如来
↓
観世音菩薩 東
南方補陀落浄土