生憎の雨空の中、「仏法興隆花まつり千僧法要」が東大寺大仏殿で営まれました。
この法要は、昭和43年4月26日より毎年続けられている法要で全国各地域・各宗派から、
多くの僧侶が参集し、宗派の垣根を越えお互いを尊重し合い、慶讃の一般の人々と集い、営まれています。
天気が良ければ、南大門の傍の、金鐘ホールからの500人以上の一大行列で大仏殿まで繰り広げられたそうですが、
今回は、雨のため中門から傘をさしての大仏殿への入堂でした。
太鼓が大仏殿にとどろき、雅楽が奏でられ、法螺貝の音とともに、次々と入堂してきます。
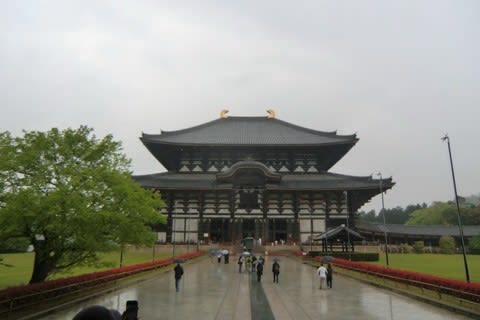
雨に煙る大仏殿


大佛・毘盧遮那仏


待機する楽人 雅楽の笙と温度保治用の電気コンロ器


両翼の法螺貝の音に迎えられ、僧侶が続々と入堂


大佛の台座周辺は、僧侶で埋め尽くされます


撒かれた散華

法螺吹奏と導師(モニター映像の写真)


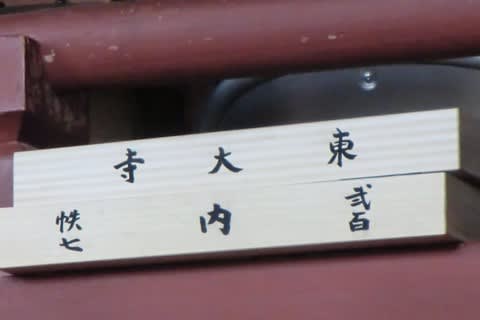
準備された般若心経と経箱です。何巻あるのでしょう…


これぞ大般若転読と思わせる数です。堂内の参詣者にも僧侶が廻って転読の風で祈祷。


各宗派の団体が声明、念仏などを大佛様の前で唱えます。(読経写真はモニター映像)

法要が終わって
花まつり千僧法要
大仏殿法要 次第
先、 開式の辞 司 会
次、 惣 礼 会長行発声
次、 法螺吹奏 金峯山青年僧の会
次、 声明散華 天台仏教青年連盟
次、 大衆着座
次、 表 白
次、 開経偈
次、 加盟団体法要
声明(四智梵語) 全真言宗青年連盟
声明念仏 融通念仏宗青年会
般若心経 全国曹洞宗青年会
大般若経転読
妙法蓮華経観世音菩薩普門品偈
木 剣 全国日蓮宗青年会
念 仏 全国浄土宗青年会
次、 回 向
次、 四弘誓願(しぐせいがん)
次、 法螺吹奏 金峯山青年僧の会
次、 大衆起立
次、 惣 礼 会長行発声
次、 閉式の辞 司 会
終了後、アショカピラー法要




この像はブッダによる初転法輪(初めての説法)の地で知られる
サルナートの獅子柱頭・アショカピラーを模ったものです。
インドのアショカ王が建立した石柱「アショカピラー」の頭部を復元した3匹の獅子の記念碑です
1988年に法要を記念してこの宝塔が建立されました。
今、世界ではイスラム国によるテロ事件が頻発し、多くの人々が殺傷され、被害者、難民問題が生じる中、
国内の宗教者が一堂に会し、平和を祈願、東北はじめ震災で命を亡くされた方々を追悼する場があることは
素晴らしいことです。
日本人こそ「神仏習合」、「拘らない心」を世界に発信していかねばならない…と感じました。
世界の宗教指導者が延暦寺(大津市)に集う「比叡山宗教サミット」が30周年を記念し、
今年8月に「世界宗教者平和の祈りの集い」が同寺や京都市で開かれるそうです。
行けるものなら行ってみたいと思っています。
帰路こんな光景も…


鹿が松の新芽を…口の中、松ヤニ大丈夫?
この法要は、昭和43年4月26日より毎年続けられている法要で全国各地域・各宗派から、
多くの僧侶が参集し、宗派の垣根を越えお互いを尊重し合い、慶讃の一般の人々と集い、営まれています。
天気が良ければ、南大門の傍の、金鐘ホールからの500人以上の一大行列で大仏殿まで繰り広げられたそうですが、
今回は、雨のため中門から傘をさしての大仏殿への入堂でした。
太鼓が大仏殿にとどろき、雅楽が奏でられ、法螺貝の音とともに、次々と入堂してきます。
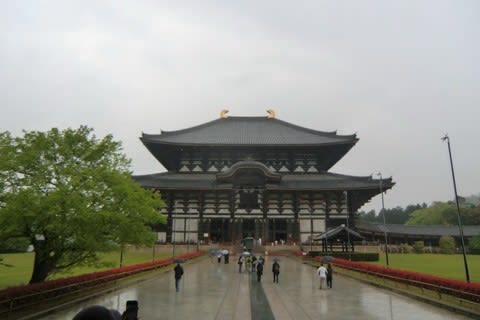
雨に煙る大仏殿


大佛・毘盧遮那仏


待機する楽人 雅楽の笙と温度保治用の電気コンロ器


両翼の法螺貝の音に迎えられ、僧侶が続々と入堂


大佛の台座周辺は、僧侶で埋め尽くされます


撒かれた散華

法螺吹奏と導師(モニター映像の写真)


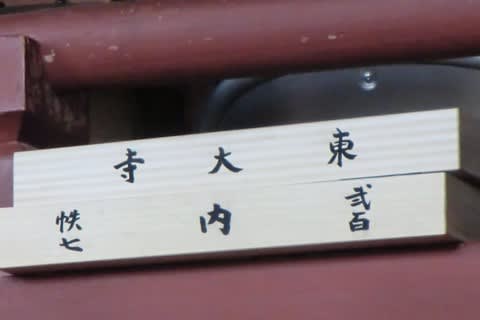
準備された般若心経と経箱です。何巻あるのでしょう…


これぞ大般若転読と思わせる数です。堂内の参詣者にも僧侶が廻って転読の風で祈祷。


各宗派の団体が声明、念仏などを大佛様の前で唱えます。(読経写真はモニター映像)

法要が終わって
花まつり千僧法要
大仏殿法要 次第
先、 開式の辞 司 会
次、 惣 礼 会長行発声
次、 法螺吹奏 金峯山青年僧の会
次、 声明散華 天台仏教青年連盟
次、 大衆着座
次、 表 白
次、 開経偈
次、 加盟団体法要
声明(四智梵語) 全真言宗青年連盟
声明念仏 融通念仏宗青年会
般若心経 全国曹洞宗青年会
大般若経転読
妙法蓮華経観世音菩薩普門品偈
木 剣 全国日蓮宗青年会
念 仏 全国浄土宗青年会
次、 回 向
次、 四弘誓願(しぐせいがん)
次、 法螺吹奏 金峯山青年僧の会
次、 大衆起立
次、 惣 礼 会長行発声
次、 閉式の辞 司 会
終了後、アショカピラー法要




この像はブッダによる初転法輪(初めての説法)の地で知られる
サルナートの獅子柱頭・アショカピラーを模ったものです。
インドのアショカ王が建立した石柱「アショカピラー」の頭部を復元した3匹の獅子の記念碑です
1988年に法要を記念してこの宝塔が建立されました。
今、世界ではイスラム国によるテロ事件が頻発し、多くの人々が殺傷され、被害者、難民問題が生じる中、
国内の宗教者が一堂に会し、平和を祈願、東北はじめ震災で命を亡くされた方々を追悼する場があることは
素晴らしいことです。
日本人こそ「神仏習合」、「拘らない心」を世界に発信していかねばならない…と感じました。
世界の宗教指導者が延暦寺(大津市)に集う「比叡山宗教サミット」が30周年を記念し、
今年8月に「世界宗教者平和の祈りの集い」が同寺や京都市で開かれるそうです。
行けるものなら行ってみたいと思っています。
帰路こんな光景も…


鹿が松の新芽を…口の中、松ヤニ大丈夫?


































































































































