京都府南丹市日吉町中世木で2016「第3回せつぶん草まつり」が3月6日開催されました。
天気予報がかんばしく無さそうだったので、5日に出掛けてきました。
京都縦貫道園部ICから10分程度で道路も整備され快適なドライブ。
ICを出ると、すぐに道の駅「京都新光悦村」次には「スプリングスひよし」。
府道364号、田園風景の中を進むと、せつぶん草祭の黄色い幟の出迎えで「中世木公民館」の受付へ。
先日、大阪鶴見区の「咲くやこの花館」で大事にガラスケースで咲いていた小さなせつぶん草の花…
また、2月25日京都、北野天神梅花祭の出店の山野草の中にも鉢植えの小さな花…
「群生」が楽しみ…、期待に違わず可憐に沢山咲いてい居ました。
「数日前まで、積雪で少し花の形が悪くなっているのもあります…」と
地元で世話をされている方のお話しもありましたが、いえいえ十分堪能させて頂きました。


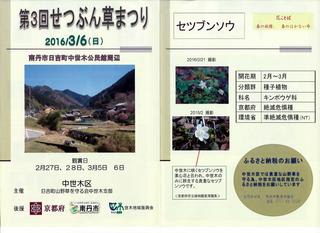









 「セツブンソウ」(キンポウゲ科)
「セツブンソウ」(キンポウゲ科)
節分の頃に花を咲かせるのでセツブンソウです。
日本原産の植物で、関東より西の地域に分布します。石灰岩地帯を好み、落葉樹林内の斜面などにまとまって自生します。
凍てつくような真冬に芽を出して花を咲かせ、後に葉を茂らせ、木々の新緑がまぶしくなる晩春には茎葉が枯れて
地下の球根(塊茎)の状態で秋まで休眠に入ります。
根は秋頃から地下で伸び始めますが、セツブンソウが地上に顔を見せるのはせいぜい春の3ヶ月程度です。
可憐さとはかなさが魅力の山野草で、地植えや鉢植えで楽しめるようです。
球根ですが、種子からも発芽し3年位してから花が咲くそうです。
地面から花茎を伸ばして細かく切れ込んだ葉っぱ(総苞片)を開き、その先端に可憐な白い花が1輪咲きます。
花びらに見える部分は萼で通常5枚あります。本来の花びらは退化して、先端が2又に分かれた黄色い蜜腺(ネクター)になっており、雄しべを囲むようにつきます。
蜜腺は名前の通りで、あまい蜜を出す器官です。雄しべの先端に付いている花粉が入った葯も紫色で鮮やかです。
球根の大きさは径1.5cmほどで、先端の尖った球形です。

もう一種類咲いていたのは、「アズマイチゲ」です。



「アズマイチゲ(東一華)」(キンポウゲ科 イチリンソウ属)
「東」は関東を意味しているそうですが、全国各地に自生しています。
「一華」はイチリンソウ属の花の一名で、花が茎の先に1つだけつくことからきています。
草丈15~20cmほどの小さな多年草です。 茎を1本立て、茎頂に三枚の小葉(三出複葉)からなる3枚の葉を輪生状につけ、
その中心から花茎を1本ほぼ直立させて径2~3cmほどの可憐な花を1輪つけます。
花被片(ガク片で花弁はない)は8~13枚で白色。しばしば花被片の裏側が淡紫色になります。根生葉(地際の葉)は多くの場合花時にはありません。
落葉樹の疎林や半日陰になる林縁に生育します。石灰岩地を好みます。
中世木には、他にも春の山野草が色々咲くそうです。
ユキワリイチゲ(キンポウゲ科)、イチリンソウ(キンポウゲ科)、ニリンソウ(キンポウゲ科)、ミスミソウ(キンポウゲ科)、
ヤマエンゴサク(ケシ科)、キバナノアマナ(ユリ科)、ヒトリシズカ(センリョウ科)など。
これらを総称して、スプリング・エフェメラル(Spring ephemeral)と言い、春先に花をつけ、夏まで葉をつけると、あとは地下で過ごす一連の草花。春植物(はるしょくぶつ)ともいう。直訳すると「春の儚いもの」「春の短い命」というような意味で、
「春の妖精」とも呼ばれています。
これらの花は、虫媒花で、受粉を手伝う、蜂や蝶を意味することもあるとか。
公民館には手書きのパネルが掲示されていました。
「何故中世木地区に希少植物が多いのか?」
【「里山として手入れが行き届いている点や、気象条件もあるが、最大の要因は地質にある。」と光田先生(同志社大学理工学部准教授 京都府指定希少野生生物保全検討委員会委員 種子植物、シダ植物等植物学者)は地質図で説明された。(写真が上手く写らなかったので地図は省略)
・黄緑色427地質 ・京都の鞍馬、貴船は同じ緯度の右側縦形の黄緑色の所 ・光田先生は緑色岩帯と説明された。
枕状溶岩は、海底で火山が噴火した時に、水中に噴出したマグマによって、枕状に作られたもの。同時に緑色岩(緑色岩は海底堆積の玄武岩を含み、石灰岩同様に石灰分が多く含まれる。)もその時に作られる。
*光田先生は、最高級の庭石とされる京都の鞍馬石や貴船石と同じ地質(緑色岩帯)にあることが一番の要因と考えているとされた。
石灰岩の中を流れてきた水にはカルシュウム分が多く含まれる。
カルシュウム分が多く含まれる水が希少植物に作用しているのかも分からない。
(但し、光田先生はそこまで言及されていない。このパネル作成者の推論。中世木川の水質検査や分析が必要)】
中世木川、木住川と田原川が合流する手前辺りに「枕状溶岩の露出」しているところが手書きの地図で示されていました。
これらの詳細に興味のある方は、「地質調査総合センター・京都西北部地域の地質」を検索してみてください。
セツブンソウ(節分草)は、京都府カテゴリーでは「絶滅危惧種」です。
詳しくは、2015「京都府レッドデータブック」で確認してください。
天気予報がかんばしく無さそうだったので、5日に出掛けてきました。
京都縦貫道園部ICから10分程度で道路も整備され快適なドライブ。
ICを出ると、すぐに道の駅「京都新光悦村」次には「スプリングスひよし」。
府道364号、田園風景の中を進むと、せつぶん草祭の黄色い幟の出迎えで「中世木公民館」の受付へ。
先日、大阪鶴見区の「咲くやこの花館」で大事にガラスケースで咲いていた小さなせつぶん草の花…
また、2月25日京都、北野天神梅花祭の出店の山野草の中にも鉢植えの小さな花…
「群生」が楽しみ…、期待に違わず可憐に沢山咲いてい居ました。
「数日前まで、積雪で少し花の形が悪くなっているのもあります…」と
地元で世話をされている方のお話しもありましたが、いえいえ十分堪能させて頂きました。


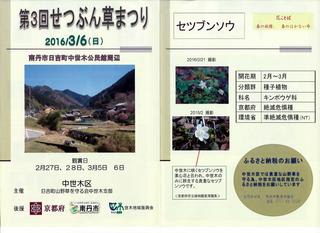










節分の頃に花を咲かせるのでセツブンソウです。
日本原産の植物で、関東より西の地域に分布します。石灰岩地帯を好み、落葉樹林内の斜面などにまとまって自生します。
凍てつくような真冬に芽を出して花を咲かせ、後に葉を茂らせ、木々の新緑がまぶしくなる晩春には茎葉が枯れて
地下の球根(塊茎)の状態で秋まで休眠に入ります。
根は秋頃から地下で伸び始めますが、セツブンソウが地上に顔を見せるのはせいぜい春の3ヶ月程度です。
可憐さとはかなさが魅力の山野草で、地植えや鉢植えで楽しめるようです。
球根ですが、種子からも発芽し3年位してから花が咲くそうです。
地面から花茎を伸ばして細かく切れ込んだ葉っぱ(総苞片)を開き、その先端に可憐な白い花が1輪咲きます。
花びらに見える部分は萼で通常5枚あります。本来の花びらは退化して、先端が2又に分かれた黄色い蜜腺(ネクター)になっており、雄しべを囲むようにつきます。
蜜腺は名前の通りで、あまい蜜を出す器官です。雄しべの先端に付いている花粉が入った葯も紫色で鮮やかです。
球根の大きさは径1.5cmほどで、先端の尖った球形です。

もう一種類咲いていたのは、「アズマイチゲ」です。



「アズマイチゲ(東一華)」(キンポウゲ科 イチリンソウ属)
「東」は関東を意味しているそうですが、全国各地に自生しています。
「一華」はイチリンソウ属の花の一名で、花が茎の先に1つだけつくことからきています。
草丈15~20cmほどの小さな多年草です。 茎を1本立て、茎頂に三枚の小葉(三出複葉)からなる3枚の葉を輪生状につけ、
その中心から花茎を1本ほぼ直立させて径2~3cmほどの可憐な花を1輪つけます。
花被片(ガク片で花弁はない)は8~13枚で白色。しばしば花被片の裏側が淡紫色になります。根生葉(地際の葉)は多くの場合花時にはありません。
落葉樹の疎林や半日陰になる林縁に生育します。石灰岩地を好みます。
中世木には、他にも春の山野草が色々咲くそうです。
ユキワリイチゲ(キンポウゲ科)、イチリンソウ(キンポウゲ科)、ニリンソウ(キンポウゲ科)、ミスミソウ(キンポウゲ科)、
ヤマエンゴサク(ケシ科)、キバナノアマナ(ユリ科)、ヒトリシズカ(センリョウ科)など。
これらを総称して、スプリング・エフェメラル(Spring ephemeral)と言い、春先に花をつけ、夏まで葉をつけると、あとは地下で過ごす一連の草花。春植物(はるしょくぶつ)ともいう。直訳すると「春の儚いもの」「春の短い命」というような意味で、
「春の妖精」とも呼ばれています。
これらの花は、虫媒花で、受粉を手伝う、蜂や蝶を意味することもあるとか。
公民館には手書きのパネルが掲示されていました。
「何故中世木地区に希少植物が多いのか?」
【「里山として手入れが行き届いている点や、気象条件もあるが、最大の要因は地質にある。」と光田先生(同志社大学理工学部准教授 京都府指定希少野生生物保全検討委員会委員 種子植物、シダ植物等植物学者)は地質図で説明された。(写真が上手く写らなかったので地図は省略)
・黄緑色427地質 ・京都の鞍馬、貴船は同じ緯度の右側縦形の黄緑色の所 ・光田先生は緑色岩帯と説明された。
枕状溶岩は、海底で火山が噴火した時に、水中に噴出したマグマによって、枕状に作られたもの。同時に緑色岩(緑色岩は海底堆積の玄武岩を含み、石灰岩同様に石灰分が多く含まれる。)もその時に作られる。
*光田先生は、最高級の庭石とされる京都の鞍馬石や貴船石と同じ地質(緑色岩帯)にあることが一番の要因と考えているとされた。
石灰岩の中を流れてきた水にはカルシュウム分が多く含まれる。
カルシュウム分が多く含まれる水が希少植物に作用しているのかも分からない。
(但し、光田先生はそこまで言及されていない。このパネル作成者の推論。中世木川の水質検査や分析が必要)】
中世木川、木住川と田原川が合流する手前辺りに「枕状溶岩の露出」しているところが手書きの地図で示されていました。
これらの詳細に興味のある方は、「地質調査総合センター・京都西北部地域の地質」を検索してみてください。
セツブンソウ(節分草)は、京都府カテゴリーでは「絶滅危惧種」です。
詳しくは、2015「京都府レッドデータブック」で確認してください。










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます