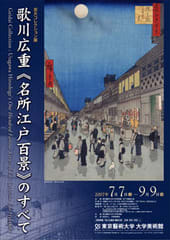久しぶりに、なんとも爽やかな話を読んだ!
そして面白かった!
あまりにも爽やか系だと、どうもへそ曲がりの私としては
「物足りない」とか思ってしまうのだけど、
『しゃべれども しゃべれども』はよかった。
(新米)噺家の主人公、彼の元に、なぜか口下手な人たちが集まってくる。
トラウマのせいで吃音が出てしまう幼馴染、
口下手のために失恋、うまく感情表現できないすっごい美人、
大阪弁を直そうとしないためにクラスでは敵視され、親ともぶつかってばかりの小学生、
言いたいことが言えないプロ野球解説者。
みんながなぜか落語を習ってみよう、自分たちではなしてみよう、
ということになり、
いろんな困難を乗り越えて手作りの高座で発表会。
それぞれのトラウマをいつの間にか乗り越える・・・
というベタな展開ではあるのだけれど、比較的長い話であるのにもかかわらず、
私的にも面白い。
たぶん、登場人物が魅力的なのだろう。
メインの人物だけでなく、おばあちゃん、憧れのヒロイン、クラスのボス的存在の男の子、落語の師匠たち。
みんなそれぞれいい味出している。
映画化されたときのキャストも好印象なのかも。
(香里奈ってかわカッコいい!)
江戸文化が大好きな友達が、落語を聞きに行くのが趣味、
とか言っていたけど、
私も連れてって欲しいなぁ、なんて思ったりして。
そして面白かった!
あまりにも爽やか系だと、どうもへそ曲がりの私としては
「物足りない」とか思ってしまうのだけど、
『しゃべれども しゃべれども』はよかった。
(新米)噺家の主人公、彼の元に、なぜか口下手な人たちが集まってくる。
トラウマのせいで吃音が出てしまう幼馴染、
口下手のために失恋、うまく感情表現できないすっごい美人、
大阪弁を直そうとしないためにクラスでは敵視され、親ともぶつかってばかりの小学生、
言いたいことが言えないプロ野球解説者。
みんながなぜか落語を習ってみよう、自分たちではなしてみよう、
ということになり、
いろんな困難を乗り越えて手作りの高座で発表会。
それぞれのトラウマをいつの間にか乗り越える・・・
というベタな展開ではあるのだけれど、比較的長い話であるのにもかかわらず、
私的にも面白い。
たぶん、登場人物が魅力的なのだろう。
メインの人物だけでなく、おばあちゃん、憧れのヒロイン、クラスのボス的存在の男の子、落語の師匠たち。
みんなそれぞれいい味出している。
映画化されたときのキャストも好印象なのかも。
(香里奈ってかわカッコいい!)
江戸文化が大好きな友達が、落語を聞きに行くのが趣味、
とか言っていたけど、
私も連れてって欲しいなぁ、なんて思ったりして。