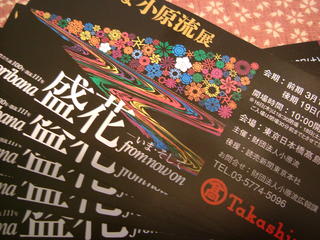子どもが6年間お世話になった小学校。
卒業式を終え、入学式はまだだけど、明日4月からは中学生。
いまから思ってもとってもいい学校、そして学校生活でした。
広い校庭が自慢で、都心の方の校庭が狭い小学校を見ると「こんなの学校じゃな~い!」と言ったものでした。
ある日校長先生がその校庭の一部を畑にする、と言ったときは大ブーイングの嵐。
それでも残ったまだまだ広い校庭で休みの日は野球チームが2面に分かれて練習できるほどです。
その校庭でいろんなことをして遊びました。
一輪車に乗れるようになりたくて、なんども転びながら練習して、ケガのうえからまた擦り傷を作ったりして、いまでも一生残るようなキズがひじに残っています。
その次は竹馬で、背が低いのに一番高い竹馬に悠々と乗れるようになり、みんなのことをいつも見下ろしていました。「竹馬名人」の異名をとったことも。
先生にも恵まれました。
女性の先生はとても厳しくて、男性の先生は反対にとても優しくしてくれました。
いつも先生にいろんな話を聞いてもらっていたように思います。
いろんな友達もできました。
女の子同士で遊ぶのが好きなようですが、男子とも反発することなく仲良く過ごせた6年間だと思います。
昔は「男子~」「女子~」とか言って分かれてしまい、妙に意識しあってケンカばかりしていましたが、今はそうでもないのでしょうか?
勉強も頑張りました。
保護者会などで教室に行ったときに掲示してある習字、作文、研究発表などを見るのが私の楽しみでした。
音楽委員の仕事も頑張って、いつもなにかの伴奏のピアノを弾いていました。
自信をもって中学生になれるようなしっかりとした土台を作ってきたこの6年間。この小学校のことは娘も私も忘れる事はないと思います。本当にお世話になりました。
卒業式を終え、入学式はまだだけど、明日4月からは中学生。
いまから思ってもとってもいい学校、そして学校生活でした。
広い校庭が自慢で、都心の方の校庭が狭い小学校を見ると「こんなの学校じゃな~い!」と言ったものでした。
ある日校長先生がその校庭の一部を畑にする、と言ったときは大ブーイングの嵐。
それでも残ったまだまだ広い校庭で休みの日は野球チームが2面に分かれて練習できるほどです。
その校庭でいろんなことをして遊びました。
一輪車に乗れるようになりたくて、なんども転びながら練習して、ケガのうえからまた擦り傷を作ったりして、いまでも一生残るようなキズがひじに残っています。
その次は竹馬で、背が低いのに一番高い竹馬に悠々と乗れるようになり、みんなのことをいつも見下ろしていました。「竹馬名人」の異名をとったことも。
先生にも恵まれました。
女性の先生はとても厳しくて、男性の先生は反対にとても優しくしてくれました。
いつも先生にいろんな話を聞いてもらっていたように思います。
いろんな友達もできました。
女の子同士で遊ぶのが好きなようですが、男子とも反発することなく仲良く過ごせた6年間だと思います。
昔は「男子~」「女子~」とか言って分かれてしまい、妙に意識しあってケンカばかりしていましたが、今はそうでもないのでしょうか?
勉強も頑張りました。
保護者会などで教室に行ったときに掲示してある習字、作文、研究発表などを見るのが私の楽しみでした。
音楽委員の仕事も頑張って、いつもなにかの伴奏のピアノを弾いていました。
自信をもって中学生になれるようなしっかりとした土台を作ってきたこの6年間。この小学校のことは娘も私も忘れる事はないと思います。本当にお世話になりました。












 『テクニック』
『テクニック』