ある事情から中国の民族楽器による名曲とはどういうものか、調べようと思い立ち「中国民楽四大家」なるCDを購入、聴いてみた。因みにこのCDで取り上げている民族楽器とは「板胡:バンフー」「二胡:アルフー」「琵琶:ピーパー」「嗩ノウ=(クチ偏)に内:スオナー」の4つ。 中国の伝統音楽に明るい方には常識だろうが、初めて正面から耳を傾けた者としての第1印象から・・・・。
* 「板胡」と「二胡」の音色が聴き分けられたか? というと正直自信はない。音域的にも差は感じられなかった。前者は<幸福年>、後者は<二泉映月>
という題がついた曲。 どちらも霧深い湖面をたゆたう雰囲気、といえば良いだろうか。ヴァイオリンでこの感じが出せるか? 出ないだろう。
* 「琵琶」は日本に伝わり、鎌倉末期から室町前期にかけて流浪の民となった<法師>が弾き語りに用いた楽器である。弦の数や音域などで違いがあるそうだが、
法師が平家物語を語りながら、合間に挟まれる曲想(というよりは掛け声のような”合いの手)”を入れる。それにはトレモロと撥で強く弦を叩く奏法が
相応しい。それはこの中国琵琶でも同じ。<寒鴉戯水>。 私には琵琶の音が最も違和感が少ない。
* PCに内臓される漢字があてはまらないので「スオナー」と表記するが、この楽器は俗に「チャルメラ」の名で日本では知られる形状をしており、甲高い
音で速いパッセージを吹く。 因みに日本の朝廷に伝わり「雅楽」と総称される楽曲演奏に用いられる楽器群の中に、この「スオナー」は見当たらない。
(また、胡弓の類もみかけない。 この背景には何かがあるのだろう)。
さて、インドの民族楽器に<シタール>というのがあり、独特の音調と憂いに満ちた響きをもっている。気の利いたインド料理店ではBGMに流したり、ナマ演奏を聞かせてくれる。この<シタール>にはラヴィ・シャンカールという名人がいて、ロンドン交響楽団と共演で「シタール協奏曲」まである。それは私の好きな曲の一つだが、これまた、シタールが旋律を豊かに歌いあげることはあっても、民族楽器が集まって西洋音楽にいう「和声」を形作ることはない。「掛け合い」はどの民族音楽にもあるが、異なる音程を重ね合わせて旋律を増幅し、或は変型/発展させてゆく楽想は無い。これはインドだけでなく、中国にも日本にも発達しなかった。 よくいわれるような音階構成の違いよりも、和声の欠如は意義が大きく違う。その理由・背景は何か? 碩学による文化人類学的研究が既に世にはあるのかもしれないが、あれば知りたいものである。 近代数学との関連か?
幕末、多くのヨーロッパ人が日本に来たおり、幕府あるいは朝廷は接待の宴で雅楽に近いものから俗な謡・小唄・三味線と琴の合奏まで様々な音楽でもてなしたらしいが、ハリスやオールコックなどの日記類を読むと、5音だけの音階で、しかもメロデイだけの単調さに飽き飽きした、との感想ばかりだ。奇異な音調にしか映らなかった、というところか。
明治維新後、日本人は西洋音楽に接し(楽譜/音階/和声)の存在を知った。その驚きたるや大変なものであったろう。留学した人々が音楽理論と作曲法を学び、帰国後、日本の風土にあった唱歌や童謡、歌曲を大正時代にかけて創作した。それらが戦後長らく”初等教育における音楽教育”として情操教育上の効果を発揮したのは疑いない。 楽譜は読めないがカラオケはできる、こういう日本人は明治以後の音楽教育で造られた。また、小中学校段階での器楽教育やクラブ活動、これはアジアになかで日本にしか発達しなかった。その理由は? この辺りが現代日本人の自ら気づかぬ特異性なのだろう。 その特異性に気づいていない。
* 「板胡」と「二胡」の音色が聴き分けられたか? というと正直自信はない。音域的にも差は感じられなかった。前者は<幸福年>、後者は<二泉映月>
という題がついた曲。 どちらも霧深い湖面をたゆたう雰囲気、といえば良いだろうか。ヴァイオリンでこの感じが出せるか? 出ないだろう。
* 「琵琶」は日本に伝わり、鎌倉末期から室町前期にかけて流浪の民となった<法師>が弾き語りに用いた楽器である。弦の数や音域などで違いがあるそうだが、
法師が平家物語を語りながら、合間に挟まれる曲想(というよりは掛け声のような”合いの手)”を入れる。それにはトレモロと撥で強く弦を叩く奏法が
相応しい。それはこの中国琵琶でも同じ。<寒鴉戯水>。 私には琵琶の音が最も違和感が少ない。
* PCに内臓される漢字があてはまらないので「スオナー」と表記するが、この楽器は俗に「チャルメラ」の名で日本では知られる形状をしており、甲高い
音で速いパッセージを吹く。 因みに日本の朝廷に伝わり「雅楽」と総称される楽曲演奏に用いられる楽器群の中に、この「スオナー」は見当たらない。
(また、胡弓の類もみかけない。 この背景には何かがあるのだろう)。
さて、インドの民族楽器に<シタール>というのがあり、独特の音調と憂いに満ちた響きをもっている。気の利いたインド料理店ではBGMに流したり、ナマ演奏を聞かせてくれる。この<シタール>にはラヴィ・シャンカールという名人がいて、ロンドン交響楽団と共演で「シタール協奏曲」まである。それは私の好きな曲の一つだが、これまた、シタールが旋律を豊かに歌いあげることはあっても、民族楽器が集まって西洋音楽にいう「和声」を形作ることはない。「掛け合い」はどの民族音楽にもあるが、異なる音程を重ね合わせて旋律を増幅し、或は変型/発展させてゆく楽想は無い。これはインドだけでなく、中国にも日本にも発達しなかった。 よくいわれるような音階構成の違いよりも、和声の欠如は意義が大きく違う。その理由・背景は何か? 碩学による文化人類学的研究が既に世にはあるのかもしれないが、あれば知りたいものである。 近代数学との関連か?
幕末、多くのヨーロッパ人が日本に来たおり、幕府あるいは朝廷は接待の宴で雅楽に近いものから俗な謡・小唄・三味線と琴の合奏まで様々な音楽でもてなしたらしいが、ハリスやオールコックなどの日記類を読むと、5音だけの音階で、しかもメロデイだけの単調さに飽き飽きした、との感想ばかりだ。奇異な音調にしか映らなかった、というところか。
明治維新後、日本人は西洋音楽に接し(楽譜/音階/和声)の存在を知った。その驚きたるや大変なものであったろう。留学した人々が音楽理論と作曲法を学び、帰国後、日本の風土にあった唱歌や童謡、歌曲を大正時代にかけて創作した。それらが戦後長らく”初等教育における音楽教育”として情操教育上の効果を発揮したのは疑いない。 楽譜は読めないがカラオケはできる、こういう日本人は明治以後の音楽教育で造られた。また、小中学校段階での器楽教育やクラブ活動、これはアジアになかで日本にしか発達しなかった。その理由は? この辺りが現代日本人の自ら気づかぬ特異性なのだろう。 その特異性に気づいていない。















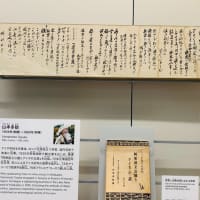









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます