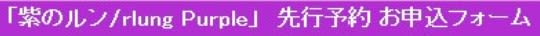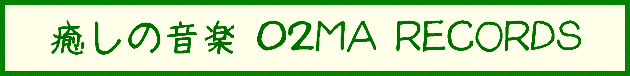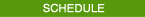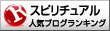大量のごろごろした石を横目に「那智の滝」へ向かいます。

水害前と同じ様に大変賑っていました。
こんな平安装束を纏っての参拝者も。
それが、今回逢いに行った方の発案であった事を夜に地元の人が通う勝浦一の海鮮居酒屋「吾作」さんで初めて知らされました。
「熊野」という言葉が復活するまだ何十年も前の時代の事です。
その頃、私達和歌山人ですらこのエリアを「南紀勝浦」と呼んでいました。
熊野詣に使われていた「熊野」と言う言葉は、
高度成長期の日本のバブル時代に、「南紀」という流行の言葉にすり替えられて忘れられてしまったと聞きました。
当時は大阪からでも半日以上かかる、最も交通の不便な僻地でした。
でもそこには昔からの「熊野」のそのままの姿が残っていました。
子供の頃の、その和歌山海南市からも遠い「南紀」に海水浴に連れて行かれた時の風景を覚えています。
そして「熊野」を取り戻すプロジェクトが、
その平安衣装の発案の時から始まったのでした。

御瀧は一体どうなっているのでしょう・・・

石段を下ります。

傍らには切り倒された丸太が積み上げられていました。

最初に飛び込んできた景色がこれ!

以前観た時とは違う景色が広がっていました。

瀧だけを観るとそうでもないのですが、

滝壺より下の鬱蒼としていた杜がなぎ倒され流され無くなっています。

ぽっかりと上空が開けた「那智の滝」がそこにはありました。

ここでも水の威力を痛感します。

水の時代の始まり。
風や地や火のうちでも昨年からの日本での災害を考えると、
一番強烈なのが水のエナジーなのかもしれないのを感じさせられてしまいます。

参拝所の舗装路が突然滑落していました。

あまりのその姿には声を無くしました。

あと、瀧の音が変わっていました。
「バサッ・バサッ・」と断続的に降り落ちる大きな水音は以前にはキオクにありません。
森がなくなり音の響く環境が変わった事もあるのでしょうが・・・

その滝口は、まるでバンザイ!しているかの様にも観えます。

たぶん・滝口の上流の地形も変化している事が考えられ、水の量が一定じゃなく断続的にまとまって落ちて「獅子おどし」的効果が起こっているのではないかという事でした。

至る所でなぎ倒された巨木の伐採された切株が観えます。

さらに近くにまで登ります。

これぞ立派な「那智の滝」です!

でも・この瀧の下方は以前からするとあり得ない光景が広がっていました。

巨木の根っこも剥き出しに、

とりあえず・ユンボがちょこちょこ動き回っていました。

でも・これが「変容」の現実です!
「無常」。
すべてのものは、これ以上細かく切り刻めないレベルでのフレームの連続で、
何一つ同じ状態をキープするものはありません。
今の「那智」はそれを大きな形で解り易く教えてくれます。

その夜に、今回逢いに行かせてもらった方より沢山の話を聞かせてもらいました。
その中の熊野三山の熊野権現の話。
「新宮」は過去、
「那智勝浦」は今現在、
そして「本宮」は未来を、
司るという事を教えて戴きました。
たまたまこれまでの何十年かは変化がなかっただけの事で、それはこれまでの長い長い瀧の歴史からするとほんの少しの期間。
たまたまその間に人間の都合で「世界遺産」とかなんとかに登録されたからといって、
大自然からすれば知った事ではありません。
熊野の「今」、
その那智が変容を始めています!
そしてこれは、
日本の、世界の雛形でもあります。

苔の森。

役の行者の頃よりも、
さらに遥か以前から坐す熊野の聖地です。
赤青黄緑五全国ネット通販決定!まだ未体験の皆様にはコチからどうぞ。
ヒーリングミュージック 癒しの音楽
究極のリラクゼーションサウンドスパ