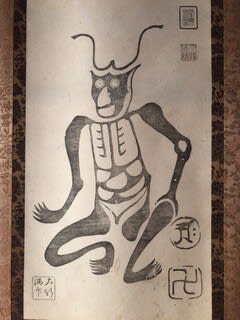私の生家は 茨城県にあります。
国道125号線沿いの 霞ヶ浦のほとりです。
滅多に聞かれる事はありませんが、
そう答えると、聞いた人からは だいたい
「ふ~ん」とか「へ~~」とかの反応があります。
まれに「その辺、行った事があります!」と言われれば、
「レンコンが美味しいんですよ」とか
「鯉は 洗いより旨煮!
でも、寒くなると、何といっても
鯉こくが美味しくて、あったまりますよね!!!」
などとお話できます。
けれど、<霞ヶ浦>と聞いて
連想が戦争と直結する方々とは
話が続きません。
12月4日「予科練の歌」の続きです。
その中のお一人は
「あれは昭和20年の ○月○日、
私は・・・・・・」
と必ず年月日入りで記憶をたどって
何度も何度も お酒が入る度に
同じお話をして下さった方。
戦友が 霞ヶ浦のほとりに実家があったとかで、
終戦の年に もう一人の戦友と 訪れたのだそうです。
必ず年号入りで、
そして 必ず 大陸での戦闘体験まで続きます。
「だから戦争は良い! いけない!」だとか
「私はその戦闘で勝った! 負けた!」 だとか
「辛かった、悲しかった、楽しかった、嬉しかった」だとかは
決しておっしゃらないけれど、
必ず終わりまで語り続ける方でした。
だから、どう、 ではなく、
とにかく、口に出してしまわなければいられないくらいの、
かなり過酷で強烈な体験で、
そして 消化しきれずに胸の奥に残っている記憶なのだろう、
と 今の私なら想像もできますが、
当時は
「どうして こうも毎度 同じ話を繰り返すのだろう」
くらいしか考えられずに
ただただ 相槌を打ちながら呆れていたのでした。
お家の人たちは もう 誰も聞いてくれないんだろうな、
なんて思っていました。
(それを お家の人に確認した事はありません。)

一ヶ月ほど前のケヤキ。ケヤキの黄葉も美しい。
もうお一人は
出身地を伝えると
「えええっっっ!!!!!」
と大げさに驚いて 絶句なさった方です。
私は「?????」でしたが、
やがて
「私は予科練にいたのです」と。
「あ、そうですか」
「・・・・・・・・・・・」
沈黙は 私の言葉の続きを期待なさっているからだと感じて
私は 言葉を探しました。
「あそこには 「武器学校前」というバスの停留所があって、
私は時々バスに乗ってそこを通りました」
実は、私と予科練のつながりは
「予科練の歌(若鷲の歌)」があっただけで、
他には何もないのでした。
その停留所で降りた事もないし。
あとは、「武器学校前」というバス停の名前が
恐ろし気だなぁ、と思っていたというくらいで。
陸上自衛隊武器学校 https://www.mod.go.jp/gsdf/ord_sch/
けれど、その人は
私を見つめて 次の言葉を待っているようでした。
あと? 他に? 何を話せって?
「私はバスに乗って たまに通るだけでしたけれど、
あそこは 窓から見ると
大きな格納庫のような屋根が見えて」
「そう、そう!!」
「・・・・・・。」
「・・・・・・。」
「その向こうに、霞ヶ浦が広がっているんです」
「そう、そう!!!」
「・・・・・・。」
「・・・・・・。」
他に、何かある?
ただ、その時のその方が
今にも笑いたそうな、泣きたそうな、
複雑な表情をずっとなさっていたと
今 思い出せるのです。
そして その表情を思い出すと
見開いた目は 涙をためていたようにも思えるのです。
そのお顔を 忘れられません。
けれど そのお顔を思い出したのは、
ご高齢だったその方が亡くなられた時でも
その後 奥さまが亡くなられた時でもなく
だいぶ経ってからでした。
そう、それは 今年
朝ドラ「エール」で 予科練の歌を聞いてからだったのです。
同じ年代の奥さまが
ご主人が予科練にいた事を
ご存知ないはずはありません。
けれど どれほどの思い出話をなさってきたでしょう?
あるいは 息子さんや娘さんに それから お孫さんに
お話なさってきたでしょう?
死を覚悟して 予科練の地に赴いて
生きながらえて
戦後を生きぬいて
繁栄を築いて
安定した生活を手に入れて。
今の私なら
それらのすべてが 日本の近現代史だったのだなぁ
と思うのですが。
いくらでも思い出話をお聞きしたいくらいなのですが。
あの老人のうるんだ瞳に出会った時は
少々迷惑に思ったのでした。
うまく言えませんが、
あの しわくちゃの顔の
笑っているような泣いているような顔を
私は忘れないようにしたいと思います。
朝ドラ「エール」で聞いた懐かしい歌が
口をついて出てくると
「うふふ」と思っていたのですが、
「予科練の歌」つまり「若鷲の歌」だけは
あの方のお顔を思い出して
心がザワザワして
最後まで歌えなかったし、笑えない私でした。
私の思い出話にお付き合いいただき、
ありがとうございました。

「エール」の最終回は
必要か? と思っていた歌謡ショーでしたが、
馬具職人の岩城さんこと、吉原光男さんの
「イヨマンテの夜」を聞けて、大満足でした♪
劇団四季のご出身とは 知りませんでした!