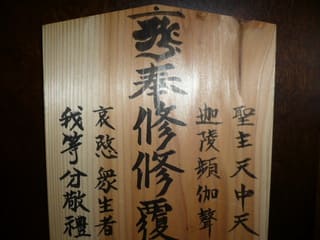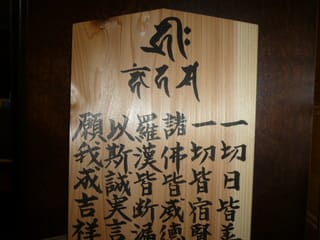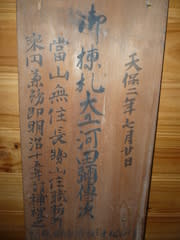吉祥寺の北門の事は、
まだお話してしていませんでした。
少々 というか、多々(?) 傷んでいましたので、
改修工事をしました。
 2023年6月3日
2023年6月3日
 6月7日
6月7日
 8月9日
8月9日
 8月22日
8月22日

 9月4日
9月4日
新しい材木でできた部分は わかりやすいです。
 9月13日
9月13日
それを黒く塗ると、わからなくなってしまいますね。
黒い鉄でできた 古い門扉も新しくします。
これまで 開けにくく、閉めにくい扉でした。
 10月27日
10月27日

 10月30日
10月30日
門扉は、あっという間に新しく取り替えられました。

古い部分も、新しくなった部分も、
気持ち良く新年を迎える事ができました。
以上、ご報告でした。