昨日から順番に洗ってます!
昨日は、メインで使ってるBb管のニューヨーク#7とハーセスパイプのC管。
今日は、ベンジーのピッコロとヤマハのフリューゲルとモンケのBb管をお掃除。
お掃除だけじゃつまんないからって、ついでにちょびっとずつ吹いてみたりして。
C管はこの前ちょろっと出して吹いた時には、あ~なんかヘタレたなぁ…と思ったんだけど、単に中が汚すぎただけだったみたいで、洗ったら元気はつらつジャイアンツになっていた!
ベンジーのピッコロも、あーもーぉ地球からピッコロなくなったらいいのに…と思ったりしてた時期もあったけど、今日吹いたら、あら~私が悪かったわ!という感じで、やっぱり地球にいてくれてありがとう!という気持ちになった。
ヤマハのフリューゲルも、私のイメージが悪かっただけみたいで、ようやくちょっと良さが戻ってきた。
ケノンの音のイメージに若干改造されているものなんだけど、自分がケノンってどんな音?っていう体たらくだったので、そういうことじゃいけなかったらしい。でもまぁまぁ分かってきたかも。ちなみになぜかマウスピースはなぜかボビーシュー!
モンケは明日洗う予定だったんだけれど、旦那がベト7のオケスタを一緒にしようよ!というので、「マウスピース貸してくれたらね」というわけの分からない交換条件を出し、あっさりOKが出たので、それなら…と1月以来久しぶりにひっぱり出してきて、何か汚い気もしたのでとっとと洗った。
で、旦那のシュミットを借りて吹くことに。
旦那は結構大きいMPを使っている。数学には強いけど、暗記ができない私としては、17.2だの何だの言われても、それがナンボノもんか良く分からないんだけど、とりあえず1Cくらいのサイズらしい。
私は7Cを使ってるので、結構違う気はしたけれど、もう朝からフリューゲルもピッコロもB管も、実はその前にヤマハの8310Zなんかも吹いてたから、もーなんでもいいしーぃ!という無敵モードに突入し、気にせず使わせてもらうことにした。
カップは広いけど、体感的には浅く感じる。これって7Cが意外と深いからか?それともシュミットのこのマウスピースが広いので相対的に浅く感じるのか?そこは結局定かではないけれど、意外と普通に吹けるし、それに何よりロータリーに合っててとても吹きやすい!
やっぱりロータリー用に1つマウスピースを買おう。バックボアだけをシュミット(#7)にして、それで吹こう!と思ったこともあったけれど、やっぱり餅はモチ屋なのかも!
せーの!でいきなりオケスタをやってみて思ったのは、イメージがある部分と、ここってどんなところだっけ?と考えてる間に吹き始めちゃう時では、音程の取りとかニュアンスとかも全然違ってくるし、そのうちどんどん流れ作業的になっていっちゃったあたりでは、もうただ譜面に書いてある音を機械的に並べるだけになってしまう!
そうなると楽器が急に嫌がって、響きがばらつきだすのがメチャメチャ分かる。こういうさらい方じゃいけないな…と反省。ちゃんと音楽は音楽として練習していなくちゃいけない、というのが最近の私の中の結論!
ところで、途中に8310Zを吹いたんだけど、久しぶりに吹いてみて、あーやっぱりヤマハは簡単でいいなぁ~っと思った。変な鳴りムラが全然ない。だいたいで吹いていてもちゃんとしたピッチになってる。バックに比べて、ファの音(Es)が低い感じがするけど、それはきっと平均率だからだと思う。
で、とても吹きやすい半面、ピッチが平均律的なので音の機能(そういうのってなんていうんだろう?えーっとコード感とでもいうんだろうか?)が、逆にハッキリしない。音自体はハッキリしてるんだけど、音楽的な浮き沈みがなくて、全部がベターっと塗ったような感じになりやすい。きっと超工夫すればいろいろ出来るんだと思うけれど、吹きやすいがゆえにそれに甘えてしまうと、なんだか「喜び」感がなくなって、何吹いても同じだなぁ…みたいな気分になる。バックでコードを感じながら丁寧に練習すると、和音が次々変わっているのがとっても良く分かって、そのコードによって、ワクワクしたり、ちょっと淋しくなったり…そういう浮き沈みがなんとも楽しく、そして最後の和音にたどり着いたとき、ホッとした感じになったりすると、よーっしゃーっとなる。
でも、そこまでコントロールするのが難しい。特に私がいい加減になりやすいのは下のシドレあたり。シとドは半音しかないんだけれど、絶対音の私は「ラ・シ」と思っているせいか、半音っていう認識がちょっと緩い。同じくドとレは全音なんだけど頭の中は「シ・ド」なのでなんだか狭めにとってしまっている…ということに最近気付いた。多分昔からではなく、ここ何年かだと思う。
他の音にもこういう部分がある。もっと幅の広い音程でもいい加減なところがあるし。
こういうのをメロディーのときはピタゴラスチックに、和音と感じられるときは純正調チックに、はたまたグレーな感じのところはそれなりに…みたいなのを、別に頭じゃ音律云々考えてないけど、耳と心で最適と思われる音同志の関係を作りながら進む。
今いる音から次の音へ、どんなふうにつなげるか、どんなルートで次の音へ行くか?そういうのを感じながら吹く。
こんな感じでクラークもやってるよんッ!
前に通称「ぼうさん」と呼ばれていた先生についてたときに、クラークは和声進行を感じて練習しろ、って言われてたことを再確認しつつ!
やたら楽しいから、お勧めです。
今日は新年度にやるA合奏のスコアなんぞも作ってたから、吹いた時間は短かったけれど、楽器の特性とかいろいろ感じることができて、なんだか有意義だった!
明日は8310Zとコルネットを洗おう!
昨日は、メインで使ってるBb管のニューヨーク#7とハーセスパイプのC管。
今日は、ベンジーのピッコロとヤマハのフリューゲルとモンケのBb管をお掃除。
お掃除だけじゃつまんないからって、ついでにちょびっとずつ吹いてみたりして。
C管はこの前ちょろっと出して吹いた時には、あ~なんかヘタレたなぁ…と思ったんだけど、単に中が汚すぎただけだったみたいで、洗ったら元気はつらつジャイアンツになっていた!
ベンジーのピッコロも、あーもーぉ地球からピッコロなくなったらいいのに…と思ったりしてた時期もあったけど、今日吹いたら、あら~私が悪かったわ!という感じで、やっぱり地球にいてくれてありがとう!という気持ちになった。
ヤマハのフリューゲルも、私のイメージが悪かっただけみたいで、ようやくちょっと良さが戻ってきた。
ケノンの音のイメージに若干改造されているものなんだけど、自分がケノンってどんな音?っていう体たらくだったので、そういうことじゃいけなかったらしい。でもまぁまぁ分かってきたかも。ちなみになぜかマウスピースはなぜかボビーシュー!
モンケは明日洗う予定だったんだけれど、旦那がベト7のオケスタを一緒にしようよ!というので、「マウスピース貸してくれたらね」というわけの分からない交換条件を出し、あっさりOKが出たので、それなら…と1月以来久しぶりにひっぱり出してきて、何か汚い気もしたのでとっとと洗った。
で、旦那のシュミットを借りて吹くことに。
旦那は結構大きいMPを使っている。数学には強いけど、暗記ができない私としては、17.2だの何だの言われても、それがナンボノもんか良く分からないんだけど、とりあえず1Cくらいのサイズらしい。
私は7Cを使ってるので、結構違う気はしたけれど、もう朝からフリューゲルもピッコロもB管も、実はその前にヤマハの8310Zなんかも吹いてたから、もーなんでもいいしーぃ!という無敵モードに突入し、気にせず使わせてもらうことにした。
カップは広いけど、体感的には浅く感じる。これって7Cが意外と深いからか?それともシュミットのこのマウスピースが広いので相対的に浅く感じるのか?そこは結局定かではないけれど、意外と普通に吹けるし、それに何よりロータリーに合っててとても吹きやすい!
やっぱりロータリー用に1つマウスピースを買おう。バックボアだけをシュミット(#7)にして、それで吹こう!と思ったこともあったけれど、やっぱり餅はモチ屋なのかも!
せーの!でいきなりオケスタをやってみて思ったのは、イメージがある部分と、ここってどんなところだっけ?と考えてる間に吹き始めちゃう時では、音程の取りとかニュアンスとかも全然違ってくるし、そのうちどんどん流れ作業的になっていっちゃったあたりでは、もうただ譜面に書いてある音を機械的に並べるだけになってしまう!
そうなると楽器が急に嫌がって、響きがばらつきだすのがメチャメチャ分かる。こういうさらい方じゃいけないな…と反省。ちゃんと音楽は音楽として練習していなくちゃいけない、というのが最近の私の中の結論!
ところで、途中に8310Zを吹いたんだけど、久しぶりに吹いてみて、あーやっぱりヤマハは簡単でいいなぁ~っと思った。変な鳴りムラが全然ない。だいたいで吹いていてもちゃんとしたピッチになってる。バックに比べて、ファの音(Es)が低い感じがするけど、それはきっと平均率だからだと思う。
で、とても吹きやすい半面、ピッチが平均律的なので音の機能(そういうのってなんていうんだろう?えーっとコード感とでもいうんだろうか?)が、逆にハッキリしない。音自体はハッキリしてるんだけど、音楽的な浮き沈みがなくて、全部がベターっと塗ったような感じになりやすい。きっと超工夫すればいろいろ出来るんだと思うけれど、吹きやすいがゆえにそれに甘えてしまうと、なんだか「喜び」感がなくなって、何吹いても同じだなぁ…みたいな気分になる。バックでコードを感じながら丁寧に練習すると、和音が次々変わっているのがとっても良く分かって、そのコードによって、ワクワクしたり、ちょっと淋しくなったり…そういう浮き沈みがなんとも楽しく、そして最後の和音にたどり着いたとき、ホッとした感じになったりすると、よーっしゃーっとなる。
でも、そこまでコントロールするのが難しい。特に私がいい加減になりやすいのは下のシドレあたり。シとドは半音しかないんだけれど、絶対音の私は「ラ・シ」と思っているせいか、半音っていう認識がちょっと緩い。同じくドとレは全音なんだけど頭の中は「シ・ド」なのでなんだか狭めにとってしまっている…ということに最近気付いた。多分昔からではなく、ここ何年かだと思う。
他の音にもこういう部分がある。もっと幅の広い音程でもいい加減なところがあるし。
こういうのをメロディーのときはピタゴラスチックに、和音と感じられるときは純正調チックに、はたまたグレーな感じのところはそれなりに…みたいなのを、別に頭じゃ音律云々考えてないけど、耳と心で最適と思われる音同志の関係を作りながら進む。
今いる音から次の音へ、どんなふうにつなげるか、どんなルートで次の音へ行くか?そういうのを感じながら吹く。
こんな感じでクラークもやってるよんッ!
前に通称「ぼうさん」と呼ばれていた先生についてたときに、クラークは和声進行を感じて練習しろ、って言われてたことを再確認しつつ!
やたら楽しいから、お勧めです。
今日は新年度にやるA合奏のスコアなんぞも作ってたから、吹いた時間は短かったけれど、楽器の特性とかいろいろ感じることができて、なんだか有意義だった!
明日は8310Zとコルネットを洗おう!










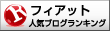














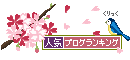

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます