藤原弘達・創価学会を斬る 41年目の検証 言論出版の自由を守る会編
(日新報道 2012/2)
------(232P)---(以下、本文)-------
◆ 田中角栄自民党幹事長に仲介を依頼
度重なる出版中止の要求が不調に終った創価学会・公明党は、藤原弘達を押さえ込むためにはより強い政治力の発動が必要と判断。竹入義勝公明党委員長(当時)を通じて、田中角栄自民党幹事長(当時)に出版中止の仲介を依頼。田中は藤原弘達に電話を入れて出版の中止を要請するとともに、10月15日と23日の二度、赤坂の料亭「千代新」と「乃婦中川」で藤原弘達と会い、「創価学会を斬る」の出版を取り止めるよう求めた。
田中に出版中止の仲介を依頼した当事者である竹入は、平成10年8月に「朝日新聞」に連載した手記「秘話・55年体制のはざまで」において、その事実を次のように認めている。
「創価学会批判の本が出るというので、私が田中さんに頼んで仲介に動いてもらった」(H10・8・26日付「朝日新聞」)
このうち10月15日の「千代新」での会談の際には、隣室で池田と竹入が、藤原弘達と田中のやりとりに聞き耳を立てていたとの「産径新聞」の報直がある。また平成20年に創価学会から造反した矢野絢也元公明党委員長は、自著「私が愛した池田大作『虚飾の王』との五〇年」において、言論出版妨害事件の経緯と顛末を詳述しているが、その中で10月23日の「乃婦中川」での藤原・田中会談に言及。当時、公明党の書記長だった自分も竹入に誘われて「乃婦中川」に赴き、隣室で会談の成り行きを見守っていたことを次のように明かしている。
「竹入氏から「お前も来い」と声をかけられて、ノコノコついていった。1969年10月23日のことだ。
場所は赤坂の『のぶ中川』という料亭。(中略)料亭に着いてみると、二階の部屋が三つ並びで押さえられていた。私と竹入氏は一番奥の部屋で待機することになった。真ん中が角栄氏の控え室。一番手前が弘達氏というわけだ。角栄氏が説得に成功すれば、その場で私らもそちらの部屋に移り、そのまま手打ち式になだれ込む、という段取りだった」
この藤原・田中会談の内容とその後の顛末は、矢野の「私の愛した池田大作「虚飾の王」との50年」や、昭和60年10月に藤原弘達が日新報道から出版した「創価学会・公明党をブッた斬る」に詳述されている。当事者の記述だけに、その内容は迫真性に富んでおり、極めて興味深い。以下、その一部を紹介しヨう。まずは矢野手記から。
「ところがここに来ても弘達氏は頑強である。説得になかなか『うん』と言ってくれない。こちらの出した条件はこうだった。最初は強引に『出版そのものを取りやめろ』と迫ったのだが、それでは弘達氏の受け入れる余地がない。そこで、『初版は出していい。出したうえで大半をこちらが買い取る。新たな増刷はしないと確約してほしい。その代わり、非常にうまみの大きい仕事をこちらから回す』と提案した。だが、弘達氏は頑として首を縦に振らない。とうとう角栄氏が我々の部屋へ来て泣きついてくる。例の威風堂々とした、押し出しのいい普段の姿とは打って変わって、いかにも困り果てた風情である。
『おい。弘達、ダメなんだよ。固くてダメだ。全然聞き入れようとしないよ』しかしこちらとしても、ハイそうですかと引っ込むわけにはいかない。
『そんなこと言わないで。なんとか頼む。もう一押し、に押ししてみてくれ』
竹入氏がそう言って、仕方なく角栄氏は再び弘達氏の部屋へ。しかしまたも拒絶されてしまう。
『おい、やっぱりダメだあ』
『こっちこそダメだ。なんとかしてくれ』
今にして思えば、当時、飛ぶ鳥を落とす勢いの天下の自民党幹事長を、なんともひどい役どころでコキ使ったものである。これもまた学会や池田先生を守るためという、我々の執念の発露なのだ」(「私の愛した池田大作『虚飾の王」との50年」)
同様に、藤原弘達も「千代新」「乃婦中川」での田中との会談の様子を次のように書いている。
「当時の自民党幹事長・田中角栄が、私に会いたいというので、赤坂の料亭『千代新』へでかけたのは十月十五日のことである。この時、私が『この問題について総理(注・佐藤栄作)は知っているのか』とただしたところ、田中幹事長は『総理には、いっていない。自分は竹入らとの平素のつきあいから頼まれたものだ』と言明した。
田中角栄の、私の本の出版を初版だけにして、その殆どを買い取る“斡旋”案は、要するに、本をヤミからヤミへ葬ろうというもので、もちろん、私は一蹴した。再度、10月23日夜、同じ赤坂の「乃婦中川」で会った時、私は田中角栄にいった。「角さん、こんなことやっていたら、あんたは絶対に総理大臣になれませんぞ』--今でも覚えている。あの田中角栄が顔面蒼白になったものだ。
これで談判決裂になったのだが、私としては、田中角栄がこの問題に介入したことは最後まで伏せておくつもりだった。(中略)
しかし、その後も妨害やイヤガラセは続出した。あまつさえ、12月13日、NHK二党間討論(共産党-公明党)において、公明党・正木良明議員が「そんなこと(出版に対する圧力、妨害)はしていない。全くのウソである」と全面否定した。ここに至っては、もはや、何おかいわんやである。黙っていては、私が言論人として自殺行為に等しいウソをついたことになる。十二月十五日、『赤旗」記者の取材を受けた時、私はいった。
『よし、こうなれば名前を公表しよう。それは自民党の田中幹事長だよ…NHKテレビ討論会という公の場で、公明党代表が出版妨害などしていない、全部ウソだといったのだから、私も黙ってはいられない』
言論-出版妨害に田中角栄が介入した事実は、こうして私の口から明らかにしたのである」(「創価学会・公明党をブッた斬る」)
◆ 殺到した抗議と脅迫の電話
こうした政治的圧力と並行して創価学会は、自らに批判的な報道に抗議することを主たる任務とする全国各地の言論部員に、藤原弘達と日新報道に対する抗議行動を指示。そのため藤原の自宅や日新報道には、連日、「ぶっ殺すぞ」とか「地獄に堕ちろ」といった脅迫まがいの電話や手紙が殺到し、抗議の葉書や手紙の量も段ボール箱数箱分に及んだという。
当時、日新報道の編集部員だつた日新報道社長の遠藤留治は、熾烈だつた脅迫電話や抗議について次のように言及している。
「それはひどいものでした。(注=抗議の葉書、手紙が)やはり段ボール箱で何箱にものぼったんじやないでしょうか。電話での脅迫もひどいものでしたので、警察がそれとなく藤原弘達氏のお子さんなど家族の警備をしたほどでした。ですから藤原弘達氏は身の安全を図るため、都内のホテルを転々として「創価学会を斬る」の執筆を続け、私たちも移動しながら編集作業を続ける有り様でした。なお、この抗議電話や葉書は出版後もますますエスカレートし、内容もひどいものでした」(「フォーラム21」H15・7・1号)
そうした創価学会の言論出版妨害の一端は、石原慎太郎東京都知事が書いた「国家なる幻影」(平成11年・文藝春秋社刊)にも垣間見える。同書には次のようにある。
「あれは水野氏(注=当時のサンケイ新聞の社主)の案に興味を示し私が買って出て、日本の新興宗教についての総合的なルポタージュ『巷の神々』をサンケイ紙上に連載している間(注=昭和42年)に筆が創価学会に及び、私が皮肉な批判を書いたら学会から抗議がきて、紙上で取り消すなり謝罪しなけれはサンケイの不買運動を展開するという脅しがあつた。現にそのために関西のある地域で突然サンケイの購読が中止され、その示威行動としてかなりの部数が減らされた。
現地の営業部は仰天し、報告を受けた本社でも問題になった。編集局からの相談に、私は違った事実を書いた訳ではないし、私が台東体育館で見た池田会長を迎えての大会のシュプレツヒコールの段取りとその印象はいつか記録映画で見たナチスの大会と酷似していて、それなりに見事なものだったが一方どこか空恐ろしい印象でもあった、といった記述はあくまでも表現の問題であってどんな組織だろうとそれを侵すことは出来ぬはずだと言い張った。
私を呼びつけた水野氏も間に挟まつていささか困惑していたと思うが、こちらはいかにも頑固に論をとり下げず、その内面倒になった水野氏が次第に怒り出しとうに入っていたアルコールのせいで弾みがついてしまい、取つ組み合いにまでなった。
『お前みたいな恩知らずは、今に誰か人を使ってこの世から消してやる』などと物騒なことを口走る相手に、『まあ、たがいに頭を冷やして話し合いましよう』
といって辞したが、すぐにまた呼びがかかり、今度は素面で、「考えてみたらこやつらはいかにもけしからんな。天下の公器をなんと心得ているんだ。いいから好きなようにやれ、こんな新聞の一つや二つ潰してもかまわんよ。相手の本部にもそう伝えておけといっといた。なに、奴らも馬鹿じやなかろうが』
結果は相手がどう判断したのか知らないが不買運動は消えてなくなった。私としてはそんな出来事でようやく創価学会なるものの体質の芯が覗けた思いだったが、同じ性格の事件が後にも起こり、参議院での公明党議員の演説の陳腐さを揶揄した私のエッセイについて院内の公明党が筋の通らぬ文句をつけてきて今度は私自身が標的にされることにもなった。
さらに後になって藤原弘達氏の学会批判の出版に、学会が田中角栄を介して出版とりつぶしの弾圧をかけて露見した時、つくづくこの巨大な組織の抱いている世間への奇妙な劣等感とそれがひっくり返つての思い上がりに危惧を抱かぬ訳にいかなくなった」
---------(238P)-------つづく--










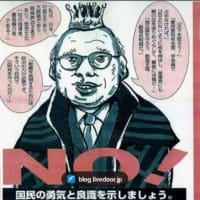




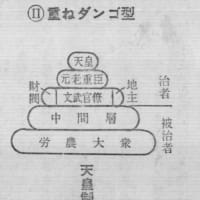





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます