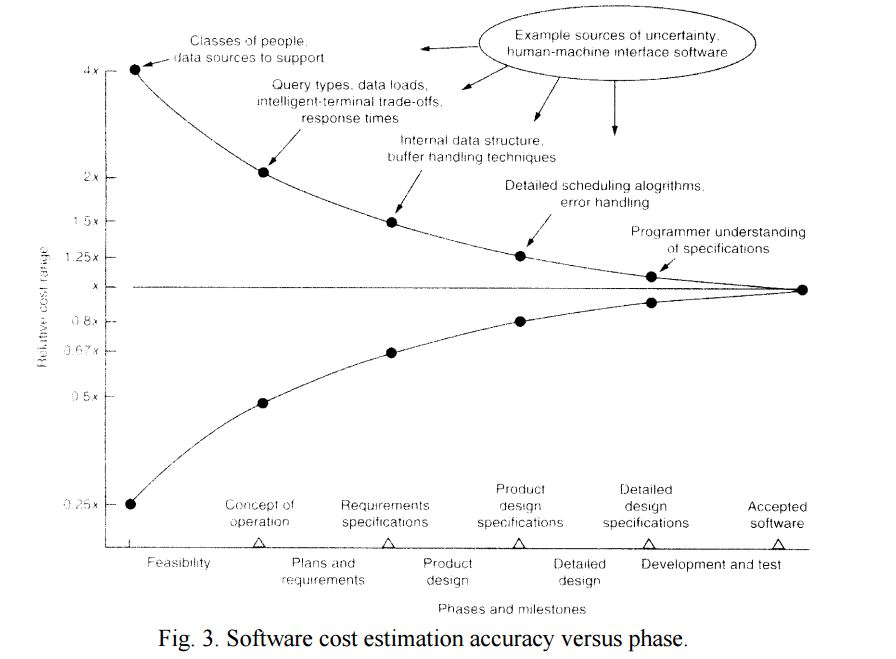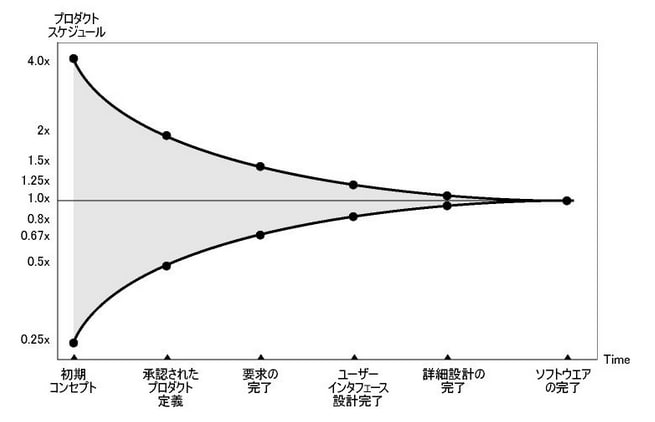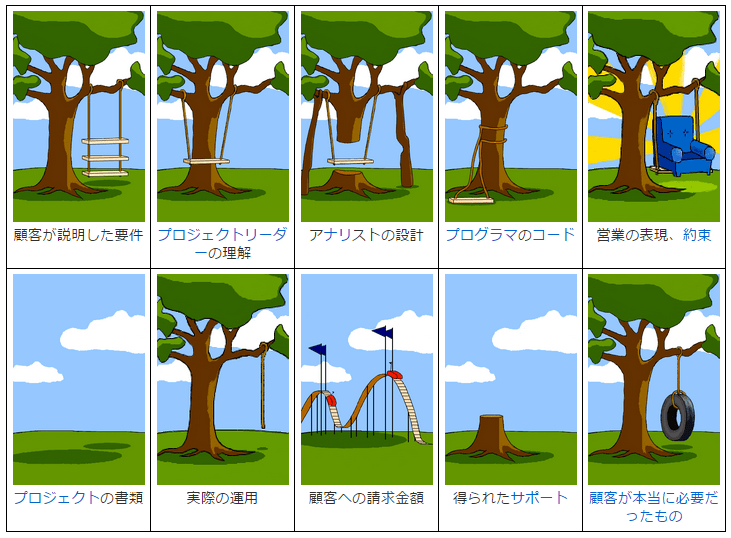JTF2015にいってきた。
ソフトウェアエンジニアのための「機械学習理論」入門
をメモメモ
背景
・機械学習は結構前からある
・ツールがオープンソース+ディープラーニング:某日経BPがあおりだす
オープンソース好きを助けたい
日経の人が煽ると、1年後に忘れ去られる→ちゃんと使えば役に立つ
場図ワードで終わらせたくない
NIIの資料を使うよ(数式スキップ!)
・第二部の途中くらいまで
・データサイエンスと機械学習
パーツを組み合わせて、データサイエンス
・いろんな判断
→なににもとづくか
データに基づいて、過去のデータから判断:データサイエンス
・データサイエンスに必要な知識
・ビジネスの理解
・分析理論の理解
・データの理解
・データサイエンスの誤解
データサイエンティスト:事実を明らかにする?
ビジネス判断はスーツの役割?→誤解
→ビジネスに役立つ判断まで導く
・どんなふうに機械学習を使うか
アルゴリズム
過去のデータ
判断できる
・機械学習アルゴリズムの分類
分類(AかBか)
回帰(数値で判断)
誤差関数(最小2乗法)による回帰→2乗誤差を小さくする
オーバーフィッティングの問題→一般化力
実際に良くやるのはテスト用データを用意しておく
・いけてない機械学習の例
分類:決定木→根拠ない:比較検討
データの理解
・試行錯誤で見つけ出す方法
テストセットを用意しておく
ビジネスに適用してみる→いいアルゴリズムを適用する
ソフトウェアエンジニアのための「機械学習理論」入門
をメモメモ
背景
・機械学習は結構前からある
・ツールがオープンソース+ディープラーニング:某日経BPがあおりだす
オープンソース好きを助けたい
日経の人が煽ると、1年後に忘れ去られる→ちゃんと使えば役に立つ
場図ワードで終わらせたくない
NIIの資料を使うよ(数式スキップ!)
・第二部の途中くらいまで
・データサイエンスと機械学習
パーツを組み合わせて、データサイエンス
・いろんな判断
→なににもとづくか
データに基づいて、過去のデータから判断:データサイエンス
・データサイエンスに必要な知識
・ビジネスの理解
・分析理論の理解
・データの理解
・データサイエンスの誤解
データサイエンティスト:事実を明らかにする?
ビジネス判断はスーツの役割?→誤解
→ビジネスに役立つ判断まで導く
・どんなふうに機械学習を使うか
アルゴリズム
過去のデータ
判断できる
・機械学習アルゴリズムの分類
分類(AかBか)
回帰(数値で判断)
誤差関数(最小2乗法)による回帰→2乗誤差を小さくする
オーバーフィッティングの問題→一般化力
実際に良くやるのはテスト用データを用意しておく
・いけてない機械学習の例
分類:決定木→根拠ない:比較検討
データの理解
・試行錯誤で見つけ出す方法
テストセットを用意しておく
ビジネスに適用してみる→いいアルゴリズムを適用する