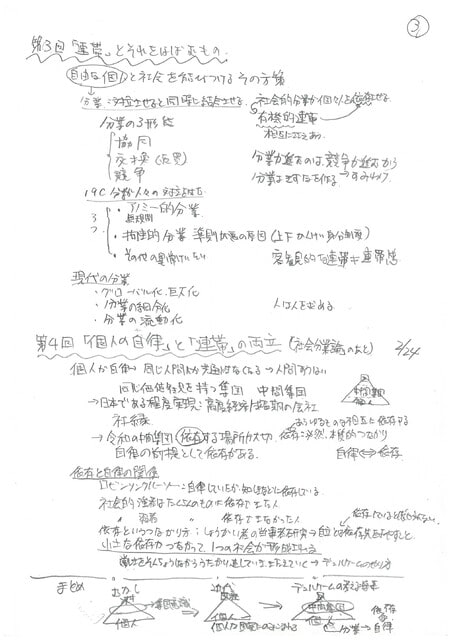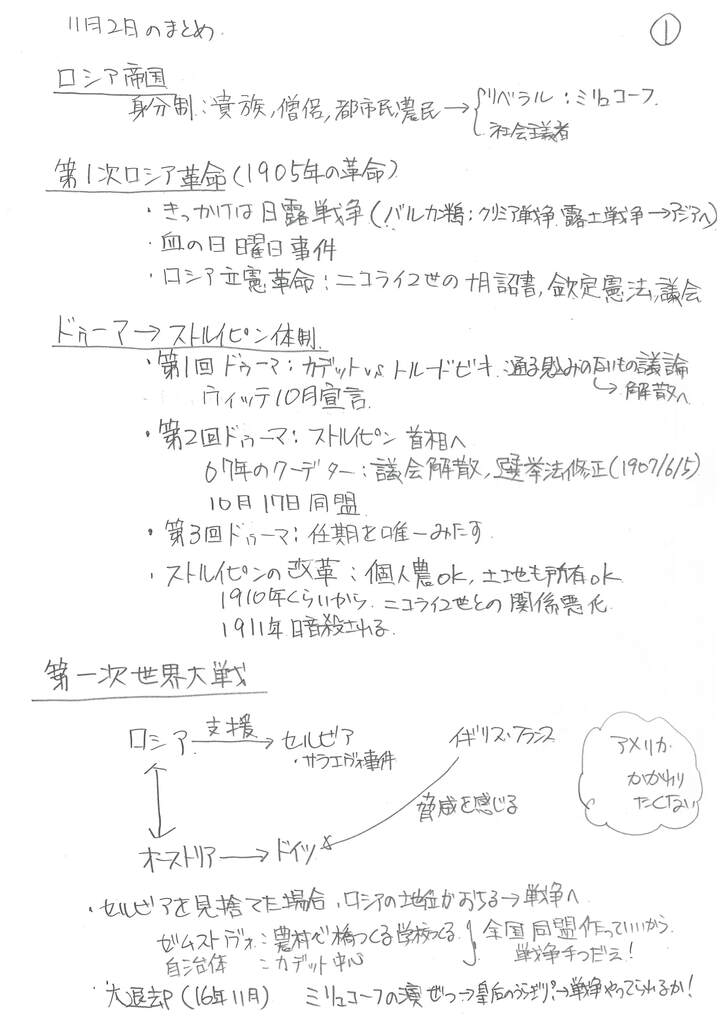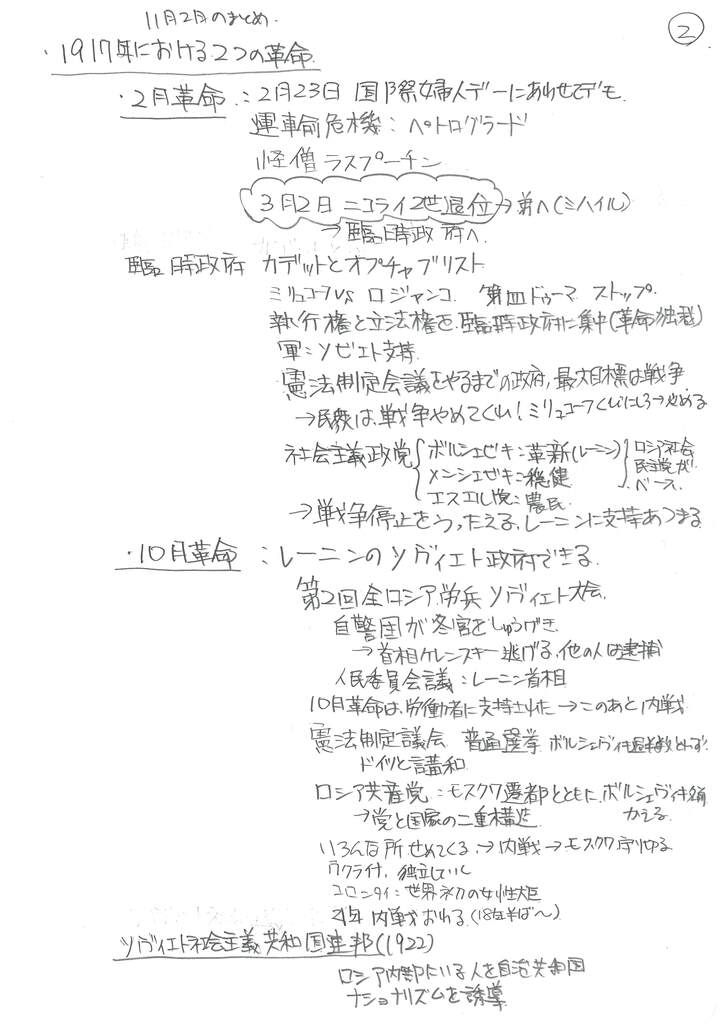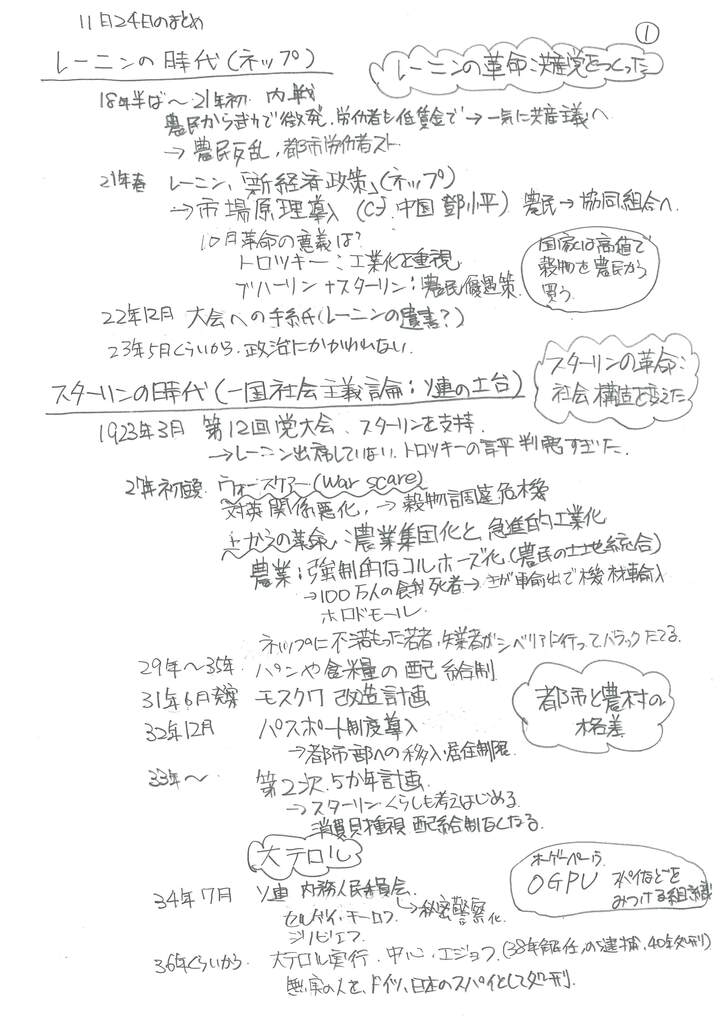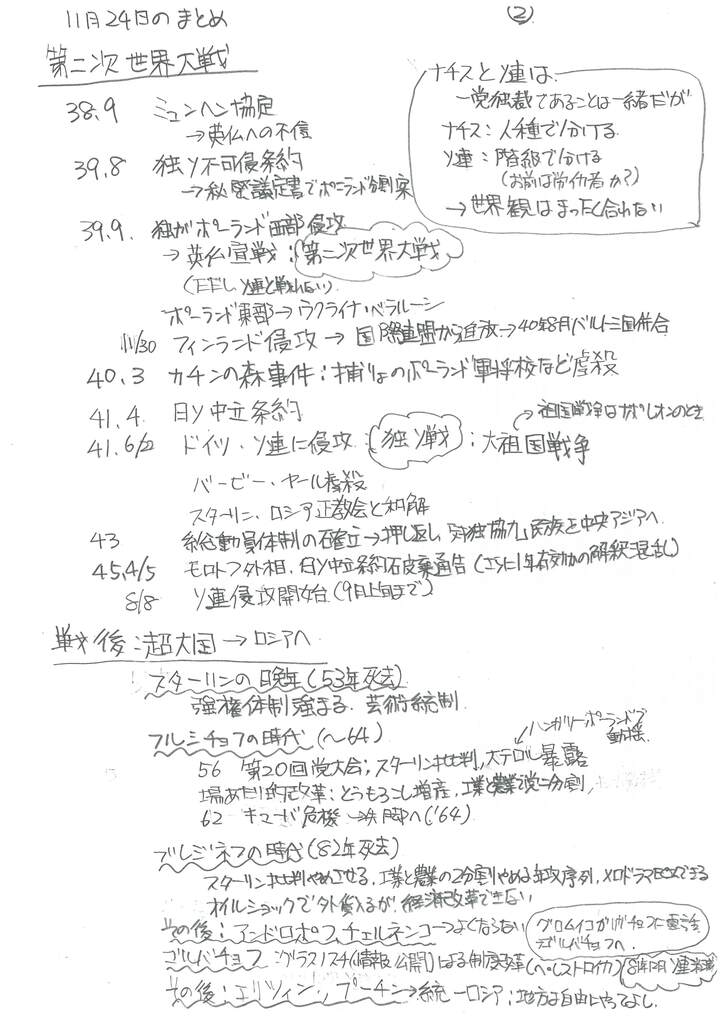以前、「3か月でマスターする世界史」のまとめの12回のとき
「論調がちょっとちがっている。
詳しくは、全体のまとめで書こうと思う。」
と書いておきながら、全体のまとめを書いていなかったので、
今日はその「全体のまとめ」を行いたいと思います。
■広域支配の方法「帝国」と「帝国主義」
世界史でいくつかの国にまたがって支配する「広域支配」という状態
になったことは度々あるのですが、この広域支配には、大きく2つの
方法が世界史上、あr他われているようです。
その2つが「帝国」と「帝国主義」
■「帝国」による広域支配
支配する側が税金を取り、その代わり、支配地域の防衛をしてくれる。
そして、支配する側と支配される側の交通網を整備・統一し、貿易
を促進する(そのため通貨も統一する)
基本的に、支配される側の自治が認められている
→支配地域から税金を取るが、支配地域を経済的搾取・文化強制をする
のではなく、地方の文化・自治を認めた緩やかな支配
(国家のフランチャイズ?)
具体例:帝国主義が現れるまでの広域支配はすべてこれ
(13Cまで)
ヨーロッパ:
東西ローマ帝国
ペルシア:
アケメネス朝ペルシア(BC6C~BC3C)
ササン朝ペルシア(BC3C~AD7C)
イスラム
ムハンマドの啓示(610頃)
正統カリフ時代(661~)
ウマイヤ朝(661~)・後ウマイヤ朝(756~)
アッバース朝(750~1258)
→ファーティマ朝、ハムダーン朝、ブアイフ朝、サーマーン朝、
カラハン朝、ウィグルに分断
中国
秦・漢←匈奴の攻撃(遊牧民族)
北魏・隋←鮮卑、五胡
唐←突厥
北宋←契丹と共存
南宋
(13C)
元(大元ウルス)→金、南宋を滅ぼし、さらに広域に
→ジュチ・ウルス(キプチャク・ハン国)
フレグ・ウルス(イル・ハン国)
チャガタイ・ウルス(チャガタイ・ハン国)に分裂
(14C)
ポスト・モンゴル
オスマン帝国(1300頃~1922)
ティムール朝(1370~1507)
サファヴィー朝(1501~1736)
ムガル朝(1526~1858)
■「帝国主義」による広域支配(植民地支配)
「支配する側」と「支配される側」に分け、
「支配する側」は「支配される側」から交易により資源・財産を搾取する。
しかし、「支配する側」は「支配される側」が求める資源・産物を
必ずしも持っていないので、搾取に限界がある。
そこで低コストで集められる資源をどこか(中継国)から取得し、
それを売りつけるという形をとる
例1:奴隷貿易(三角貿易)
「支配する国」→「中継国」:
イギリスー(銃・織物)→西アフリカ
「中継国」→「支配される国」:低コストの資源=黒人奴隷
西アフリカー(黒人奴隷)→アメリカ
「支配される国」→「支配する国」
アメリカー(砂糖・綿花)→イギリス
例2:アヘン貿易
「支配する国」→「中継国」:
イギリスー(綿織物)→インド
「中継国」→「支配される国」:低コストの資源=アヘン
インドー(アヘン)→清(中国)
「支配される国」→「支配する国」
清ー(茶・銀)→イギリス
「支配する側」は国家としてのまとまりをもち、
正当性を主張するための何らかのイデオロギーを持つ
具体例:
ヨーロッパの絶対王政・重商主義を経た後の
イギリス + 植民地
フランス + 植民地
ドイツ + 植民地
ロシア帝国(領土を拡大していった)
アメリカ(ヨーロッパの植民地→独立・領土拡大→フィリピン植民地)
日本 + 植民地?領土拡大?(韓国・満州・台湾)
※帝国主義がすすむにつれ、帝国は崩壊し、帝国主義(の植民地側に)
組み入れられるようになった
■そしてどうなった
※ここから先は、第12回のところです。放送内容ではなく、
個人的見解を書きます
(=以下のことは放送でははっきり言っていない。自分の受けた印象)
戦後、支配する側は西側諸国となった。
(ロシアはこれに入らず、社会主義陣営(ソ連)を形成していった(東側))
国際連合・国際連盟は西側諸国+ソ連の支配する国が中心のため、
支配の分割方法を調整するだけで、平和には結びつかない
国際連盟→第二次世界大戦を結局招く
国際連合→ウクライナ紛争後、実質機能していない
(機能不全の例:イスラエル)
しかし、帝国主義は、いつかは破綻する(植民地から搾取しつくしてしまえば、搾取するものがなくなるから、その時点で終わる)。
第二次世界大戦後、「大東亜戦争」(太平洋戦争というと、真珠湾とか太平洋が中心だけど、そっちじゃなく、ビルマとかの戦線の方)で生き残った「陸軍中野学校」卒業生等は現地住民とともに「大東亜共栄圏」をマジに実現しようとして現地民を教育し、独立運動へもっていった(が、結局それは独立ではなく日本支配だということが見透かされ、どこも日本は撤退させられるが、独立できるまでの組織化に日本が関与したから独立できたことは確か)
例:
ビルマ(ミャンマー) →アウンサン将軍:ビルマ国民軍
インド→チャンドラ・ボース:インド国民軍・自由インド仮政府
インドネシア→日本支配→協力したスカルノ:インドネシア独立戦争
これらの独立をきっかけに、アフリカ・アジアで次々と独立。
西側諸国の植民地支配ができなくなってきた。
そこで、植民地支配のうまみを残すため、信託統治という方法を利用する
こともあったが、実際には経済的支配(通貨の利用)などにより、依存という
名の搾取を続けている。
■今後はどうなる
(ここは本当に個人的見解=独断と偏見)
資本主義というのは、この搾取構造がベースにあり、世界は資本主義で
回っているので(社会主義は失敗してわずかな国しか残っていない)、
植民地構造は形は変えるにしても残って当然、貿易依存は当然という
考えになっていた。
ところが、ウクライナ紛争でロシアがSWIFTから外されても、(=貿易
出来なくても)国家がやっていけることから、今まで搾取されてた植民地
並の国家は、「もしかしたら資本主義・西側諸国に依存しなくても、
1国でやって行けるんじゃね?」と思い始め、各国が独立し、
アメリカ等の西側諸国に対抗するためにゆる~く結束するという
(帝国・帝国主義とは違う)「新しい広域連合の形」ができて来た
その一つがBRICSであり、
■何が12回で論調が狂ったのか
この「3か月でマスターする世界史」では、「帝国」と「帝国主義」を明確に分けている。
そして、「帝国」は「帝国主義」につぶされたものの、システム的にはいろんなところで起こり、永続可能なんだけど、
植民地に依存する「帝国主義」は、資本主義の本質に根差しているものの
植民地がなくなれば終わってしまうものなので、いつかは終わる
(ってか、もう、植民地は作れないので、西側諸国は、いままで国民として1つにまとまっていたものを、支配する「富」の側と、支配される「貧」の側にわけ、「貧」の方から搾取するという方法に変わりつつある)。
って、普通見ている人は思うと思う(つまり、世の中は変わる)。
ところが12回で、この区別をなくし、まるで資本主義というのが、これからも続く、国際間の依存を前提とした貿易も続くような感じで、 アメリカ1国集中がなくなって、基準がなくなったみたいなことを言いだしたから、見ている人は、ついていけなくなった・・・
見ている人としては、いやいや、帝国主義も、そのもとにしている資本主義や貿易による他国依存経済は、もう無理でしょ、国がそれぞれ独立して、(
斎藤幸平氏などが唱える)新しい資本主義だよね、そういう国が独立して、帝国より弱い新しい広域支配が今始まろうとしてるよね・・・って思って12回を見始めたと思うんですよ(少なくとも自分はそう)
なので、12回を見て、大いにズッコケ、「いままで見て来たのは、
何だったのかあ~」と思わずにはいられない・・・っていうと大げさですね
それ関係なく、世界史のまとめには、いい内容だったと思います
(12回以外は。ただし、1、2回は見ていないのでわかんないけど)
■いままでのまとめ
BC6~AD6のペルシャ、AD6~12のイスラム、BC3~AD12の遊牧民族のまとめ - ウィリアムのいたずらの、まちあるき、たべあるき
神番組発見!これを大学入試前に見たかった。大学入試で世界史を取った人、ヨーロッパとかははっきりしていて、後は暗記するだけなんだけど、なんとなくもやもやしていると...
goo blog
元とポスト・モンゴルのまとめ - ウィリアムのいたずらの、まちあるき、たべあるき
「3か月でマスターする世界史」13世紀に元が統一したときの話(第7回)と、そのあと、14、15世紀以降の中央アジア・西アジアについての話(第8回)をまとめてみま...
goo blog
中国とヨーロッパの立場が逆転する14~19世紀のまとめ(+おまけ:繁殖奴隷について) - ウィリアムのいたずらの、まちあるき、たべあるき
NHKEテレの「3か月でマスターする世界史」の続き第9回、第10回のまとめ。中国とヨーロッパの立場が逆転する14~19世紀の話結局2枚になってしまって、1枚目に10...
goo blog
第一次世界大戦、第二次世界大戦、きっかけは日本って話 - ウィリアムのいたずらの、まちあるき、たべあるき
三か月でマスターする世界史、第11回、第12回のまとめ第11回日露戦争をきっかけに、イギリスはロシア、フランスと近づいた。日露戦争の時ロシア側についたドイツは孤...
goo blog