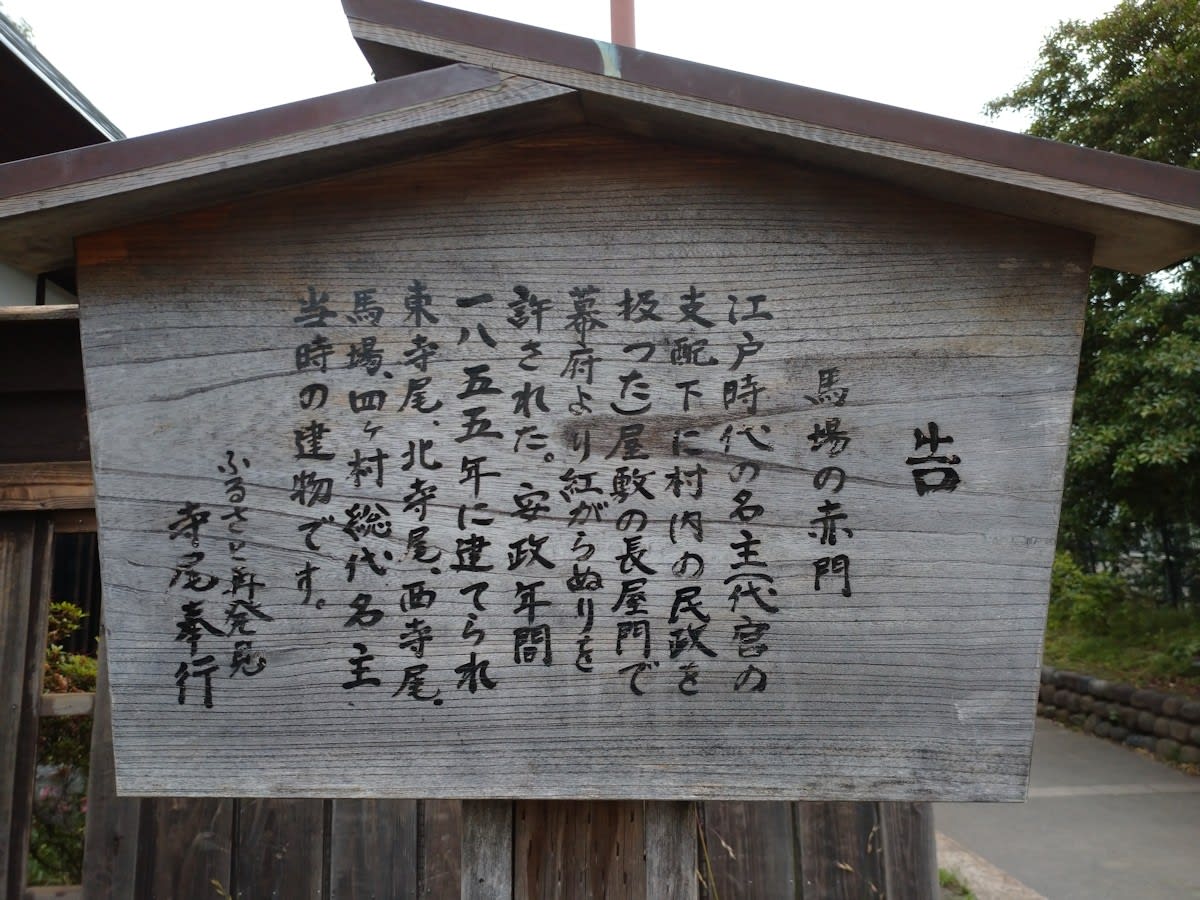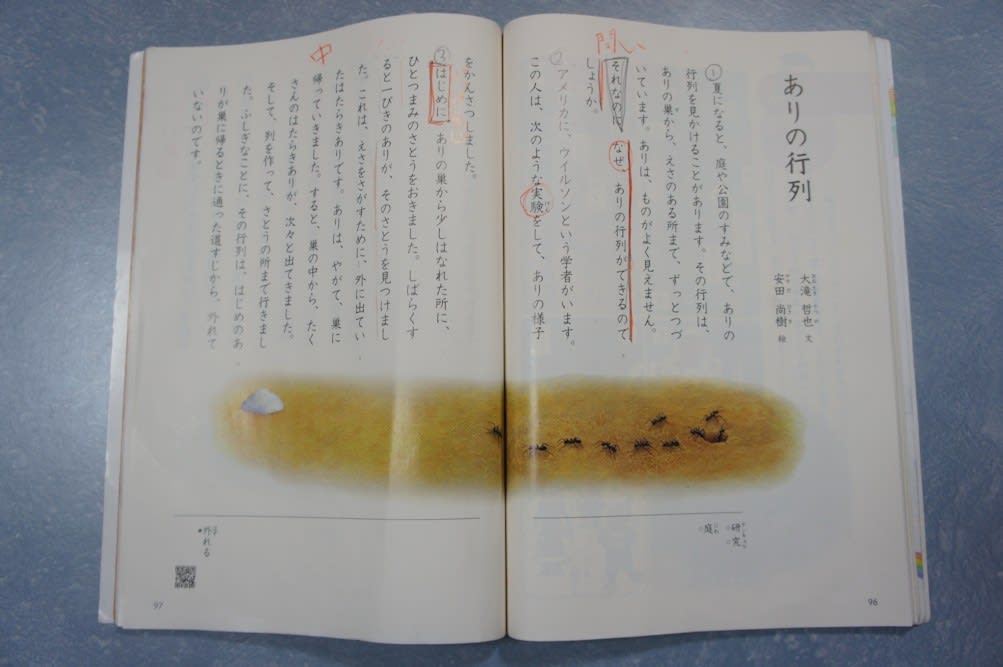この春からベランダガーデニングを始めてみました。
家に3匹いたネコも、最後まで残ったアビが亡くなって(2019年6月6日)からもう2年が経ちました。この機会に娘に鳥を飼ってもらおうかという話も出ましたが、それは立ち消えになりました。ネコは好きだけれど、今は飼える状況ではないということで、動物を飼うのはしばらくお預けです。それならと、私がベランダで植物を育ててみようという気になり、ベランダガーデニングを始めたという次第です。
私が小学生だったころは、家でいろんな生き物を飼うのが好きで、庭で植物を育てるというのもその一つでした。そのころは、庭のチューリップやスイセンの球根を掘り上げて分球させて、秋に植えるくらいのことしかできませんでしたが。今は、種、球根、苗と、昔は見たこともなかったような様々な園芸品種がかんたんに入手できるようになりました。幸いなことに、近くには「サカタのタネ ガーデンセンター横浜」という国内最大級の園芸センターもあって、いろいろな現物を見て購入する楽しみもあります。私の中に眠っていたシーズ(種)の一つをちょっと起こしてみようか、みたいな感じでもあります。

アマリリスだけは昔から育てていて、3本あります。プランターの左右にあるオレンジ色の花を咲かせる2本は25年くらい前に私が買ったものです。しかし、10年間くらい私が栽培放棄して瀕死の状態だったものを、妻が水やりしてよみがえらせて元気になったので、2個の球根に株分け(いわばクローン生殖)したものです。ちょっとした歴史ありです。まん中の白い株は妻が6年ほど前に買ったもの。


みんないっせいに咲かないで、時間差で咲きます。最初の白い花が開花してから、3本目のオレンジの花が開花するまでに3週間くらいかかっています。オレンジ花のクローン2本でも開花日が10日程ずれているのがおもしろいところです。遺伝子はまったく同一、環境もほぼ同じなのになぜでしょう?

これは4月に、球根から栽培を始めた「はなかたばみ ラッキークローバー」。成長が早くて、植えて1.5か月くらいでここまで生育しました。四つ葉のクローバーはなかなか見つかりませんが、この植物の葉は全て四つ葉という、全てラッキーということです。

このベランダは比較的日当たりがいいほうなのですが、さらに太陽の方向に向かってほふくして伸びるようになりました。太陽が大好きな植物です。

はなかたばみと同じく4月に球根で植えた「ゼフィランサス」。

初夏から秋にかけて花を咲かせるそうなので、もう少し待ちましょう。

5月に苗で入手したイングリッシュ・ラベンダー。青いところがつぼみのようです。

開花するとこんな感じで、つぼみのほうが青色がきれいだったかな。でも、開花してよい香りを放っています。

5月に苗を入手したサンパチェンス。サカタのタネが、インパチェンスから品種改良で作った品種ということで、サカタの一推しの商品です。

鉢に2株植えましたが、成育旺盛らしいので、1株で十分だったかな。花もチラホラ咲き始めました。これからが楽しみです。
(続く)