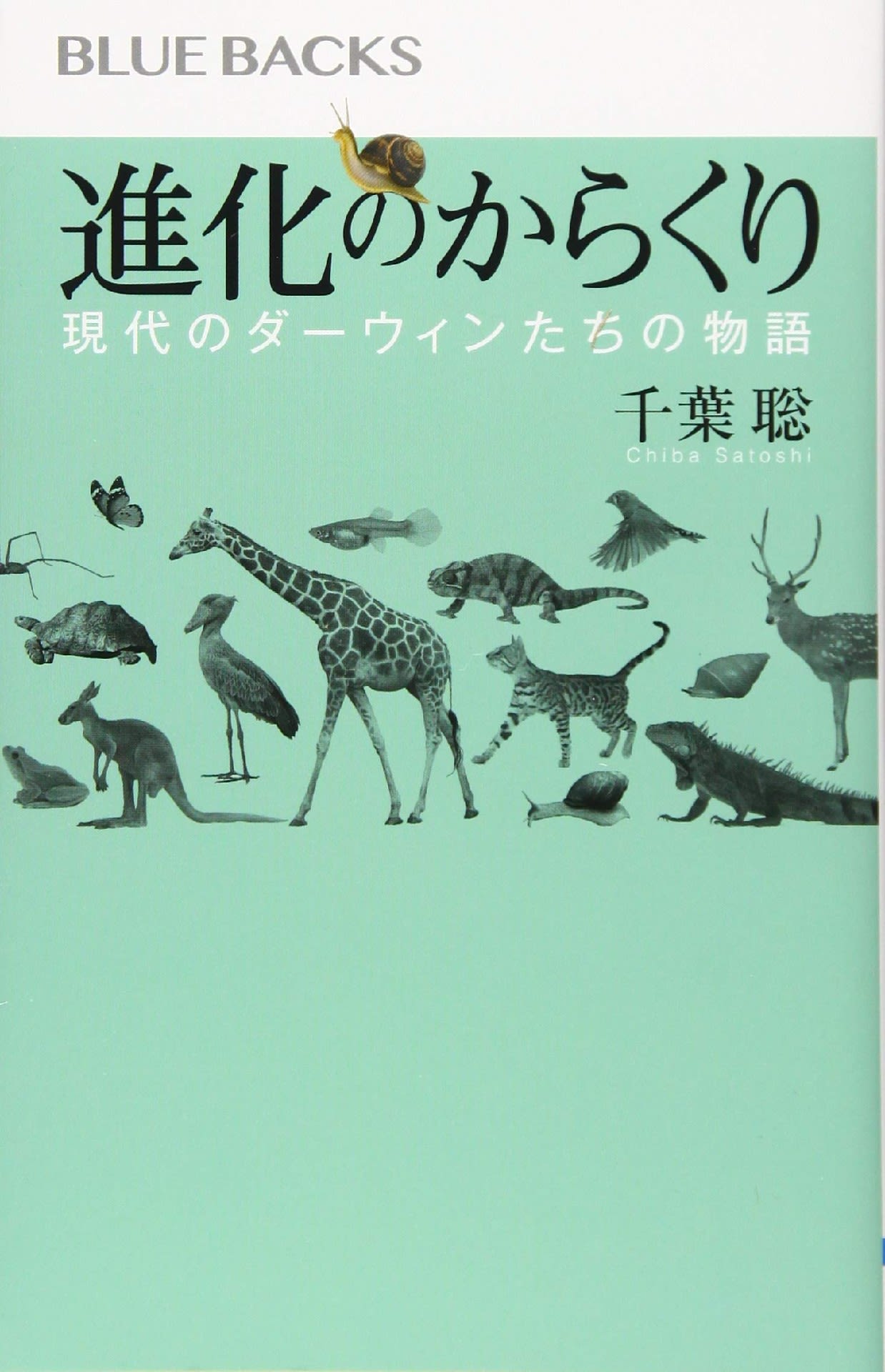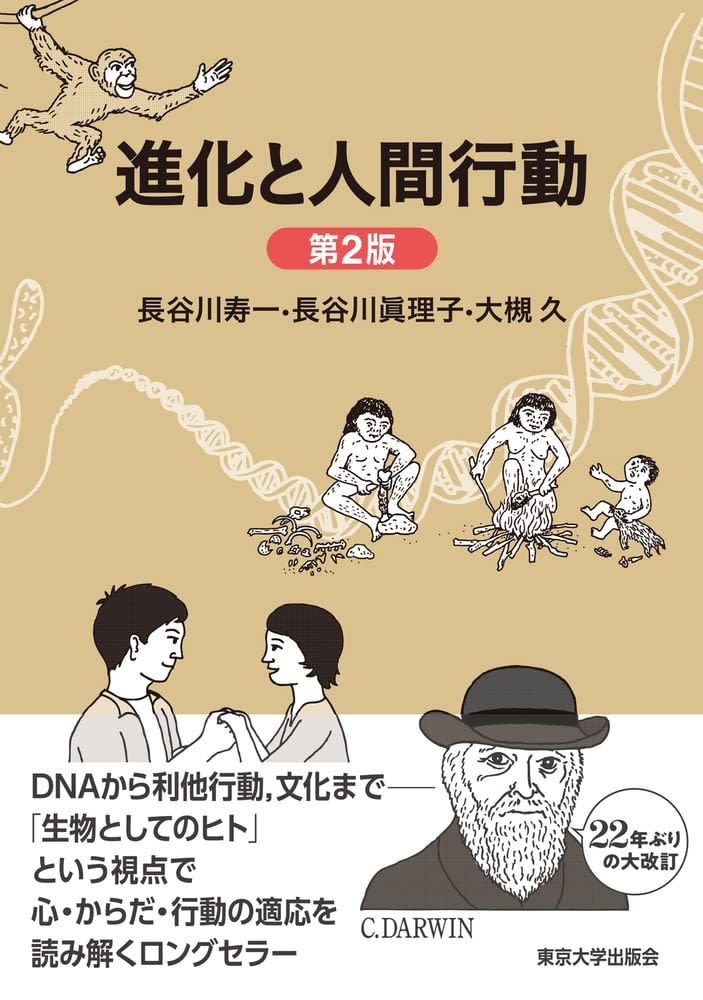スバンテ・ペーボ博士が、「絶滅したヒト科動物のゲノムと人類の進化に関する発見」でノーベル生理学・医学賞を受賞したのが、2022年10月だった。本書はまさにこの分野ーゲノム解析による進化人類学ーの現在の知見をまとめた本であり、こうした学術的なかたい内容の本としては、ずいぶんと売れたようである。帯には「ノーベル賞で話題!」と書かれていて、ペーボ博士の業績はどうすごいのか、いかに革新的だったのかといったことの解説が書かれているものだと思っていた。しかし、そうした内容は「はじめに」において少しだけ触れられているものの、詳しい説明はまったくなかった。本書の初版が出たのが2022年2月だったから、間に合わなかったということもあるのだろうが、期待がはずれてしまった。また、この分野の研究が急速に発展してきた最大の立役者は、研究技術の革新があったことだと思われる。どういった技術が使われてこの研究が行われているのかについて、しっかりした解説が欲しかったが、これも簡単な記述だけで済まされていて肩透かしを食らってしまった。だから、売れているというわりには、期待外れの感があったことは否めない。
しかしながら、様々な異論が多くて仮説の段階を脱していない説ばかりだが、現時点での研究状況や成果が網羅的にまとめられているという点で、多くの情報が得られるというメリットはあった。その中で、私が興味を持ったところを挙げてみた。
【はじめに】
・ここ数年、古代DNA研究が活況を呈している。その背景には、次世代シークエンサの実用化が大いに関係している。次世代シークエンサの技術を使うと、サンプルに含まれるすべてのDNAを高速で解読することができる。2006年に次世代シークエンサが実用化し、2010年にネアンデルタール人の持つすべてのDNAの解読に初めて成功するなど、古代DNA解析にもとづいた人類集団の成り立ちに関する研究が非常に活発になり、現在では世界各地の一流科学誌に毎週のように論文が掲載されている。
【第一章 人類の登場】
・ネアンデルタール人の脳容積の平均は1450ミリリットルで、中にはホモ・サピエンス(平均1490ミリリットル)を凌ぐものもいたことがわかっている。ただし、ネアンデルタール人の脳で発達するのは主として視覚に関わる後頭葉の部分である。一方、ホモ・サピエンスで発達するのは、思考や創造性を担うと考えられている前頭葉で、このことは、同じような容積を持ちながらも、私たちとネアンデルタール人とでは、社会生活や認知が異なっていたであろうということを示唆している。
【第二章 私たちの「隠れた祖先」ーネアンデルタール人とデニソワ人】
・古代試料にはごくわずかなDNAしか残されておらず、しかもそれは非常に短い断片となっている。PCR法を使って、それらの試料を増幅して分析を行うのだが、この際に問題になるのが外在性DNAの混入、いわゆるコンタミネーションである。これは古代試料のDNA分析が始まった1980年代から、研究者を悩まし続けている問題だ。現代人のDNAの混入は、発掘調査の現場から実験室の分析に至るまで、あらゆる過程で起こる危険性がある。実験室での手順については、世界の主要なラボでコンタミネーションの危険性をほぼ払拭できるようになっている。発掘時、あるいは人骨試料の保管時にこの問題が残っていたが、近年では、のちのDNA分析を前提とした発掘が行われるようになっており、発掘の時点からコンタミネーションを起こさないように慎重な措置が取られるようになってきた。
・人骨からではなく、洞窟堆積物からも古代ゲノムを検出することができるようになった。核ゲノムでは、得られたデータが同一個体からなのか、あるいは複数の個体に由来するのかなどを判定しなければならず、人骨から得られたデータよりも解析が困難になる。それでも今後この方法は、ネアンデルタール人やホモ・サピエンスの解析に応用されて、化石の空白地域での集団の変遷についても、新たな知見をつけ加えていくことが期待される。
・ホモ・サピエンスとネアンデルタール人、デニソワ人は60万年ほど前に共通の祖先から分岐したが、その後の交雑によって、互いのDNAを交換することがあった。一般に生物進化では、隔離によって集団の分裂が起こり、その状態が長く続くことで種分化して、異なる種が成立する。けれども、数十万年の人類進化の歴史を概観すると、分化とともに交雑がホモ・サピエンスを形成するために重要であった。
【第三章 「人類揺籃の地」アフリカー初期サピエンス集団の形成と拡散】
・現在では、ホモ・サピエンスがアフリカで誕生したということはほぼ定説となっている。もっとも古いホモ・サピエンスの化石が、アフリカの30万年ほど前の地層で発見されているからだ。しかしながら、ネアンデルタール人やデニソワ人の共通祖先から分岐したのが60万年ほど前なのにもかかわらず、誕生からかなり長期間にわたってホモ・サピエンスの祖先と考えられる化石がないことや、数十万年前にネアンデルタール人とのあいだで交雑があったことなどを考えると、ホモ・サピエンスの最初の祖先はアフリカではなくユーラシア大陸にいて、30万年前以降にアフリカ大陸に移動したグループがのちに世界に広がることになるアフリカのホモ・サピエンスとなり、ユーラシアに残ったグループは絶滅したというシナリオも考えられる。
【第四章 ヨーロッパへの進出ー「ユーラシア基層集団」の東西分岐】
・西アジアで農耕が始まるのは1万1000年前とされている。彼らはヨーロッパに農耕とゲノムをもたらすことになるが、もともと中東の農耕民は単一の集団ではなかった。
・それまでの狩猟採集民の生活から、およそ4900~4500年前に、ハンガリー、ウクライナ、アルタイ山脈に広がる地域で、ヤムナヤと呼ばれる牧畜を主体とする集団の文化が生まれた。彼らは瞬く間に広範な地域への拡散を成し遂げ、ヨーロッパの農耕社会の遺伝的な構成を大きく変えることになった。たとえば彼らの流入後、ドイツの農民の遺伝子の4分の3がヤムナヤ由来の遺伝子に置き換わったことがわかっている。現代のヨーロッパの言語は、インド・ヨーロッパ語族と呼ばれるグループに分類される。ヤムナヤ集団がインド・ヨーロッパ語の祖語を話していたとする可能性も出てきている。
・次世代シークエンサを使った古人骨の分析では、その人骨の持つすべてのDNAを解析することになる。したがって、その人物が持っていたヒト由来のDNAだけではなく、細菌やウイルスのDNAもデータとして取得できる。このため、過去の疾病を特定することも可能になる。3回、世界的大流行が発生したぺストもその例となっている。
【第五章 アジア集団の成立ー極東への「グレート・ジャーニー」】
・長らく人類未踏の地であったミクロネシア、メラネシア、ポリネシアに進出したのがオーストロネシア語を話す人びとである。この言語は、台湾から東南アジアの島嶼部、ニュージーランドやハワイ、イースター島などの太平洋の島々、そしてアフリカ大陸東岸に位置するマダガスカルまでの地球上のおよそ半分を占める広大な地域で話されている。その中で、台湾の先住民の使うオーストラロネシア語がもっとも古く、台湾内部の先住民の各グループ間での違いが大きいことから、言語学の研究からは台湾が源郷であり、さらにその祖先は、中国南部の海岸地域に居住していた集団であると考えられている。これを「アウトオブ台湾モデル」と呼ぶ。
【第六章 日本列島集団の起源ー本土・琉球列島・北海道】
・日本人の成り立ちについては、「二重構造モデル」と呼ばれる学説が定説として受け入れられている。二重構造モデルでは、旧石器時代に東南アジアなどから北上した集団が日本列島に進入して基層集団を形成し、彼らが列島全域で均一な形質も持つ縄文人となったと仮定している。一方、列島に入ることなく大陸を北上した集団は、やがて寒冷地適応を受けて形質を変化させ、北東アジアの新石器人となったと考えられている。弥生時代の開始期になると、この集団の中から朝鮮半島を経由して、北部九州に稲作をもたらす集団が現れたとされ、それが渡来系弥生人と呼ばれる人びとになる。つまり、縄文人と渡来系弥生人の姿形の違いは、集団の由来が異なることに起因すると説明している。
【第七章 「新大陸」アメリカへー人類最後の旅】(内容略)
【終章 我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのかー古代ゲノム研究の意義】
・人類集団間(いわゆる人種や民族)よりも、同じ集団の二人の間のほうが遺伝的な変異(SNP)が大きい。ホモ・サピエンスのゲノムは99.9パーセントまで共通である。研究者は残り0.1パーセントの違いに注目して、個人ごとあるいは集団ごとの違いを明らかにしていく。細かい違いを問題にしていくというのは、科学の方法としてはオーソドックスなものなので、研究の方向として間違っているわけではない。この0.1パーセントの中に、人びとのあいだに見られる姿形や能力の違いの原因となっている変異があることも事実である。ただし、大部分は交配集団の中に生まれるランダムな変化で、基本的に能力などの違いを表すものではない。(私は著者とは違って、この0.1パーセントの遺伝子の違いによって生み出される何が私たちを苦しめているのかを解明することは重要だと考える)