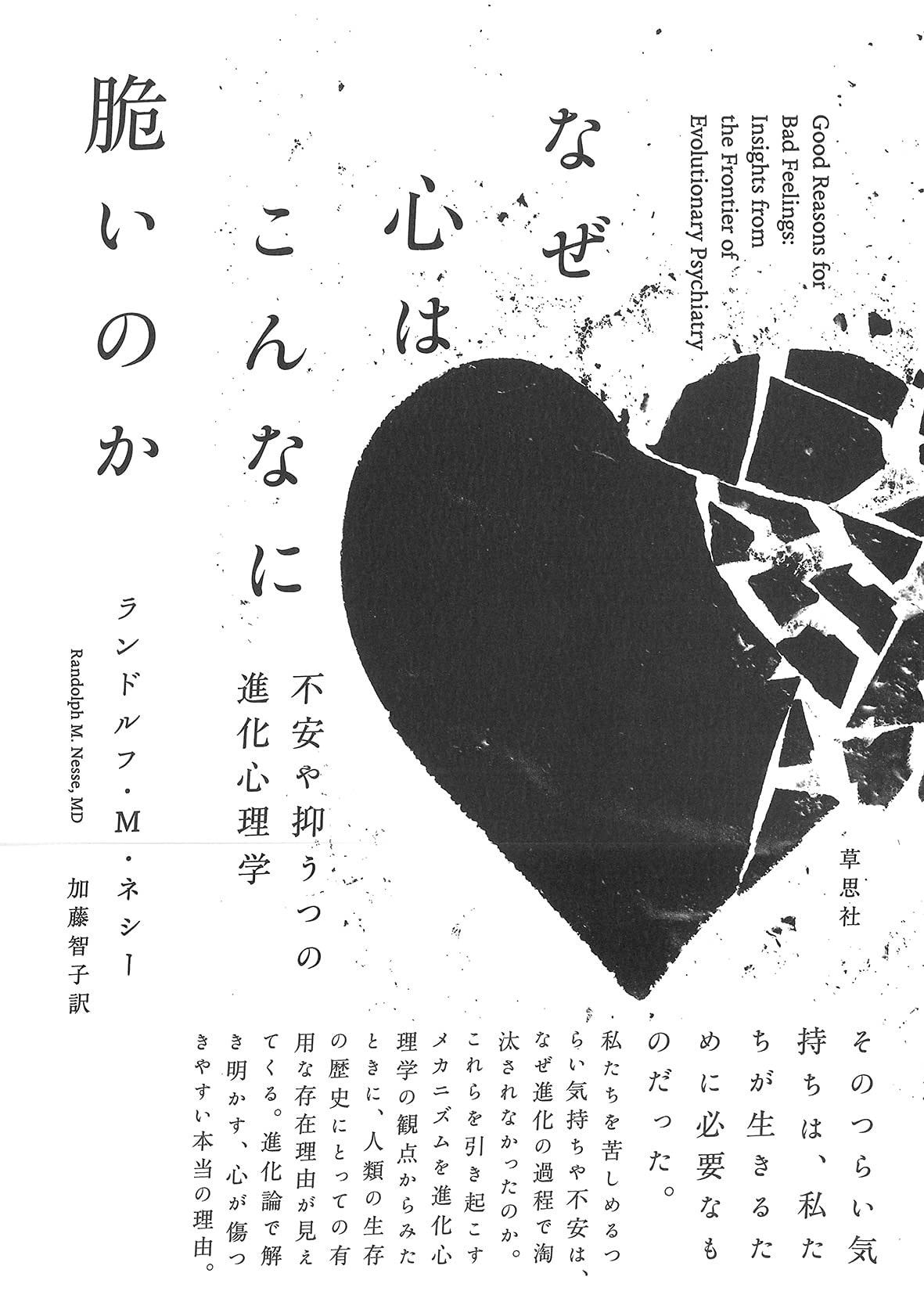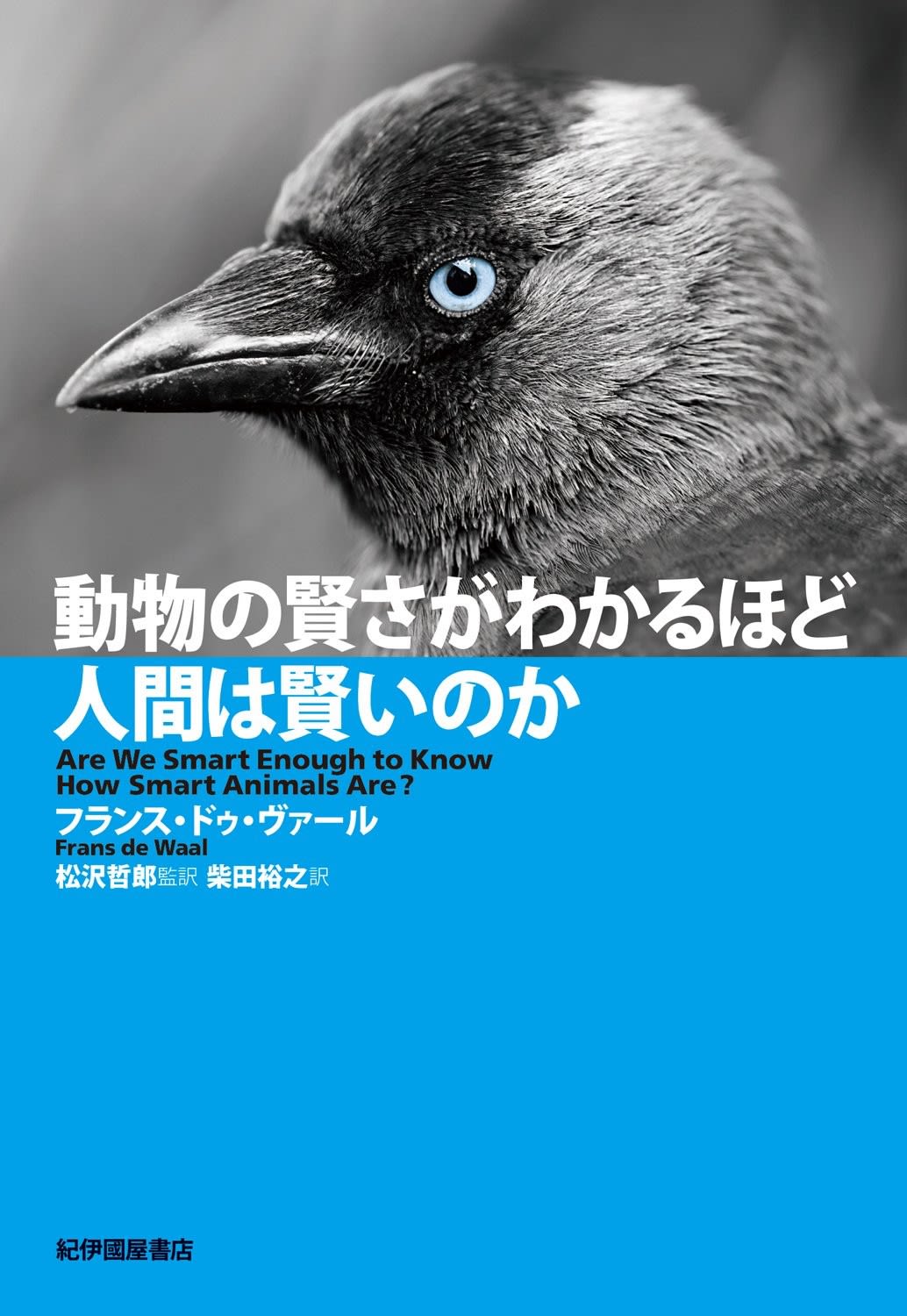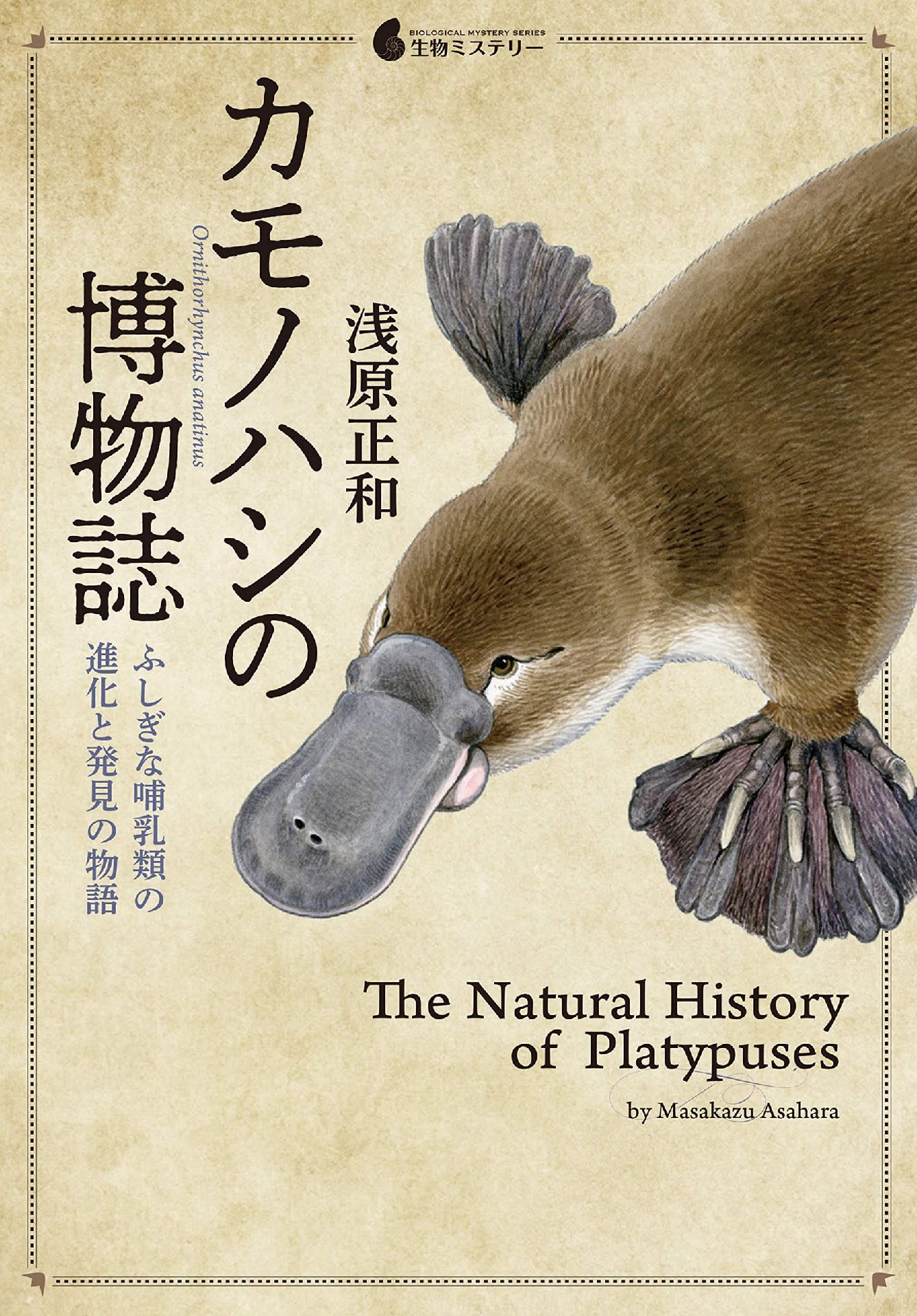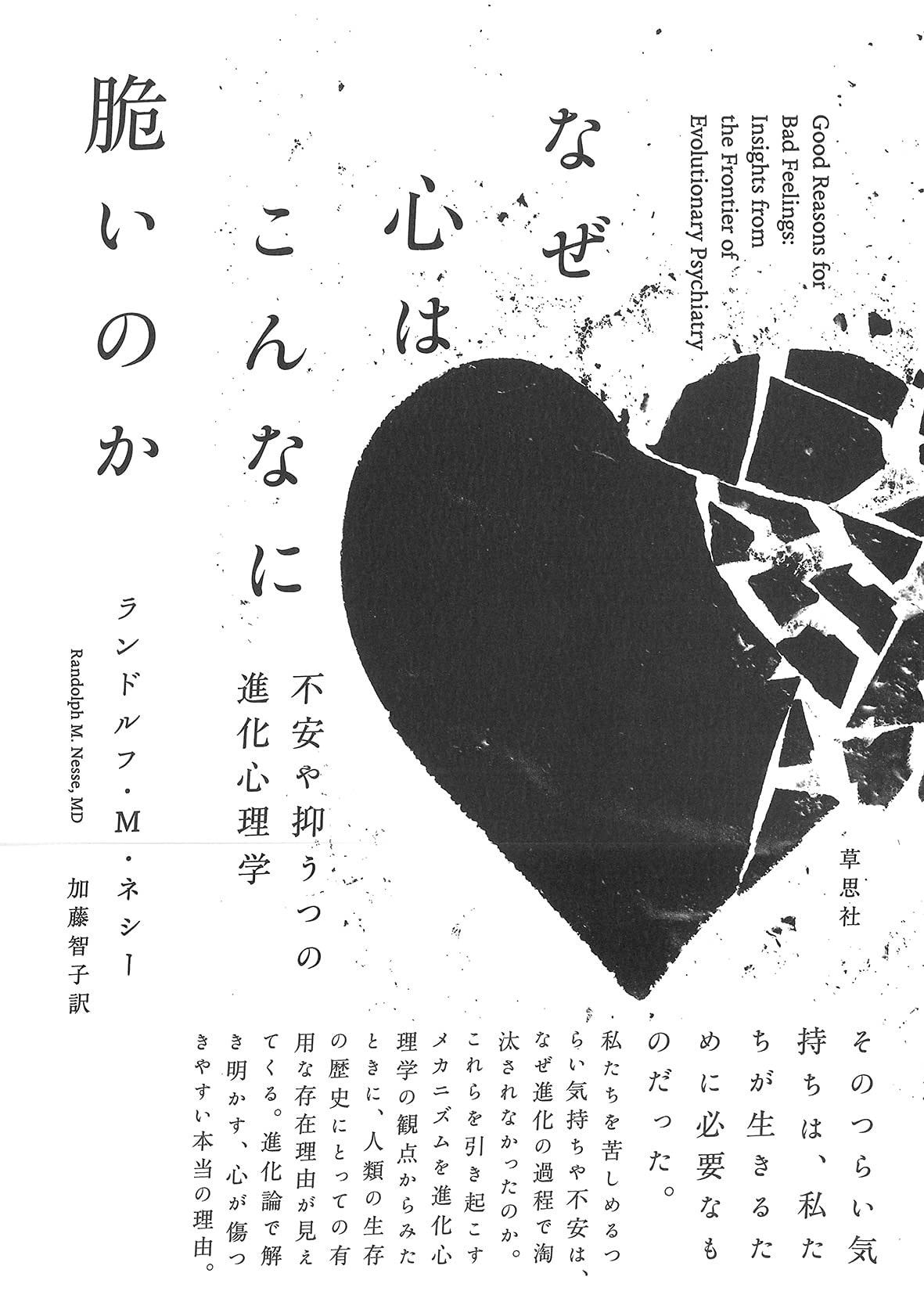
まず最初に、本書の副題に「進化心理学」という言葉が入っているが、原題が「Good reasons for bad feelings: Insights from the frontier of evolutionary psychiatry」であるので、「進化精神医学」とするほうが正しい。著者のランドルフ・M・ネシーは精神医学者であるが、進化医学の開拓者的な立場にいる人でもある。
なぜ精神疾患は存在するのか?なぜこれほど多くの人が精神疾患を患うのか?なぜ不安やうつ病、依存症や拒食症、自閉症や統合失調症、双極性障害を引き起こす遺伝子は、自然選択によって消え去らなかったのか?そうした問いを考えることで、精神疾患のより深い理解と、より効果の高い治療の実現につながる。それを示すことが、本書の目的であるとしている。
エピローグの最後のほうで書かれている結論を、先に引用しておく。『私は、進化や行動について学ぶことが即時的な恩恵をもたらすかどうかについては断言できないと考えていた。だが実際に多くの症状について、私の提供する治療は大きな変化を遂げた。パニック障害が闘争・逃走反応システムの誤報であること、そして誤報が起きる仕組みは煙探知機の原理によって説明できることを臨床医が理解していれば、パニック障害の治療は大きく改善される。飢餓に対する防御メカニズムは、正のフィードバック・スパイラルを起こしやすいこと、そして過酷なダイエットによってそのようなシステムが起動してしまうことを知っていれば、摂食障害の治療を改善できる。人間に備わる学習メカニズムと、大昔には想像もつかなかったような新たな物質とその入手経路が組み合わさることで依存症が生まれるという認識によって、依存症の治療を改善できる。そして、私が教えた精神科の研修医たちは口を揃えて、うつ病の患者に「どうしてもうまくいかないけど諦められない、重要な目標がありますか?」という質問をしてみることが非常に重要だと感じる、と言っている。』
468ページある本書の内容は盛沢山であった。いろいろと勉強になったので、興味深かったポイントを章ごとに記録しておきたい。
1.新たな問い
・愚かな行為によって自分の存在をこの世から消し、その遺伝子を自ら抹消した人に贈られる「ダーウィン賞」という賞がある(調べたら、実在するとてもブラック・ユーモアな賞である)。その一方で、恐れが強く、家を出ることもままならない人もいる。そういう人は早死にすることはないが、多くの子どもをもつこともない。不安の程度が中ぐらいの人は、より多くの子どもを残す。その結果、中程度の不安をもつ人の占める割合が一番多くなる。
・ネシーは進化生物学者ジョージ・ウィリアムズと議論を重ね、1994年(日本版は2001年)に共著で「病気はなぜ、あるのかー進化医学による新しい理解」という本を出している。これが、進化医学という新しい分野の発展の契機となった。今では、ほとんどの主要な大学で進化医学の講義が行われるようになっているという(これは米国のことであって、日本はどうなのだろうか?)。
2.精神疾患は病気なのか
・精神医学の診断体系として、米国で作られたDSM(Diagnositc and Statistical Manual of Mental Disorders)(精神疾患の診断・統計マニュアル)があり、世界中で使用されている。これは定期的に改訂されてきているが、改訂のたびに論争が起きた。現在は、2013年に改訂されたDSM-5が使われている。296人からなる米国精神医学会の特別委員会が、ときに激しい論争も交えながら、10年の歳月ををかけて作成した。この版では、パーソナリティ障害群がほかの疾患と同じカテゴリーに移され、「物質依存」と「物質乱用」が「物質使用障害」として一つにまとめられるなどいくつかのカテゴリーが統合され、「広場恐怖症」が「パニック障害」から独立して記載されるなどの変更により、それ以前の版よりも一貫性が高く、有用な版となった。一方で、カテゴリーを「軽度」から「重度」までのスケールに置き換えるという提案が却下されたことや、遺伝子、血液検査、スキャンといった方法による検査ができるまでに至ってないことなど、まだ不満が持たれている。
3.なぜ私たちの心はこれほど脆いのか
・精神疾患を含めた病気全般について、私たちが脆弱である6つの進化的理由を挙げている。①ミスマッチー私たちの体は現代的な環境に対応する準備ができていない。②感染症ー細菌やウイルスが私たちよりも速い速度で進化している。③制約ー自然選択には限界がある。④トレードオフー体のあらゆる機能には利点と難点がある。⑤繁殖ー自然選択は繁殖を最大化するものであり、健康を最大化するものではない。⑥防御反応ー痛みや不安などの反応は脅威を前にした状況では有用だ。
・上記の⑥防御反応について。人間の苦しみを生み出す防御反応のほとんどは、そのときだけに限ってみれば不必要だが、それでも完全に正常な反応である。これは、煙探知機が誤って作動して警報を鳴らすのと似ているので、「煙探知機の原理」とよんでいる。不必要な嘔吐や痛みがたまに起きるのも、食中毒や組織損傷から身を守る防御反応が確実に起きてくれることを考えれば、決して無駄ではない。
・病気を適応としてみることは、進化医学の分野で見られる深刻な誤謬だ。病気は、自然選択によって形づくられた適応ではないからだ。一部の病気に関連づけられる遺伝子や形質は、それぞれが利点と難点をもたらし、自然選択に影響を与える。だが、統合失調症や依存症、自閉症、双極性障害といった病気そのものに有益な点があるのではという考えは間違っている。「なぜ自然選択は、私たちを病気に対して脆弱にするような形質を残したか?」という問題設定が正しい。
4.辛い気持ちの妥当な理由
・目標を追求する過程で、いくつかの特定の状況に遭遇すると、それぞれ異なる適応上の課題を突き付け、さまざまな情動を形づくる。機会という状況は熱狂を引き起こす。成功という状況は喜びを引き起こす。脅威という状況は不安を引き起こす。喪失という状況は悲しみを引き起こす。
5.不安と煙探知機
・さまざまな不安障害はそれぞれ危険な状況と関連性がある。動物による危害の可能性→小動物恐怖症、転落による怪我→高所恐怖症、捕食者や人間による攻撃→パニック発作・広場恐怖症、社会的地位の喪失→社会不安障害、病気→心気症、社会的拒絶→魅力の欠如への恐怖、怪我・失血→針への恐怖・失神する恐怖。
・著者は患者に、パニックの症状は命を脅かすような危険から逃げる際には有用であり、パニック発作はトーストが焦げたときの煙探知機のアラームの誤報なのだと説明するようになった。これを聞くと患者のおよそ4分の1は、こう言うようになった。「先生、ありがとうございます。そういうことだったんですね。これで納得がいきました。もし、また助けが必要になったら電話します」
・著者は臨床医としての駆け出しのころ、不安障害の患者に対して、彼らが病気になってしまったことへの同情を示そうとしていた。そのせいで、自分は弱くて問題を抱えた存在なのだと多くの患者に感じさせてしまっていた。だが、不安は役に立つ反応であること、ただし行きすぎてしまうケースがよくあるのだと説明するようになると、多くの人は自分がおかしいわけではないと感じられ、勇気づけられたと話してくれるようになった。
6.落ち込んだ気分と、諦める力
・ロンドンの精神分析医だったジョン・ボウルビィは、落ち込んだ気分がもつ機能を進化的に考えた最初の研究者の一人だ。動物行動学者コンラート・ローレンツと生物学者ロバート・ハインドとの対話にヒントを得て、母親から引き離された赤ん坊の行動に、進化的な視点から注目した。母親と引き離される時間が長くなると、最初は抵抗して泣き、次に黙ってうずくまり、体を揺らすようになる様子は、絶望した大人そっくりだった。赤ん坊の泣き声は母親が戻ってきて赤ん坊を抱きあげる動機になる。泣いている時間が長くなるとエネルギーの無駄使いになり、かつ捕食者を引き寄せてしまうので、ひっそり静かにしているほうが有益である。これらの発見は愛着理論として発展した。
・心理学者のエリック・クリンガーの1975年の論文で、気分は状況の良し悪しによって変化するということを示している。人は、人生に関わるような目標に向けて前進しているとき、いい気分を味わう。だが、目標達成を阻害するような障害が現れると、不満感が生じ、しばしば怒りや攻撃性として表出する。そして、目標に向けての全身がままならない状態になると、やる気がそがれ、一時的に社会的引きこもり状態になる。達成不可能な目標を完全に諦めた後には、落ち込んだ気分は消え、代わりに喪失によって引き起こされる一時的な悲しみがやってくる。そしてその後は、達成し得る別の目標を追求すべく、新たに動き始めるのだ。しかし人生には、例えば職探しやパートナー探し、命に関わる病気の治療法など、諦められない目標もある。そのような場合には、人は達成できない目標の追求から抜け出せなくなり、本格的なうつ病へと発展してしまう。
7.妥当な理由のない辛い気持ち:気分調節器が壊れるとき
・数千もの遺伝子の差異が、身長や糖尿病の発病の有無、血圧、うつ病などに影響を与えているが、それぞれの遺伝子による影響はごくわずかだ。その一つ一つを異常と呼ぶのは理に適わない。
8.個人をどう理解すべきか
9.罪悪感と悲嘆ー善良さと愛情の代償
・クリニックで診察にあたっていると、人間の本性に関する考え方が患者の人生や悩みに影響していることがはっきりとわかる。患者のパーソナリティーを短時間で把握するために、著者は一つの質問をしている。それは、「人間の本性とはどのようなものだと思いますか?」という問いだ。この人の治療はおそらく成功するだろう、と一番思わせてくれる解答は、「ほとんどの人は、ときには良いこともするし悪いこともします。状況による部分は。とても多いと思います」というものだ。より頻繁に耳にする答えからは、人類全体を含めたほとんどすべてのことを良いか悪いかで断罪しようとする、人間の強い傾向がみてとれる。「ほとんどの人は、良い人間だと思います。皆、できるだけ正しいことをしようとしているわけですから」と答える患者は、神経症傾向があることが多く、治療における関係性は良好なものになることが多い。一方で、「大体の人は自分のことしか考えていません。でも、そんなものですよね」というような答えを返す人は、親しい人間関係で問題を抱えていることが多い。
・社会的行動・協力的行動が、血縁選択(ウィリアム・ハミルトン、ジョン・メイナード=スミス)、相互利益、便宜の交換(ロバート・トリヴァース)という概念で説明できるようになったことは、私たちの時代におけるもっとも偉大な科学的達成の一つだ。しかし、それでも説明しきれない部分は残る。選択の作用によって強力能力が形成される仕組みとして、このほかに少なくともあと二つの可能性、コミットメントと社会選択がある。
・社会選択は、倫理的行動をとる傾向であり、私たちの遺伝子に息づいている。ほとんどの人は、親や兄弟姉妹、配偶者との関係を通して、心からの思いやりというものを体験する。そしてそれは友達や、ときには犬や猫との関係にも強く存在することがある。私たちがペットを大切に感じるのは、ペットもまた私たちのことを大切に思ってくれるからだ。そしてそれは、社会選択を通した何千年にもわたる家畜化の結果だ。
・私たち人間も、ほかの人間が下す選択によって家畜化されている。私たちは正直で信頼できて、親切で気前が良く、そしてできれば裕福で力をもった人をパートナーや友達に選ぶ。このプロセスによって、「利他的な遺伝子のランダムでない集まり(スチュアート・ウェスト)」が発生する。私たちはそうしたプロセスから恩恵を受けるだ、同時に社会不安や、人にどう思われているのだろうという絶え間ない心配は、深い人間関係を実現するために必要な代償なのだ。
10.汝自身を知れ―否、知るな!
・動物行動学会に行って、研究者たちと議論していたら、当然のように「無意識」を確信しているような話が多く出てきた。「無意識」を研究する精神分析は、現代の精神医学からは排除されているが、著者はそれ以来、「無意識」や「抑圧」が現実にあるように考えるようになった。ある研究では、精神疾患に至る二つの主な経路が明らかにされた。一つ目の経路は内面化、つまり抑制、不安、自己非難、神経症、抑うつだ。そして二つ目の経路は外面化、つまりほとんど抑制することなく自己の利益を追求するという、社会的対立や依存症につながりやすい方法だ。そして私たちの多くは、この二つのグループのあいだをうろうろしている。
・この二つの戦略は、短寿命型と長寿命型の生活史戦略、およびその精神疾患との関連性の可能性と関係している。幼年期に厳しい環境にされされると、長期的利益の価値を低く捉えるようになり、長期的な関係性を犠牲にしてでも目の前の機会をつかもうとする行動が引き起こされることが示されている。このことが、幼少期の困難な経験と境界性パーソナリティ障害との関連性を説明する助けになるかもしれない。
11.不快なセックスが、遺伝子にとって都合がいい理由
・自然選択によって、私たちの脳と体は繁殖を最大化するように形づくられている。そして、そのために、人間の幸福という甚大な犠牲が払われているのだ。だから、性的な問題やフラストレーションは、どこにでも当たり前にあるものだ。
・「妻がセックスしたがらなくてどうしていいかわからないんです。別れたくはないけど、セックスのない人生も嫌なんです」という患者に対して、先輩医師は次のような簡潔な助言を与えた。「それなら、選択肢は四つあります。セックス・セラビーに通うか、離婚するか、浮気するか、あるいは結婚生活を続けてマスターベーションするか。その中から選べばいいだけです」。こんなそっけない助言をするなんて、あまりにぞんざいな対応のように当時の著者には思えた。だが実際のところ、この助言は多くの人が体験する難問に見事に答えている。
12.食欲と、その他の原始的な欲望
13.いい気分と、その有害な理由
・人間にとって精神活性作用をもつほとんどの化学物質は、昆虫の神経システムを妨害するために進化を遂げた。人間の脳内の化学物質が今とは違う種類のものだったら、私たちはこれほどまでに依存症に脆弱ではなかっただろう。だが、私たちと昆虫は5億年ほど前に共通の祖先から分岐したのだ。私たちの神経物質は、今も昆虫のそれとほとんど変わらないままだ。幸い、ほとんどの植物性神経毒は、人間を死に至らしめることはない。だがドラックは、私たちの動機付け構造をハイジャックし、人生のコントロールを奪ってしまう。
14.適応度の崖っぷちに引っかかる心
・統合失調症と自閉症と双極性障害は、それぞれまったく異なる病気だ。しかし、共通点も存在する。まず、どの病気も、有病率はそれぞれ世界人口の約1%であり、軽症型はそれぞれ全人口の2~5%だ。これらの病気が遺伝的要因による影響を受けることは、強力なエビデンスによって支持されている。発症リスクのうち遺伝的変異による影響が占める割合は、双極性障害が70%、統合失調症が80%、自閉症が50%だ。
・2000年代に入るころには、これらの病気を引き起こす対立遺伝子が近々発見されるに違いないという期待が高まった。しかし特定の遺伝子は見つからなかった。もう少しマクロな視点で遺伝子マーカーに注目し、精神疾患を持つ人たちのほうが、特定の遺伝子座における遺伝子変異を持つことが多いのかどうかを検証したが、結局そのような遺伝的変異は存在しないということがわかった。その理由として考えられる一つの可能性は、関連する遺伝的変異があまりにもまれなものであるため、たとえそれが大きな影響力をもっていたとしても見つけることができない、というものだ。そして、遺伝的要素による影響の大部分は、小さな影響力をもつ多数の対立遺伝子による非常に複雑な相互作用によって生み出されていることが示されている。
・ゲノム刷り込みは、遺伝子が母親由来か父親由来かに応じて遺伝子のスイッチを選択にオフにすることができる。この仕組みによって、母親由来の遺伝子は、胎児をほんの少し小さいまま保つことで、お産をより安全なものにして優位性を得る。一方で父親由来の遺伝子は、胎児が大きく成長させることで優位性を得る。進化生物学者のバーナード・クレスピらは、父親由来の対立遺伝子の発現比率が大きくなると自閉症のリスクが上がり、母親由来の対立遺伝子の発現比率が大きくなると統合失調症のリスクが上がるというエビデンスを集めた。体の大きな赤ん坊は父親由来の遺伝子の発現が強くて自閉症に可能性が高くなり、小さい赤ん坊は統合失調症への脆弱性が高くなると予測されるが、500万人のデンマーク人の医療記録の調査によって予測が裏付けられている。
・最近確立された新たな手法によって、統合失調症への脆弱性に影響を与える遺伝的変異の多くが初めて現れた時期は、人間がチンパンジーと分岐した後、つまり約500万年前以降に現れたと考えられることがわかった。
・著者は「崖型の適応度関数」というモデルを提唱している。これによると、ある形質の適応度が最大となる点が崖の淵にあたる場合、個体の繁殖の成功が最大化される点よりも少し高いところに形質の平均値がくるように自然選択が働く。平均値の形質をもつ個体のうち数パーセントは、崖の外側にはみ出し、高い病気リスクをもつことになる。この考え方は一般には認識すらされていない。しかしこのモデルは、特定の精神疾患を引き起こす特定の遺伝的原因が見つからない理由を説明できる可能性があると考えている。問題は欠陥のある遺伝子によって引き起こされるのではない。代わりに、ペーパーロック現象(ブレーキを使いすぎるとブレーキが効きにくくなる現象)に見られるような内因的なトレードオフが、崖型の適応度地形を形づくった結果として、リスクが生じるということになる。
エピローグ.進化精神医学―島ではなく、橋となる
・そして最後に、本書と同じ、なんで人間はこんなに苦しいのかという問題に取り組んだあのシッダールタが登場する。シッダールタは、人生の痛みと悲しみを目の当たりにし、その原因と解決方法を求める探求を始めた。そして彼の出した結論は、すべての苦悩は欲望から発する、というものだった。この答えは正しいように思える。もしシッダールタが現代に生きていたら、彼はおそらく、なぜ自然選択は欲望とその追及によって引き起こされる苦しみや喜びの情動を形づくったのだろう、という問いに取り組んでいたのではないだろうか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今年一年ありがとうございました。よいお年をお迎えください。