連休中に京都府八幡市にある松花堂庭園・美術館に行ってきました。
3月26日~5月5日に美術館で「椿・桜そして竹~絵画の中の春爛漫~」で日本画の展示会が開かれていたので、この機会に初めて訪れてみました。
京阪八幡市駅からバスで約10分「大芝・松花堂前」下車すぐ。
石清水八幡宮の社僧、松花堂昭乗が隠棲していた坊(寺)の跡です。

有名な料亭が松花堂弁当を出しているお店が園内にあるので、そちらの名前が目だっています。
絵画を見る前に先ず庭園の方へ。


広い園内に茶室が3軒もあって、日本庭園で見ることのできる代表的な垣が18種もあり、それぞれ名前がつけられていたので、ちょっと参考になりました。

茶室「梅隠」。
千宗旦好みの四畳半茶室を再現したものです。
その右手に見えるのが、

萩光悦垣(はぎこうえつがき)。

竹枝穂垣(たけえだほがき)。

茶室「松隠・閑雲軒」。
松花堂昭乗が住んでいた男山の坊「滝本坊」の脇に小堀遠州が建てた茶室を再現したものです。

つくばいの向こうのが松明垣(たいまつがき)。

萩穂垣(はぎほがき)。

茶室「竹隠」。
美しい金明孟宗竹の林を背景にしています。
現在の数奇屋大工が工夫と技術を尽くして建てた茶室で、春と秋の観光シーズンにはここで日曜茶席が開催されます。

寒竹あやめ垣。

萩小松明垣(はぎこたいまつがき)。

昭乗垣(しょうじょうがき)。
竹を細かく編んで、向こう側の人からの目隠しがしっかりできています。

ここから先は撮影禁止のエリア。
メインの茶室「松花堂草庵」と旧泉坊書院、それに露地の庭園や古墳を利用した庭園等、目の保養になる素晴らしいものでした。

謡曲「女郎花」にちなんだ女塚。

愛好家の方達による「瓢箪展」が4月30日~5月2日に開催されるそうで、残念、1日早く来てしまいました。











 。
。











 (大げさ)。
(大げさ)。





 。
。 。
。














 ・・最高っの贅沢やね。
・・最高っの贅沢やね。












































 欲しーい
欲しーい と思ったら、自分で作れる
と思ったら、自分で作れる
















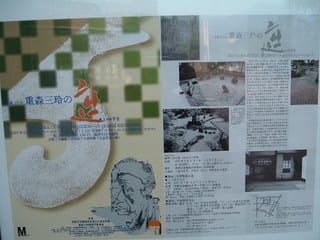











 花嫁花婿(さっきとは別のカップル)がいて、平安神宮専属のカメラマンに撮影してもらっていました。
花嫁花婿(さっきとは別のカップル)がいて、平安神宮専属のカメラマンに撮影してもらっていました。 6月8日(金)には平安神宮の庭園が無料公開されます。
6月8日(金)には平安神宮の庭園が無料公開されます。




























 アーーーーッ
アーーーーッ




















