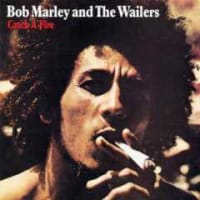先にレビューを書いた、ピアノソナタ変ロ短調のところでも触れたが、この楽曲はショパンが自身17歳のときに、4番目(作品番号3)に作曲した本格的なソナタ曲である。当然ことながら後年の彼の作品に見られるような独創性は全くなく、この曲も自身の意志でなく、師であるヨゼフ・エルスナーに強制的に書かされたと言われている。
しかしながら、(結果論で申し訳ないが・・・)ショパンにはやはり天賦の才がこの当時からあったと思われる様々な個所がこの曲の随所にみられ、残念ながら録音盤がとても少ない中で、ピアノを志すものに取っては大変参考にな曲である。まず第1楽章ではかなりバッハを意識している。更に半階音を利用した転調に執拗に拘っている。ただ演奏家にいわせるとこれだけに拘っていて単調でつまらないといわれるが、主題の再現部で変ロ短調で始まり、ト短調を経てハ短調にやっとたどり着くというしても凝った展開であり、これは後年のショパンの作品で再現部を登場させないことが彼の拘りであることを考えると、彼なりのソナタ形式への一石ということでその成長過程であることがわかる。第2、第3楽章もショパンらしい。マズルカを引用した部分(第2楽章)もあり、また、民族音楽を引用している5/4拍子(第3楽章)はスラヴ民謡をモチーフにしていて、ワルツ部分は後々にチャイコが引用している。この地味に感じる第2・第3楽章はショパン的には成功した部分である。問題は第4楽章で、これはどう聴いてもベートーヴェンの「皇帝」である。半階音で転調がよどみないために演奏には相当な技術が必要であるが、逆にそれだけと言ってしまえばおしまいで、既にベートーヴェンがピアノソナタを書いたときにはこんなレベルの発想すらなかったと思わされる。この第1・4楽章と真ん中の2楽章の対比が実にショパンらしいと思うのが、一方で高度な演奏技術を必要といるが単調で斬新でない、もっと言ってしまえば実りのない自己満足的な部分と、全くショパンの出自を表現したような中間楽章は、音楽技術だけではなく、この曲の作者の意図をくみ取らないと容易に表現ができない斬新さ、音楽家の主張を強調した内容が1曲の中の混在しているところで、17歳のショパンがとても良くわかる楽曲として仕上がっている。当時は演奏家ヴィルトゥオーソも流行していた時代であり、この頃はワルシャワにいたショパンは音楽家になるのか演奏家になるのかの狭間にいた時期である。音楽家として大成できるのかという不安が、彼の演奏技術を前面に出させていまったのだと思う。無論、後世の偉大な演奏家たちもそんなことは重々理解しているから、演奏で聴衆をひきつける第1・4楽章がテクニックの自己満足曲になってしまっては、中々この曲を演目には選ばないというのが本音であろう。
しかし、またまた結果論で考えてみれば、僅か3年後にあの名曲、コンチェルトの第1番を完成させている訳で、そう考えるとこの間の進歩は目覚ましいものがある(しかも正確には第2番が先に作られている。発表は9年後であるが・・・)。そしてそれを最後にショパンは祖国を捨てざるを得なくなった訳であるが、実はそれによりショパンが音楽家として大きく大成することになるのだが、それもこれねこの時代に音楽と真摯に向き合って沢山の実験をしてきたからであろうと思う。そんなショパンの大作曲家になるまでの努力の記録が、まさにこのピアノソナタハ短調だと言って良いのではないか。
こちらから試聴できます