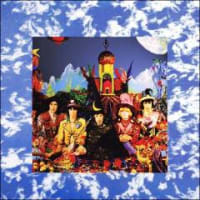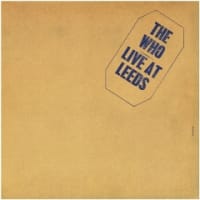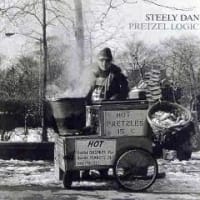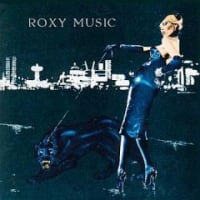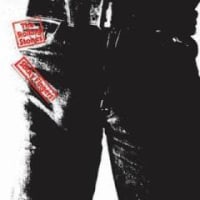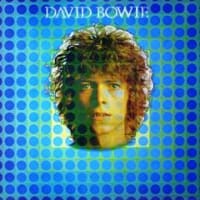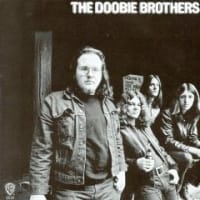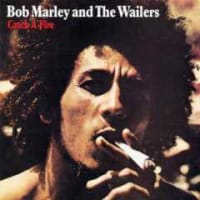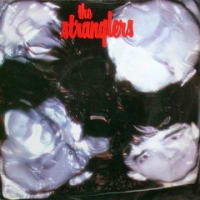今年2009年は、メンデルスゾーンの生誕200年である。実はそんなことを昨年から結構大きな声を出して言っていたが、クラシック関係者には殆ど相手にされなかった。それで蓋を開けたら、ハイドンの没後200年の方が大きく取り上げられて、なるほど、音楽関係者ってそっちなのかと・・・? だが、待てよ、今年がメンデルスゾーンの生誕200年ということは、この時期はロマン主義音楽家が次々に誕生している筈だからと。そう、序ながら触れておくと来年はショパンとシューマンの生誕200年、2011年はリスト、2013年はワーグナーとヴェルディの生誕200年である(渋いところではロシアのアレクサンドル・ダルゴムイシスキーも2013年誕生だ)。この団塊の世代が過ぎると、暫く大物は、余り出てこなくて、2018年のグノー、2019年のオッフェンバック、2022年のフランクから2024年ブルックナーとスメタナ、2025年ヨハン・シュトラウス辺りが生誕200年で次の団塊だろうか。いやいやロマン主義創立200年キャンペーンというのを暫く出来ると思うのだが、ダメかなぁ。
さて、メンデルスゾーンの音楽というのは、私の耳書聴き方が悪いのか、楽典に関する知識が不足しているのか、それとも根本的に才能もセンスもないのか分からないが、実にモーツァルトに似ていると思う。このブログでも何度か書いたかも知れないが、多分これから何度も書くと思う。特に、交響曲は似ているというか可也影響されていると思う。実はメンデルスゾーンに関してはそんなに詳しくないし、音楽も聴きこんでないので、時間があったらもっと聴きこみ、楽譜も見てみたいのだが、さきほど、交響曲といったが、モーツァルトの書いた交響曲に似ているわけではなく、例えば、第1番にしても交響曲というより、ヴァイオリン協奏曲あたりに似ている、というか完全に影響を受けているのではないかと思う。この第4番もそうだ、この交響曲には「イタリア」という副題がついていて、イタリア旅行がきっかけで書いたのだが、私の知っているイタリアの印象と全然違う。特に、第1楽章って、イタリアの何を書いたのだろうと思う。それで聴いているとこの第1主題のテンポの良さで連想できるのが、「オリエント急行」である。但し、幾ら彼がブルジョワの出でお金持ちであっても、オリエント急行の開通は1883年で、メンデルゾーンは既にこの世にいない。だが、もしかしたら、そんなイタリアの旅だったら楽しいだろうなという、やはり、当時の富裕層が考えた旅の方法だったのじゃないかと思う。(但し、オリエント急行派残念ながらイタリアは通らないのであるが)。それと、もうひとつこの第1楽章はモーツァルトの「フィガロの結婚」序曲に似ている。フィガロの結婚とは、もともとフランス劇作家ボーマルシェの戯曲で、イタリアのロレンツァ・デ・ポンダが台本を書いたかの有名な「セビリアの理髪師」3部作であり、第1部をイタリアの作曲家パイジェロが、第2部はご存知ロッシーニ、そして第3部をモーツァルトがオペラ化している。それまでドイツ語に拘っていたモーツァルトも、このフィガロはイタリア語で公演している。これはこじつけだが、メンデルスゾーンの見たイタリアの中にモーツァルトの音楽が強く影響されていたと思えるのである。
但し、彼の名誉のために申し上げると、第4楽章になって、ローマやナポリの舞曲であるサルタレロを引用している。この楽曲の標題「イタリア」に最も相応しいのはこの部分だと思う。
こちらから試聴できます