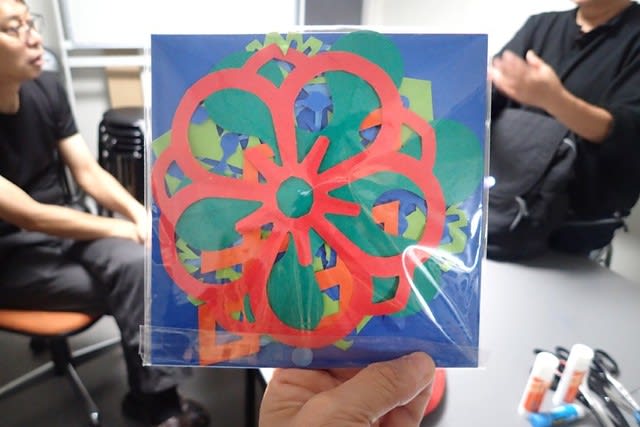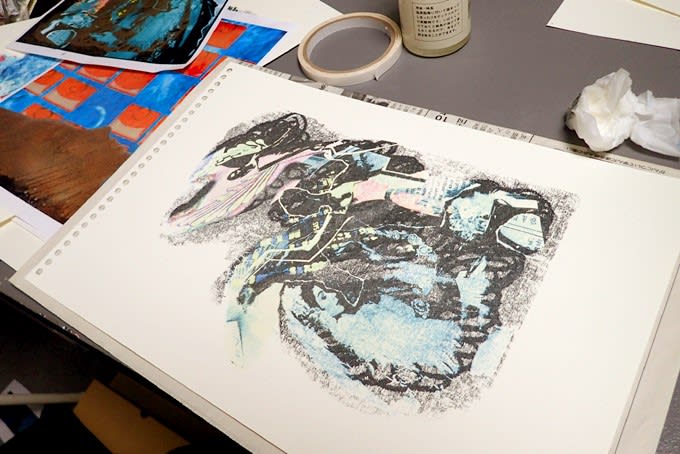身近にある日常品を用いて
あぶりだしに取り組みました。
各自
あぶりだしについて
予習し
あぶりたいものを持参。
柑橘系の果物
酢、塩、コカ・コーラ、
ヨーグルト・・・
リトマス試験紙で
酸度を測りながら
あぶってみました。
クエン酸、土、肥料は
水に溶かして実験・・・
予想通り
酸性の水溶液であれば
あぶりだしができることを確認。
その後は
創作活動に取り組みました。
酸性の水溶液での
あぶりだしの他・・・
食塩水での実験もおこないました。
あぶることで水分を飛ばすと・・・
結晶化した塩跡が浮かび上がります。
塩水で描く展開や
書への展開も見受けられました。
今回の実験をもとに
後日の更なる展開を期待して
この日の活動を終えました。
*
活動後の雑談タイムでは
作品制作に関わる
言葉使いが話題になりました。
「制作」と「製作」
「染織」と「染色」
発音は同じですが
漢字が違うと、意味が違うことや
「展覧会」と「展示会」
作った物を披露する意味では同じ。
では、何が違うのか・・・
などなど
部員の皆さんが直面した
体験談や認識の仕方について
話し合いました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

徳永写真美術研究所
大阪・鶴橋にて
写真・写真表現・シルクスクリーンetc.
表現の研究活動をおこなっています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・