もう終わってしまった、春の花の話題。
コブシに似た「ハクモクレン(白木蓮)」という木がある。一般に単に「モクレン」と呼ぶ人も多いが、正確な標準和名は「ハクモクレン」。
コブシと比べて木はやや小さく、花は大きく閉じ気味で、開花時期がやや遅いので、識別できるのだが、やっぱり少々まぎらわしい。コブシと違って中国原産で日本に自生せず、もっぱら庭に植えられるのだが、たまに街路樹で並木に植えられることがある。秋田市内では3か所知っていて、2か所をだいぶ前に紹介済み。
泉のハミングロードに続く道路と卸町の猿田川沿いの公園。
そしてもう1か所が、手形の市立秋田東中学校前。ソメイヨシノが見頃だった4月中旬撮影。
 正門~グラウンドの横にかけてハクモクレン並木
正門~グラウンドの横にかけてハクモクレン並木
狭い道路で片側だけに歩道があって、そこに10本弱植えられている。
若くもないと思われるが、小ぶりな木。泉のハクモクレンに似ていて、大きくならない品種なのだろう。卸町のはもっと大きいはず。
 逆光です
逆光です
 たわわに咲く
たわわに咲く
4月下旬になって、泉のハミングロード。【15日補足・ハミングロードは、地域の人たちが手入れしてくれる草木が、通行人を楽しませてくれる遊歩道。】
 枝垂れ桜が咲き乱れる一角
枝垂れ桜が咲き乱れる一角
【15日補足】ハミングロードは泉小学校敷地に沿ってL字に曲がり、その直進方向の狭い市道の歩道(学校が近いので設けてあると思われる)が、以前も取り上げたハクモクレン並木。
 その向こうがハクモクレン並木
その向こうがハクモクレン並木
今年もよく咲いていたものの、一部の木もしくは枝が枯れてしまったり、不格好になっていたものもあった。だからあえて撮影しなかった。
5月に入ると、ハクモクレンは散って葉が出てきたのだが…
 赤紫色の花が遅れて咲いた
赤紫色の花が遅れて咲いた
けっこうな本数がある中、2本だけ赤紫色の花を咲かせていた。これは知らなかった!
これはハクモクレンの色違いではなくて、近縁ながら別種。これこそ、標準和名が「モクレン」なのだが、ハクモクレンと明確に区別するために「シモクレン(紫木蓮)」と呼ぶこともある。
これも庭木にされ、ハクモクレンより開花が遅く、木も小さめ(シモクレンの大木って見たことない)の傾向。【15日追記】コブシではこんな色の花はないし、大きさや開花時期の差も大きいため、コブシとシモクレンを混同することはあまりない(若木とか葉は別ですが)。
意図的に2本だけこのような形で植えるとは考えづらい。秋大前の複数品種がある八重桜並木とか、雄株だけを植えたはずのイチョウ並木で銀杏が実る木があるようなもので、ハクモクレンにシモクレンが2本だけ混ざってしまったのだろうか。【15日追記】もしくは、当初のハクモクレンが枯れたので、代わりに手配した苗が、シモクレンだったとか。
 この木もやや不格好で、中ほどの枝が枯れている
この木もやや不格好で、中ほどの枝が枯れている
 奥がハミングロードの枝垂れ桜エリア。ほぼ葉桜
奥がハミングロードの枝垂れ桜エリア。ほぼ葉桜
コブシに似た「ハクモクレン(白木蓮)」という木がある。一般に単に「モクレン」と呼ぶ人も多いが、正確な標準和名は「ハクモクレン」。
コブシと比べて木はやや小さく、花は大きく閉じ気味で、開花時期がやや遅いので、識別できるのだが、やっぱり少々まぎらわしい。コブシと違って中国原産で日本に自生せず、もっぱら庭に植えられるのだが、たまに街路樹で並木に植えられることがある。秋田市内では3か所知っていて、2か所をだいぶ前に紹介済み。
泉のハミングロードに続く道路と卸町の猿田川沿いの公園。
そしてもう1か所が、手形の市立秋田東中学校前。ソメイヨシノが見頃だった4月中旬撮影。
 正門~グラウンドの横にかけてハクモクレン並木
正門~グラウンドの横にかけてハクモクレン並木狭い道路で片側だけに歩道があって、そこに10本弱植えられている。
若くもないと思われるが、小ぶりな木。泉のハクモクレンに似ていて、大きくならない品種なのだろう。卸町のはもっと大きいはず。
 逆光です
逆光です たわわに咲く
たわわに咲く4月下旬になって、泉のハミングロード。【15日補足・ハミングロードは、地域の人たちが手入れしてくれる草木が、通行人を楽しませてくれる遊歩道。】
 枝垂れ桜が咲き乱れる一角
枝垂れ桜が咲き乱れる一角【15日補足】ハミングロードは泉小学校敷地に沿ってL字に曲がり、その直進方向の狭い市道の歩道(学校が近いので設けてあると思われる)が、以前も取り上げたハクモクレン並木。
 その向こうがハクモクレン並木
その向こうがハクモクレン並木今年もよく咲いていたものの、一部の木もしくは枝が枯れてしまったり、不格好になっていたものもあった。だからあえて撮影しなかった。
5月に入ると、ハクモクレンは散って葉が出てきたのだが…
 赤紫色の花が遅れて咲いた
赤紫色の花が遅れて咲いたけっこうな本数がある中、2本だけ赤紫色の花を咲かせていた。これは知らなかった!
これはハクモクレンの色違いではなくて、近縁ながら別種。これこそ、標準和名が「モクレン」なのだが、ハクモクレンと明確に区別するために「シモクレン(紫木蓮)」と呼ぶこともある。
これも庭木にされ、ハクモクレンより開花が遅く、木も小さめ(シモクレンの大木って見たことない)の傾向。【15日追記】コブシではこんな色の花はないし、大きさや開花時期の差も大きいため、コブシとシモクレンを混同することはあまりない(若木とか葉は別ですが)。
意図的に2本だけこのような形で植えるとは考えづらい。秋大前の複数品種がある八重桜並木とか、雄株だけを植えたはずのイチョウ並木で銀杏が実る木があるようなもので、ハクモクレンにシモクレンが2本だけ混ざってしまったのだろうか。【15日追記】もしくは、当初のハクモクレンが枯れたので、代わりに手配した苗が、シモクレンだったとか。
 この木もやや不格好で、中ほどの枝が枯れている
この木もやや不格好で、中ほどの枝が枯れている 奥がハミングロードの枝垂れ桜エリア。ほぼ葉桜
奥がハミングロードの枝垂れ桜エリア。ほぼ葉桜










 フェンス越し
フェンス越し

 白い桜の数本先、照明柱付近にまだ咲かない桜
白い桜の数本先、照明柱付近にまだ咲かない桜 路面に花びらが
路面に花びらが つぼみが開き始めていた
つぼみが開き始めていた 葉桜の中に満開の桜
葉桜の中に満開の桜 遅咲き桜の花
遅咲き桜の花 天気が悪いですが
天気が悪いですが また違う桜が!
また違う桜が! 白い八重桜
白い八重桜 完全に枯れてしまった桜も2本
完全に枯れてしまった桜も2本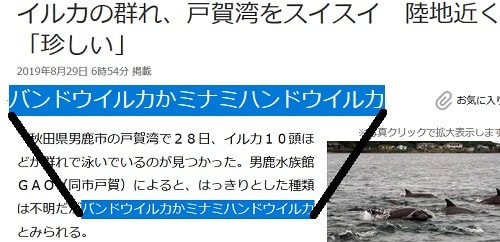 魁のサイトにも掲載
魁のサイトにも掲載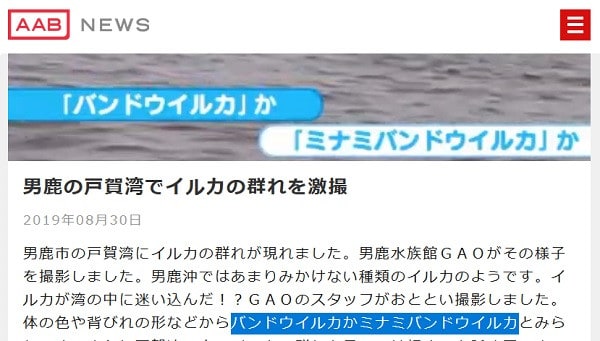 AABサイトより抜粋
AABサイトより抜粋 NHK秋田ニュースサイトより抜粋
NHK秋田ニュースサイトより抜粋 シロツメクサとムラサキツメクサ
シロツメクサとムラサキツメクサ いろいろ生えている とある空き地
いろいろ生えている とある空き地 近くで観察。後ろの方にも咲いている
近くで観察。後ろの方にも咲いている 花はきれいでかわいらしい
花はきれいでかわいらしい 別の空き地でも。両脇はヨモギ(強風にあおられています)
別の空き地でも。両脇はヨモギ(強風にあおられています) 花も実もある
花も実もある この鳥
この鳥 ちょっと違う?!
ちょっと違う?! 反対側も。この面のほうが白い部分が多い?
反対側も。この面のほうが白い部分が多い? たぶん
たぶん 勝平側から。右が上流
勝平側から。右が上流 川尻側の岸から
川尻側の岸から 橋の中央付近から
橋の中央付近から 白い鳥がたくさん
白い鳥がたくさん 中州では黄色い菜の花系の花が咲く。右奥の流木には鵜(カワウかウミウかは断定不能)
中州では黄色い菜の花系の花が咲く。右奥の流木には鵜(カワウかウミウかは断定不能)
 地べたに直接、ただいるだけ
地べたに直接、ただいるだけ 離れて休むウミネコ2羽
離れて休むウミネコ2羽 浮島で優雅なひととき?
浮島で優雅なひととき? 駐車場から中州と新川橋
駐車場から中州と新川橋 8月上旬
8月上旬 10月上旬
10月上旬
 11月初め
11月初め

 地面に落ちた果実もいくつか
地面に落ちた果実もいくつか 秋の西日を受ける
秋の西日を受ける 10月上旬
10月上旬 2008年撮影。後ろ姿の花子(左)とだいすけ
2008年撮影。後ろ姿の花子(左)とだいすけ 2008年撮影の花子
2008年撮影の花子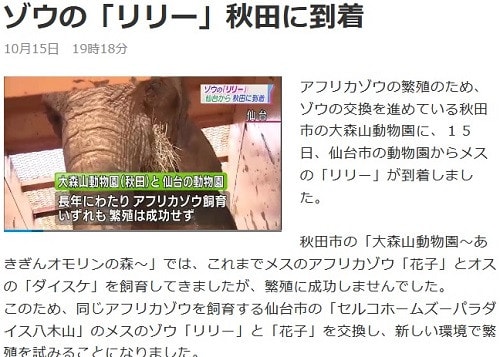
 NHK秋田とNHK仙台
NHK秋田とNHK仙台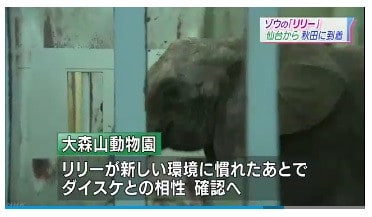 NHK秋田
NHK秋田 16日付秋田市地域面
16日付秋田市地域面 デカイ! ※比較は一般的な長さの蛍光ペン。左上には小さいつぼみがある
デカイ! ※比較は一般的な長さの蛍光ペン。左上には小さいつぼみがある 咲いた!!
咲いた!! ペンより大きい
ペンより大きい つぼみと花
つぼみと花 クジャクサボテンの花のアップ
クジャクサボテンの花のアップ 下がイースターカクタス
下がイースターカクタス (再掲)名古屋市
(再掲)名古屋市 まだ木々も芽吹かず、寒い日も多い4月初めの光景
まだ木々も芽吹かず、寒い日も多い4月初めの光景
 水中を歩いているけど、またすぐ立ち止まる
水中を歩いているけど、またすぐ立ち止まる ババヘラとダイサギ。どちらも獲物を待つ?!
ババヘラとダイサギ。どちらも獲物を待つ?! 落葉が進む
落葉が進む イガイガ
イガイガ 12月初め
12月初め 上のほうに何かある
上のほうに何かある 果実が付いていた
果実が付いていた 6月。今年も青々と茂る
6月。今年も青々と茂る 雪の中、葉を付けている!
雪の中、葉を付けている! 落葉
落葉 まだ残ってる
まだ残ってる すっかり落葉
すっかり落葉 線路の向かい側から
線路の向かい側から ナツズイセンの花
ナツズイセンの花 はじかみ(芽生姜)みたいに見えるけど、たぶん有毒
はじかみ(芽生姜)みたいに見えるけど、たぶん有毒
 千秋トンネル・手形側。左上に咲いている
千秋トンネル・手形側。左上に咲いている


 横向きだった花と違い、果実は上向き
横向きだった花と違い、果実は上向き 西側の本丸から二の丸裏にかけての道
西側の本丸から二の丸裏にかけての道 葉はない
葉はない
 分かりにくいけど、全面に点々と
分かりにくいけど、全面に点々と 日陰のキツネノカミソリ
日陰のキツネノカミソリ 手前右
手前右 ずらり
ずらり 立つ者、座る者、目をつぶる者、口を開ける者さまざま
立つ者、座る者、目をつぶる者、口を開ける者さまざま カメラ目線。ちょっと警戒させてしまった
カメラ目線。ちょっと警戒させてしまった 観覧車もある。現地にしては寒い日のせいか、屋内は人が多いのに、外はほとんどいない
観覧車もある。現地にしては寒い日のせいか、屋内は人が多いのに、外はほとんどいない 港らしい光景
港らしい光景 海鳥がずらりと乗っかる
海鳥がずらりと乗っかる びっしりと同じ方向を向いて整列
びっしりと同じ方向を向いて整列 そこ(右端)に座っているのがウミネコ
そこ(右端)に座っているのがウミネコ 新メンバー参入
新メンバー参入 ユリカモメがセンターをゲット!
ユリカモメがセンターをゲット! 思い思いに過ごすユリカモメ
思い思いに過ごすユリカモメ


