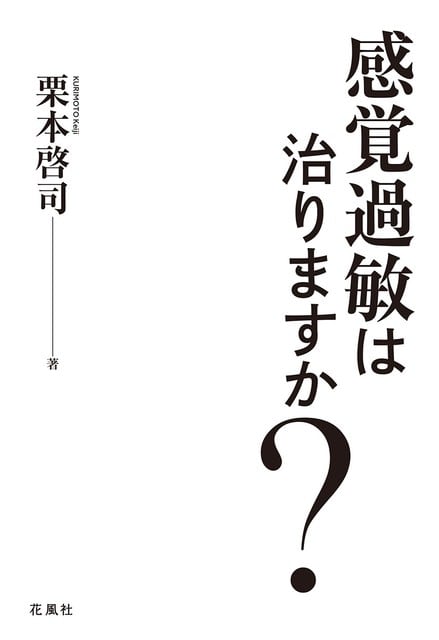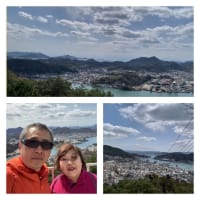さて、5月23日と31日に行われる「どこでも治そう on zoom」produced by チーム神奈川
のテーマは「新しい日常を構築しよう」です。
私たちは非常時を経験しました。
それは全世界どこにいても逃れられないものでした。
そしてわかったこと。
それは花風社クラスタがやってきた「一次障害を治す」が正しい取り組みだったということです。
ご本人のために、ご家庭のために、そして社会のために。
なるべく一次障害を治す。
なるべく支援を減らす。
そうやって取り組んできた読者のご家庭は、こういう時でも乱れませんでした。
むしろ密を減らしたい事業所の一助となるべく、ご家庭での時間を増やした(増やせた)ご家庭も多かった。
そして親子楽しく暮らし、この間にもどんどん発達していかれた。
お子さんだけではありません。
赤本こと『自閉っ子、こういう風にできてます!』のときにはあれほど過敏だった藤家さん
しょっちゅう発熱して身体も弱かった藤家さんがエッセンシャルワーカーとしてきつい現場で仕事をこなし社会貢献している。
歩くこと、ものをつかむことも覚束なかったこよりさんのご次男も同様。
他人への思いやりも育ち、様々な家庭の事情で職場に来られなくなった同僚の分も仕事をこなしている。
これもすべて、土台から身体を育て、
なるべく一次障害を治し
体感と情緒が安定する生活を目指してきたご本人とご家庭の努力の賜物です。
いわゆる重い方も同様。
福祉作業所が閉まってもおうちで穏やかに過ごしている人たち。
有名なお医者さんでも患者さんの多くが乱れているそうですが
一向に乱れが見られない花風社クラスタのお子たちです。
わかったこと。
ていねいにていねいにその子の身体を育てていくことは、非常時にも周囲と協調して生き抜く強い人に育てること。
自立性が一つでも高まれば、それだけ社会貢献だということ。
食事が、排泄が、一つでも自立していればそれだけ誰かの負担を減らせること。
それがわかったコロナ禍でもありました。
一方で、ギョーカイ発の支援はあくまで平時の支援に過ぎなかったことがわかりました。
そして不要な資格商売が鳴りを潜めるのも見ましたね。
いらない資格はいらなかった。
まさに「支援者は、もういない」世界がやってきます。
「ありのままでいいんですよ」と偏食をほったらかしにしておいたご家庭では、買い物もままならない中で苦労が続いたでしょう。
恐怖麻痺に駆られた家族は先行きの見えなさに親子でメンタルを崩したでしょう。
怖がりの親に育てられたばかりに、太陽や外の風に当たることさえできていないお子さんもいるかもしれません。
「ステイホーム感染」も増えてきたということ。お日様にもあたらなかったらそりゃそうでしょうね。
学びの機会を失った子どもたちに積極的な手当をしたご家庭もあれば
将来を嘆き、自粛警察活動に日々を費やしていたご家庭もあるかもしれません。
当然差がつきます。
(それにしてもいい加減休暇も続きすぎ。
そろそろ子どもたちを学校に戻してあげてほしいですね。)
呼吸器やアレルギーなど、基礎的な疾患を治そうという花風社クラスタの試みを「トンデモ」と馬鹿にしていた人たちは基礎疾患をほうっておいたがゆえにより不安な日々を過ごしていたことでしょう。
「お母さんは頑張らなくていいんですよ」と甘い言葉をささやいていた支援者たちも最後には自分の身を守りたい。マスクもつけられない子をもう送ってこないでと訴える。それは生き物としての本能。最後の最後には支援者も我が身を守るのがよくわかったと思います。
視覚支援でスケジュールを提示しようにも、今は大人だって、健常者だってこの先どうなるかわかりません。
今後立ち直りに莫大なお金がかかり、発達障害にお金が回らなくなったとき、金目当ての支援者たちはどんどん去っていくでしょう。
障害特性にあぐらをかいていた「使えない労働者」は真っ先に首を切られるかもしれませんね。
私たちはpost and/or COVID-19の発達支援がどうなるかに注目しています。
一方でとっくに支援を当てにしないで済む方に舵を切っているのが私たちです。だからこそ強かった。
こういう非常時を経験したからこそ、これから作る「新しい日常」はより一層「一次障害を治す」に向かっていく。疫病がこれだけ生活を変えることがわかった。社会が障害特性を配慮しようと、ウイルスは配慮しない。そして今後お子さんたちが生きていく長い時間の中では、こういうことがまたあることかもしれないからです。
こういう状況の中で、新しい日常に向けて、花風社では「どこでも治そう on zoom」produced by チーム神奈川
を行います。
5月23日には浅見のミニ講演。
「治るかどうかは生きるか死ぬか コロナ禍の中で見えたこと」
について話します。
新しい日常を作る。
経済を立て直す。
すべて主語は「私たち」です。行政ではありません。
そういうことを話します。
浅見ミニ講演に続き、南雲明彦さんに
「支援を整理する時代へ~生き抜くための作戦会議~
というテーマで話していただきます。
下記が南雲さん講演の今のレジュメです。
=====
コロナ時代をどう生きる?
(1) 自己紹介
(2) 新型コロナウイルスの影響で「普通」が変わる
(3) 見通しが立たない時代をどう生きる?
支援者はもういない
(4) 一億総ステイホームの幕開け
(5) 「生きづらい」と叫んでも、誰も来ない
(6) 「ありのままでいいんだよ」では、生きていけない
充実したステイホーム
(7) 自己肯定感より、安定した衣食住
(8) YouTubeは支援の宝庫
(9) 子どもたちに必要なのは自己肯定感ではなく「役割」
(10) 家族(親子)の力が試されている
(11) 子どもは支援されるより、支援したいと思っている
支援の整理整頓
(12) コロナで不要のものは整理される
(13) 必要な支援は自分たちで生み出す
(14) 家族は生き抜く土台
=====
「生きづらいと叫んでも、誰も来ない」
「ありのままでいいんだよ、では生きていけない」
「自己肯定感より、安定した衣食住」
「子供たちに必要なのは、自己肯定感ではなく役割」
これが私たちの提言する「新しい日常」です。
そして本講演は5月31日。
栗本さんの講座です。
仮タイトルは「感覚過敏、治るが勝ち!」
今回、どれだけ感覚過敏を治しておいてよかったか、よくわかったと思います。
感覚過敏がないことは、生活をラクにし、自分を守り、家族を含めた他人を守ります。
そして花風社には『感覚過敏は治りますか?』という本があります。
各過敏(聴覚過敏、視覚過敏、触覚過敏等)別に具体的な治し方を書いてあります。
あの本の活用の仕方を徹底的にやります。
花風社の取り組みは正しかった。
だからこそ花風社は、今後も発信し続けます。
そのための土台もあります。
5月はチーム神奈川
6月は長崎の「どこでも治そう発達障害」企画。
皆様との対話の中で私たちは
「新しい日常」への模索を続けます。
週末のうちにMLを流します。
そのあとこのブログに要項を貼ります。
皆様のご参加をお待ちしております。
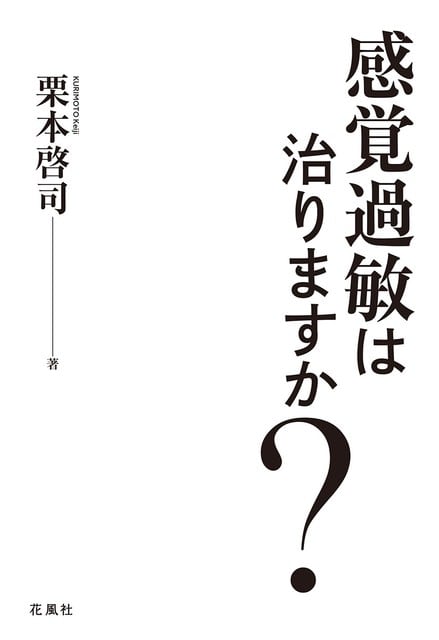
のテーマは「新しい日常を構築しよう」です。
私たちは非常時を経験しました。
それは全世界どこにいても逃れられないものでした。
そしてわかったこと。
それは花風社クラスタがやってきた「一次障害を治す」が正しい取り組みだったということです。
ご本人のために、ご家庭のために、そして社会のために。
なるべく一次障害を治す。
なるべく支援を減らす。
そうやって取り組んできた読者のご家庭は、こういう時でも乱れませんでした。
むしろ密を減らしたい事業所の一助となるべく、ご家庭での時間を増やした(増やせた)ご家庭も多かった。
そして親子楽しく暮らし、この間にもどんどん発達していかれた。
お子さんだけではありません。
赤本こと『自閉っ子、こういう風にできてます!』のときにはあれほど過敏だった藤家さん
しょっちゅう発熱して身体も弱かった藤家さんがエッセンシャルワーカーとしてきつい現場で仕事をこなし社会貢献している。
歩くこと、ものをつかむことも覚束なかったこよりさんのご次男も同様。
他人への思いやりも育ち、様々な家庭の事情で職場に来られなくなった同僚の分も仕事をこなしている。
これもすべて、土台から身体を育て、
なるべく一次障害を治し
体感と情緒が安定する生活を目指してきたご本人とご家庭の努力の賜物です。
いわゆる重い方も同様。
福祉作業所が閉まってもおうちで穏やかに過ごしている人たち。
有名なお医者さんでも患者さんの多くが乱れているそうですが
一向に乱れが見られない花風社クラスタのお子たちです。
わかったこと。
ていねいにていねいにその子の身体を育てていくことは、非常時にも周囲と協調して生き抜く強い人に育てること。
自立性が一つでも高まれば、それだけ社会貢献だということ。
食事が、排泄が、一つでも自立していればそれだけ誰かの負担を減らせること。
それがわかったコロナ禍でもありました。
一方で、ギョーカイ発の支援はあくまで平時の支援に過ぎなかったことがわかりました。
そして不要な資格商売が鳴りを潜めるのも見ましたね。
いらない資格はいらなかった。
まさに「支援者は、もういない」世界がやってきます。
「ありのままでいいんですよ」と偏食をほったらかしにしておいたご家庭では、買い物もままならない中で苦労が続いたでしょう。
恐怖麻痺に駆られた家族は先行きの見えなさに親子でメンタルを崩したでしょう。
怖がりの親に育てられたばかりに、太陽や外の風に当たることさえできていないお子さんもいるかもしれません。
「ステイホーム感染」も増えてきたということ。お日様にもあたらなかったらそりゃそうでしょうね。
学びの機会を失った子どもたちに積極的な手当をしたご家庭もあれば
将来を嘆き、自粛警察活動に日々を費やしていたご家庭もあるかもしれません。
当然差がつきます。
(それにしてもいい加減休暇も続きすぎ。
そろそろ子どもたちを学校に戻してあげてほしいですね。)
呼吸器やアレルギーなど、基礎的な疾患を治そうという花風社クラスタの試みを「トンデモ」と馬鹿にしていた人たちは基礎疾患をほうっておいたがゆえにより不安な日々を過ごしていたことでしょう。
「お母さんは頑張らなくていいんですよ」と甘い言葉をささやいていた支援者たちも最後には自分の身を守りたい。マスクもつけられない子をもう送ってこないでと訴える。それは生き物としての本能。最後の最後には支援者も我が身を守るのがよくわかったと思います。
視覚支援でスケジュールを提示しようにも、今は大人だって、健常者だってこの先どうなるかわかりません。
今後立ち直りに莫大なお金がかかり、発達障害にお金が回らなくなったとき、金目当ての支援者たちはどんどん去っていくでしょう。
障害特性にあぐらをかいていた「使えない労働者」は真っ先に首を切られるかもしれませんね。
私たちはpost and/or COVID-19の発達支援がどうなるかに注目しています。
一方でとっくに支援を当てにしないで済む方に舵を切っているのが私たちです。だからこそ強かった。
こういう非常時を経験したからこそ、これから作る「新しい日常」はより一層「一次障害を治す」に向かっていく。疫病がこれだけ生活を変えることがわかった。社会が障害特性を配慮しようと、ウイルスは配慮しない。そして今後お子さんたちが生きていく長い時間の中では、こういうことがまたあることかもしれないからです。
こういう状況の中で、新しい日常に向けて、花風社では「どこでも治そう on zoom」produced by チーム神奈川
を行います。
5月23日には浅見のミニ講演。
「治るかどうかは生きるか死ぬか コロナ禍の中で見えたこと」
について話します。
新しい日常を作る。
経済を立て直す。
すべて主語は「私たち」です。行政ではありません。
そういうことを話します。
浅見ミニ講演に続き、南雲明彦さんに
「支援を整理する時代へ~生き抜くための作戦会議~
というテーマで話していただきます。
下記が南雲さん講演の今のレジュメです。
=====
コロナ時代をどう生きる?
(1) 自己紹介
(2) 新型コロナウイルスの影響で「普通」が変わる
(3) 見通しが立たない時代をどう生きる?
支援者はもういない
(4) 一億総ステイホームの幕開け
(5) 「生きづらい」と叫んでも、誰も来ない
(6) 「ありのままでいいんだよ」では、生きていけない
充実したステイホーム
(7) 自己肯定感より、安定した衣食住
(8) YouTubeは支援の宝庫
(9) 子どもたちに必要なのは自己肯定感ではなく「役割」
(10) 家族(親子)の力が試されている
(11) 子どもは支援されるより、支援したいと思っている
支援の整理整頓
(12) コロナで不要のものは整理される
(13) 必要な支援は自分たちで生み出す
(14) 家族は生き抜く土台
=====
「生きづらいと叫んでも、誰も来ない」
「ありのままでいいんだよ、では生きていけない」
「自己肯定感より、安定した衣食住」
「子供たちに必要なのは、自己肯定感ではなく役割」
これが私たちの提言する「新しい日常」です。
そして本講演は5月31日。
栗本さんの講座です。
仮タイトルは「感覚過敏、治るが勝ち!」
今回、どれだけ感覚過敏を治しておいてよかったか、よくわかったと思います。
感覚過敏がないことは、生活をラクにし、自分を守り、家族を含めた他人を守ります。
そして花風社には『感覚過敏は治りますか?』という本があります。
各過敏(聴覚過敏、視覚過敏、触覚過敏等)別に具体的な治し方を書いてあります。
あの本の活用の仕方を徹底的にやります。
花風社の取り組みは正しかった。
だからこそ花風社は、今後も発信し続けます。
そのための土台もあります。
5月はチーム神奈川
6月は長崎の「どこでも治そう発達障害」企画。
皆様との対話の中で私たちは
「新しい日常」への模索を続けます。
週末のうちにMLを流します。
そのあとこのブログに要項を貼ります。
皆様のご参加をお待ちしております。