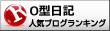反対運動も結構だが離島の経済が逼迫しているなら受け入れも仕方ないのでは?
瀬戸内に浮かぶ豊島(てしま)も産業廃棄物の受け入れでゴミの島になったけど
若者が出て行ってしまう島の現状を考えるとそういう選択もあると思うのです。
「国境の島、立ち行かない」…最終処分場調査受け入れめぐり島は二分
配信
 </picture>
</picture>高レベル放射性廃棄物の最終処分場の文献調査受け入れを促進する請願を賛成多数で採択した対馬市議会本会議=12日午後
原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場選定に向け、文献調査受け入れに関する請願について採択した長崎県対馬市議会。実は約16年前、議会は誘致反対を決議したが、今回は一転して調査受け入れの意思表示を行った。その背景には、人口減少と少子高齢化が深刻化している「国境の島」の現実がある。一方で主要産業である漁業への風評被害を危惧する声も根強く、会期中に表明される市長の判断に注目が集まる。 【イラストで見る】核ごみ最終処分場選定の流れ 「何かしないと、このままでは国境の離島として立ち行かなくなる」 調査受け入れ促進の請願を提出した地元の建設業界4団体のうち、同県建設業協会対馬支部の関係者はそう危機感をにじませた。 市の人口は年々減り、今年8月末には約2万8千人となり、平成27年から約14%も減少した。若者の転出が主な要因で、生産年齢人口(15~64歳)は40年間で半減、65歳以上の高齢化率は30%を超えている。 市は28年度から10年間の「第2次市総合計画」を策定し、観光客誘致などを進めてきた。しかし新型コロナウイルスの影響、ロシアによるウクライナ侵略などによる燃料費高騰が地域経済を追い込んでいる。建設業界は「人手不足で市の公共事業も受注できない」ほどの状態に陥り、衣料品などの店舗もインターネット通販の普及で需要が流出しているという。 市議会は19年に原発の最終処分場の誘致反対決議を行ったが、今回は地域の将来への危機感が差し迫っていたことが、請願採択につながった。 建設業界の請願は最終処分場について「世界最先端の土木建設プロジェクト」と評価。「わが国の技術で対応可能な事業であり、業界としても協力すべきだ」と明確に受け入れを支持している。 業界関係者は昨年以降、HLWの地層処分の主体となる原子力発電環境整備機構(NUMO)の説明会や、青森県六ケ所村の使用済み核燃料再処理工場など原発関連施設の視察に参加。その中で「山がちな対馬でトンネル掘削の実績は豊富で、道路や港湾などのインフラ整備にも貢献できる。地域の活性化にもつながる」との手応えを得たという。 また、対馬周辺は北朝鮮がミサイル発射を繰り返し、軍事的な緊張感が高まっている。「半島有事」の場合には、邦人輸送などで対馬が最前線に立たされる。ある市議は「最終処分場の調査に対馬が名乗りを上げることで、エネルギーを含めた安全保障の重要性を国民に認識してほしい」と期待する。 ただ、この市議も「肌感覚では半分の市民が最終処分場受け入れに反対」と明かす。12日の市議会では否決されたが、受け入れ反対の請願も出されていた。請願を出した美津島町西海漁業協同組合の幹部は「風評被害で養殖マグロの値段が下がったら大変。最終処分場が安全というなら、いっそ国会議事堂の下につくればいい」と語気を強める。一方、対馬真珠養殖漁業協同組合の執行部は「経済活性化につながるなら」と受け入れの請願を市議会に提出し、今年6月の総会にはかったが、反対多数で否決され、取り下げた。 比田勝尚喜(ひたかつなおき)市長は令和2年3月の選挙で「最終処分場の誘致はしない」と明言して再選され、現在は態度表明を避けている。市民を二分することになった最終処分場問題は、古代から名高い「防人(さきもり)の島」を揺るがしている。(牛島要平)