黄金の扉を開ける賢者の海外投資術 (単行本)
橘 玲 (著)
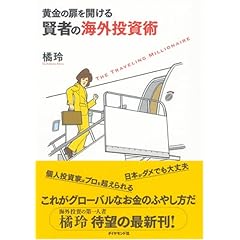
場所:江東区図書館
現時点での橘本の集大成。
これまでに書かれてきたもののエッセンスがつまってます。
これ一冊でいいかも。
ってのは、これまでの下地があるからですが。
一番簡単なのはインデックス買っとけ。
自分という人的資本を考えたら、レバレッジかけて!
経済合理的には、海外に証券口座持って手数料を極限まで下げるべきだし、FXだって使うべき。
頭では理解できても、なかなか…
ヘッジファンドの話はおもしろかった。
行動経済学で合理的な経済人は否定されたかと思いきや、合理的でない経済人の集合体である市場は意外に合理的だったり。
実におもしろい。
てことで、とりあえずインデックス買っとけ。
最後の2章は、お得意の税からいかに逃れるかのお話。
これも頭ではわかるけど、って感じ。
橘 玲 (著)
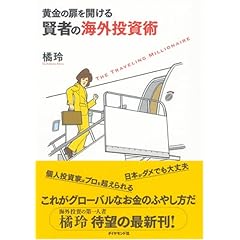
場所:江東区図書館
現時点での橘本の集大成。
これまでに書かれてきたもののエッセンスがつまってます。
これ一冊でいいかも。
ってのは、これまでの下地があるからですが。
一番簡単なのはインデックス買っとけ。
自分という人的資本を考えたら、レバレッジかけて!
経済合理的には、海外に証券口座持って手数料を極限まで下げるべきだし、FXだって使うべき。
頭では理解できても、なかなか…
ヘッジファンドの話はおもしろかった。
行動経済学で合理的な経済人は否定されたかと思いきや、合理的でない経済人の集合体である市場は意外に合理的だったり。
実におもしろい。
てことで、とりあえずインデックス買っとけ。
最後の2章は、お得意の税からいかに逃れるかのお話。
これも頭ではわかるけど、って感じ。
コーチングの神様が教える「できる人」の法則 (単行本)
マーシャル・ゴールドスミス (著), マーク・ライター (著), 斎藤 聖美

場所:江東区図書館
もしかしたら今までに出会った中で一番の本。
確かに!と思うことが数ページおきにでてきました。
もちろん知らなかったこともいっぱい書いてますが、こうしたほうがよいとわかっているけどできていないこと、やったほうがいいと理解しているけどやってなかったこと、こういうのがいっぱい書いてありました。
自分がどうもいまひとついけてない、その理由がわかったような気がします。
いけてるやつになるために、一つ一つクリアしていきたいと思います。
まずは、これ。
20の悪い癖。
これをやめることからとりかかりたいとおもいます。
一つずつ消していきます。
1.極度の巻けず嫌い
2.何かひとこと価値をつけ加えようとする
3.善し悪しの判断をくだす
4.人を傷つける破壊的コメントをする
5.「いや」「しかし」「でも」で文章を始める
6.自分がいかに賢いかを話す
7.腹を立てているときに話す
8.否定、もしくは「うまくいくわけないよ。その理由はね」と言う
9.情報を教えない
10.きちんと他人を認めない
11.他人の手柄を横どりする
12.言い訳をする
13.過去にしがみつく
14.えこひいきする
15.すまなかったという気持ちを表わさない
16.人の話をきかない
17.感謝の気持ちを表わさない
18.八つ当たりする
19.責任回避する
20.「私はこうなんだ」と言いすぎる
この後に、もっとよくなるにはどうするか、というのがあるんですが、これは上の20をクリアしてからにします。
ゆっくりでも確実にいけてるやつになろうと決意した今日この頃です。
マーシャル・ゴールドスミス (著), マーク・ライター (著), 斎藤 聖美

場所:江東区図書館
もしかしたら今までに出会った中で一番の本。
確かに!と思うことが数ページおきにでてきました。
もちろん知らなかったこともいっぱい書いてますが、こうしたほうがよいとわかっているけどできていないこと、やったほうがいいと理解しているけどやってなかったこと、こういうのがいっぱい書いてありました。
自分がどうもいまひとついけてない、その理由がわかったような気がします。
いけてるやつになるために、一つ一つクリアしていきたいと思います。
まずは、これ。
20の悪い癖。
これをやめることからとりかかりたいとおもいます。
一つずつ消していきます。
1.極度の巻けず嫌い
2.何かひとこと価値をつけ加えようとする
3.善し悪しの判断をくだす
4.人を傷つける破壊的コメントをする
5.「いや」「しかし」「でも」で文章を始める
6.自分がいかに賢いかを話す
7.腹を立てているときに話す
8.否定、もしくは「うまくいくわけないよ。その理由はね」と言う
9.情報を教えない
10.きちんと他人を認めない
11.他人の手柄を横どりする
12.言い訳をする
13.過去にしがみつく
14.えこひいきする
15.すまなかったという気持ちを表わさない
16.人の話をきかない
17.感謝の気持ちを表わさない
18.八つ当たりする
19.責任回避する
20.「私はこうなんだ」と言いすぎる
この後に、もっとよくなるにはどうするか、というのがあるんですが、これは上の20をクリアしてからにします。
ゆっくりでも確実にいけてるやつになろうと決意した今日この頃です。
マネーと常識 投資信託で勝ち残る道 (単行本)
ジョン・C・ボーグル (著), 林 康史 (翻訳), 石川 由美子 (翻訳)
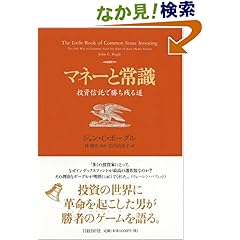
場所:江東区図書館
バンガードの創業者ボーグルの本。
インデックス万歳。
データを並べてこれでもかこれでもかとインデックス投資の優位性を説明してくれています。
インデックスに勝つアクティブを見つけることは無理、インデックス買っておけばいいんだからコンサルタントとかアドバイザもいらない、とにかく低コストのインデックス買っとけ。
セクタなんかに色気をだしてはだめ、市場全部を買うこと。
理論に裏打ちされた当たり前のこと。
だけど、退屈。
たまによそ見したくなるときも。
そんな時に手にとって軌道修正を。
ジョン・C・ボーグル (著), 林 康史 (翻訳), 石川 由美子 (翻訳)
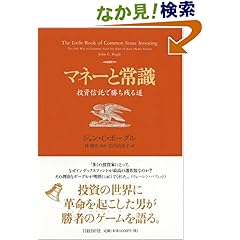
場所:江東区図書館
バンガードの創業者ボーグルの本。
インデックス万歳。
データを並べてこれでもかこれでもかとインデックス投資の優位性を説明してくれています。
インデックスに勝つアクティブを見つけることは無理、インデックス買っておけばいいんだからコンサルタントとかアドバイザもいらない、とにかく低コストのインデックス買っとけ。
セクタなんかに色気をだしてはだめ、市場全部を買うこと。
理論に裏打ちされた当たり前のこと。
だけど、退屈。
たまによそ見したくなるときも。
そんな時に手にとって軌道修正を。
新しい株式投資論―「合理的へそ曲がり」のすすめ (PHP新書 488) (新書)
山崎 元 (著)

場所:江東区図書館
市場は効率的ではない、でも簡単に儲けられるものでもない。
インデックス投資でもいいけど、せっかくだから知的なゲームとして株式投資を楽しみましょう、という本。
独自の優位な情報があるからといって儲かるわけではない。
なぜなら、その情報が他の投資家に広まらない限り、他の投資家はその株を買ってくれないから。
長期でなんて考えていると、別の材料が出て、下手したら損してしまうかも。
難しい。
アノマリーも大いに利用すべきだけど、いつでも通用するものでもない。
もしかしたらそのアノマリーの利用者は自分よりも前にたくさんいて、畑は荒れ果てた後かもしれない。
自分は前を走っているか?ついてくるやつはいるか?前を走りすぎていないか?もしかしたら前にいっぱい走っていないか?
そういうことをちゃんと考えながら投資をしないといけません。
ケインズは美人投票といったけれども、その美人に最初に投票していたらいいけど、あとから投票しても全然もうかりません。
優良株だからといって、すでに高値ならそこに儲けの源泉はないのです。
それよりも性格の良い不美人を探しましょう。
必要以上に低値に放置されているかも。
経営者がちょっとまともなことをするだけで、みんなの見る目がちょっと変わるだけで、大いに価値をあげるかもしれません。
そういう視点で銘柄をさがしてみよう。
読み返すたびに発見がありそうです。
買って手元に置こうと思いました。
山崎 元 (著)

場所:江東区図書館
市場は効率的ではない、でも簡単に儲けられるものでもない。
インデックス投資でもいいけど、せっかくだから知的なゲームとして株式投資を楽しみましょう、という本。
独自の優位な情報があるからといって儲かるわけではない。
なぜなら、その情報が他の投資家に広まらない限り、他の投資家はその株を買ってくれないから。
長期でなんて考えていると、別の材料が出て、下手したら損してしまうかも。
難しい。
アノマリーも大いに利用すべきだけど、いつでも通用するものでもない。
もしかしたらそのアノマリーの利用者は自分よりも前にたくさんいて、畑は荒れ果てた後かもしれない。
自分は前を走っているか?ついてくるやつはいるか?前を走りすぎていないか?もしかしたら前にいっぱい走っていないか?
そういうことをちゃんと考えながら投資をしないといけません。
ケインズは美人投票といったけれども、その美人に最初に投票していたらいいけど、あとから投票しても全然もうかりません。
優良株だからといって、すでに高値ならそこに儲けの源泉はないのです。
それよりも性格の良い不美人を探しましょう。
必要以上に低値に放置されているかも。
経営者がちょっとまともなことをするだけで、みんなの見る目がちょっと変わるだけで、大いに価値をあげるかもしれません。
そういう視点で銘柄をさがしてみよう。
読み返すたびに発見がありそうです。
買って手元に置こうと思いました。
定時に帰る仕事術 (単行本)
ローラ スタック (著), Laura Stack (原著), 古川 奈々子 (翻訳)

場所:江東区図書館
いわゆる仕事術の本。
効率よく仕事をこなすと書くとちょっとネガティブなイメージになってしまうので、生産性を高く日々を過ごすTIPSが100の項目にわたって書かれています。
目から鱗というような記述があるわけではありません。
きわめてオーソドックスで、どこかで目にしたことがあるようなことばかりが書いています。
それでもこの本がお薦めなのは、この本だけでおおよそこの類の本に書かれていることが網羅されているから。
この本だけ読んだら、他はいらないんじゃないかと思います。
その意味で、手元において、しばしば見返したいと思いました。
今日から意識して取り組んでみようと思ったこと。
初対面の人と話をするときには、会話の中で必ずその人の名前を言う。
3回ぐらい言ったらたぶんその人の名前を覚えられるはず。
名前を覚えるのが苦手なのでやってみる価値ありと思いました。
ローラ スタック (著), Laura Stack (原著), 古川 奈々子 (翻訳)

場所:江東区図書館
いわゆる仕事術の本。
効率よく仕事をこなすと書くとちょっとネガティブなイメージになってしまうので、生産性を高く日々を過ごすTIPSが100の項目にわたって書かれています。
目から鱗というような記述があるわけではありません。
きわめてオーソドックスで、どこかで目にしたことがあるようなことばかりが書いています。
それでもこの本がお薦めなのは、この本だけでおおよそこの類の本に書かれていることが網羅されているから。
この本だけ読んだら、他はいらないんじゃないかと思います。
その意味で、手元において、しばしば見返したいと思いました。
今日から意識して取り組んでみようと思ったこと。
初対面の人と話をするときには、会話の中で必ずその人の名前を言う。
3回ぐらい言ったらたぶんその人の名前を覚えられるはず。
名前を覚えるのが苦手なのでやってみる価値ありと思いました。
「投資バカ」につける薬 (単行本)
山崎 元 (著)
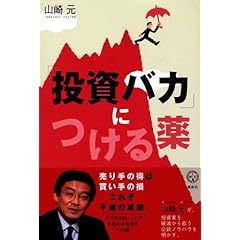
場所:江東区図書館
再読:良書です、投資に対する姿勢がぶれていると感じているときは手にとって読み直したいと思います
推薦:おおあり、最低限の投資に対するスタンスが学べます
わからん商品には手を出すな。
金融商品というのは、市場から売り手が商品を仕入れてきて、それになんらかのパッケージングをして買い手に売るものであるから、素材の商品の期待リターンを売り手と買い手で分け合う構造になっている。
すなわち、売り手の儲けはそれだけ買い手の損になるということ。
わざわざ売り手に儲けをわたす複雑な商品を買う必要がありますか?
直接、市場から素材を調達したほうがよいのではないですか?
アクティブ投信やデリバティブはその典型的な例。
こんなことが書かれています。
他にも、ドルコスト平均法にはあまり意味がないこと、外貨投資は投機であること(為替の見通しにかけた丁半ばくち)、危機感をあおるもの(例:日本破綻、インフレ、など)はたいがいあやしいこと、なんてことが書かれています。
これからも投資を続けていきますが、自分のスタンスがぶれているんじゃないかと感じたときは、手にとって読み返したい一冊です。
山崎 元 (著)
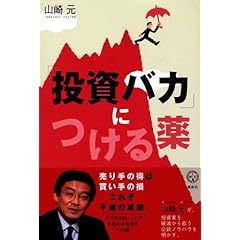
場所:江東区図書館
再読:良書です、投資に対する姿勢がぶれていると感じているときは手にとって読み直したいと思います
推薦:おおあり、最低限の投資に対するスタンスが学べます
わからん商品には手を出すな。
金融商品というのは、市場から売り手が商品を仕入れてきて、それになんらかのパッケージングをして買い手に売るものであるから、素材の商品の期待リターンを売り手と買い手で分け合う構造になっている。
すなわち、売り手の儲けはそれだけ買い手の損になるということ。
わざわざ売り手に儲けをわたす複雑な商品を買う必要がありますか?
直接、市場から素材を調達したほうがよいのではないですか?
アクティブ投信やデリバティブはその典型的な例。
こんなことが書かれています。
他にも、ドルコスト平均法にはあまり意味がないこと、外貨投資は投機であること(為替の見通しにかけた丁半ばくち)、危機感をあおるもの(例:日本破綻、インフレ、など)はたいがいあやしいこと、なんてことが書かれています。
これからも投資を続けていきますが、自分のスタンスがぶれているんじゃないかと感じたときは、手にとって読み返したい一冊です。
マッキンゼー流図解の技術 (-)
ジーン ゼラズニー (著), 数江 良一 (翻訳), 管野 誠二 (翻訳), 大崎 朋子 (翻訳)
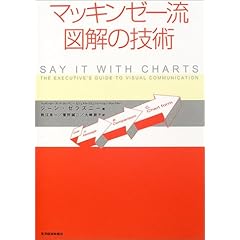
場所:江東区図書館
再読:良書です。購入して手元におきたい一冊です。
推薦:プレゼンテーションで言いたかったことがどうも伝わらない、言いたかったことと違うことが議論されてしまう、というような人にはお薦めです。
英文題名の"SAY IT WITH CHARTS"がこの本の全てをあらわしています。
プレゼンテーションで図表を使う際の鉄則が詰まっています。
大事なことはメッセージを明確にすること。
そのためには何を比較して示せばよいか。
そうすれば、自ずと使える図表の形が決まってきます。
逆に言えば、メッセージと図表がずれていると、聞いている方は混乱し、悪い場合には違うメッセージを受け取ってしまいます。
タイトルは抽象的な名詞を並べるのでなくて、メッセージを書くこと。
×:当社の売り上げ動向
○:当社の売り上げは倍増した
このメッセージをサポートするように比較方法を選び、チャートにあらわす。
比較方法は5種類。
・コンポーネント:全体に対するパーセンテージ
・アイテム:項目のランキング
・時系列:期間内の変化
・頻度:範囲内の項目
・相関:変数間の関係
つきつめると、たいがいはこの5種類に落ちます。
チャートフォームも基本は5種類。
・パイ:コンポーネントに使用
・バー:アイテム、相関に使用
・コラム:時系列、頻度に使用
・ライン:時系列、頻度に使用
・ドット:相関に使用
もちろん例外もありますが、たいがいはこれでOK。
例が豊富なので、手元に置いて活用したい本です。
こういうのを見るとさすがはマッキンゼーと思ってしまいます;)
ジーン ゼラズニー (著), 数江 良一 (翻訳), 管野 誠二 (翻訳), 大崎 朋子 (翻訳)
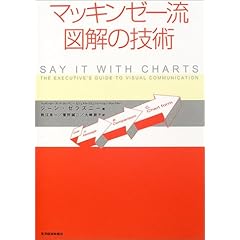
場所:江東区図書館
再読:良書です。購入して手元におきたい一冊です。
推薦:プレゼンテーションで言いたかったことがどうも伝わらない、言いたかったことと違うことが議論されてしまう、というような人にはお薦めです。
英文題名の"SAY IT WITH CHARTS"がこの本の全てをあらわしています。
プレゼンテーションで図表を使う際の鉄則が詰まっています。
大事なことはメッセージを明確にすること。
そのためには何を比較して示せばよいか。
そうすれば、自ずと使える図表の形が決まってきます。
逆に言えば、メッセージと図表がずれていると、聞いている方は混乱し、悪い場合には違うメッセージを受け取ってしまいます。
タイトルは抽象的な名詞を並べるのでなくて、メッセージを書くこと。
×:当社の売り上げ動向
○:当社の売り上げは倍増した
このメッセージをサポートするように比較方法を選び、チャートにあらわす。
比較方法は5種類。
・コンポーネント:全体に対するパーセンテージ
・アイテム:項目のランキング
・時系列:期間内の変化
・頻度:範囲内の項目
・相関:変数間の関係
つきつめると、たいがいはこの5種類に落ちます。
チャートフォームも基本は5種類。
・パイ:コンポーネントに使用
・バー:アイテム、相関に使用
・コラム:時系列、頻度に使用
・ライン:時系列、頻度に使用
・ドット:相関に使用
もちろん例外もありますが、たいがいはこれでOK。
例が豊富なので、手元に置いて活用したい本です。
こういうのを見るとさすがはマッキンゼーと思ってしまいます;)
「頭のいい人」はシンプルに生きる―「快適生活」の方法 (単行本)
ウエイン・W. ダイアー (著), Wayne W. Dyer (原著), 渡部 昇一 (翻訳)

場所:江東区図書館
再読:しばしば読み返したい、ブックオフで見つけたら即ゲット!
推薦:対人関係で割を食ってしまう人、断われない人、要求したいのに取り下げてしまう人は是非これを読んでください
ついついやってしまって不快に思ったりなんとなくいやだなぁと思ったり後悔したりしていたことがあります。
そうならないためにはどうすればよいかなんとなくわかっていたつもりでしたが、できていなかったことも事実です。
で、そういうことを明示的に書いてくれていました。
例えば、「お伺いを立てる代わりに、言い渡せ」
質問してもよろしいでしょうか、と聞かずに、…を知りたいのです、という。
返品してもかまわないでしょうか、と聞かずに、返品しにきました、という。
それでいいはずです。
へりくだる必要のない場面でへりくだっていたような気がします。
・「タバコの煙がいやならいやとはっきり言って」
ついつい我慢してましたが、言えばよかったんですね。
聞いてくれたらラッキー、聞いてもらえなくても言わなかったのと状況は変わらない。
そういう時は言って見るもんですね。
・「できると思います」を「できます」に言い換えよ。
これもそのとおりだと思います。
そいつができるかどうかわからないから、質問しているわけで、返ってきた答えも話半分で聞くでしょう。
できます、と答えても、ほんまかいなと思うのが普通です。
できると思います、だと、それよりも弱くなります。
できなかったときには、できますと答えようができると思いますと答えていようが、相手の受ける印象は、こいつはできるというていたからまかせたのに…だろうからおんなじです。
これからは、できると言い切ってみよう。
過去の時点に「ああすべきであった」と言ってくる人には、過去は変えようがない、現時点で何ができるか、未来に向けてどう改善できるかを話し合うようにする。
不毛な話し合いをさけるにはこれですね。
今更言っても仕方のないことは言わない。
他人の例を示して説得にかかってくる人には、きっぱりと他人と自分は関係ないと言い切ってしまう。
あなた以外はこんなこと言わないとか、誰にでもこうしています、的な言われ方をすることがよくあるように思います。
なんでいっしょやないといかんのやと、素直に言い返せばよいのでした。
・どうでもいいことは大目にみる
これは気がついていたことです。
できているかどうかはちょっと置くとして。
自分あるいは守りたい人やものに害がない限りは、とやかく言う必要はありません。
例えば、会話の中の相手の発言のちょっとした間違いを訂正するために1時間も議論する必要はありません。
ついついやっちゃうんですけどね。
・不快なことにいちいち過剰反応しない
これも上に近いですが、やり過ごしてしまえばいいのです。
自分の存在に関わることならそうもいきませんが、スルーしてしまってもよいことならスルーしてしまいましょう。
・「遠い」に目くじらを立てるのではなく共通項を大切にする
良好な人間関係を継続するには大事にしたい考え方です。
違いを意識しだすと、嫌なところばかりが目に付きます。
それはやめましょう。
・不毛な論争ほどエネルギーを浪費する
上に書いたのと同じですね。
かけるコストと得られるベネフィットを比較して、後者が上回るときのみ論争をすべきです。
・上手なウソが人間の幅を広げる
自分を振り返って少々バカ正直な気がします。
これで損していることもしばしば。
うまいウソがつけるようになりたいと思います。
・いつもみんなに理解される必要はない
目から鱗が落ちた気がします。
当たり前ですね。
全員に理解されることなんて不可能なんですから。
選択と集中、自分が絶対にこの人だけはと思う人にだけ理解されたら十分じゃないですか。
・雑音にはラジオのスイッチを切る要領で
とやかく言う人はどないしようととやかく言うてくるのです。
であれば、聞かないあるいは意識しないのが正解です。
おそらくこの本は二度三度読み返すと、そのたびに発見がありそうです。
読み直したいと思いました。
ウエイン・W. ダイアー (著), Wayne W. Dyer (原著), 渡部 昇一 (翻訳)

場所:江東区図書館
再読:しばしば読み返したい、ブックオフで見つけたら即ゲット!
推薦:対人関係で割を食ってしまう人、断われない人、要求したいのに取り下げてしまう人は是非これを読んでください
ついついやってしまって不快に思ったりなんとなくいやだなぁと思ったり後悔したりしていたことがあります。
そうならないためにはどうすればよいかなんとなくわかっていたつもりでしたが、できていなかったことも事実です。
で、そういうことを明示的に書いてくれていました。
例えば、「お伺いを立てる代わりに、言い渡せ」
質問してもよろしいでしょうか、と聞かずに、…を知りたいのです、という。
返品してもかまわないでしょうか、と聞かずに、返品しにきました、という。
それでいいはずです。
へりくだる必要のない場面でへりくだっていたような気がします。
・「タバコの煙がいやならいやとはっきり言って」
ついつい我慢してましたが、言えばよかったんですね。
聞いてくれたらラッキー、聞いてもらえなくても言わなかったのと状況は変わらない。
そういう時は言って見るもんですね。
・「できると思います」を「できます」に言い換えよ。
これもそのとおりだと思います。
そいつができるかどうかわからないから、質問しているわけで、返ってきた答えも話半分で聞くでしょう。
できます、と答えても、ほんまかいなと思うのが普通です。
できると思います、だと、それよりも弱くなります。
できなかったときには、できますと答えようができると思いますと答えていようが、相手の受ける印象は、こいつはできるというていたからまかせたのに…だろうからおんなじです。
これからは、できると言い切ってみよう。
過去の時点に「ああすべきであった」と言ってくる人には、過去は変えようがない、現時点で何ができるか、未来に向けてどう改善できるかを話し合うようにする。
不毛な話し合いをさけるにはこれですね。
今更言っても仕方のないことは言わない。
他人の例を示して説得にかかってくる人には、きっぱりと他人と自分は関係ないと言い切ってしまう。
あなた以外はこんなこと言わないとか、誰にでもこうしています、的な言われ方をすることがよくあるように思います。
なんでいっしょやないといかんのやと、素直に言い返せばよいのでした。
・どうでもいいことは大目にみる
これは気がついていたことです。
できているかどうかはちょっと置くとして。
自分あるいは守りたい人やものに害がない限りは、とやかく言う必要はありません。
例えば、会話の中の相手の発言のちょっとした間違いを訂正するために1時間も議論する必要はありません。
ついついやっちゃうんですけどね。
・不快なことにいちいち過剰反応しない
これも上に近いですが、やり過ごしてしまえばいいのです。
自分の存在に関わることならそうもいきませんが、スルーしてしまってもよいことならスルーしてしまいましょう。
・「遠い」に目くじらを立てるのではなく共通項を大切にする
良好な人間関係を継続するには大事にしたい考え方です。
違いを意識しだすと、嫌なところばかりが目に付きます。
それはやめましょう。
・不毛な論争ほどエネルギーを浪費する
上に書いたのと同じですね。
かけるコストと得られるベネフィットを比較して、後者が上回るときのみ論争をすべきです。
・上手なウソが人間の幅を広げる
自分を振り返って少々バカ正直な気がします。
これで損していることもしばしば。
うまいウソがつけるようになりたいと思います。
・いつもみんなに理解される必要はない
目から鱗が落ちた気がします。
当たり前ですね。
全員に理解されることなんて不可能なんですから。
選択と集中、自分が絶対にこの人だけはと思う人にだけ理解されたら十分じゃないですか。
・雑音にはラジオのスイッチを切る要領で
とやかく言う人はどないしようととやかく言うてくるのです。
であれば、聞かないあるいは意識しないのが正解です。
おそらくこの本は二度三度読み返すと、そのたびに発見がありそうです。
読み直したいと思いました。
「捨てる!」技術 (単行本(ソフトカバー))
辰巳 渚 (著)

場所:江東区図書館
再読:何度でも読み返したい本、特にモノが増え始めたなという気配を感じたらこれを読んで捨てるきっかけにしたい
推薦:いろんな意味でモノに執着してしまっている人へ、でもそういう人には響かないかも
三度目ぐらいの読み直し。
読むたびに発見があるというわけではないですが、捨てることを躊躇している自分にドライブをかけてくれます。
その意味では、たまに読み返して、勢いをつけて捨てるをやるのがよいかもしれません。
読み終えた今改めて机の周りを見回してみると、捨ててもよさそうなモノがいっぱいです。
思い切って捨ててしまっても恐らくは後悔しません。
なんとなれば再入手できそうです。
本なんかの場合は、自分の脳にインデックスがなければその本を再び手に取ろうと思わないわけですし、インデックスがあればアマゾンあたりでなんとか見つけられそうです。
昔は(今もちょっと)本棚にずらりと並ぶ様が壮観であったりしたわけですが、この本を読んでからは、本は情報を入手するための手段に過ぎない、または、ある時間を楽しませてくれる娯楽にすぎないと考えられるようになりました。
そうすると、この後の一生でしばしば手に取る本しか手元におかないでよいことに思い至りました。
しばしば手に取る本でも、再入手が容易なら手放してもよいかもしれません。
この辺は見返す頻度と再入手のコスト(時間・おカネ)の相関で決まりそうです。
一回使ったらそれで良しとせよ。
この考え方は体になじんでいませんでしたが、これでいいのかもしれません。
それ以来使っていないのはなんらかの理由がありそうです。
合わなかったのかもしれないし、使う場面がなかったのかもしれない。
そういう理由に思い至ったら捨てればいい。
そういう理由を考えるきっかけが、一回使ったらそれで良しとせよなんですね。
この視点でしばらく家の中を見回ってみることにします。
色々と捨てられそうです。
辰巳 渚 (著)

場所:江東区図書館
再読:何度でも読み返したい本、特にモノが増え始めたなという気配を感じたらこれを読んで捨てるきっかけにしたい
推薦:いろんな意味でモノに執着してしまっている人へ、でもそういう人には響かないかも
三度目ぐらいの読み直し。
読むたびに発見があるというわけではないですが、捨てることを躊躇している自分にドライブをかけてくれます。
その意味では、たまに読み返して、勢いをつけて捨てるをやるのがよいかもしれません。
読み終えた今改めて机の周りを見回してみると、捨ててもよさそうなモノがいっぱいです。
思い切って捨ててしまっても恐らくは後悔しません。
なんとなれば再入手できそうです。
本なんかの場合は、自分の脳にインデックスがなければその本を再び手に取ろうと思わないわけですし、インデックスがあればアマゾンあたりでなんとか見つけられそうです。
昔は(今もちょっと)本棚にずらりと並ぶ様が壮観であったりしたわけですが、この本を読んでからは、本は情報を入手するための手段に過ぎない、または、ある時間を楽しませてくれる娯楽にすぎないと考えられるようになりました。
そうすると、この後の一生でしばしば手に取る本しか手元におかないでよいことに思い至りました。
しばしば手に取る本でも、再入手が容易なら手放してもよいかもしれません。
この辺は見返す頻度と再入手のコスト(時間・おカネ)の相関で決まりそうです。
一回使ったらそれで良しとせよ。
この考え方は体になじんでいませんでしたが、これでいいのかもしれません。
それ以来使っていないのはなんらかの理由がありそうです。
合わなかったのかもしれないし、使う場面がなかったのかもしれない。
そういう理由に思い至ったら捨てればいい。
そういう理由を考えるきっかけが、一回使ったらそれで良しとせよなんですね。
この視点でしばらく家の中を見回ってみることにします。
色々と捨てられそうです。
臆病者のための株入門 (新書)
橘 玲 (著)

場所:江東区図書館
再読:投資のポリシが揺らいだらぜひとも本書を手にとって軌道修正したい
推薦:経済学的に見て王道の投資法が書かれているので、投資を志す全ての人にお薦めしたいところではありますが、特に投資の道に入ってきたばかりの夢多き人には「インデックス買っとけ、以上。」では物足りなく感じられるでしょう、自分も実際そうでした、ということで、ある程度痛い目にあってからの方がより理解が深まるのではないかと思います。もちろん最初から素直にここに書かれていることが出来るとすんごく効率的です。もちろん儲かるかどうかはわかりませんが、リスクに見合った期待リターンが狙えるはずです。
前半では、ジェイコム男、ホリエモン、デイトレードを例にトレーディングの世界を紹介。
華やかで、誰でも億万長者になれるような錯覚を起してくれますが、所詮ギャンブルです。
一部の目だった人のせいでそう見えているだけで、影には財産をなくした人がいっぱい。
普通の人が手を出すべきものではありません。
もちろん、ギャンブルと割り切って、遊びの範囲で嗜むことは結構。
ただし、それは財産形成の手段でなくて趣味。
中盤では、経済学と資本主義と投資のお話。
1.株式投資は確率のゲームである
2.株式市場はおおむね効率的であるが、わずかな歪みが生じている
3.資本主義は自己増殖のシステムなので、長期的には市場は拡大し、株価は上昇する
株式投資に勝つには、市場の歪みを利用するか、長期投資で樹から果実が落ちるのを待つか、しかない。
インデックス投資は後者、長期的には市場の拡大と同程度の収益が得られるが、退屈極まりない。
バフェット流は、前者と後者の合わせ技、これが出来れば、それはもうかりますわな。
後半になって、いよいよ経済学的に王道の投資法の紹介。
「インデックス買っとけ、以上。」
もうちょっと具体的に書くと、MSCIワールド・インデックスに連動するファンドがあればいいんだけど、ないので、
MSCIコクサイ・インデックス85%
TOPIX15%
の割合で持っとく、以上。
投資コストからするとETFでの保持がベスト、コストの安いインデックスファンドがあればそれでもよし。
全部株ではちょっとという人は、国債の割合を増やして、調節。
もっとアグレッシブにいってもいいんではという人は、一部の資産で個別銘柄を物色し未来のバフェットを目指すのも一興。
橘 玲 (著)

場所:江東区図書館
再読:投資のポリシが揺らいだらぜひとも本書を手にとって軌道修正したい
推薦:経済学的に見て王道の投資法が書かれているので、投資を志す全ての人にお薦めしたいところではありますが、特に投資の道に入ってきたばかりの夢多き人には「インデックス買っとけ、以上。」では物足りなく感じられるでしょう、自分も実際そうでした、ということで、ある程度痛い目にあってからの方がより理解が深まるのではないかと思います。もちろん最初から素直にここに書かれていることが出来るとすんごく効率的です。もちろん儲かるかどうかはわかりませんが、リスクに見合った期待リターンが狙えるはずです。
前半では、ジェイコム男、ホリエモン、デイトレードを例にトレーディングの世界を紹介。
華やかで、誰でも億万長者になれるような錯覚を起してくれますが、所詮ギャンブルです。
一部の目だった人のせいでそう見えているだけで、影には財産をなくした人がいっぱい。
普通の人が手を出すべきものではありません。
もちろん、ギャンブルと割り切って、遊びの範囲で嗜むことは結構。
ただし、それは財産形成の手段でなくて趣味。
中盤では、経済学と資本主義と投資のお話。
1.株式投資は確率のゲームである
2.株式市場はおおむね効率的であるが、わずかな歪みが生じている
3.資本主義は自己増殖のシステムなので、長期的には市場は拡大し、株価は上昇する
株式投資に勝つには、市場の歪みを利用するか、長期投資で樹から果実が落ちるのを待つか、しかない。
インデックス投資は後者、長期的には市場の拡大と同程度の収益が得られるが、退屈極まりない。
バフェット流は、前者と後者の合わせ技、これが出来れば、それはもうかりますわな。
後半になって、いよいよ経済学的に王道の投資法の紹介。
「インデックス買っとけ、以上。」
もうちょっと具体的に書くと、MSCIワールド・インデックスに連動するファンドがあればいいんだけど、ないので、
MSCIコクサイ・インデックス85%
TOPIX15%
の割合で持っとく、以上。
投資コストからするとETFでの保持がベスト、コストの安いインデックスファンドがあればそれでもよし。
全部株ではちょっとという人は、国債の割合を増やして、調節。
もっとアグレッシブにいってもいいんではという人は、一部の資産で個別銘柄を物色し未来のバフェットを目指すのも一興。
図解 ひとめでわかるビジネス会計 (単行本(ソフトカバー))
田中 靖浩 (著)

場所:江東区図書館
再読:購入してもよいかも
推薦:会計の概略がつかみたい人
会計を俯瞰できます。
キーワードを説明するときに使うと便利そう。
心に残ったのをいくつか…
ROE<株主資本利益率>
=当期純利益/資本(株主資本)
=当期純利益/売上 × 売上/資産 × 資産/資本
ということで、ROEを向上するには
・売上に対する利益を向上すること
・資産に対する売上を向上すること
・負債を有効活用すること=レバレッジを効かせる!
↑最後のが目から鱗でした
PPM<製品ポートフォリオマネジメント>
・金のなる木(Cash Cows、成長率は低いが市場シェアが高い)事業で回収した資金を
・問題児(Question Marks、市場シェアは低いが成長率は高い)事業に投入し、
・花形(Stars、成長率、シェアともに高い)事業に育てることを目指す
・負け犬(Dogs、成長率、シェアともに低い)事業からは撤退
↑当たり前のことですが文字にすると再確認させられます
NPV(Net Present Value)<正味現在価値>
・将来のCIF(Cash In Flow)とCOF(Cash Out Flow)を現在価値に割り引いたもの
・IRRと資本コストが等しいとNPVは0になる
・投資判断はNPVが正でないとNG、すなわちIRRが資本コストを上回るということ
管理可能原則
・部門の評価は管理可能利益、管理可能費のみで判断すべきもの
・管理不能費は、例えば使用する建物が会社方針で決められたならそれについての減価償却は部門にとって管理不能
・責任と権限が一致しないといけないという当たり前のこと
EVA(Economic Value Added)<経済的付加価値>
・利益額や売上利益率だけで比較するのではなくて、
・RI<残余利益>(=利益額から資本コスト(投資額から導かれるこれだけは儲けて欲しいという額)を引いたもの)や、
・ROI<投資利益率>(=利益額/投資額)でも判断するべき
↑たまたま今儲けていたとしても、それはそれまでに膨大な投資をしているかもしれないので、それも考慮して比較しないと不公平ということ
田中 靖浩 (著)

場所:江東区図書館
再読:購入してもよいかも
推薦:会計の概略がつかみたい人
会計を俯瞰できます。
キーワードを説明するときに使うと便利そう。
心に残ったのをいくつか…
ROE<株主資本利益率>
=当期純利益/資本(株主資本)
=当期純利益/売上 × 売上/資産 × 資産/資本
ということで、ROEを向上するには
・売上に対する利益を向上すること
・資産に対する売上を向上すること
・負債を有効活用すること=レバレッジを効かせる!
↑最後のが目から鱗でした
PPM<製品ポートフォリオマネジメント>
・金のなる木(Cash Cows、成長率は低いが市場シェアが高い)事業で回収した資金を
・問題児(Question Marks、市場シェアは低いが成長率は高い)事業に投入し、
・花形(Stars、成長率、シェアともに高い)事業に育てることを目指す
・負け犬(Dogs、成長率、シェアともに低い)事業からは撤退
↑当たり前のことですが文字にすると再確認させられます
NPV(Net Present Value)<正味現在価値>
・将来のCIF(Cash In Flow)とCOF(Cash Out Flow)を現在価値に割り引いたもの
・IRRと資本コストが等しいとNPVは0になる
・投資判断はNPVが正でないとNG、すなわちIRRが資本コストを上回るということ
管理可能原則
・部門の評価は管理可能利益、管理可能費のみで判断すべきもの
・管理不能費は、例えば使用する建物が会社方針で決められたならそれについての減価償却は部門にとって管理不能
・責任と権限が一致しないといけないという当たり前のこと
EVA(Economic Value Added)<経済的付加価値>
・利益額や売上利益率だけで比較するのではなくて、
・RI<残余利益>(=利益額から資本コスト(投資額から導かれるこれだけは儲けて欲しいという額)を引いたもの)や、
・ROI<投資利益率>(=利益額/投資額)でも判断するべき
↑たまたま今儲けていたとしても、それはそれまでに膨大な投資をしているかもしれないので、それも考慮して比較しないと不公平ということ
非常識会計学!―世界一シンプルな会計理論 (単行本)
石井 和人 (著), 山田 真哉 (著)

場所:江東区図書館
再読:あり、手元に置きたい
推薦:簿記を勉強中の人
会計学を俯瞰できる本。
簡潔にまとまっており、非常に読みやすい。
実務ではもっと細かい知識がいるのは当たり前だけど、幹の部分をつかむにはたいへんお薦め。
固定資産の固定が、流動と対になる言葉であって、長期間(企業に)留まっているという意味であることを恥ずかしながら始めて認識いたしました。
費用収益対応の原則、保守主義の原則、実現主義の原則、…
簿記を勉強したときには、財務書評の作り方はわかったんだけれども、その裏にはこういう考え方や哲学があったのだなぁ。
石井 和人 (著), 山田 真哉 (著)

場所:江東区図書館
再読:あり、手元に置きたい
推薦:簿記を勉強中の人
会計学を俯瞰できる本。
簡潔にまとまっており、非常に読みやすい。
実務ではもっと細かい知識がいるのは当たり前だけど、幹の部分をつかむにはたいへんお薦め。
固定資産の固定が、流動と対になる言葉であって、長期間(企業に)留まっているという意味であることを恥ずかしながら始めて認識いたしました。
費用収益対応の原則、保守主義の原則、実現主義の原則、…
簿記を勉強したときには、財務書評の作り方はわかったんだけれども、その裏にはこういう考え方や哲学があったのだなぁ。












