大震災の後で人生について語るということ [単行本]
橘 玲 (著)


場所:江東区図書館
基本的には、これまでの橘本と書いてることはそれほど変わりない。
これまでもダークサイドに落ちないためにはどうするかを描いてきていたが、それでも黄金の羽根の拾い方が見つかればアップショットが狙えるという面があった。
今回の大震災を受け、そこがリスク回避をするためにはどうするかにフォーカスされたように思う。
失われた4つの神話、
・不動産神話
・会社神話
・円神話
・国家神話
と大震災を経て、自分だけではコントロールが難しい国家の特に財政面のリスクからいかに自分を切り離すか。
著者の主張を全部取り入れられるわけではないけれども、ヒントはいっぱい。
迷いが生じたり、ちょっと浮かれているかもと思ったときは、手にとって考えを修正するのに使いたい本。
以下、メモ。
●<P.39>このことを概念的に説明すると、マイホームでは、あなたという家主が賃借人から月額二〇万円の家賃を受け取っている、ということになります。この「見えない家賃」が帰属家賃で、海外赴任などでマイホームを賃貸に出すと(すなわち賃借人があなたから他人に代わると)、このキャッシュフローが「見える家賃」へと現実化するのです。
このことからわかるように、マイホームの所有者は、帰属家賃という見えない収入を受け取っています。このため海外では、資産を不動産以外(株式や債券)に投資しているひととの公平を期すため、帰属家賃に課税するところもあります(スイス、オランダ、ベルギーなど)。その是非はともかくとして、マイホームとは不動産投資であり金融資産そのものということがこれでわかるでしょう。
★帰属家賃に課税したほうが、筋としては通るなぁ。
●<P.51>銀行にお金を預けるときは、一〇万円でも一〇〇万円でも利息は変わりません。一億円なら大口預金になって、利息をすこし上乗せしてもらえます。このように、投資額によって利回りは変わらないか、大口の投資家が有利になるのが基本です。
ところが賃貸物件の利回りを比較すると、価格の安いワンルームマンションの利回りが明らかに高く、分譲マンションや一戸建てになるにしたがって利回りは低くなります。これは、ワンルームマンションのほうがリスクが高い(物件価格が下落する可能性が大きい)ためです。
年金生活者などに販売されている投資用ワンルームマンションでは、不動産業者が十分な利益を得てもなお魅力的な利回りを維持するために、家賃をそうとう高く設定しなければなりません。しかしこれではだれも借りてくれませんから、いずれは家賃を引き下げるか、家賃保証会社が破綻するほかありません。これでは、あちこちでトラブルが起きるのも当然です。
その一方で、一戸建てやファミリー向けのマンションの利回りが低いのは、借り手がいなくて家賃が下がるからです。後述するように、日本では借地借家法によってファミリー向けの賃貸物件の供給が少なく、結婚して子どもができるとマイホームを購入するのが”常識”とされています。そのうえ「賃貸よりマイホームが得だ」とほとんどのひとが信じているので、賃料の高い物件を借りるのは外資系企業の幹部社員などごく一部しかいません。ただしこうした需要があるのは東京の都心部に限られているので、郊外の大型物件の賃料は大幅にディスカウントせざるをえないのです。
このことを賃貸する側から見れば、常識とは逆に、家賃の安いワンルームマンションほど不利で、賃料の高い大型物件を大家族で借りたほうが得だということになります。
月額家賃三〇万円で家を借りていると聞けば、だれもがもったいないと思うでしょう。しかしこの物件の市場価格が一億円だとすれば利回りは年三.六パーセント(三六〇万円÷一億円)で、実質利回りの平均(五パーセント)を大きく下回っています。これが高額の賃貸物件に住む資産家がいる理由で、彼らは割安な不動産物件を借り、資金をより利回りの高い(正確にはリスク/リターン比の高い)収益機会に投じたほうが有利だということを知っているのです(不動産業界のひとたちが賃貸物件に住んでいる理由もここから説明できます)。
★なるほど。
多くの人が家族を持つタイミングで持ち家に流れることから、ファミリー向けの賃貸市場への供給は少ないんだけども、需要はもっと少ないってことか。
そうすると、少ない供給でも需要よりは多いので供給過多ってことになって、値段が下がる。
こんなところにも黄金の羽根は落ちているのかぁ、これは目から鱗だ。
今後、賃貸市場が活性化すると思われ、そのうち需要と供給はマッチして適正な価格に落ち着くはず。
割安な賃貸物件を見つけたら、それをさっさと借りて長く住むってのはいいかもしれない。
●<P.55>個人がマイホームを購入すべき理由として、「年をとれば家が借りられなくなる」といわれますが、高齢化社会では高齢者に入居してもらわなければ空室を埋めることができませんから、これも過去の話になってしまいました。国土交通省は高齢者専用賃貸住宅(高専賃)の普及にちからをいれていますが、そうでなくても今後は高齢者が賃貸市場の主役にならざるをえないでしょう。
★最近新聞を見ていてびっくりした。
女性向けファッション誌の広告がたくさんのってたけど、ほとんどアラフォー向け。
ファッションの市場をその世代が支えてるってこと。
おそらく10年後は、この層がそのまま年食ってアラフィフ向け雑誌ばかりになるはず。
市場はお金を払ってくれる層に向けて商品を供給する。
賃貸市場もそう。
とすれば、恐ろしい予想が頭をよぎる。
若いと家が借りられない…
そんな時代がくるかもしれない。
●<P.75>日本的雇用慣行がなかなか変わらないのは、それが均衡解として安定しているからです。しかしナッシュ均衡は、いったん成立すると未来永劫変わらないわけではありません。左側通行と右側通行を変えるのはものすごく大変です。しかし沖縄では、敗戦による占領で交通ルールがアメリカと同じ右側通行になり、本土復帰七年目の一九七八年七月三〇日に左側通行に戻されました。このときは、わずか八時間ですべての道路標識・標示が変更されたといいます。
ここに、ナッシュ均衡のもう一つの特徴があります。それはきわめて頑健ですが、いったん状況が代わると一瞬のうちにもうひとつの均衡解に移ってしまうのです(右側通行と左側通行が混在することはありません)。
雇用慣行がナッシュ均衡だとすれば、日本的雇用がアメリカ型になったり、アメリカ型雇用が日本型になったりすることも考えられます。どのような条件で、このような変化が起きるのでしょうか。
青木昌彦によれば、雇用慣行がどちらの解に至るかは、期待賃金(労働供給関数)と実質賃金(限界生産曲線)の関係で決まります。サラリーマンの実質賃金が期待賃金より大きければ、すべての労働者が正社員を目指して日本的雇用に至ります。逆に実質賃金が期待賃金よりも低くなれば、サラリーマンはいなくなってアメリカ型雇用という均衡解に達するのです。このことをもっと簡単にいうと、「サラリーマンになるのは損だ」とみんなが思うようになれば、日本的雇用は崩壊するのです。
★変化点はすぐそこまで来ているかもしれない。
それでもサバイバルするには、どうすればよいだろうか?
●<P.80>サラリーマンとはすべての人的資本をひとつの会社に投資することですから、これは「タマゴをひとつのカゴに盛る」のと同じです。だれもがすぐに気づくように、この投資が成功するには、そのカゴが壊れないことが絶対条件になります。ところがこの一〇年で、会社が倒産するのは珍しいことではなく、大手企業でも頻繁にリストラが行われるようになりました。
★この状況が続いて、昔には戻らないとみんなが思うようになれば、それはすなわち上で引用した「サラリーマンになるのは損だ」とみんなが思うようになること…
●<P.82>前頁図(19)では、人的資本は会社に完全に依存していますから、いったん食を失えばその大半が毀損してしまいます。金融資本はレバレッジをかけて不動産に投資されているので、地価が下落したり、天変地異で不動産の価値がなくなればたちまち債務超過に陥ってしまうでしょう。そしておそろしいことに、日本にはこうしたハイリスクな人生のポートフォリオを持つひとたちがものすごくたくさんいるのです。
★知り合いを見回したときに、家持ちですんごく不安を感じさせるのとそうでないのがいるけど、その違いはこれかぁ。
人的資本が会社にほぼ完全に依存しているか、いざとなったら会社の外に出ていってもなんとかなりそうかの違いか。
●<P.127>国家の財政赤字とは、要するに国家が通貨(円)を過剰に印刷して市場に供給することです。通貨もまたひとつの商品ですから、当然、需要に対して供給が増えれば価値は下がります。財政破綻とは、円の信用が失墜して通貨の価値が大きく毀損することです。
このように考えると、国家破産は原理的に三つの経済事象しか引き起こさないことがわかります。
(1)高金利 国債の信用に投資家が不安を抱けば、債券価格は下落して金利が上昇します。
(2)円安 外国為替市場ではさまざまな国の通貨が売買されており、日本円の価値が下がれば、当然、外貨の価値が上がって円安になります。
(3)インフレ 通貨というのはモノやサービスを売買するときの指標ですから、通貨の価値が下がれば物価は上昇してインフレになります。
国家破産というのは、この三つの経済現象が同時に、かつ異常なレベルで発生することです。日本はずっとデフレと低金利に悩まされてきましたが、〇七年の世界金融危機以降は、それに円高が加わりました。国家破産後は、いまとまったく逆の「インフレ・高金利・円安」世界がやってくるのです。
ここで強調しておきたいのは、国家破産をいたずらに恐れる必要はないということです。財政が破綻すればなにが起きるかあらかじめわかっていて、なおかつそれ以外のことは原理的起こりえないのですから、原発事故のように、放射能という未知の恐怖に襲われるわけではありません。
★投資を、利殖ではなく、国家財政破綻に対する保険、リスクヘッジと考えてみよう。
色気を出すから、ほんとは気にしちゃいけないとわかっちゃいるのにマーケットタイミングが気になったりする。
日本国財政が抱えるリスクを極力最小化するには、そういう視点で投資を考えてみると、迷いの要素は少なくなりそう。
●<P.144>製造業やサービス業の労働者がグローバル化の荒波に飲み込まれるのは、それがだれでもできる代替可能な仕事だからです。こうした仕事の象徴がマクドナルドの店員で、厳密に定められたマニュアルどおりに作業すれば、新人でも初日からベテランと同じハンバーガーをつくることができます。これが”マックジョブ”で、会社の場合はバックオフィスの仕事に相当します。
その一方で、医師や弁護士、公認会計士、あるいは俳優や歌手、スポーツ選手のように、代替不可能な視覚や技能、能力が必要な(だれでもできるわけではない)仕事もあります。
こうしたクリエイティブクラスに、グローバル化は多大な恩恵をもたらします。
(英語を母語とする)彼らの仕事に国家や民族は関係なく、ひとたび成功すれば世界市場を相手に莫大な利益を手にすることができるからです。-アメリカではライシュの予言どおり、超富裕層と貧困層の二極化が進行しました。
ところで『ブラック・スワン』のナシーム・タレブは、クリエイティブクラスのなかにも、「拡張可能な仕事」と「拡張不可能な仕事」があるといいます。拡張可能なのがクリエイター、拡張不可能なのがスペシャリストで、この区別は、これからの仕事を考えるうえできわめて重要です。
★どれを選ぶかは生き方の問題。
それぞれにメリットがありデメリットがある。
それを無視して羨んだり、卑下したり、ないものねだりしても無駄。
●<P.160>グローバルな世界では、労働者の二割のクリエイティブクラスと八割のマックジョブに分かれるとロバート・ライシュは予言しました。そのクリエイティブクラスには、拡張可能なクリエイターと拡張不可能なスペシャリストの仕事があります。
今後日本でも同様の変化が起きるのであれば、この本を読んでいるほとんどのひとにとって、人生設計の最適戦略はスペシャリストを目指すことになるでしょう。アメリカでもクリエイターの数はきわめて少なく、クリエイティブクラスのほとんどはスペシャリストです(クリエイターが目立つのは、ごく少数がとてつもない成功をするからです)。
日本列島には約一億二〇〇〇万人が暮らしていて、乳幼児を除けばほぼ全員が読み書きできます。しかし出版業界ではながらく、「本を読むのは人口の一〇パーセント」といわれてきました。読書調査では、月に一冊も本を読まないひとが約五割とされていますが、残りのひとたちが文芸書や専門書、ビジネス書などを読んでいるわけではありません。有り体にいってしまえば、こうした本を読むには一定程度のリテラシーが必要になるのです。
光文社で女性誌やビジネス書籍をつくってきた編集者の山田順は、『出版大崩壊』(文春文庫)で、経済書やビジネス書の読者は最大四〇〇万人しかいないとして、次のような根拠を述べます。
これは、まず一流大学卒で一流企業社員、公官庁職員、弁護士、医者などの専門職の就業人口から出した実数である。現在、東京大学の卒業生の総数は年3000~3500人。これに京大、阪大、九大などの国立大学の卒業生、早慶ほかの六大学にMARCH、関関同立などの卒業生を加えると、年約15万~20万人になる。この15万人~20万人と、毎年、一流企業、官庁、専門職に就く人数はほぼ一致している。
この構造は日本社会ではずっと変わっていなくて、就職氷河期などと言われても、この層は変動することなく、階層ピラミッドの上位層を形成している。ちなみに、1世代の年齢別人口は団塊ジュニアのときが200万人を超えていたが、少子化で現在は100万人近くまで落ちている。
さて、この年齢別人口のうち上位20万人が、定年までの約40年間本を読むとする。すると40歳分だから、800万人になる。しかし、経済書となれば読者のほとんど男性だから半分の400万人。こrが想定読者数だ。
★この数字は覚えておいておこう。
●<P.181>しかし世界の株式市場をまるごと買うことができるのなら、このような悩みはなくなります。なぜならその場合、理論上、選択肢は次のふたつしかなくなるからです。
(1)世界の株式市場は長期的に拡大する。
(2)資本主義はもう限界で、これから市場は縮小するしかない。
●<P.183>ヒトという有限な生き物にとってもっとも貴重な資源は、お金ではなく時間です。
ウォーレン・バフェットのように世界じゅうの企業の財務諸表を読み込み、徹底的に分析すれば、株価インデックスに比べて投資パフォーマンスを二〇パーセント引き上げられるとしましょう。しかし私は、仮にこの”必勝法”を知っていたとしても、実践しようとは思いません。私の投資額から考えると、その時間を仕事や趣味にあてたほうが人生の効用ははるかに大きく、それを犠牲にしてわずかな超過利潤を得たところでなんの意味もないからです。
●<P.185>さらに素晴らしいことに、ACWIの世界株ポートフォリオは、通貨の分散まで勝手にやってくれます。そこにはアメリカ企業だけでなく、ヨーロッパ(ユーロ)やイギリス(ポンド)、中国(人民元)、ロシア(ルーブル)、インド(ルピー)、ブラジル(レアル)などの企業が株式市場の時価総額に応じて含まれているからです。すなわち世界株ポートフォリオは、為替リスクに足して中立なのです。
★市場はまだ拡大するとの明るい未来にかけるなら、ACWI(1554)買っとけ、以上。
●<P.202>これまで述べたように、理論どおりなら、これらの通貨は円に対して金利差の分だけ安く(円高に)ならなければなりません。ところが現実は、すべての通貨が円に対して一四~一八パーセントも増価した(円安になった)のです。この結果、レバレッジをかけて高金利通貨を買持ちした投資家(おばさん)は、金利差と為替差益のダブルで儲かることになりました(円を売ったプロの投資家は往復ビンタのようにダブルで損をしました)。
その後ドル円レートは、二〇〇七年六月の一二三円をピークに円高に転じ、世界金融危機を経て、大震災直後の二〇一一年三月一七日には一ドル=七六円二五銭の史上最高値を記録しました。世間ではこれを「超円高」と呼びましたが、二〇〇五年初頭の一ドル=一〇〇円を基準値とし、米ドルと日本円の平均的な金利差を三パーセントとすれば、二〇一〇年に一ドル=八〇円になるのは理論どおりです(日本とアメリカのインフレ率の差から資産しても同じ結果になります)。
★とすれば、今こそが正常であって、ちょっと前が異常なのだな。
これは意識しておいていいかもしれない。
●<P.219>日本の社会でもっとも優秀なひとたちがバザール空間に集まるのは、そこに法外に有利な成功の機会があることに気づいているからでしょう。
その成功は、たんに金銭的なものではありません。バザール世界では金銭よりも「評判」のほうがはるかに価値が高く、インターネットの登場によって、成功者はとてつもない富と名声を手にするようになりました。
★そうか、じつはそっちがブルーオーシャンだったのかもしれない。
●<P.223>日本人はずっとムラ社会的な人間関係(世間)に守られて暮らしてきましたが、その窮屈な世界を憎んでもきました。故郷を捨てて都会に出ても、こんどは会社という別の世間に取り込まれて生きるしかありませんでした。
しかしいまや会社共同体も解体し、私たちは一人ひとりの金融資本と人的資本だけを頼りに、グローバルな市場経済と孤独に相対することを余儀なくされています。いずれ本書の続編として、そんな日本の希望と絶望について書いてみたいと思います。
★をを、続編あり、待ち遠しい。
【アクション】
日本国の国家財政破綻リスクからリスクフリーにするには、どのようなポートフォリをを組むべきかを考える。























 知っているようで知らない 法則のトリセツ
知っているようで知らない 法則のトリセツ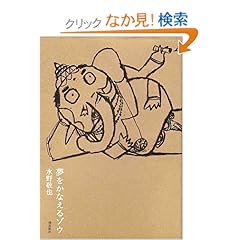 夢をかなえるゾウ
夢をかなえるゾウ ウォーレン・バフェット 自分を信じるものが勝つ!―世界最高の投資家の原則 (スピークス・シリーズ)
ウォーレン・バフェット 自分を信じるものが勝つ!―世界最高の投資家の原則 (スピークス・シリーズ) 元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術[第2版]
元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術[第2版]