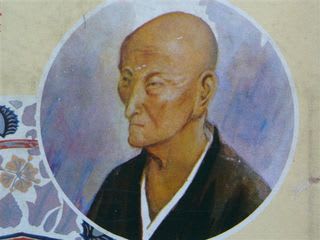地球温暖化防止のため、京都議定書の目標達成のため、冷暖房温度の設定や、蛇口をこまめに閉めること、過剰包装を断わる、などの
提案を環境省がしているそうだ。
その中にはアイドリングストップ(15秒以上止まっているならお得らしい)というのもあるが、車を運転してて「こりゃあ無駄だ」と思うことが他にもあるので、いくつか書いてみたい。
1.制限速度
信号もない見通しのいい道路でも、制限速度40キロというのがある。流れに乗るなら40キロじゃどうも無理だ。確か燃費は時速80キロの時が最もいいらしいから、できるだけそれに近い方が、排出される二酸化炭素も少ないはず。スピード出しても構わない所なら、制限速度はもっと上げてもいいのではないかと思う。
もちろん、制限速度60キロだとしても60キロ出さないといけないわけではない。「0~40」が「0~60」と、許容幅が広くなるだけのこと。急ぐ人が急げばいいだけの話。
とはいえ、後ろに何台も連ねてトロトロ走っているのを見ると、「何考えてんだろね」と思ってしまう。制限速度云々より、マナーの問題のような気もする。
2.右折時
進行方向右側のたとえばコンビニに入るため右折しようとしている車の後ろに、左横をすり抜けられない車がずらっと並ぶ時がある。センターラインへの寄りが足りないからだが、美川憲一じゃないけど「もっとはじっこ寄りなさいよ!」とでも言いたくなる。
こういう場合は、少しはみ出すくらいに、つまりセンターラインを跨ぐようにして待つのが正しいはず。そうすりゃ渋滞が起きることもない。
対向車が危ない? いやいや、自分の車線で2台通れるのなら、対向車線も余裕は充分あるはず。
3.一旦停止
停止線で一回止まり、ちょっと出て確認のためまた止まる、というようなことをその昔教習所でも教わったし、今もそう指導されているようだが、見通しのいい所なら、スピードを落とすだけでもいいのかもしれない。2回も止まるなんて、無駄無駄。
T字路のちょうど縦棒の下の方からやってきて、右折または左折しようとして右側からの車を待っている時、すぐそばまで来て左折ウィンカーを出されるとカチンと来る。そういう場合、ウィンカーは早めに出してほしいよね(中にはウィンカーも出さない奴もいるんだけど)。その間も、二酸化炭素は無駄に出されているわけだし。気が利かないというか。
4.踏切
都会では〈あかずの踏切〉みたいな所もあるようだが、遮断機下りてから列車来るまで、長過ぎるように思う。何かルールでもあるのかもしれないが、もちっと短くならないものか。
それと、遮断機上がっている時もほとんどの車が一旦停止して左右を確認しているけれども、99.9999%は列車来ないんじゃないだろうか。まず来ない列車のためにいちいち止まるなんて、技術の進歩した今、もうやめてもいいんじゃないかと。
「安全第一」という意見ごもっとも。ただ、クルマなり道路なりいうものは、そもそも早く目的地に移動するために作られたものだ。それが前提。安全第一であるならば、クルマになんか乗ることはできない。
制限速度など、ルールや法律で決まっていることなら、そのルールを変えればいいだけの話。
…とまあ、またまた小理屈を並べましたが、本気で地球温暖化を防止するのなら、思い切ってこれくらいのこともしないと。

〔イラストは、三井住友海上HPの「交通安全のとびら」より〕