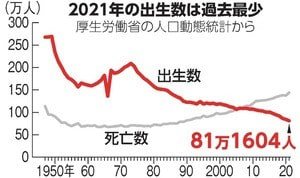坂村真民の言葉(6) 大切なのは…
|
坂村真民について (坂村真民記念館 プロフィールから抜粋) |

『今』
大切なのは
かつてでもなく
これからでもない
一呼吸
一呼吸の
今である
真民さんにとって大切なことは、過去でもなければ未来でもない。
『息をする』、その一呼吸が大切なのだと。
真民さんは機会あるごとに今を生きる一瞬の大切さを説いている。
「一途に生きる」ことがどんなに難しいことか、私たちは知っている。
ときに妥協し、自分をなぐさめ、自分に嘘をつく……。
筋の通った一本の道を歩ゆんでいきたい。
でも、人生行路は平坦な道ではない、山あり谷あり、紆余曲折の変化に富んだ道を
右により、左により、立ち止まり、時に後ろを振り返り、来し方道を眺める。
「雨にも負けて、風にも負ける」人生の辛い時期に遭遇しても、
遅い歩みではあるけれど、一歩を踏み出すことが次の一歩を繰り出すための
貴重な経験となることを私たちは知っている。
だから、「生きる」ということは、
真民さんのように「決然と今を生きる」ことも大切だが、
「ゆらりゆらりと揺れながら生きる」ことにも意味があるのではないかと思う。
良寛さんのように、風に吹かれるまま、世間のしがらみを捨て、
なかなか難しいことだが、気の向いた方向に歩いていくのも粋な生き方だと思う。
愛弟子とも愛しい人とも言われた貞心尼との出会いは、良寛和尚70歳のときで、
歳の差40歳といわれている。
それから4年、良寛の遅い春は終わりを告げる。
臨終の席に呼ばれた美貌の貞心尼に良寛は辞世の句を贈る。
裏を見せ表を見せて散る紅葉
私、良寛は貴女(貞心尼)の前で、風に散りゆくもみじのように裏も表てもなく、
すべての飾りを捨てて真心をつくすことができました。
良寛の童子のような素直な心を散りゆくもみじに例えて貞心尼に贈った歌です。
また、潔い人生訓の歌として現在も多くの人に愛されています。
さて、本題の真民さんは自分の生き方を次のような詞で表現しています。
『妥協』
決して妥協するな
妥協したらもうおしまい
一番恐ろしいのは
自己との妥協だ
つねに鞭うち
つねに叱咤し
つねに前進せよ
私は求道者でもなければ、人生の達人者でもない。
普通に生きて、悩んで、一歩進んで二歩下がる、
曲がりくねった道を踏み外す場合だってある。
幸せだとか、不幸せだとか考える時間もなく、
時々、真民さんの詞に励まされながら、
今日という時間を大切に生きてゆきたい。
(読書案内№184) (2020.6.19記)