
小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が日本中の怪異譚を集め、編集した「怪談」(KWAIDAN)。
これを名匠・小林正樹が構想10年、総製作費は当時の金額で凡そ4億円、撮影に1年余を掛け、4話オムニバス形式で映画化したものです。
飛行機の格納庫内に広大なセットを組み、そのシーンのほとんどのシーンをこのセットで撮影、ワン・カットごとの映像設計、色彩設計は完璧に作り込まれ、美しくも悲しく、そして恐ろしい怪異の世界を現出させています。
これほど完璧に作り込まれた日本映画は、近年ではまず観ることはできないでしょう。かつての日本映画の底力を感じさせてくれる一大傑作と断じて良い。
古い日本映画に興味がおありの方は、一度は御覧になることをおススメいたします。
********************
第1話【黒髪】
京の都に住む貧しい武士(三国連太郎)は立身出世のため、甲斐甲斐しく尽くしてくれていた妻(新珠美千代)と無理矢理離縁し、身分の高い武士の娘(渡辺美佐子)を新たに妻に迎えると、京を離れ新たな任地へ向かいます。
貧乏暮らしに嫌気がさしての行動でしたが、新しく迎えた妻は冷酷な性分で、三国さん演じる武士は、離縁した元妻が恋しくて仕方がなくなります。
それから数年の歳月が過ぎ、任期を終えた武士は、夜半に京に戻り、かつて元妻と暮らしていた屋敷を訪ねますが、門は朽ちて、家の周りは草が生い茂り、とても人が住んでいそうにはない。茫然としながら家の中に入る武士。
すると屋敷内の部屋の一角から明かりが漏れ、機を織る音が聞こえる。
もしや!と思い入ってみると、そこには以前と変わらぬ美しい元妻が!
再会の喜びに浸る武士。妻は以前と変わらず優しく迎え入れてくれます。
契りを結ぶ二人…。
翌朝、至福の表情で目覚めた武士は、部屋の様子が昨夜とは違っていることに愕然とします。ボロボロの廃屋の床に一人転がっていた自分の横には、元妻が…。
いや、まてよ?
妻の身体を揺り動かす武士。その正体を知り、武士は絶叫します。
それは骸でした。何年も前に息絶えた女の、白骨と化した骸に、かつてと変わらぬ美しい黒髪が張り付いている!
昨夜契った女はこの骸だったのか!?恐怖のあまり屋敷を逃げ出そうとする武士。若々しい武士の姿はまるで生気を奪われたかのように、見る見るうちに老いさらばえていく。
縺れる足で必死に屋敷を出ようとする武士。その武士の後を追うかのように、黒髪が蛇のようにうねってくる…。
元妻の怨念か、愛するが故の妄執か、それとも、武士の心に溜まっていた罪悪感が見せたまぼろしなのか…。
失って初めてわかる有難さ。
しかし、失ってからでは遅い…。
三国連太郎さんの一人芝居が秀逸!
********************
第2話【雪女】
18歳の少年、巳之吉(仲代達矢)は樵を生業としている。武蔵の国の人里離れた山中である夜吹雪に見舞われ、老人樵の茂作と共に小屋に避難します。
そこに雪女が現れ、茂作に白い息を吹きかけ凍死させます。雪女は巳之吉に近づくと、「お前は若いから見逃してやる。ただし、今日見たことは誰にも口外してはならぬ。もしも口外したときは殺す」そう告げると去って行きます。
それからおよそ一年後、巳之吉は夕刻に一人街道を行く若い娘と出会います。
娘はお雪(岸恵子)と名乗り、両親ともに亡くなってしまったので、江戸の親戚を頼って行くところだと言います。
もう時刻も遅いと、お雪を自宅へ招く巳之吉。同居している巳之吉の母も優しくお雪を迎え入れ、お雪はそのまま巳之吉の家に居付き、やがて巳之吉とお雪は結ばれます。
数年の歳月が経ち、巳之吉とお雪の間には4人の子がありました。いつまでも若々しいままのお雪の姿に、村人たちは不思議がります。
仲睦まじく暮らす夫婦。ある夜巳之吉はお雪に、昔出会ったことのある雪女の話をしてしまいます。
あれほど話すなといったのに…。
お雪の表情がみるみる変わります。いつの間にか周囲の光景も青く凍てつき、そこには雪女の姿が。
雪女=お雪は巳之吉を殺すことなく去って行きます。
残された巳之吉は一人号泣するのみ…。
全編セット撮影で、ホリゾント一杯にありえない色彩の空が描かれ、そこには目のようなものが、まるで巳之吉を監視するかのように浮かんでいる。
登場人物たちは最初から、異空間の中に閉じ込められているかのようです。
異空間の中で展開された、恐ろしくも哀しい物語。
********************
第3話【耳なし芳一の話】
壇ノ浦の赤間ヶ関、阿弥陀寺に住む琵琶法師、芳一(中村嘉葎雄)は平家物語を吟ずるのが得意でした。
或る夜、芳一のもとへ甲冑姿の武士(丹波哲郎)が訪ねてきます。武士は、さる高貴な御方の御前で平家物語を吟じて欲しいと頼み、芳一を連れ出します。以来、芳一は毎夜、その武士に連れられて出かけて行くようになります。
日に日に顔色が蒼褪め、疲弊していく芳一。寺の和尚(志村喬)の問いかけにも頑として語ろうとはしません。
激しい雷雨の吹き荒ぶ夜、芳一はまたも寺を出て行きます。寺男の矢作(田中邦衛)と松造(花沢徳衛)が後をつけ、そこで見たものは、
安徳天皇および平家の公達の墓の前で、人魂に囲まれながら平家物語を吟じている芳一の姿でした。
このままでは芳一が憑り殺されてしまう。和尚は一計を案じ、芳一の全身に経文を書き連ねます。
経文が書かれた芳一の身体は亡霊には見えない。芳一を連れて行くことは出来ないはず。
その夜またしても甲冑姿の武士が芳一を訪ねてきますが、芳一の姿が見えない。困惑する武士。
しかし和尚は見逃していました。芳一の身体で、一か所だけ経文を書いていないところがあったのです。
それは、両の耳でした。
平家の亡霊から見ると、空間に両耳だけが浮かんでいるようにみえたのです。
「儂が芳一を訪ねた印として、耳を持ち帰ろう」
亡霊は芳一の両耳を千切り取ると、去って行きました。
芳一の平家物語は評判を呼び、寺には高貴な方々が多数訪れるようになり、やがて芳一は大金持ちになりましたとさ。
冒頭で描かれる壇ノ浦の合戦では、平家の武将たちは皆一様に蒼白い死相を呈しており、安徳天皇や女性たちは皆一様に無表情。これはすでに、平家の者達は死者となっているということでしょう。
これは亡霊たちの止むことのない回想なのです。
海の色は通常ではありえない血のような真っ赤な海。その海の上を、ドライアイスのような霧が這うように漂う。やはりここもまた異空間なんですね。
数百年前の平家の怨念がいまだ漂う異郷の出来事なのです。
かつての栄光に拘り、その没落を嘆く我執、妄執、怨念。
それらの黒い想念が、壇ノ浦を異界へと捻じ曲げさせてしまったのでしょうか…。
恐ろしくもまた、哀しい物語。
********************
第4話【壺の中】
物語は明治時代の東京から始まります。全国の怪異譚を収集し、それを物語に仕上げている作家(滝沢修)がおりました。
その作家、結末がないままに終わっている或る怪異譚に、自分なりの結末を創作しようとしていたのです。
その怪異譚とは…。
江戸の頃。
中川佐渡守の家臣、関内(中村翫右衛門)は参勤の途上、茶碗に水を入れと飲もうとしたとき、茶碗の中に見知らぬ男(仲谷昇)の姿が浮かび上がることに気付きます。
何度水を捨て入れ替えても、やはり浮かびあがる男の顔。初めは気味悪がって茶碗を割った関内でしたが、喉の渇きに耐え切れず、男の顔が浮かんだままの水を飲み干してしまいます。
その夜、城内で宿直の番をする関内の前に、その謎の男が現れます。男は式部平内と名乗り、昼間、関内にひどい目にあわされたと詰ります。
関内は「狼藉者!」と大音声を上げ、式部に斬りかかりますが、式部は壁の中へ忽然と消え失せてしまう。
城内あげての捜索にもかかわらず、式部は発見されず、関内の正気を疑う同僚たち。
翌日の夜半、非番で休んでいた関内の屋敷へ、三人の侍(佐藤慶、天本英世、玉川伊佐男)が訪ねてきます。
三人の侍は式部平内の家中の者と名乗り、御貴殿に斬りかかられ大怪我を負ったので養生している。傷が癒えたらいずれ「御礼」に窺うという式部の伝言を伝えます。
逆上して三人に斬りかかる関内。だが三人は斬られても斬られてもまた現れる。
精神を蝕まれ、狂気の笑い声を上げながら槍を振り回し続ける関内…。
と、ここで話は唐突に、明治の東京へ戻ります。例の作家の部屋の中には誰もいない。
作家を訪ねてきた版元(中村雁治郎)に、作家の家のおかみさん(杉村春子)は「出かけた様子はないんですけどねえ」と、作家がいないことを訝しがります。
家の中を見て回るおかみさん。台所の水を溜めた壺にふと目をやり、その途端、叫び声をあげて逃げ出します。
何事かと台所に目をやる版元。すると、水を溜めた壺の中に、
蒼白い顔をした作家の姿が浮かび上がり
おいでおいでをしている…。
作家の机の前に転がった茶碗を、カメラは映し出します。
どうやら、この茶碗で、
水を飲み干した、らしい…。
こちらはロケーションが多様され、映像は堂々たる時代劇の様式を満たしています。
その時代劇の「日常」の風景の中に、非日常の怪異が侵入してくる恐怖。
日常の中で、意味も理由も分からないまま、怪異は伝播して行く。
これから水を飲む時は、コップの中に「誰か」の姿が浮かび上がっていないか、
よおっく、確かめて下さいね…。
********************
『怪談』
制作 若槻繁
原作 小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)
脚本 水木洋子
撮影 宮島義勇
音楽音響 武満徹
監督 小林正樹
出演
【黒髪】
三国連太郎
渡辺美佐子
新珠美千代
【雪女】
仲代達矢
菅井きん
千石規子
野村昭子
浜村淳
浜田寅彦
岸恵子
【耳なし芳一の話】
中村嘉葎雄
田中邦衛
花沢徳衛
友竹正則
北村和夫
中村敦夫
中谷一郎
丹波哲郎
志村喬
【壺の中】
中村翫右衛門
田崎潤
小林昭二
青木義郎
織本順吉
佐藤慶
天本英世
玉川伊佐男
奈良岡朋子
杉村春子
宮口精二
中村雁治郎
仲谷昇
滝沢修
文芸プロダクションにんじんくらぶ作品
昭和40年 東宝配給












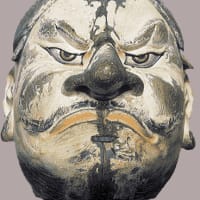







有り得る。