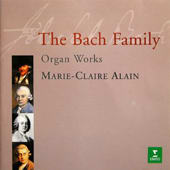
The Bach Family Organ Works
Erato 0630-17073-2
演奏:Marie-Claire Alain (Organ)
隆盛を誇ったバロック時代のオルガン音楽は、18世紀中頃にはその勢いを失っていった。教会におけるミサや礼拝における役割は、その後も変わることなく機能していたが、音楽の分野としては、ロマン主義時代になるまで、表舞台から消えていた。この様な状況は、バッハの息子達や弟子達の活動にも影響を与えていた。バッハの弟子達の中では、ヨハン・ルートヴィヒ・クレープスが多くの作品を残している。
今回紹介するCDは、この様なオルガン音楽が衰退する中で、バッハの息子達が残したオルガンのための作品を紹介するものである。
ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハ(Wilhelm Friedemann Bach, 1710 – 1784)は、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの長男として、ヴァイマールで生まれた。ゼバスティアン・バッハがアンハルト=ケーテン候の宮廷楽長に就任した1717年にはケーテンに移り、当地でラテン語学校に入学し、1723年にライプツィヒのトーマス学校に編入、1729年にはライプツィヒ大学の法学生となった。1733年にはドレースデンのソフィア教会のオルガニストに採用され、1746年にハレのマリア教会の音楽監督、オルガニストに就任、1764年までその地位にあった。その後フリーデマンは定職に就くことなく、1770年にはブラウンシュヴァイク、1774年にはベルリンに移り、演奏家、教師、作曲家として生計を立てていた。ベルリンでは、フリートリヒ大王の妹、アンナ・アマリア姫の庇護を受けていたが、1778年か1779年にはその援助を失い、1784年に貧窮の内に死亡した。フリーデマンはオルガンの名手として、時には父親を越える存在と評されることもあった。しかし現存する曲は僅かで、それらからはかつての名声を窺い知ることは出来ない。フリーデマンの作品は、1913年にマルティン・ファルクによって作品目録が作成されており、カンタータやミサ、シンフォニーや協奏曲、鍵盤楽器のための作品やオルガン曲など133曲が収録されているが、1990年代に多くの作品が発見され、今では完全な作品一覧とは言えない*。このCDに収録されているのは、プロイセンのアンナ・アマリア姫に献呈された8曲のフーガの内の1曲ヘ短調(F 31, Nr. 8)とコラール「来たれ異邦人の救い主(Nun komme der Heiden Hailand)」(F 38, 1a)、「キリスト、あなたは日であり光である(Christe, der du bist Tag und Licht)」(F 38, 1b)、「イエス、我が喜び(Jesu, meine Freude)」(F 38, 1c)および「我らキリストの徒(Wir Christenleut)」(F 38, 1f)である。「フーガヘ短調」はチェンバロのための作品と考えられている。ヴィルヘルム・フリーデマンの作品は、フーガのような自由曲の場合も、コラールの場合も、平易で分かりやすい作品になっている。コラールでは、楽節ごとにはっきりとした区切りがあり、聴くものに丁寧に分かりやすくコラールの旋律を示して行く。
カール・フィリップ・エマーヌエル・バッハ(Carl Philipp Emanuel Bach, 1714 – 1788)もヴァイマールで生まれ、ライプツィヒのトーマス学校で学び、1731年にライプツィヒ大学の法学生、1734年にフランクフルト・アン・デア・オーデルのフィアドリーナ大学(Universität Viadrina)に転校、1738年に修了し、音楽家を志す。そして1740年に、同年に即位するプロイセンのフリートリヒ大王の宮廷チェンバロ奏者に任命される。フィリップ・エマーヌエルは、この時点ですでにヨーロッパで最も有名な鍵盤楽器奏者であった。宮廷では、フルートの名手ヨハン・ヨアヒム・クヴァンツやヨハン・ゴットリープ(Johann Gottlieb Graun, 1703 – 1771)とカール・ハインリヒ(Carl Heinrich Graun, 1704 – 1759)のグラウン兄弟らとともに、フリートリヒ大王の宮廷楽団に属していた。1768年にゲオルク・フィリップ・テレマンが死亡した後のハンブルク市の音楽監督、ヨハネウム・ギムナージウムのカントールに就任、1788年に死亡するまでその地位にあった。フィリップ・エマーヌエルの作品は、鍵盤楽器のための作品を始め、フルートのための協奏曲とソナタ、室内楽曲、多くの歌曲やアリア、カンタータなど多岐にわたっており、1905年のアルフレッド・ウォトキン(Alfred Wotquenne, 1867 – 1939)による作品目録(Wq番号)と1989年のユージン・ヘルムによるより体系化された作品目録(H番号)が存在する**。このCDに収録されているのは、「4声のファンタージアとフーガハ短調(Wq 119 Nr. 7, H 103)、「アダージョニ短調」(作品番号表記なし)、「前奏曲ニ長調」(Wq 70 Nr. 7, H 107)、「フーガニ短調」( 作品番号表記なし)、「4声のフーガ変ホ長調」(Wq 119, H 102)の5曲と後掲の「B. A. C. H. によるフーガ」の6曲である。フィリップ・エマーヌエルの作品は、フーガの場合は別として、全体としてみると、対位法の論理的展開によって曲が成り立っていると言うよりも、情緒的表現にもとづいた、多感様式の色彩が濃い。
ヨハン・クリストフ・フリートリヒ・バッハ(Johann Christoph Friedrich Bach, 1732 – 1795)は、トーマス学校、ライプツィヒ大学で学んだ後、1750年にビュッケブルクのシャウムブルク=リッペ伯爵ヴィルヘルムの宮廷楽士に採用され、1759年には宮廷楽長に任命され、生涯その地位にあった。そのため彼は「ビュッケブルクのバッハ」と呼ばれている。1778年には、息子のヴィルヘルム・フリートリヒ・エルンストと共にハンブルクのカール・フィリップ・エマーヌエル・バッハを訪ねた後、ロンドンのヨハン・クリスティアン・バッハを訪ね、その演奏会を聴くと共に、グルックやモーツァルトの作品を知り、その影響を受けた。 クリストフ・フリートリヒのビュッケブルクの宮廷における活動は、1782年ヨハン・ニコラウス・フォルケルによってドイツのオーケストラの第4位と評価されるほどの名声を得た。クリストフ・フリートリヒは、鍵盤楽器のための作品や室内楽の他に、協奏曲や交響曲、歌曲、オラトーリオ、オペラ等を作曲したが、永らく評価されることがなかった。第一次世界大戦後になって徐々にその評価が行われるようになり、最近ようやくその作品や手稿の状況が把握されるようになっている。
ヨハン・クリスティアン・バッハ(Johann Christian Bach, 1735 – 1782)は、ヨハン・ゼバスティアン・バッハとアンナ・マグダレーナの間の一番末の息子で、15歳の時に父親を亡くし、カール・フィリップ・エマーヌエル・バッハの許に引き取られ、鍵盤楽器演奏の教えを受けた。1754年にイタリアを訪れ、ミラノでアゴスティーノ・リッタ伯爵に雇われ、その援助でジオヴァンニ・バッティスタ・マルティーニ神父に対位法の教育を受けた。その頃より伯爵の宮廷楽団のための器楽曲や教会音楽の作曲を始め、1760年にはミラノ大聖堂のオルガニストに就任した。教会音楽と共にオペラの作曲も始め、トリノやナポリの劇場のためにもオペラを作曲した。ヨハン・クリスティアンの名声を聞いたイギリスのゾフィー・シャルロッテ王妃の招きで1762年の夏にロンドンを訪れ、イギリスでの活動を始めた。ロンドンに於いては12のオペラを作曲、上演したが、その評判はまちまちであった。その一方で演奏会活動は大成功であった。とくにヨハン・ゼバスティアン・バッハがアンハルト=ケーテンの宮廷楽長の時に宮廷楽団員であったクリスティアン・フェルディナント・アーベルの息子であるカール・フリートリヒ・アーベル(Carl Friedrich Abel, 1723 – 1787)と共に催した「バッハ・アーベル演奏会」は、1764年2月29日から1781年5月9日まで17年間にわたってロンドンで最も評判の高い演奏会であった。1764年と1765年にはレオポルト・モーツァルトとヴォルフガンク・アマデウス・モーツァルトがロンドンを訪れ、ヨハン・クリスティアンに会い、1764年4月には8歳のアマデウス・モーツァルトと一緒に演奏を行った。この出会いによってアマデウス・モーツァルトはヨハン・クリスティアンの音楽に影響を受けた。1780年代になると、ヨハン・クリスティアンの名声に陰りが見えはじめ、弟子にピアノの生徒を取られるなど、経済的にも困窮するようになった。そして1782年1月2日にパディントンで死亡した。ゾフィー・シャルロッテ王妃は、葬儀の費用を負担し、未亡人に生涯の年金とイタリアへ帰郷する旅費も支払った。ヨハン・クリスティアンの作品は、鍵盤楽器のための作品や室内楽、交響曲や協奏曲、オペラや劇付随音楽、アリアや歌曲など多岐にわたっており、いわゆるギャラント様式に属するものと言うことが出来る。
今回紹介するCDに於いて、ヨハン・クリストフ・フリートリヒ・バッハとヨハン・クリスティアン・バッハの作品は、カール・フィリップ・エマーヌエル・バッハの「B. A. C. H. によるフーガ」と同様、伝統ある音楽一家の名字であるBACHにもとづくフーガが収録されている。3人それぞれの特徴が現れており、クリストフ・フリートリヒの曲は、H.C.F.B.B.A.C.H.(Hans [Johann] Christoph Friedrich Bückeburger BACH)の8つの音符にもとづく簡潔な小フーガである。ヨハン・クリスティアンの「B. A. C. H.にもとづくフーガ」は、これら3曲の内で最も入念に構築されたフーガである。
今回紹介するCDは、マリー=クレール・アランの演奏によるエラート盤である。マリー=クレール・アランは1926年フランス、パリ生まれのオルガニストで、父親、二人の兄もオルガニストである。パリ・コンセルヴァトアールでマルセル・デュプレに学び、特に多数の録音を行ったことで知られ、バッハのオルガン作品全曲は3度も録音している。
このCDでアランが演奏しているオルガンは、プロイセンのフリートリヒ大王の妹、アンナ・アマリア姫が所有していたものである。アマリア姫が1755年12月8日に、親戚のヴィルヘルミーネ姫宛の手紙で、その日にこのオルガンを初めて弾いたと書いている。このオルガンの製作者は分かっていない。1787年にアマリア姫が死亡した後、オルガンはベルリン=ブーフの城の教会に移設され、これを1934年に2人の音楽学者が発見、第二次大戦中は、解体されて保管されていた。1960年にポツダムのアレクザンダー・シューケ社によって、ベルリン=カールスホルストの教会に復元された。ケースやコンソール、鍵盤、マニュアルの風箱、そしてパイプの大半はオリジナルの状態で、いくつかのレギスターのパイプや他のレギスターのパイプの一部は新たに復元された***。このオルガンは、2段鍵盤とペダル、22にレギスターを備え、ピッチは、もとはカンマートーンであったが、1960年の復元後は a’ = 440 Hz、調律はキルンベルガーIII/2と記されている****。録音は1996年5月20日から24日に行われた。
このCDを含め、マリー=クレール・アランの演奏によるCDは、現在Warner Classics & Jazzのサイトにも、日本のワーナー・ミュージック・ジャパンのサイトにも掲載されていない。しかしCDショップには、バッハのオルガン曲全曲など、いくつかのCDはまだ在庫があるようで、今回紹介するCDも購入できる可能性はある。
発売元:Warner Classics & Jazz
Falck, Martin. Wilhelm Friedemann Bach; Sein Leben und seine Werke, mit thematischem Verzeichnis seiner Kompositionen und zwei Bildern. Leipzig: C. F. Kahnt, 1919: Klassikaの作品目録を参照
** Alfred Wotquenne, “Catalogue thématique des œuvres de Charles Philippe Emmanuel Bach (1714-1788)”. Breitkopf & Härtel, Leipzig 1905: E. Eugene Helms, “Thematic Catalogue of the Works of Carl Philipp Emanuel Bach”. Yale University Press, New Heven 1989:Klasikaの作品目録を参照
*** このオルガンについては“Amalien Orgel”と言うサイトで詳しく説明されている。1960年の再建後、時と共に問題が生じ、2009年からドレースデンのオルガン工房ヴェグシュナイダーによって解体修理が行われ、2010年12月に修復が完了した。
**** ヨハン・フィリップ・キルンベルガーによる調律の提案は、1766年のいわゆるKirnberger Iと、1771年に「純正作曲技法(Kunst des reinen Satzes)」で発表したいわゆるKirnberger IIが公にされた音律であるが、Kirnberger IIIは、1779年頃にヨハン・ニコラウス・フォルケルに宛てた書簡の中で言及されたもので、当時は公表されず、音律として取り上げられるようになったのは、近年のことである。なお、Kirnberger IIIの2と言う表記は、他では見当たらず、どのような違いがあるのかは不明である。

クラシック音楽鑑賞をテーマとするブログを、ランキング形式で紹介するサイト。
興味ある人はこのアイコンをクリックしてください。

「音楽広場」という音楽関係のブログのランキングサイトへのリンクです。興味のある方は、このアイコンをクリックして下さい。
| Trackback ( 0 )
|
|