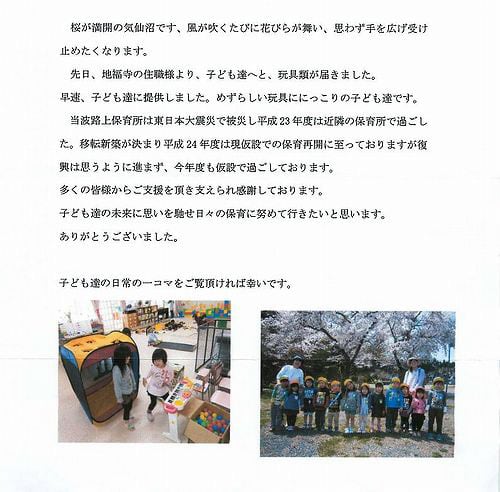【8月2日(金)】
翌朝、ホテルでは朝食代わりに おにぎりを用意してくださいまして、ちょっと疲れもたまっていたので朝10時にチェックアウト。前日ちょっと顔を出した立町ふれあい商店街にご挨拶し、また石巻駅前の観光協会さんにもご挨拶して、これにて帰京。。と行くところですが、ぬえには どうしても気になる場所が。。
それは女川町の野球場仮設にお住まいのミネおばあちゃん。
今から1年前、昨年の6月にはじめてこちらの仮設で能の上演をさせて頂いてから、思わずもミネさんから感謝のお手紙が ぬえの許に届きまして、それから交流が始まりました。またもう一人 英子さんという、やはり野球場仮設にお住まいの住民さんのご協力も頂き、この後プロジェクトとしても女川町で上演させて頂くようになり、また ぬえは家族でも活動させて頂いたこともあります。活動の場も「コンテナ村」「きぼうのかね商店街」と仮設商店街にも広がっていきました。
女川町に行くたびにミネさんに会いに行きます。息子さんとお嫁さん、そしてまだ幼いお孫さんと一緒に仮設にお住まいのミネおばあちゃん。そうだ、女川町で活動がない場合でも、石巻で時間が余ったときは おばあちゃんに会いに行ったこともあったっけ。
そんなわけで今回も帰京の前に女川町に立ち寄って ミネおばあちゃんに会いに行くことにしました。東京都は反対方面ですけどね。
。。とはいえ、ぬえたちも次の公演に向けて準備を進める作業も怠ってはいませんで、この時も女川町には事前に上演のアイデアをお伝えして、それにふさわしい会場を探して頂いていました。そこでこの日も、まず石巻から電話をして、女川町の社会福祉協議会の担当の方にお会いして頂く約束を取り付け、まずはそこに向かうことに。
女川の社協は、万石浦のそばから女川地域医療センター(旧・町立病院)のお隣に引っ越しされたとのこと。ここにお邪魔して、担当の方としばし上演についての相談をさせて頂く。。つもりでしたが、いや、これが大盛り上がりになりまして、かなり長時間。。30~40分もお話し。。というか談笑させて頂き、お祭りなど町の行事への参加まで話題にのぼりました。ぬえも次回の活動について、女川町での実現に確信を持つことができました。今年の秋頃に実施にこぎ着けるのを、とりあえずの目標にしようと考えています。
社協をおいとまして、高台にある医療センターの駐車場から女川町の旧中心部を見下ろしてみると。。

横転した江島共済会館ビルはそのままでしたが、それまで更地だった沿岸の地域は大掛かりな工事が行われていました。コンクリートブロックも並べてあったので、まさかマリンパル女川の再建が始まったのか? と思いましたが、実際には地盤沈下した土地のかさ上げ工事のようです。
高台から下りて近づいてみると。。江島共済会館ビルのそばに祭壇がありました。これは七十七銀行女川支店の犠牲者に捧げられたもの。同支店では大地震の直後に支店長の指示によって行員が高台ではなく2階建ての支店ビル屋上に避難することになり、指示に従った13名の行員・スタッフのうち津波によって4名が死亡、支店長を含む8名が行方不明という大惨事となってしまい、この避難の経緯の是非をめぐって遺族が銀行を相手取って裁判が行われています。。


江島共済会館ビルとともに現在も横倒しのまま残されている女川サプリメントの建物。いつの間にか被害の状況を記した説明板が立てられていました。

これを読むと、建物の中にいまだに車が残されている、とのこと。。知りませんでした。よく中を見てみると。。なるほど。。わかりますか? 建物と一緒に横倒しになったピンク色の小型乗用車が部屋いっぱいになって残されていました。。


この2つの建物と、女川交番の3つが、女川町では「震災遺構」として保存するかどうかの議論が続いています。気仙沼の第十八共徳丸、志津川の防災庁舎ビル、石巻の門脇小学校。。どれも保存の是非が議論され、結論が出たところもあり、まだまだ決着に至らないものもあり。。ぬえはこの女川町で、高台から江島共済会館ビルを見下ろした時、これは残すべきではない、と思い、その気持ちはいまも変わらないのですが、一方 震災の被害が風化してゆく現状や、すべての「遺構」がなくなったら、人がやって来なくなり、それは地域の再生への活力を失うことになる、という意見もあって、現実にそうなってしまった場所も見てしまった ぬえは心が揺れています。
こちらは残されている3つめの建物、女川交番。

このあたり、道路も大規模な工事が進行中で、現在はこの交番の周囲は立ち入り禁止となって近づけない状態になっていました。前述の英子さんは、この交番の まさにお隣で釣具店を経営されていた方。よくまあご無事だったと思いますが、高名なご主人は震災の犠牲となってしまわれました。英子さんの釣具店はいま、仮設商店街の中で営業を再開し、また英子さんもご主人の遺志を継いで活動されたり、ご主人の業績をまとめる作業で忙しくしておられます。それからこの流された交番も、現在は仮設商店街の中に「仮設の交番」として再開しています。
翌朝、ホテルでは朝食代わりに おにぎりを用意してくださいまして、ちょっと疲れもたまっていたので朝10時にチェックアウト。前日ちょっと顔を出した立町ふれあい商店街にご挨拶し、また石巻駅前の観光協会さんにもご挨拶して、これにて帰京。。と行くところですが、ぬえには どうしても気になる場所が。。
それは女川町の野球場仮設にお住まいのミネおばあちゃん。
今から1年前、昨年の6月にはじめてこちらの仮設で能の上演をさせて頂いてから、思わずもミネさんから感謝のお手紙が ぬえの許に届きまして、それから交流が始まりました。またもう一人 英子さんという、やはり野球場仮設にお住まいの住民さんのご協力も頂き、この後プロジェクトとしても女川町で上演させて頂くようになり、また ぬえは家族でも活動させて頂いたこともあります。活動の場も「コンテナ村」「きぼうのかね商店街」と仮設商店街にも広がっていきました。
女川町に行くたびにミネさんに会いに行きます。息子さんとお嫁さん、そしてまだ幼いお孫さんと一緒に仮設にお住まいのミネおばあちゃん。そうだ、女川町で活動がない場合でも、石巻で時間が余ったときは おばあちゃんに会いに行ったこともあったっけ。
そんなわけで今回も帰京の前に女川町に立ち寄って ミネおばあちゃんに会いに行くことにしました。東京都は反対方面ですけどね。
。。とはいえ、ぬえたちも次の公演に向けて準備を進める作業も怠ってはいませんで、この時も女川町には事前に上演のアイデアをお伝えして、それにふさわしい会場を探して頂いていました。そこでこの日も、まず石巻から電話をして、女川町の社会福祉協議会の担当の方にお会いして頂く約束を取り付け、まずはそこに向かうことに。
女川の社協は、万石浦のそばから女川地域医療センター(旧・町立病院)のお隣に引っ越しされたとのこと。ここにお邪魔して、担当の方としばし上演についての相談をさせて頂く。。つもりでしたが、いや、これが大盛り上がりになりまして、かなり長時間。。30~40分もお話し。。というか談笑させて頂き、お祭りなど町の行事への参加まで話題にのぼりました。ぬえも次回の活動について、女川町での実現に確信を持つことができました。今年の秋頃に実施にこぎ着けるのを、とりあえずの目標にしようと考えています。
社協をおいとまして、高台にある医療センターの駐車場から女川町の旧中心部を見下ろしてみると。。

横転した江島共済会館ビルはそのままでしたが、それまで更地だった沿岸の地域は大掛かりな工事が行われていました。コンクリートブロックも並べてあったので、まさかマリンパル女川の再建が始まったのか? と思いましたが、実際には地盤沈下した土地のかさ上げ工事のようです。
高台から下りて近づいてみると。。江島共済会館ビルのそばに祭壇がありました。これは七十七銀行女川支店の犠牲者に捧げられたもの。同支店では大地震の直後に支店長の指示によって行員が高台ではなく2階建ての支店ビル屋上に避難することになり、指示に従った13名の行員・スタッフのうち津波によって4名が死亡、支店長を含む8名が行方不明という大惨事となってしまい、この避難の経緯の是非をめぐって遺族が銀行を相手取って裁判が行われています。。


江島共済会館ビルとともに現在も横倒しのまま残されている女川サプリメントの建物。いつの間にか被害の状況を記した説明板が立てられていました。

これを読むと、建物の中にいまだに車が残されている、とのこと。。知りませんでした。よく中を見てみると。。なるほど。。わかりますか? 建物と一緒に横倒しになったピンク色の小型乗用車が部屋いっぱいになって残されていました。。


この2つの建物と、女川交番の3つが、女川町では「震災遺構」として保存するかどうかの議論が続いています。気仙沼の第十八共徳丸、志津川の防災庁舎ビル、石巻の門脇小学校。。どれも保存の是非が議論され、結論が出たところもあり、まだまだ決着に至らないものもあり。。ぬえはこの女川町で、高台から江島共済会館ビルを見下ろした時、これは残すべきではない、と思い、その気持ちはいまも変わらないのですが、一方 震災の被害が風化してゆく現状や、すべての「遺構」がなくなったら、人がやって来なくなり、それは地域の再生への活力を失うことになる、という意見もあって、現実にそうなってしまった場所も見てしまった ぬえは心が揺れています。
こちらは残されている3つめの建物、女川交番。

このあたり、道路も大規模な工事が進行中で、現在はこの交番の周囲は立ち入り禁止となって近づけない状態になっていました。前述の英子さんは、この交番の まさにお隣で釣具店を経営されていた方。よくまあご無事だったと思いますが、高名なご主人は震災の犠牲となってしまわれました。英子さんの釣具店はいま、仮設商店街の中で営業を再開し、また英子さんもご主人の遺志を継いで活動されたり、ご主人の業績をまとめる作業で忙しくしておられます。それからこの流された交番も、現在は仮設商店街の中に「仮設の交番」として再開しています。