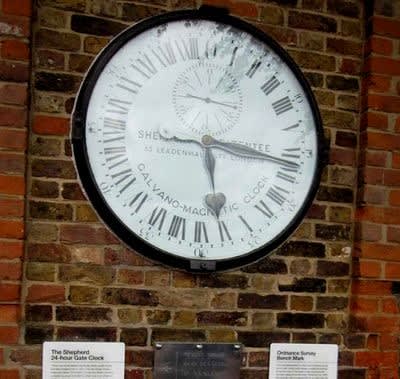平成は30年間続いたが、元年は世界50社の企業ランキングに 日本企業が37社を占めていたのが 30年後の今トヨタ一社だけになってしまったそうだ。
昭和の後期の日本は、米国マンハッタンで買ったお土産の裏を帰ってから見ると「made in Japan」、NYタイムズスケア交差点の見上げる広告は全部が日本企業でその壮観さに誇らしく思ったことがある。しかし当時は1ドル=360円で何とコーラを一本しか買えない価値しかなかったのを不思議に思った。
日本人は、酷い低賃金で休日返上で働き努力し 世界をあっと言わせる数々の成果で世界二位の経済大国を勝ち取ったのも結局は 日本人の低賃金が生み出しただったのかと気が付いたのを覚えている。
日本経済も生活も豊かになると、多くの人が夢にまで見た自家用車を持つことも出来たが 更にその後の平成では 少しづつ国内の日用品が低価格の「China、India、Vietnam」製となり 経済の主流は日本から完全にアジアに移ってしまった。
日本人の所得が上がると同手法で、アジアの低賃金の国々が台頭して負けたのだが ローマ帝国の様に絵に描いた様な 勝者の優越感と過信・油断があったからだろう。
日本経済は急速に縮少化となったが 金融緩和政策で生活維持は出来ていても 今や世界最大の借金を抱えた国になり現在に至り将来に不安を抱えてしまった。
先日の本を読むと、平成は平和で変化の少ない30年だと思っていたが 今はそうは思えなくなる。人には宿命本能で、生まれた宿命で人や国・宗教や文化の行方は決まると言う思い込みがあるそうだ。確かに人間は昔から変化のない環境で暮らすことを選ぶので 違う環境に自分を次々と合せるより 同じ環境・同じ集団で暮らした方が生き残りには適していると 思い込む傾向がある。言葉も文化も違う、世界化した平成時代にあって国民も企業も政治も正にそれだったのかも知れない。
それにしても、車を競って買い替えた時代から今は 車はいらないと言う貧乏な若者が増えているし 逆に富裕層では 高い国産の食材・衣料品の要望が戻ってきて国産品質を改めて見直されている。世界を経験して国内もゆっくりとは変化しているが、長い平和と蓄財があるために変化を抑えたり緩和する方向に舵取りをしたことも世界の潮流を甘く見る事になり 覇者の驕りもあって気が付いた時には 国内企業は無くなり経済も空っぽになってしまった。
日本人が、ワープロが便利・電子ゲームブームなどで盛り上がっていた時代に 欧米ではネット検索・ネット通販の新企業が登場し 後進国と言われていた国は ネット情報で西欧の技術を取り込み 低賃金を武器に国の経済を 日本の急成長時代よりも短期間で 日本を追い抜き 西欧までも抜き去る経済成長を達成している。
中国インドが、総人口と経済力で欧米を抜くと言われ、次にはアフリカ・中近東なども目覚ましい経済発展で追い上げているのでアジア勢に取って代わるだろうと言う長期予測もある。平成の次は「モノづくり」で国を再生・・と言うが、世にないものを作り出すのなら意味はあると思う。
日本人の熱中症と辛抱強さは、環境変化の激しい時代には弱点となったようだし 人の知識にも賞味期限はあると思わないと変化に対応できないのだ。
教育の知識は不変と思っていたが、これからは変わることをしないと 何が起きるのか判らない難しい世の中なので 大きな司令塔が欠かせない。
昭和の後期の日本は、米国マンハッタンで買ったお土産の裏を帰ってから見ると「made in Japan」、NYタイムズスケア交差点の見上げる広告は全部が日本企業でその壮観さに誇らしく思ったことがある。しかし当時は1ドル=360円で何とコーラを一本しか買えない価値しかなかったのを不思議に思った。
日本人は、酷い低賃金で休日返上で働き努力し 世界をあっと言わせる数々の成果で世界二位の経済大国を勝ち取ったのも結局は 日本人の低賃金が生み出しただったのかと気が付いたのを覚えている。
日本経済も生活も豊かになると、多くの人が夢にまで見た自家用車を持つことも出来たが 更にその後の平成では 少しづつ国内の日用品が低価格の「China、India、Vietnam」製となり 経済の主流は日本から完全にアジアに移ってしまった。
日本人の所得が上がると同手法で、アジアの低賃金の国々が台頭して負けたのだが ローマ帝国の様に絵に描いた様な 勝者の優越感と過信・油断があったからだろう。
日本経済は急速に縮少化となったが 金融緩和政策で生活維持は出来ていても 今や世界最大の借金を抱えた国になり現在に至り将来に不安を抱えてしまった。
先日の本を読むと、平成は平和で変化の少ない30年だと思っていたが 今はそうは思えなくなる。人には宿命本能で、生まれた宿命で人や国・宗教や文化の行方は決まると言う思い込みがあるそうだ。確かに人間は昔から変化のない環境で暮らすことを選ぶので 違う環境に自分を次々と合せるより 同じ環境・同じ集団で暮らした方が生き残りには適していると 思い込む傾向がある。言葉も文化も違う、世界化した平成時代にあって国民も企業も政治も正にそれだったのかも知れない。
それにしても、車を競って買い替えた時代から今は 車はいらないと言う貧乏な若者が増えているし 逆に富裕層では 高い国産の食材・衣料品の要望が戻ってきて国産品質を改めて見直されている。世界を経験して国内もゆっくりとは変化しているが、長い平和と蓄財があるために変化を抑えたり緩和する方向に舵取りをしたことも世界の潮流を甘く見る事になり 覇者の驕りもあって気が付いた時には 国内企業は無くなり経済も空っぽになってしまった。
日本人が、ワープロが便利・電子ゲームブームなどで盛り上がっていた時代に 欧米ではネット検索・ネット通販の新企業が登場し 後進国と言われていた国は ネット情報で西欧の技術を取り込み 低賃金を武器に国の経済を 日本の急成長時代よりも短期間で 日本を追い抜き 西欧までも抜き去る経済成長を達成している。
中国インドが、総人口と経済力で欧米を抜くと言われ、次にはアフリカ・中近東なども目覚ましい経済発展で追い上げているのでアジア勢に取って代わるだろうと言う長期予測もある。平成の次は「モノづくり」で国を再生・・と言うが、世にないものを作り出すのなら意味はあると思う。
日本人の熱中症と辛抱強さは、環境変化の激しい時代には弱点となったようだし 人の知識にも賞味期限はあると思わないと変化に対応できないのだ。
教育の知識は不変と思っていたが、これからは変わることをしないと 何が起きるのか判らない難しい世の中なので 大きな司令塔が欠かせない。