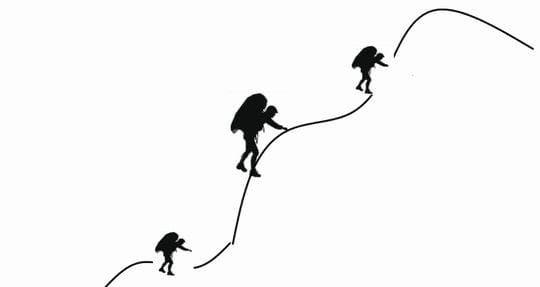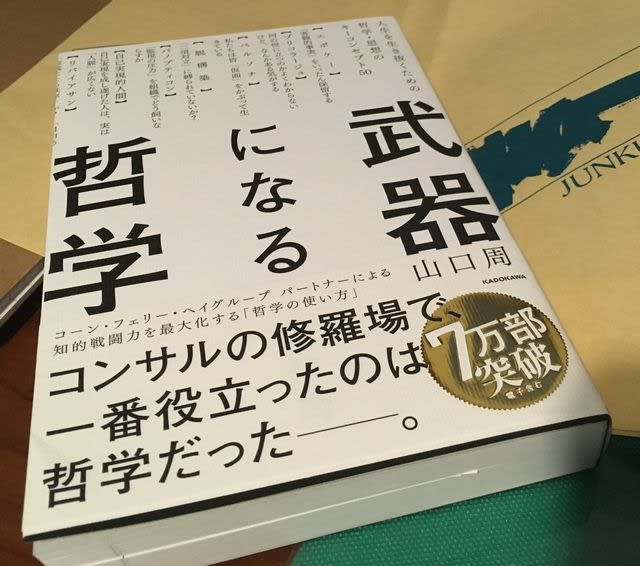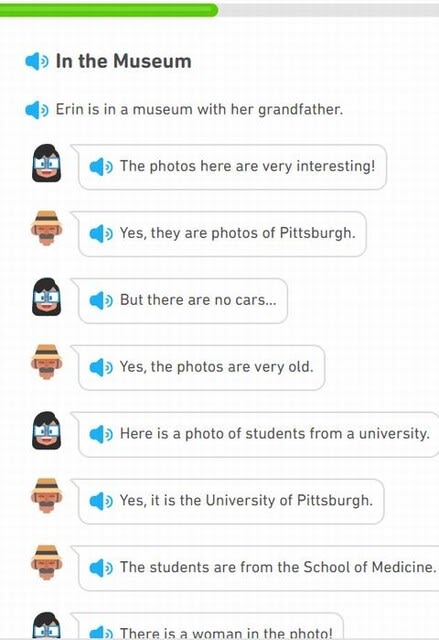この本の人生100年の視点は面白い、確かにこの国も ネット社会でグローバル化し 身近な食材でさえ輸入品で埋もれているのに 多くは未だ 終身雇用とか企業年金がある時代の延長だと考えている。現在、企業寿命は10-15年らしいから 仕事先の転職は避けられず IT化した仕事には学歴も知識も 今までの経験も役に立たない。激しい技術変化で、次々と小さな企業が 集合体になり大きな企業を乗り越え 巨大産業もモンスターの様に絶滅しつつある。
内容の中心に1950・1970・1990年に生まれた標準的な人生を題材に その時代どんな生き方と選択肢があってどのようになったのかを「仕事・家庭・夫婦のあり方」を仮想して書かれている。1950年生まれは私に近いのだが「学業・仕事・老後」の人生3ステージに硬直化し 老後が伸びたと言う暮らしはその通りだ。70年は企業寿命が短くなり 勤務先も仕事も変わる環境になればスキルを磨く勉強が必須で仕事も選ばないと生きれない・・これは現在の働き盛り世代の実情だろう。マルチな仕事を持って働くことを「ポートフォリオ・ワーク」と言うそうだ。
社会に出ると言うと、先ず 経済力となり有形資産(お金)を稼ぐ 職探しをしてきたが 100年人生を意識するなら その前に「何がしたいのか、自分の適性は」を考えた生涯関われる仕事と 支え合う友人をいくつか持つマルチワークな体制、協調できる良いパートナーを慎重に選択する必要がある。欧米の大学には、卒業前後にGap yearと言う 「エクスプローラー」と呼ぶ期間で 例えば 多くの職を体験し見て、人に出会い 出来れば世界を回り 自身の無形資産となる スキル・経験・人脈の基礎作りをして職に就くそうだが この国にはそれが無いのかも。
若さは活力だが、これも変えられる。 大昔の60歳と現60歳を比べて見れば歴然なように 、新しい事に意欲的で、創造的で運動と食生活・健康に気を付ければ 人の活力も生命に合わせて伸びるのだ。仕事も若さも、定年60歳の様な過去の年齢で止まるなら100年人生が 暗くてつまらない 長寿になってしまう。
昔、欧州からの実習生を毎年夏に10か程 ホームステイしていた時期がある。 5か国10人位の大学生だったが 彼らはGap yearと言う入学時・在学中・就職前の休暇を利用して日本企業実習に来ていた。当時、政府補助もあり みんな夏休みは世界中の国を自転車で30-50か国周ったと話してくれた、言葉もバイリンガルで日本語も加えていたが 30年前から欧州大学生は マルチ思考を学ぶ態度に感心させられた。
今の新しい世代は、生まれた環境でなく100年生きることを意識しそれを前提に人生の計画を立てる最初の世代なのだと言う。未来は多様な国籍と文化とクラウドな仕事になるだろうが 国境とか政治はどぅなって行くのだろうか・・