【9月第4週:ゴッドハンド輝 第426話 手にしたもの】
http://www.tsphinx.net/manken/wek1/wek10480.html#658
【漫研】
http://www.tsphinx.net/manken/

ぬうう…答えがキレイ過ぎてぐうの音も出ないよ?(´・ω・`)
『ゴッドハンド輝』(作・山本航暉)の「人の死をどう扱うんだ?問題」についての解答が出されて来ました。改めてこの問題をかいつまんで説明すると「少年向け医療マンガ~人の生命を左右する職業~をどう描くか?懸命に生命を救う姿を描いてその尊さを見せる事に間違いはないが、それでも人が死んでしまう事は如何に描くか?(描かざるか?)」という話です。
自分の医者としての能力が足らず(?)はじめて人を死なせてしまった時、その“物語”の主人公は(人の生命の尊さを描きたいなら)ものすご~~~く!落ち込むと思うんですよね。でも、多くの“現実”の医者がそうであるように、それは乗り越えなくてはならない。それこそ一人死なせたらもう二度とメスを取れない~それほど取り返しのつかない事~なんて描き方したら、“現実”の医者が迷惑というかwそれを理想とされたら、この世から医者は絶滅してしまうでしょう。
じゃあ、死ぬ事を描いたら立ち直らせなくてはならない。…しかし、立ち直るって事は「死んじゃったもんはしゃーないよね!wまあ、次頑張れはいいよ!次!w」って~意図的に悪く読めるように書きましたが~そういう指摘から逃れられない所があります。
…というかそれが“本当の話”と言うものですよね。「あなたの死を“糧”に、俺、“次”がんばります!(キリッ)」って立ち直るしかないんですが「…いや、別にその人の生命、あたなの“糧”じゃないから?“次”がんばるで済む話じゃないから?」って話にはならないか?って事で。大人はこういうの抱えて生きて行くしかない。
しかし、子供に対してはどうか?この生命に関する背反のメッセージは“子供向け”の物語としてどう描くべきなのか?そもそもこんな難しい話、子供に理解できるのか?(それも娯楽としてのハードルをクリアしつつ!)…それなら“教育”として「生命は大事!とにかく大事!」って事を一方的に叩き込む方が“段階”と言うものではないか?
…っていろいろ難しい問題が絡んでいて『ゴッ輝』では、ともかく主人公の輝は人死に遭わない運命のような(?)ものをもったキャラだという設定が設けられていますね。そして最近、その設定/問題に踏み込んだ。そこらへんは以前の記事で書いていますね。(↓)
【今週の一番『ゴッドハンド輝』ジュブナイルに問う命題】
http://blog.goo.ne.jp/ldtsugane/e/4389ccf382a71fb7be98772e729f960d
…んで、どうするのかな?と思って観ていたその答えが今週の話だったワケです。いや、実に見事というか…そう来たかと思ったんですが「主人公は『ゼロエピソード』で人を死なせてしまう経験をしていた」って返したんですね。この場合、少年時代にそういう経験をしていたと。その経験があるから輝の生命を救う事に対する執着はホンモノだと。
くっそ~……上手いなあw最初っから用意していたんだろうなあこの答え。…いや、僕の書き口に皮肉っぽさが混じるのは、答えがキレイ過ぎて葛藤がほとんど無いからなんですけどね(汗)以前、経験されたものという描きは『受け手』の物語共有をズラしていて、ある意味でテクニカルです。
…ちょっと難しく語りますと。ロジック上の“生命の重さ”は確保されているのだけど、実際の劇中での描きをズラす事で、“生命の重さ”が体感に達するのを軽減(調節)させているんですね。患者と対面して「治す」と宣言されたものを、死なせてしまう。そういう様を順を追って描くのはどうやってもキツいけど、記憶という抜き出し可能なエリアに入れる事で、そのキツさを調節している…という言い方でもいいです。
その上で少年時代(かつ非常時)という“許され得る”事由を置いた上でやっている。上に書いたキツい手順を踏みながら死なせ、その上で自分を許すか?許さないか?という葛藤は避けている。「自分を許して、やって行く」にしろ「自分を許さず、やって行く」にしろ(許さず辞める…も、一応、選択肢としてありますが)、どちらにしろストレスのかかる決断なんですが、そこへ“行く”のはまあ避けたんだな…と思ったり。
いや、一連の記事の中で断わっているように僕はその踏み込みが必ず必要な事だとは思っていないので、だからどうというつもりもないんですけどね。また、このタイミングでリアルタイムに人死を出しても、それは、それこそ「その為の人死」、「輝の為の展開」という感覚から逃れられないでしょうから、そこは非常に上手く描いたなあと思っています。
今回は「輝は本当に人の生命の重さを実感して、その仕事に携わっているのか?」人死に遭わない(…と思われた)輝が「生命の重さ」なんて言っても、それは言葉上だけのものではないか?その言葉に実感はあるのか?という問題に答えを返したといった所でしょうか。ここを押さえた上で、もうちょっと踏み込んだ所に行くか否かは、僕は興味のある所なんですが、それは、まあまた別の機会に観ていきたいと思います。
http://www.tsphinx.net/manken/wek1/wek10480.html#658
【漫研】
http://www.tsphinx.net/manken/

ぬうう…答えがキレイ過ぎてぐうの音も出ないよ?(´・ω・`)
『ゴッドハンド輝』(作・山本航暉)の「人の死をどう扱うんだ?問題」についての解答が出されて来ました。改めてこの問題をかいつまんで説明すると「少年向け医療マンガ~人の生命を左右する職業~をどう描くか?懸命に生命を救う姿を描いてその尊さを見せる事に間違いはないが、それでも人が死んでしまう事は如何に描くか?(描かざるか?)」という話です。
自分の医者としての能力が足らず(?)はじめて人を死なせてしまった時、その“物語”の主人公は(人の生命の尊さを描きたいなら)ものすご~~~く!落ち込むと思うんですよね。でも、多くの“現実”の医者がそうであるように、それは乗り越えなくてはならない。それこそ一人死なせたらもう二度とメスを取れない~それほど取り返しのつかない事~なんて描き方したら、“現実”の医者が迷惑というかwそれを理想とされたら、この世から医者は絶滅してしまうでしょう。
じゃあ、死ぬ事を描いたら立ち直らせなくてはならない。…しかし、立ち直るって事は「死んじゃったもんはしゃーないよね!wまあ、次頑張れはいいよ!次!w」って~意図的に悪く読めるように書きましたが~そういう指摘から逃れられない所があります。
…というかそれが“本当の話”と言うものですよね。「あなたの死を“糧”に、俺、“次”がんばります!(キリッ)」って立ち直るしかないんですが「…いや、別にその人の生命、あたなの“糧”じゃないから?“次”がんばるで済む話じゃないから?」って話にはならないか?って事で。大人はこういうの抱えて生きて行くしかない。
しかし、子供に対してはどうか?この生命に関する背反のメッセージは“子供向け”の物語としてどう描くべきなのか?そもそもこんな難しい話、子供に理解できるのか?(それも娯楽としてのハードルをクリアしつつ!)…それなら“教育”として「生命は大事!とにかく大事!」って事を一方的に叩き込む方が“段階”と言うものではないか?
…っていろいろ難しい問題が絡んでいて『ゴッ輝』では、ともかく主人公の輝は人死に遭わない運命のような(?)ものをもったキャラだという設定が設けられていますね。そして最近、その設定/問題に踏み込んだ。そこらへんは以前の記事で書いていますね。(↓)
【今週の一番『ゴッドハンド輝』ジュブナイルに問う命題】
http://blog.goo.ne.jp/ldtsugane/e/4389ccf382a71fb7be98772e729f960d
…しかし、『ゴッドハンド輝』は“少年マンガ”なわけです。「医者という仕事は人の生命を救うやり甲斐のある仕事だ」、「人の生命を救えるという事はとても嬉しい事だ。充実する事だ」、「そういう“夢”をもって医学を志して欲しい」……ここらあたりまでをテーマとしてマンガで描く事を遮るものはないでしょう。
……じゃあ、そっから先はどうしましょう?「それでも人は死んでしまう」事は子供にどう伝えましょう?「医者をやっている以上しゃーないよ?次がんばればいいよ?」………と、言うのか?まあ、ズバッと子供にそういう難しい命題を突きつけてしまうマンガも僕は好きなんですが。少なくとも『ゴッドハンド輝』はそれを躊躇した。躊躇したから件の設定があるのだと思います。
…んで、どうするのかな?と思って観ていたその答えが今週の話だったワケです。いや、実に見事というか…そう来たかと思ったんですが「主人公は『ゼロエピソード』で人を死なせてしまう経験をしていた」って返したんですね。この場合、少年時代にそういう経験をしていたと。その経験があるから輝の生命を救う事に対する執着はホンモノだと。
くっそ~……上手いなあw最初っから用意していたんだろうなあこの答え。…いや、僕の書き口に皮肉っぽさが混じるのは、答えがキレイ過ぎて葛藤がほとんど無いからなんですけどね(汗)以前、経験されたものという描きは『受け手』の物語共有をズラしていて、ある意味でテクニカルです。
…ちょっと難しく語りますと。ロジック上の“生命の重さ”は確保されているのだけど、実際の劇中での描きをズラす事で、“生命の重さ”が体感に達するのを軽減(調節)させているんですね。患者と対面して「治す」と宣言されたものを、死なせてしまう。そういう様を順を追って描くのはどうやってもキツいけど、記憶という抜き出し可能なエリアに入れる事で、そのキツさを調節している…という言い方でもいいです。
その上で少年時代(かつ非常時)という“許され得る”事由を置いた上でやっている。上に書いたキツい手順を踏みながら死なせ、その上で自分を許すか?許さないか?という葛藤は避けている。「自分を許して、やって行く」にしろ「自分を許さず、やって行く」にしろ(許さず辞める…も、一応、選択肢としてありますが)、どちらにしろストレスのかかる決断なんですが、そこへ“行く”のはまあ避けたんだな…と思ったり。
いや、一連の記事の中で断わっているように僕はその踏み込みが必ず必要な事だとは思っていないので、だからどうというつもりもないんですけどね。また、このタイミングでリアルタイムに人死を出しても、それは、それこそ「その為の人死」、「輝の為の展開」という感覚から逃れられないでしょうから、そこは非常に上手く描いたなあと思っています。
今回は「輝は本当に人の生命の重さを実感して、その仕事に携わっているのか?」人死に遭わない(…と思われた)輝が「生命の重さ」なんて言っても、それは言葉上だけのものではないか?その言葉に実感はあるのか?という問題に答えを返したといった所でしょうか。ここを押さえた上で、もうちょっと踏み込んだ所に行くか否かは、僕は興味のある所なんですが、それは、まあまた別の機会に観ていきたいと思います。
 | ゴッドハンド輝(53) (少年マガジンコミックス) |
| 山本 航暉 | |
| 講談社 |










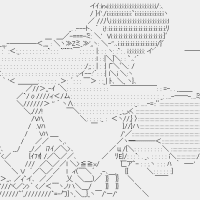
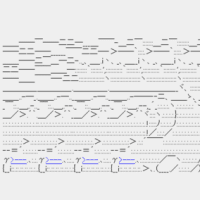
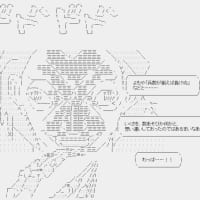
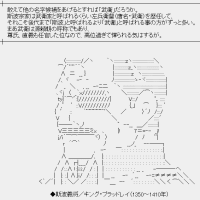
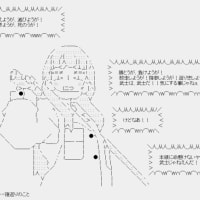
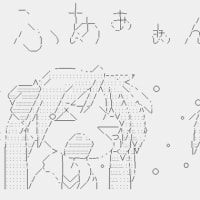

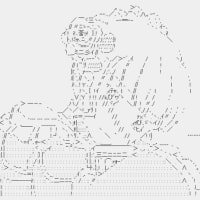

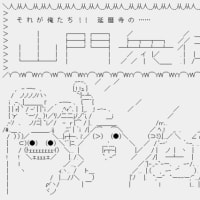
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます