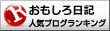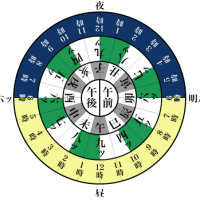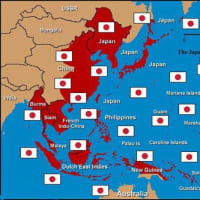再び開いて読みよります。
なにせ700頁以上もあるけん読み応えのあります。
いろいろ調べものしながら読むけんまだ大概楽しめます。
是には中対馬小路には「パンだ家」妙楽寺新町には
「おいしゃん家」も出てきます。
その中で古門戸町の項に面白い記事があります。
「博多人形の名将・早川善三」さんです。
行町の「入軒」北側にすんどった善三さん・・・
考えたらおいしゃん家もそのあたりばってんが
うちが石橋人形から爺さんが譲り受けたとはそのずっと後、昭和7年です。
善三さんは萬行寺前町の博多人形屋「讃井清兵衛」に弟子入りしたばってんが
師匠は素焼きに彩色する技術しか持たんかったけん
善三さんな発憤苦心の研究ば続け、人形の原型ば作る技術も習得し
年季明けの明治10年頃、独立の人形師になります。
また、小堀流の細工物人形(山笠の人形)の制作にも
手ば伸ばし山笠では幾多の名作人形ば作って賞賛を受けたてあります。
※古来祇園山笠人形は、「小堀正直さん(京都四条の木偶師)」が
貞享4年に博多津中からの招聘によって博多に伝わったとされます。
それまで山笠人形は藩許の小堀家独占事業やったとばってんが
明治維新の大変革で企業の自由が許されました。
この善三さんが明治23年に県庁の委嘱ば受けて作った「国会人形」
ていう県民の啓蒙運動に使用される細工人形ば作りました。
その仲間の一人が「白水六三郎」さんであります。
今、山笠人形師で活躍しよる「白水英章」君はこの六三郎さんの
子孫であります。
昔は古ノ一界隈にはうちはじめ人形屋さん人形師さんが
多かったとです。現在ベテランの人形師さんの置鮎琢磨さんも
以前は中対馬小路に住んでありました。
まいっぺん手元にある博多人形師の系図ば見返してんろうて思います。

「追記」
明治32年の追山で東町流で古門戸町内で一番棒ば舁いとった人が電柱に挟まれて即死・・・・・
※博多風土記では明治32年となっとるばってん当時の「九州日報」では
明治31(1898)年となっとります。新聞の方が正しいかも?
当番町(金屋小路)はその山台ば承天寺に持って行ってそのまんま「施餓鬼棚」にして
追討供養(大施餓鬼ば執行)ばしたとです。
その山笠台は承天寺に寄進されましたげな。
「儀礼、歴史、起源伝承 宇野功一著」より
ここから今に至る「円爾山笠発起説」に「施餓鬼棚説」が初めて山笠起源説に
追加されるごとなったとですよ・・
この博多風土記が舁かれたころはまだ
「古門戸町」が「大和町」ていう名前に決まろうか?て
言う頃です。結局住民の反対で今の「古門戸町」になっとります。
下は明治期の博多の町割りです。